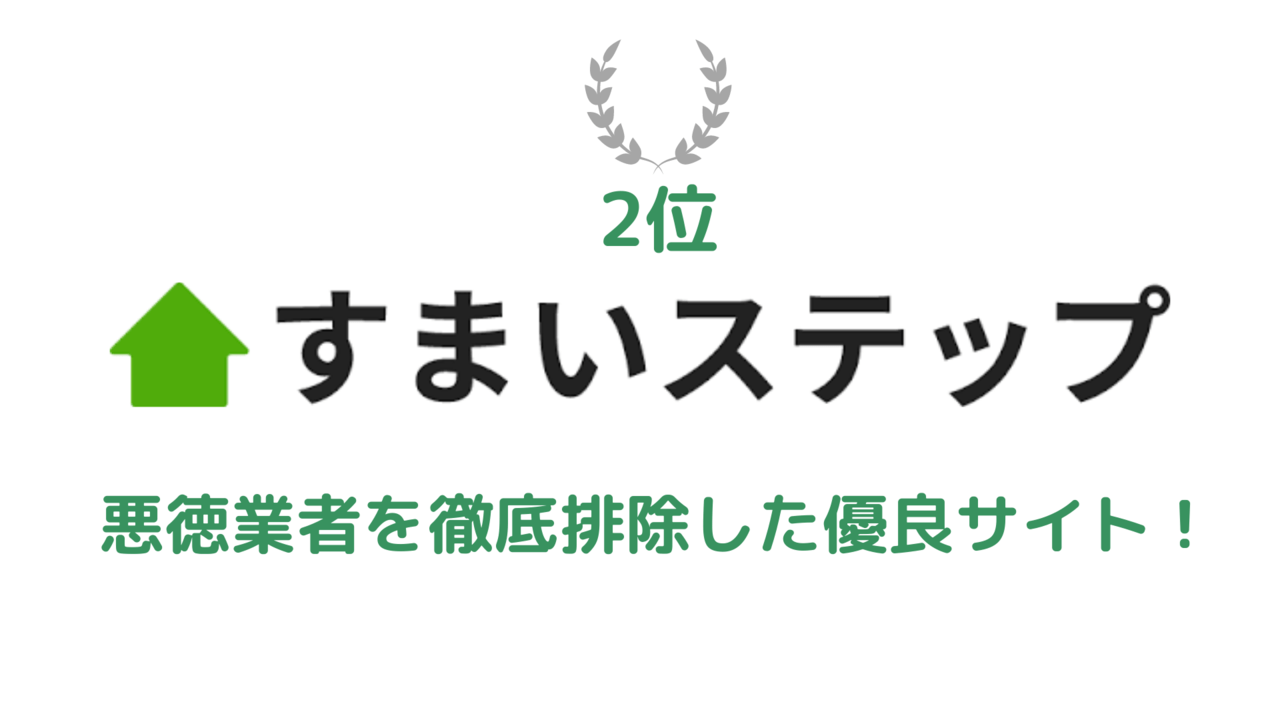広い土地を持っている方にとって、毎年納める固定資産税の金額は気になるところです。土地が広ければ広いほど税金は高くなるのでしょうか?また、高くなるのであればどの程度高くなるのでしょうか?そのような点について漠然とした不安を抱えている方も多いようです。
原則として、広ければ広いほど税金は高くなりますが、工夫や対応次第で低くすることも可能です。そのためには、税額の算出方法や節税対策を知っておくことが望ましいです。固定資産税の算出方法や特例などを知らなければ、税金を抑えられないだけではなく、場合によっては税金が大きく増えてしまうことも考えられます。
この記事では、土地が広くなると税金は高くなるのか、また、どれほどの割合で高くなるのかについて詳しく解説します。算出方法の手順やおすすめの節税対策についてもまとめました。税金で損をしないためにも、ぜひこの機会に正しい知識を学んでおきましょう。
不動産一括査定サイト利用者が選んだおすすめサービスTOP3
この記事を読まずに、先におすすめの査定サービスを知りたい人におすすめなのが、以下の3サービスです。 マイナビ編集部で実施した独自アンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声と編集部の知見が合わさってできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)
土地が広いと固定資産税は高くなる

200㎡以下である小規模住宅用地と200㎡以上の一般住宅用地では課税標準額が変わります。ここでは、それぞれの課税標準額について詳しく解説します。さらに、併せて都市計画税の税額についても解説します。
200㎡超は小規模住宅用地の特例適用なし
まず、住宅用地は面積が200㎡を超えるか超えないかで固定資産税額が異なります。200㎡以下の部分は小規模住宅用地として課税されるため、課税標準額は評価額の6分の1となります。一方、200㎡を超えた部分は一般住宅用地として課税されるため、課税標準額は評価額の3分の1です。
固定資産税の評価額は、時価の70%くらいが目安です。それに加えて、200㎡を超えると小規模住宅用地の特例が適用されず、減額率が6分の1から3分の1になることに注意しましょう。
併せて徴収される都市計画税も高くなる
面積が200㎡を超えると都市計画税も高くなります。200㎡以下の部分は課税標準額の3分の1であるのに対して、200㎡を超えた部分は課税標準額の3分の2が都市計画税として算出されます。このように、都市計画税も200㎡を超えると高くなることに注意が必要です。
固定資産税の算出方法

次に、固定資産税の算出方法について、その手順を詳しく解説します。節税する上で、固定資産税の計算は非常に重要です。ぜひ、この機会に算出方法を覚えておきましょう。
手順1.固定資産税評価額を調べる
固定資産税を計算するには、まず固定資産税評価額を確認する必要があります。評価額は、納税通知書で確認する方法、固定資産税評価証明書で確認する方法、固定資産税路線価から概算を求める方法などで知ることができます。
以下で各方法について詳しくご説明します。
納税通知書で確認する
納税通知書は毎年5月から6月頃、その年の1月1日時点で土地を所有していた人に送られます。その中にある課税明細書の価格欄に固定資産税評価額が記載されています。
もし課税明細書を紛失してしまった場合は、市役所で固定資産税評価証明書を入手可能です。その際は、土地の所有者であることを証明する必要があるため、本人確認書類を忘れずに持参しましょう。なお、入手する際には発行手数料が生じます。
固定資産税評価証明書を取得して確認する
市区町村役場の納税課などで取得できる固定資産税評価証明書でも確認できます。取得する際は、借地人や借家人、相続人など所有者本人が取得手続きをする必要があります。もし、代理人が取得手続きする場合は、委任状が必要です。
所有者本人が取得する場合も、身分証明書や借地人であることを証明できる書類が必要となることがあります。取得手続きをする前に、必要な書類を確認しておきましょう。納税通知書と比べて、固定資産税評価証明書の取得は少し手間がかかります。
固定資産税路線価でも概算がわかる
固定資産税路線価から概算することもできます。路線価とは、道路に面している土地1㎡の評価額です。
固定資産税路線価から、道路ごとに接している土地の㎡あたりの評価額がわかります。この路線価の評価額を参考にして、だいたいの固定資産税評価額を算出できます。この場合の計算式は次の通りです。計算式に出てくる地積とは、土地の面積のことです。
路線価については、国税庁の下記ページも参考にしてください。
参考:国税庁「令和2年分の路線価等について」
手順2.課税標準額を計算する
続いて、課税標準額を計算します。住宅が建っている場合と建っていない場合に分けて、それぞれの計算方法を紹介します。
住宅が建っている土地の課税標準額
住宅が建っている土地の課税評価額は、小規模住宅用地か一般住宅用地かで算出方法が異なります。この場合の住宅とは、自宅として使用している一戸建ての他、賃貸アパートや賃貸マンションなども含まれます。小規模住宅用地と一般住宅用地、それぞれの算出方法を以下の表にまとめました。
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
| 小規模住宅用地 | 評価額×1/6 | 評価額×1/3 |
| 一般住宅用地 | 評価額×1/3 | 評価額×2/3 |
この表からもわかる通り、小規模住宅用地のほうが税金は低くなります。
住宅が建っていない土地の課税標準額
宅地で住宅が建っていない場合は、負担水準の均衡化によって課税標準額が減額されます。負担水準とは、宅地の課税標準額が評価額に対して占める割合です。負担水準が70%を超える場合、次の計算式で課税標準額を算出します。
条例等によって上限は70%ではない場合もあるため、注意が必要です。課税標準額を計算する場合は、その土地の負担水準の上限を確認してから行う必要があります。
手順3.固定資産税を算出する
続いて、固定資産税を算出します。計算式は次の通りです。税率は市町村によって異なる場合があるため、注意しましょう。
都市計画区域の場合は、以下の計算式で都市計画税を算出します。
多くの場合、課税標準額が30万円未満の場合は課税対象から外されます。ただし、市町村によっては異なることもあるため、事前に確認が必要です。
住宅があると固定資産税は下がる

住宅が建っている土地の場合、住宅用地の特例が適用されて固定資産税は下がります。その場合、建っている住宅が平屋であるのか、2階建であるのかによっても税額が異なります。ここでは、住宅用地の特例について解説するとともに、建物の固定資産税についてもまとめました。
住宅用地の特例で土地の固定資産税は下がる
住宅として利用している土地には、住宅用地の特例が適用されます。住宅用地の特例は、一戸建てだけではなく賃貸アパートや賃貸マンションも対象です。住宅用地の特例が適用されると、課税標準額が大きく軽減されます。軽減されることによって固定資産税額も下がるため、節税対策として効果的です。
一定条件を満たす新築住宅には、固定資産税額の軽減措置もあります。この軽減措置は、2022年3月31日までに新築された住宅で居住部分の床面積が50㎡以上、280㎡以下であることが条件です。併用住宅では、居住する面積の割合が50%以上である必要があります。
この軽減措置では、一般住宅の新築一戸建ては3年間にわたって固定資産税額が50%減額されます。新築マンションの場合は5年間にわたって50%減に、長期優良住宅の場合は軽減される期間が長くなりさらにお得です。長期優良住宅の新築一戸建ては5年間、新築マンションは7年間、固定資産税額の50%が減額となります。
建物の固定資産税は2階建のほうが平屋よりも安い
床面積が同じでも、平屋か2階建で固定資産税の金額は異なります。一般的に、基礎や屋根面積が広くなる平屋の方が評価額が高くなる傾向にあります。それに伴い、固定資産税も平屋のほうが高いです。最近は平屋の住居が人気で建築数も増加傾向にありますが、節税の面で考えると2階建住宅のほうがお得といえるでしょう。
平屋の場合でも、造りやその土地がある場所などで固定資産税が変わります。造りとしては、コンクリート造りより木造のほうが資産評価額は低くなります。さらに使用される資材が少ないシンプルな造りであれば、資産評価額を抑えられる可能性があります。
建物の固定資産税を考える上で、その建物が建っている土地の価格も重要です。土地の価格が低い場所に建てればその分、固定資産税は抑えられます。住宅を建てる場合は、これらのことも考慮したうえで建てるようにしましょう。
2階建と平屋の違いについてはこちらの記事も参考にしてみてください。

古い家をどうするかで土地の固定資産税は上がる

古い家は扱い方次第で、固定資産税が大きく上がってしまう場合があります。賢く税金を抑えるためには、どのような場合に固定資産税が増えてしまうのかを知っておくことも重要です。
ここでは、古家の扱い方によってどの程度リスクが出るのかをご紹介します。
住宅を取り壊した場合は最大で4倍に上がる
土地に建造物がある場合、固定資産税特例措置が適用されるため、土地に対する固定資産税は軽減されますが、古い家屋を取り壊した後は固定資産税特例措置が受けられなくなることに注意が必要です。
固定資産税特例措置が適用対象外となった場合、土地に対する固定資産税の税額は最大で4倍になる可能性があります。このように税額に大きく関わるため、住宅の取り壊しのタイミングは非常に重要です。
更地にする前後で固定資産税がどう変わるかについては以下の記事でも紹介しています。

併せて、解体費用についてはこちらの記事もお勧めです。

特定空き家に指定されると大幅に増える
空き家対策特別措置法によって特定空き家に指定されると、軽減措置対象から外されてしまいます。特定空家に指定される基準は次の通りです。
- 倒壊などによる危険性のある住宅
- 衛生面において悪影響が及ぶとみられる住宅
- 適切な管理がされていないことから周囲の景観を損ねている住宅
- その他周辺の生活環境の保全のために、放置は不適切とみられる住宅
この基準からもわかる通り、空き家を放置するのはリスクが高いです。古い家で住んでいないからといって、長期間にわたり放置してしまうと特定空き家に指定される可能性が高まります。適切な管理をされていない空き家は、近隣住民とのトラブルの原因にもなりかねません。
現在住んでいない家を所有している方は、そのような意味でも注意が必要です。特定空き家に指定されると税金が大きく増えます。古い家を所有している場合は上記の基準を踏まえた上で、特定空き家に指定されないように気をつけましょう。
空き家を放置するリスクについてはこちらの記事もお勧めです。

固定資産税の負担を減らす方法

固定資産税は対応や管理の仕方などで減らすことができます。利用できる方法は積極的に利用して、固定資産税を抑えましょう。ここではその方法として分筆、一部を貸し出す、売却する方法を紹介します。それぞれに特徴があるため、自分にとって最適な方法で税金の負担を減らしていきましょう。
分筆して節税する
固定資産税路線価の評価額が異なる2つの道路に面している敷地内で、自宅とアパートなどが一筆で登記されている場合、分筆することで固定資産税を節税することができる場合があります。ただし、分筆手続きの際には境界線の確定や登記申請費などが必要です。場合によっては100万円以上かかることもあるため注意しましょう。
分筆に必要な境界線の確定は、専門的な知識や設備が必要となります。そのため、費用はかかっても土地家屋調査士などの専門家に相談するのがお勧めです。
土地を分筆して売却する際には、こちらの記事も合わせて読んでみてください。

一部を貸し出す
広い土地を所有している場合は、その一部を駐車場を運営している会社などに貸し出して、その収益で固定資産税の負担を減らすこともできます。土地の一部を駐車場運営会社に貸し出した場合、借りる側は権利が弱い賃貸借であるため、土地を返してもらいやすいというメリットがあります。別の用途で使いたくなったときに問題になりにくいのもメリットの一つです。
貸し出しできる土地の面積があまり広くなくても、1台から貸し出しできる駐車場運営会社もあります。駐車場運営会社に貸し出す場合は、ひとつの会社に相談して決めるのではなく、複数の会社に相談してそれぞれの契約内容などを比較した上で決めるのがお勧めです。
土地を更地のまま所有しているだけでは収益がなく、固定資産税だけ毎年払うことになってしまいます。もし、所有している土地の有効活用方法が思いつかない場合は、一部貸し出すことを検討してみるのもお勧めです。
売却する
土地の一部、または全部を売却することで固定資産税の負担を減らす方法です。売却してしまえば、固定資産税を払う義務もなくなります。ただし、居住していた土地を全部売却したら、その売却代金で新たな住居を購入する必要があることには注意しましょう。
土地を売却する際は、その土地がどの用途地域に属するかで売却価格が大きく変わります。商業施設や集合住宅などで需要がある土地の場合は、高い金額で売却できる可能性があります。その一方、戸建てしか建築できない土地は売却価格が低くなる場合が多いです。
土地の売却は大きな金額が動く取引です。一度売却してしまえば、その土地から収益を得ることはできません。失敗しないためにも、土地の売却を検討する際は不動産会社の査定を参考にしましょう。複数の不動産会社に査定してもらって比較検討するのがお勧めです。不動産一括査定サイトなどを利用するのも効果的です。
地方の不動産を売却したいなら一括査定サイト「イエウール」がおすすめ
地方の不動産の売却を検討している人に編集部がおすすめしたい一括査定サービスが「イエウール」です。イエウールがおすすめな理由について、以下にまとめています。
■イエウールがおすすめな理由
- 月間ユーザー数No.1で安心(2020年7月時点)
- 提携している不動産会社の数も業界No.1(2020年7月時点)
- 全国エリアをカバーしているので地方の不動産も売却しやすい
- 田んぼや畑など農地の売却にも対応している
- 悪徳業者が排除される仕組みがあるので安心して利用できる
※2020年7月「不動産の一括査定サイトに関するランキング調査」より(株)東京商工リサーチ調べ
一括査定サイトに関してより詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。

まとめ

土地の面積が大きくなると固定資産税は高くなります。面積が200㎡を超えると小規模住宅用地の特例が適用されません。それに合わせて都市計画税も高くなります。
また、古い家などを放置した結果、特定空き家として指定されると税金が大幅に高くなってしまうため注意が必要です。取り壊す場合も、固定資産税特例措置が適用されなくなるため事前にタイミングなどを考慮する必要があります。
ただ、分筆したり、一部を貸し出したり、売却したりすることによって税額を抑えることもできますので、所有している広い土地をうまく利用して、税金の負担を少しでも減らしましょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。