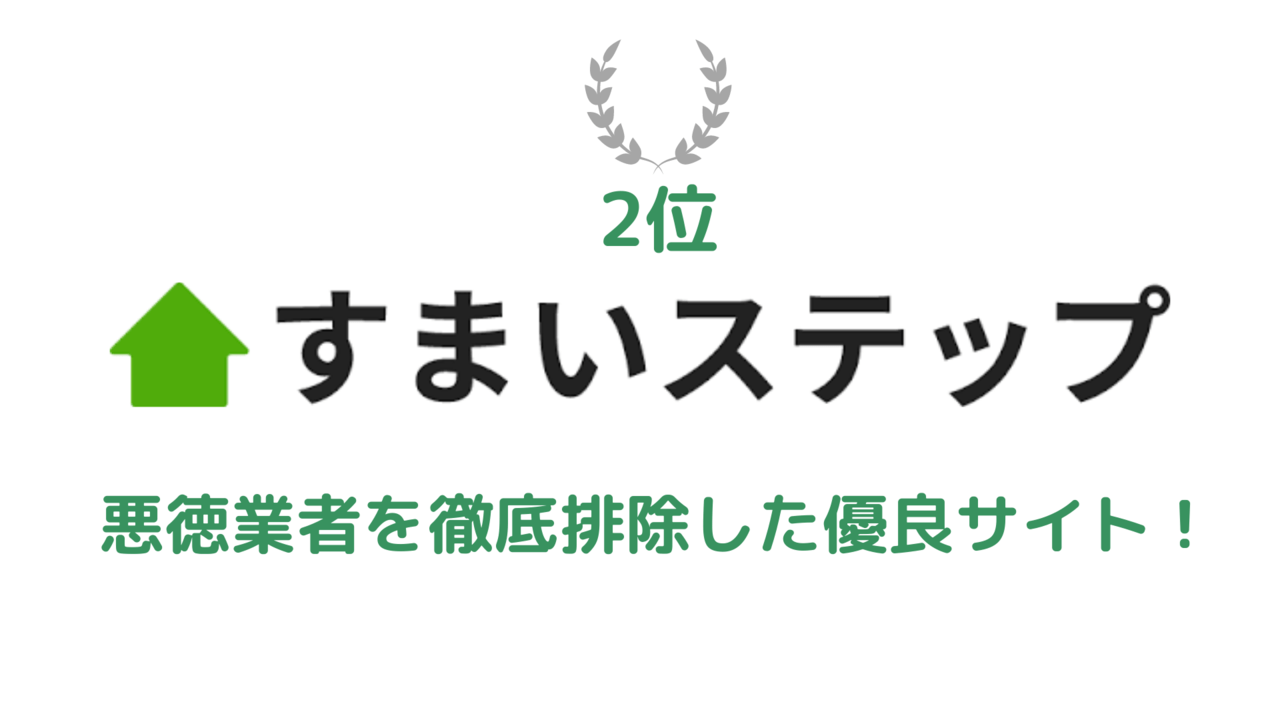抵当権とは、ローンを組んで不動産を購入するときに、金融機関が滞納による残債を不動産の売却などで回収できる権利です。抵当権がついた不動産の売却は困難で、通常はローンを完済することで抵当権を抹消します。しかし不動産の売却や相続で、抵当権の一部だけを抹消した方がよい場合があります。
ローンを完済したことがない人にとっては、抵当権抹消さえ初めての人が大半です。抵当権の一部抹消となると余計にわけがわからず、手続きに困ってしまうでしょう。
そこでこの記事では、抵当権の一部抹消が必要なケースや、手続きの例について詳しく解説していきます。1つ1つの手順は難しくないので、準備を整え抵当権の一部抹消をしてみてください。
不動産一括査定サイト利用者が選んだおすすめサービスTOP3
この記事を読まずに、先におすすめの査定サービスを知りたい人におすすめなのが、以下の3サービスです。 マイナビ編集部で実施した独自アンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声と編集部の知見が合わさってできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)
抵当権一部抹消が必要なケースとは

まずは抵当権の一部抹消が必要なケースには、どんなものがあるのか見ていきましょう。いずれも人生の中で何度もあることではありません。しかし、一部抹消をしないと困ってしまうので、以下で紹介する3つケースは覚えておきましょう。
抵当権がある土地の一部を売却したい
抵当権は、複数の不動産を担保にして設定することができます。例えば土地Aと土地Bを担保として、土地Cのローンを組んでいる場合を考えてください。ローンの完済前に、土地Bだけ売却するときに、抵当権の一部抹消が必要になります。
土地Aは売却する予定がなかったり、土地Bにだけ買主が見つかったりすることはあります。抵当権を全て抹消できた方がよいですが、資金不足などもあるので、一部を抹消することになります。
抵当権が残っていると、滞納で買主は不利益を被る可能性があるため、売却自体が難しいでしょう。
分筆をして抵当権が付いていない土地を相続したい
遺産の中に、抵当権が付いた広い土地がある場合を想定してみてください。相続人が複数人いると、土地を分けて相続することになります。抵当権が付いている土地は、基本的に分けてもそれぞれの土地に抵当権が付いたままになります。
せっかく遺産を相続するのに、抵当権が付いたままの土地では、抹消のために支払いが必要です。しかし、分けた土地分の抵当権を抹消できれば、相続した土地はそのまま資産となります。
道路買収されるので抵当権の一部抹消をしたい
抵当権が付いている土地の一部を、道路拡張のため売却しなければならない場合があります。売却前にローンを完済して、抵当権抹消ができればベストですが、簡単ではありません。
思い入れのある土地で売却を拒否しても、最終的には不利な条件で強制収用される可能性があります。提案された補償内容を受け入れ、買収される土地の分だけ、抵当権を抹消する必要があります。
土地を分筆して抵当権一部抹消をする手続き例

それでは実際の手続きについて、土地を分筆してから抵当権の一部を抹消する方法を解説していきます。以下の6つの手続きについて、1つずつこなして行きましょう。
- 土地家屋調査士に土地の分筆を依頼
- 土地の現状を調べる
- 土地の境界が不明なら測量
- 土地の分筆方法を検討し境界標の設置
- 金融機関から抵当権消滅承諾書をもらう
- 必要書類をそろえて法務局に提出する
土地家屋調査士に土地の分筆を依頼
一部の土地だけ抵当権を抹消したいのなら、土地を分筆する必要があります。分筆には、土地の境界を決めて登記の手続きをします。全て自身で行うことも可能ですが、知識が必要なため、専門家である土地家屋調査士に依頼をしましょう。
基本的に相談や見積書の作成は無料でできます。分筆の登記だけでも3ヶ月程度かかるので、期間に余裕をもって相談から始めてください。
トータルでかかる費用は、土地の広さや隣接する土地の数、取り寄せが必要な書類の数などで変わります。分筆する土地の面積が100㎡程度の場合、土地家屋調査士への報酬で6万円程度、測量などで35万円以上かかると思っておいてください。自身で登記の手続きはできても、測量は専門家の力が必要になるので、大幅な節約はむずかしいでしょう。
土地の現状を調べる
土地の現状を調べるために、登記簿謄本や公図・測量図を、市役所や法務局から取り寄せます。書類の取り寄せ方法によって、かかる実費は以下のように変わります。
| 取り寄せ方法 | 登記簿謄本 | 公図・測量図 |
| 書類での請求 | 600円 | 450円 |
| オンライン請求+郵送 | 500円 | 450円 |
| オンライン請求+窓口受取り | 480円 | 430円 |
窓口での受取りは平日に行く必要があるので、自身で取り寄せる場合は、オンラインで請求をし、郵送してもらうのが手軽です。土地家屋調査士に依頼した場合でも、報酬とは別でこられの実費の請求はされます。
土地の境界が不明なら測量
分筆したい土地の境界が不明なら、測量を行い確定しておかなければなりません。隣接している土地すべての所有者と、立ち会いの下で境界を確認するので、分筆の手順の中で期間がかかりやすい工程です。隣接する土地の所有者が非協力的であったり、権利関係が複雑だったりしたら、1年以上かかることもあります。
土地に埋め込まれている境界の印が、書類上とは異なる可能性もあるので、目視でも確認しておかないと、後から問題が起きます。分筆して売却しても、契約不適合責任を売主は負わなければならず、損害賠償や売買の解約もあり得ます。
土地の確定測量について、詳しく知りたい方はこちらの記事も読んでみてください。

土地の分筆方法を検討し境界標の設置
測量が終わったら、土地をどんな形で分筆するのかを検討します。土地の形によって、将来の使い勝手が大きくかわってしまいます。建築基準法では、2m以上は道路に接していないと建物が建てられないです。土地を旗竿状に分ける場合、奥の土地が2m以上道路に接するようにしておかないと、現在は建物があっても、建て替えができません。
自身で分筆案が思い浮かばないなら、要望を土地家屋調査士に伝えると、いくつかの案を出してくれます。遺産相続が絡むなら、形の違いによる価値も考慮して検討しましょう。
あとは完成した分筆案に沿って境界の印を設置し、分筆の登記をします。分筆の登記は抵当権一部抹消の申請と同時にできます。この段階で分筆の登記までする必要はありません。
金融機関から抵当権消滅承諾書をもらう
分筆しただけでは、まだそれぞれの土地に抵当権が付いたままです。次はローンを支払っている金融機関に行き、抵当権一部抹消承諾書にサインをもらいます。
埼玉の法務局を例に挙げると、抵当権一部抹消承諾書には、以下の項目を埋めます。
- 分割前の土地の所在・地番・地目・地積
- 分割後の土地の所在・地番・地目・地積
- 分割する土地の所在・地番・地目・地積
- 抵当権の設定をした登記の受付番号
- 抵当権を抹消する土地はどれか
- 書類を作成した日付
- 抵当権者の住所・指名・捺印
金融機関にとって抵当権一部抹消は、担保が減りもしもの時に融資額を回収できないリスクが増えます。担当が納得できる理由を用意して、承諾書をもらえるようにしましょう。
必要書類をそろえて法務局に提出する
分筆と抵当権一部抹消で法務局に提出書類は以下のようになります。
- 登記申請書
- 土地の筆界確認書
- 地積測量図
- 抵当権一部抹消承諾書
- 手続きを代理で行ってもらうための委任状
筆界確認書とは、土地の境界を隣接地の所有者と合意したことを確認する書類です。また書類とは別に、登記申請のために登録免許税が必要で、土地1つに対して1,000円かかります。
基本的に必要な書類は、手続きを依頼した専門家が用意してくれます。委任状にサインをしておけば、待っているだけで手続きは終わるでしょう。
遺産の抵当権一部抹消は相続手続きからする

ここまで紹介してきた抵当権の一部抹消方法は、自身の不動産であることが前提です。相続予定の不動産で抵当権の一部抹消をしたいのなら、先に相続の手続きをしてしまいましょう。
相続人が複数人いるなら、分割の協議で手間がかかるかもしれません。名義変更が済むと、相続税の支払いもあるので、最後まで手続きに漏れがないよう気をくばって進めましょう。
相続人を確定して遺産の分割協議をする
遺産相続は、遺言書があれば書かれた内容に沿って分けるだけです。遺言書がなければ、相続人で分割の協議をします。相続人は故人の配偶者と血族が基本で、故人の子供や兄弟が存命なら孫や甥・姪は対象外です。
分割は、現物のまま行ったり財産を現金化して行ったりします。現物で土地の一部を相続し抵当権を抹消しておきたい場合に、今回の一部抹消が必要になります。
分割の協議は後からもめないように、遺産分割協議書を作成し相続人全員が署名と捺印をします。分割の協議がまとまらないなら、弁護士などに相談をしましょう。事務所によっては無料で相談を受け付けています。
遺産の不動産の名義変更をする
遺産分割の協議で、不動産が自分のものになることで合意できたら、法務局で相続の登記をします。登記で必要になる書類は以下のものです。
- 故人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 相続する予定の不動産の固定資産税評価証明書
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
固定資産税評価証明書は、名義変更する年に送られてきた最新の証明書を使います。印鑑証明書には有効期限があり、基本は3ヶ月ですが役所によって受理される基準が異なります。提出をする前に確認をとっておきましょう。
提出した書類に問題がなければ、1~2週間程度で完了します。名義変更に期限は定められていませんが、先延ばしにするほど、相続人が増えたり相続人に連絡がつかなくなったりします。認知症などで代理が必要になる場合もあるので、早めの名義変更をおすすめします。
期限までに相続税を納税する
相続税の納税は、亡くなったのを知ってから10ヶ月以内にしないと、延滞税を取られてしまいます。相続税の計算方法は以下のようになっています。
相続で取得する金額によって、課せられる税率が異なります。金額毎でかかる税率を下記表にてまとめましたので、計算式に当てはめて算出してください。
| 相続で取得する財産の金額 | 税率 |
| 1,000万円以下 | 10% |
| 3,000万円以下 | 15% |
| 5,000万円以下 | 20% |
| 1億円以下 | 30% |
| 2億円以下 | 40% |
| 3億円以下 | 45% |
| 6億円以下 | 50% |
| 6億円超え | 55% |
参考文献:国税庁「No.4155 相続税の税率」
計算された相続税は、財産のトータルにかかる税金です。相続人が複数いる場合は、各人が総額の何割を相続するかで、支払いを均等に割ります。
不動産の相続税について、詳しく知りたい方はこちらの記事も読んでみてください。

抵当権一部抹消をするときの注意点
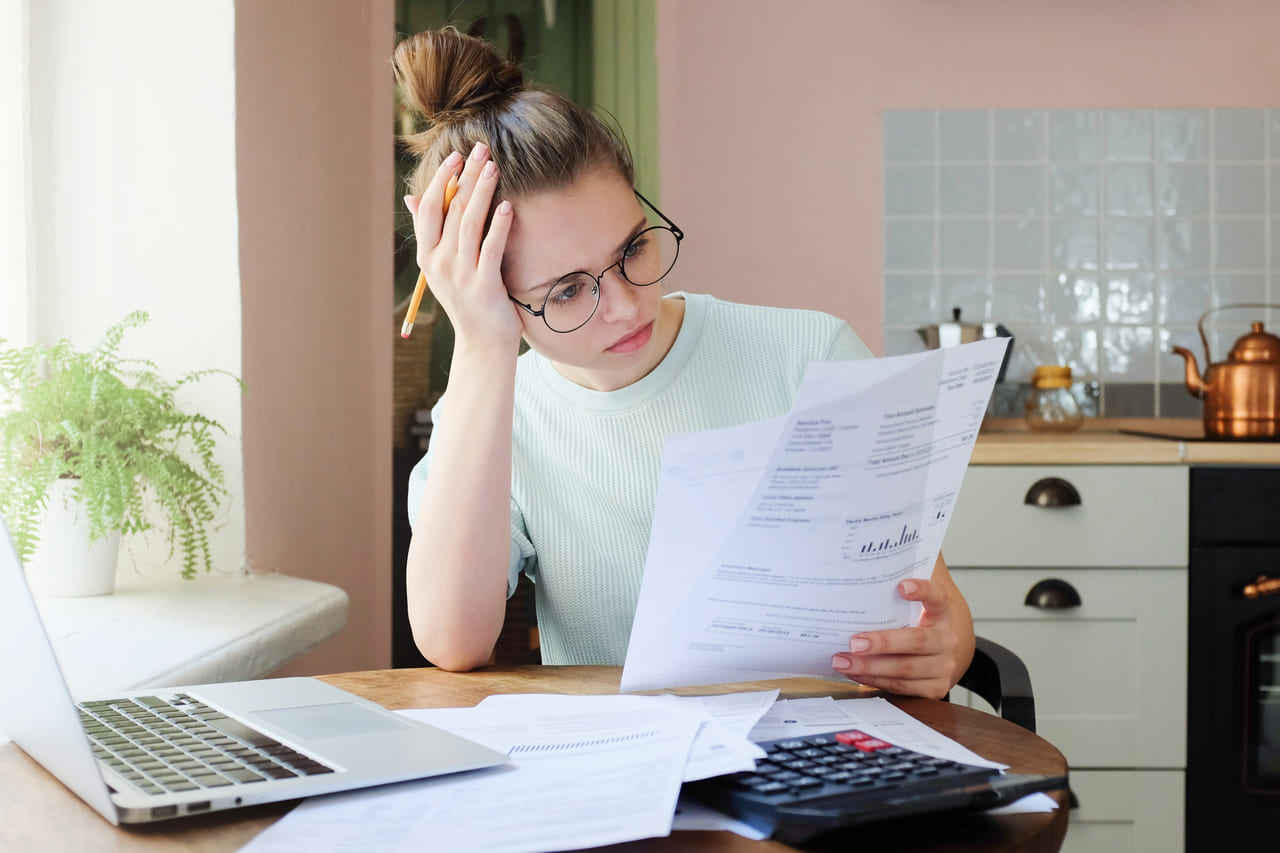
紹介してきた抵当権の一部抹消方法だけでは、状況によって上手くいかない場合があります。手続きの途中で困らないために、3つの注意点について解説していきます。ただでさえ慣れない手続きですから、注意点は事前に把握して、ミスを減らしましょう。
自身で書類の提出をするなら最寄りの法務局に相談
抵当権を抹消する登記は、不動産を管轄している法務局に申請する必要があります。しかも、法務局によって手続きに細かい違いがある場合も有ります。自身で書類の提出をするつもりなら、法務局の確認からしましょう。法務局は北海道以外なら、県や都・府に1つです。電話などで相談してみてください。
専門家に手続きを依頼する予定なら、気にしなくて大丈夫です。依頼をして委任状を作成しておけば、結果を待つだけです。境界の確定が済んでいないと一手間かかりますが、手続きでミスはなくなります。
完済で受け取る書類の紛失は余計な手間がかかる
将来抵当権が残っている不動産で抹消の手続きをするときは、ローン完済するときに受け取る書類を紛失しないでください。ローンを完済すると、金融機関から以下の書類が送られてきます。
- 弁済証書
- 登記事項証明書
- 登記済証or登記識別情報
- 委任状
登記済証や登記識別情報は一度紛失してしまうと、自身で再発行の申請はできません。司法書士を経由して再発行を依頼するか、事前通知制度という物を使います。いずれにしても、余計な手間や費用がかかってしまいます。書類が届いたら大事に保管をし、抵当権の抹消をしてしまいましょう。
抵当権で住所や名前の変更があるなら追加の書類
抵当権を設定してからローンの返済までに、何十年もかかります。その間に諸事情で住所や名前が変わることは珍しくありません。通常の抵当権抹消に追加で住所変更登記や氏名変更登記を行います。
引っ越しで1回だけ住所が変わっている場合は、住民票の写しを役所から取得します。住所が複数回変わっているなら、経緯がわかる書類として戸籍の附票を使います。市町村の合併などで、市や町名が変更された場合は、住所変更登記は必要ないです。地番まで変更された場合は手続きをしてください。
氏名の変更がある場合は、住民票の写しと変更が合ったことがわかる戸籍謄本を取得して、氏名変更登記をします。書類を個別に揃えようとすると、余計な手間も費用もかかってしまいます。自身で抹消の手続きをするなら、どれだけ追加で手続きが必要かも把握しておきましょう。
抵当権抹消でよくある疑問

最後は抵当権抹消の手続きで、よくある疑問について解説します。ちょっとした言葉の意味の違いや、手続きを依頼する必要性などの疑問を解消し、不安なく手続きに進めるようになってください。
手続きは専門家に依頼したほうがよいのか
登記の申請は、専門家への報酬として数万円かかります。相続や住所変更などもあると、費用はどんどん増えてしまいます。少しでもかかる費用を抑えたいのなら、自身で手続きをしてください。測量以外なら手間はかかっても自身でできます。
手続きのミスと手間を省きたい人は、専門家に依頼することをおすすめします。抵当権の一部抹消のため、自身はどれだけの手続きが必要なのか把握できていなかったり、平日は仕事で忙しかったりすると、なかなか手続きが完了しません。時間をかけすぎると、抵当権を抹消した不動産を活用するタイミングを逃す恐れもあります。
抵当権と根抵当権は何が違うのか
抵当権の一種として、不動産に根抵当権が設定されている場合があります。根抵当権は通常の抵当権と違い、返済しても抹消しないで次の融資に使えます。抵当権抹消には費用がかかるから、事業などで何度も融資と返済を繰り返す場合は、費用の節約で抵当権が残る根抵当権が便利です。
リバースモーゲージを利用しているなら、個人の不動産でも根抵当権が設定されます。リバースモーゲージにしていても、将来不動産を残したいのなら、根抵当権の抹消は可能です。融資を全額返済してから、金融機関に抹消の相談をしてください。
共同抵当権では抹消はどうするのか
共同抵当権とは、1つの不動産を複数の不動産の担保として抵当権が設定されています。不動産AとBの担保として不動産Cに共同抵当権がある場合、不動産Cの抵当権を完全に抹消するには、不動産AとBでローンの返済をし、それぞれで抵当権抹消登記をします。
AとBで同時に抹消登記をする必要はなく、返済プラン通りに完済し、手続きをしてください。もし登記の目的や抹消原因、手続きの日付が同一なら、抹消と登記の申請は1件で問題ないです。
共有不動産の抵当権抹消は1人からでも申請できるのか
誰かと共有している不動産に付いている抵当権は、共有者全員で抹消の申請をする必要はありません。申請者が共有者の誰か1人であれば、申請は通ります。
抵当権の抹消というのは、不動産の所有者にとって利益のあることです。もし全員の協力が必要だと、なにか事情があって協力できない人がいたら、他の人が不利益を被ってしまいます。
まとめ

抵当権の一部を抹消できれば、抹消できた不動産の活用用途が格段に増えます。自由に売買することができ、相続で残債の負担なく土地に家を建てることも可能です。
土地で抵当権の一部抹消をする場合は、分筆をしてから金融機関と相談をして抹消の手続きをします。土地の境界が曖昧なら、分筆のための測量で高額の費用がかかるでしょう。専門的な知識も必要になるので、すべて専門家に依頼してしまったほうが、ミスがなくおすすめです。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。