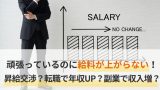戸建ての購入は、人生に大きな影響を及ぼす決断の一つです。その一方、戸建て購入は何度も経験するものではないので、十分な知識がないことが多いです。そのため、購入後に後悔してしまう方も少なくありません。
そこでこの記事では、戸建てを購入するときに知っておきたい、15の注意点について解説します。購入までには決めるべきことが沢山ありますが、準備段階から理想の戸建てを探すまでの流れにそって段階別に、注意点を確認してください。
また、戸建ての購入はどんなに注意をしていても、失敗する確率を0%にするのは難しいです。もしものために、失敗した時のの対処法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
※LIFULL HOME'S 住まいの窓口来場者(390組)を対象とした調査(集計期間:2019年4月~2020年3月)より
戸建てを購入するまでの流れ
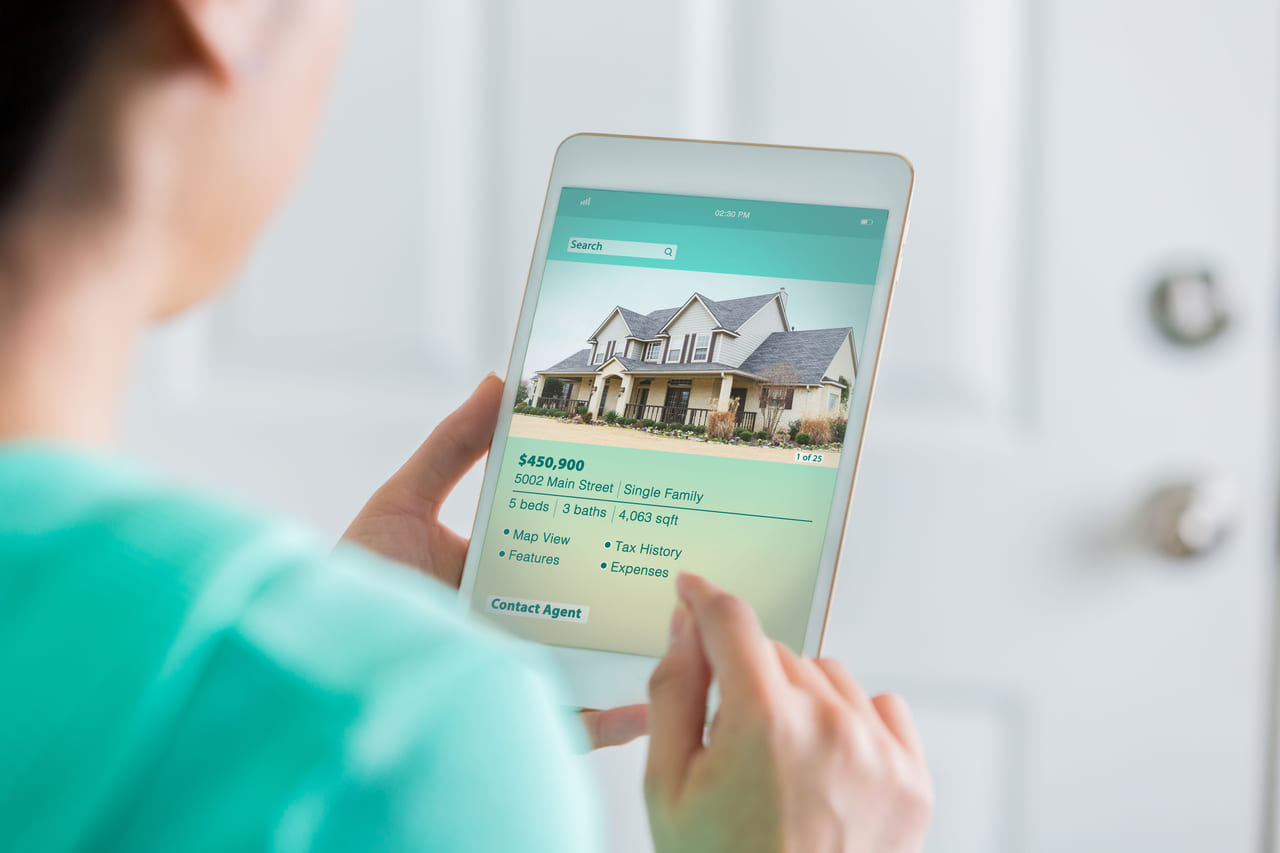
戸建ての購入の注意点を知る前に、まずは購入するまでの流れをざっくりと把握しておきましょう。準備段階から入居までは、以下の6つのステップを踏みます。
- 購入するタイミングや充てられる予算の確認
- どんな戸建てを購入したいのかの情報収集
- 気になる戸建てを扱う不動産会社に問い合わせ
- 戸建ての最終絞り込みをして売買契約
- 新築なら完成後に内覧
- 決済をして戸建ての引き渡し
不動産会社と売買契約を結んでしまうと、簡単に破棄はできません。違約金を払わなければならない場合もあるので、本記事では売買契約までの注意点をメインに紹介していきます。
戸建てを購入する準備段階の注意点

準備段階では、そもそも戸建てを購入した方がよいのかや、タイミングは今がベストなのか、予算をいくらにするのかと、決めることが沢山あります。1つ1つの決断が人生を左右するので、準備段階から注意点を確認しながら、慎重に進めてください。
賃貸より購入の方がメリットがあるのか
戸建ての購入は、理想の生活ができるという思いでワクワクします。しかし1度購入してしまうと、簡単に手放すことはできません。戸建ての購入にもデメリットはあるので、本当に賃貸よりメリットがあるのかの確認が必要です。
| 購入 | 賃貸 | |
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
費用面だけを考えると、何年住み続けるのかや維持費にいくらかけるのかなどで、購入と賃貸でどちらがお得かは断定できません。比較をするなら生活のしやすさも含めて検討する必要があります。
購入と賃貸のメリットデメリットから、それぞれおすすめの人は以下のようになります。
- 購入がおすすめの人:自身で自由にできる家に住み、将来家を資産として残したい
- 賃貸がおすすめの人:ライフサイクルに合わせて、最適な家で暮らしたい
購入するのは戸建てで問題ないのか
賃貸より購入する方がよいと決まったら、次は購入する物件の種類について検討しましょう。家の購入となると、大きく分けて戸建てかマンションかの2択になります。戸建てとマンションのメリットデメリットは以下のようになります。
| 戸建て | マンション | |
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
同額の物件を購入する場合、毎月の出費はマンションの方が高額になりやすいですが、長期定期に見ると大きな差はないです。
購入と賃貸と同様に、戸建てとマンションの場合でも、生活のしやすさが決断をするポイントとなります。
- 戸建てがおすすめの人:開放感のある環境で、自由にカスタマイズしながら暮らしたい
- マンションがおすすめの人:管理の手間を減らして安全に暮らしたい
戸建かマンションかについて、さらに詳しく比較をしたい人はこちらの記事も参考にしてみてください。
マイナビニュース「都心で購入するなら戸建てかマンションか – FPがポイントを解説」
ライフプランにあったタイミングなのか
戸建てを思い立ったときに購入しようとすると、後悔をしやすいです。国土交通省の住宅市場動向調査報告書によると、購入している年齢層のメインは30代となっています。しかしあくまで統計の結果であり、人によって事情は変わります。
購入するタイミングは、ライフプランを考えると主に4つあります。
- 結婚
- 出産
- 子供の独立
- ローンの返済
一人暮らし前提の家に夫婦で生活するのは狭く不便なので、結婚が一つ目のタイミングとなります。二つ目の出産も、結婚と同様に家族の人数が増え子育てについても考えるから、購入する戸建ての条件が大きく変わります。
三つ目の子供の独立は、夫婦での暮らしに戻るから、必要な広さや立地は子育て中とは変わります。四つ目のローンの返済は、多くの金融機関で返済は75歳未満となっており、高齢だと長期ローンが組めなくなるため、タイミングが決まります。
最適なタイミングは人によって変わりますが、ライフイベントを基準に考えると、自身に合ったタイミングが絞り込めます。
何歳でマイホームを購入したかのアンケート調査について、詳しく知りたい人はこちらの記事を読んでみてください。
マイナビニュース「マイホーム、何歳で購入した? 経験者に聞いた、住宅購入のタイミング」
戸建てを購入する予算を決める注意点

戸建てを購入する場合、多くの人はローンを組んで毎月支払っていきます。安易にローンの支払いは家賃分の出費を充てるから問題ないと考えてしまうと、将来家を手放さなければならなくなるかもしれないです。そうならないために、予算を決めるときの注意点を3つ紹介します。
物件の価格以外にも費用は発生する
戸建ての購入には、物件の価格以外の手数料や維持費で多額の費用がかかります。購入の段階と維持する段階で、それぞれ以下の項目で出費があります。
戸建てを購入する段階でかかる費用
- 仲介手数料
- 登録免許税
- 印紙税
- ローンの事務手数料
- 不動産取得税
- 引っ越しなど入居までの諸費用
購入した戸建ての維持費
- 固定資産税・都市計画税
- 火災や地震の各種保険
- 外装や内装の修繕費
購入段階では、仲介手数料が高額になりやすいです。相場は(購入価格×3%+6万円)+消費税で、100万円以上の出費になるでしょう。その他の費用も含めて、購入する戸建ての価格に5~6%程度は上乗せした予算を想定してください。
維持費で生活を圧迫しやすいのが、固定資産税と都市計画税です。それぞれ購入した戸建ての評価額に対して、1.4%と0.3%の税率で支払いをします。年4回の分割払いにできますが、年間で数十万円の出費は負担となります。
修繕費は一度すると10年や20年は必要ありません。しかし屋根や外装の修繕になると、100万円以上の出費も珍しくないです。貯金をしておかないと、修繕自体ができないです。
ローンの返済負担率は上限だと生活が苦しくなる
ローンの返済負担率とは、年収に対して年間でどれだけ返済できるかの割合です。年収600万円で年間120万円返済をするなら、返済負担率は20%となります。ローンの審査に通るには、一般的に35%以内が安全とされています。
しかしローンの返済負担率を審査が通る上限にしてしまうと、ギリギリの生活になってしまう可能性があります。返済負担率は額面の年収で計算され、手取り年収で計算すると生活に充てられるお金はさらに減少します。
余裕のある生活を送るためには、額面年収で20%程度の返済負担率にしておけば、手取り年収でも30%は超えず、家賃の負担と同程度になるでしょう。
金利の低さだけで金融機関を選ばない
ローンを組むときの金利は、0.1%の違いでも長期的に見ると数十万円の違いにつながります。しかし金利の低さだけで金融機関を選ぶと、思い通りに支払いができない場合があります。
金利の種類は大きく分けて、固定金利と変動金利の2種類があります。固定金利なら完済まで金利は一定だから、返済プランを建てやすいです。変動金利は固定金利より低く、2020年段階では低水準で推移していますが、将来はわかりません。
またローンは、組む段階で融資の手数料や団体信用生命保険料、繰り上げ返済でも手数料がかかります。これらの諸費用と金利を考え、トータルで安くなる金融機関を選びましょう。
金利が低く戸建ての価格が落ち着いているタイミングが、買い時とよく言われます。しかしライフプランによる出費も考慮して、検討した方がよいです。
戸建ての購入で利用する不動産会社の注意点

戸建てを購入することを決意し、予算の当たりも付けられたら、不動産会社に問い合わせをして売買契約に進んで行きます。どんな戸建てが欲しいのかも決めているから、どの不動産会社でも変わらないと思うのは大間違いです。
適当な不動産会社では、なかなか理想の戸建てが見つからなかったり、契約後のサポートが不十分だったりします。注意点は4つあるので、詳しく解説していきます。
不動産会社は得意分野を確認する
戸建ての購入は、仲介をメインにしている不動産会社を使います。問題は大手にするのか、地域密着の不動産会社にするのかです。
大手ならエリアにかかわらず対応してもらえ、接客もマニュアルなどによって教育されているから安定しています。意識していなかったエリアからも、理想に近い物件が見つかるかもしれません。
地域密着の不動産会社は、対応エリアは限定的ですが独自の情報網で、インターネット上にはなかった戸建てを教えてもらえる可能性があります。地域の相場にも詳しいから、価格で損をすることは少ないです。
不動産会社は担当の人柄まで見る
不動産会社の担当によっては、こちらの要望を聞かず売りたい物件だけを紹介したり、話しやすくても専門知識がなかったりして、不利益を被ることがあります。
そうならないため、専門的な知識をわかりやすく解説してくれ、こちらの要望をくみ取ってくれる担当なのかを見ましょう。
特に中古の戸建てを購入するときは、値引きの交渉も重要になってきます。信頼できない知識不足の担当では、交渉がまとまらず予算オーバーしてしまうかもしれないです。
契約する仲介業務の契約内容を確認する
不動産会社に仲介を依頼するとき、媒介契約というものを結びます。媒介契約は3種類あり、特徴は以下のようになっています。
| 媒介契約の種類 | 特徴 |
| 一般媒介契約 |
|
| 専任媒介契約 |
|
| 専属専任媒介契約 |
|
沢山の物件から理想の戸建てを見つけたいなら、一般媒介契約がおすすめです。それぞれの不動産会社との対応で手間はかかっても、他の媒介契約よりは短期間で、伝えた要望に沿った戸建ての情報が集まります。
購入の契約内容に納得できないならサインをしない
購入したい戸建てが見つかったら、売買契約の前に重要事項の説明を受けます。この説明では、戸建てがどんな状態なのかや契約をする価格、違反があったらどんな罰則があるのかなどを確認します。
もし重要事項の説明で納得できない点があるのなら、売買契約書にはサインをしないでください。この段階ではサインをしなくても、不動産会社への違約金は発生しないです。
不動産会社からの説明が不十分で、自分ではすぐに判断できないなら、一度持ち帰り専門家に相談をしましょう。都道府県宅建協会や全日本不動産協会などなら、無料で相談の受付をしています。
購入する戸建てを探すときの注意点

実際に購入をする戸建ては、どんな条件で探せば将来も後悔をしないのでしょうか?予算内におさめるため、どこかで妥協は必要になります。家族としっかり話し合い、以下の注意点を守って探していきましょう。
新築にするのか中古にするのか
戸建ての購入でよく迷うのが、新築にするか中古にするかです。それぞれのメリットデメリットを紹介するので、どちらなら理想の戸建てを見つけやすいのかを検討してください。
| 新築 | 中古 | |
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
予算などの都合で、初めて戸建てを購入するときは新築にし、老後の住み替え先として中古の戸建てを選ぶという人もいます。しかし一度購入すると何十年もそこで生活をするから、迷いやすいです。
紹介したメリットデメリットより、新築と中古でおすすめの人は以下のようになります。
- 新築がおすすめの人:多少割高でも新品で、最新設備の家に住みたい
- 中古がおすすめの人:建物の予算は抑え、立地にこだわった家に住みたい
土地は将来性まで考えて選ぶ
購入する戸建てを探している時点では、周囲に便利な施設がそろっていても、過疎化などで数十年後は生活が困難な場合があります。また中古の戸建てでは、増改築が制限されている土地もあります。
過疎化などによる生活困難を避けたいなら、現時点で商業施設や病院といった施設がそろい、周辺で開発計画があれば、将来の発展を期待できます。地域の人口の増減も判断をする目安となります。
増改築については、新築でも中古でも長く住んでいると必要になっていきます。道路の工事が予定されていたり、高圧線が建物と通ったりしている土地は避けましょう。また近隣の環境によって足場さえ組めないと、工事さえできなくなります。
間取りや部屋数は将来も問題ないのか
家族の人数や生活様式によって、暮らしやすい間取りや部屋数は決まってきます。間取りは生活動線を考えて吟味しないと、同じ通路を行ったり来たりして、生活に余計な労力がかるでしょう。
部屋数に関しては、将来子供が成長したときに、個室を用意するかどうかが鍵です。1人分ならなんとか用意できても、2人以上の個室を後から用意するのは困難です。
生活様式や家族構成を具体的にシミュレーションして、将来に問題が生じない間取りや部屋数にしてください。
新築でも中古でも細部までチェックする
購入する戸建ては、新築でも中古でも自身の目で細部までチェックをしておかないと、生活を始めてから不備に気づき、余計な出費が発生してしまいます。
外観でチェックする点は、屋根・外壁・軒・基礎の4箇所で、室内なら水回り・壁・各所の立て付けです。外観はひび割れをメインに、室内は臭いまでチェックをします。
また室内のチェックでは、点検口の存在が重要です。点検口があれば床下や天井裏の状態までチェックできます。建物物の構造によっては点検口がない戸建てもあります。そのような戸建てを購入するなら、不具合の責任者を決めておきましょう。
購入する戸建ての条件は優先順位を決めておく
購入する戸建ての条件を家族で話し合い、理想が固まっても全てを満たす物件が見つかる可能性は少ないです。たとえ注文住宅でも、立地で家族の意見が対立することはあります。
慎重に探すのはよいことですが、いつまでも迷っていると購入するタイミングを逃します。理想に近かった物件も売れてしまうかもしれないので、妥協できるポイントを優先順位を付けて決めてください。
さらに決断を早めたいなら、探す期間も決めてしまうと集中して戸建てを探せ、疲弊してしまうこともないです。
家づくり・住まい選びに関する相談ならHOME’Sの「住まいの窓口」がおすすめ
家づくり・住まい選びで悩んでいるならHOME’S 住まいの窓口に相談するのがおすすめです。HOME’S 住まいの窓口がおすすめな理由を以下にまとめています。
※LIFULL HOME'S 住まいの窓口来場者(390組)を対象とした調査(集計期間:2019年4月~2020年3月)より
戸建ての購入で失敗したときの対処法

どんなに注意をしていても、将来突発的な出来事で戸建ての購入は失敗だったと思うことはありえます。もしもの時でも迷わず最善の手を選べるよう、具体的な失敗に対する対処法を紹介します。
実践するのは購入してから10年以上先かもしれないので、頭の片隅に残しておいてください。
ローンの支払いが厳しいなら買い換え
収入の低下や介護による出費の増加などで、ローンの支払いが厳しくなることがあります。滞納が続くと最終的には、購入した戸建てが競売にかけられ、退去しなければならなくなります。
ローンの支払いを何とかし、住居も確保したいなら買い換えを検討してみましょう。ローンが残っていても、売却したお金で完済できるのなら問題ないです。新しい住居は、支払いに無理のない範囲でローンを組めばよいのです。
売却したお金で完済ができないなら、買い換えローンという手段もあります。不足分を新たなローンに上乗せしてお金を借りられます。審査は通常のローンより厳しくなりますが、通れば完済はできます。
買い換えについて、さらに詳しく知りたい人はこちらの記事も参考にしてみてください。

別の家に住むなら購入した戸建てを賃貸にする
購入した戸建ては残しておきたいけれど、別の家に住む必要があるのなら、賃貸にして家賃収入を得る方法があります。残っているローンの支払いは、家賃収入でカバーが可能です。
賃貸するには当然リスクもあります。税金などの維持費はかかり続け、入居者が決まらなければローンの支払いが重くのしかかります。管理は委託できても、出費は増えます。
また将来戻ってくる予定なら、定期借家契約で賃貸にしましょう。普通借家契約では、こちらの自己都合で解約はできません。しかし定期借家契約なら、家賃を通常より安くする必要はありますが、指定した期間が過ぎれば退去してもらえます。
戸建てに欠陥があるなら使える保証の範囲を確認する
入居前に念入りにチェックをしたつもりでも、想定外の欠陥が見つかることはあります。対処法は新築の場合と中古の場合で違います。
新築の場合は、住宅保証の適用範囲を確認しましょう。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)という法律によって、箇所ごとに最低保障期間が定められています。具体的な保障内容は、以下の三つです。
- 欠陥部分の保証
- 損害賠償の請求
- 売買契約の解除
中古の場合は、契約不適合責任という制度を使います。売買契約に記載された物件の状態と異なっていれば適用でき、こちらも契約解除まで可能です。いつまで適用できるかは、売買契約書を確認してください。
まとめ

戸建ての購入は、準備段階からやるべきことが多く不安になってしまいます。後悔は購入してから何年も経ってからすることもあります。
しかし今回紹介した注意点を知っていれば、大きな失敗を避けやすいです。購入の準備、仲介の不動産会社選び、購入する戸建て探しのそれぞれの段階で、ぜひ参考にして計画的に手続きを進めましょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。