不動産売却を行う際、業者に見積もってもらった金額の全てが売却益となるわけではなく、以下のような費用が差し引かれていきます。
- 仲介手数料
- 登記関連費用
- 印紙税
- インスペクション費
- 測量費
- その他税金
- 固定資産税精算金
不勉強のまま売却を進めてしまうと、利用できるはずの控除を利用できなかったり、計画よりも少ない金額が手元に残ったり、思わぬ損をしてしまうかもしれません。実際に残る金額はどのくらいなのかを把握するためにも、当記事で費用について学んでいきましょう。
- 不動産売却では、仲介手数料、登記関連費用、印紙税、インスペクション費、測量費、その他税金などの費用がかかります。費用によっては工夫次第で節約できるものもあるため、自分の状況と照らし合わせて確認しておきましょう。
- 仲介手数料は売却に関する主要な費用で、成功報酬として不動産会社に支払います。登記関連費用は、抵当権抹消費用や司法書士手数料などのことで住宅ローンの有無で金額に差が出ます。印紙税は売買契約書に必要な税金であり、売却金額に応じて税額が決定されます。
- インスペクション費は建物状況調査費とも呼ばれる、建物の状態を調査するための費用です。測量費は土地の境界を確定するための費用で、売主には土地の境界を明示する義務があります。その他税金は所得税や住民税などのことで、譲渡所得が発生した場合に申告と支払いが必要です。
不動産売却にかかる費用「仲介手数料」

仲介手数料は不動産売却にかかる費用の中で最も大きな部分です。このお金は不動産の売却を依頼する宅地建物取引業者に支払います。この仲介手数料は主に不動産を売却するために使う広告費用や、購入希望者との交渉に使うための費用などの仲介業務にかかる費用を指すものです。これは宅地建物取引業法においても定められており、仲介業務に必要となる費用のみに限定されています。
また、場合によっては特別な広告宣伝をしたり、購入希望者のために担当者が出張をした際には別途、費用がかかる場合もあります。このような仲介業務は不動産を売却するためにはかなり重要です。では、その手数料についてさらに詳しくみていきましょう。
売主と買主の間に立つ宅建業者に支払う
仲介手数料について正確にいうと、宅地建物取引業者(=宅建業者)に売主が買主に契約をしてもらうために協力してもらうこと(=仲介)に対して支払う費用です。これは不動産会社に仲介依頼をしてもらうことで成立する契約で「媒介契約」とも言います。売買側はこの仲介手数料の費用に消費税が上乗せされたものを支払うことになります。
また、基本的にこの費用は不動産売却が成立した場合だけの成功報酬であるということも覚えておきましょう。売買契約が締結した際には契約時に仲介手数料の半額を支払い、最終的に不動産売却が完了した際に残りを支払います。
費用発生には要件が定めらている
- 不動産会社と依頼者との間で媒介契約が成立している
- その契約に基づき不動産会社が行う媒介行為が存在する
- その媒介行為により売買契約等が有効に成立する
上記の3つの要件を満たした場合にのみ仲介手数料が発生します。
つまり、不動産会社と依頼者で媒介契約が成立した上で不動産会社が行う媒介行為(=仲介業務)があり、それにより売買契約が成立したことが条件ということです。それが成立した場合にのみ、媒介契約の要件に満たされるとして仲介手数料の費用が発生します。
上限額がある仲介手数料の相場
次に仲介手数料の相場についてもみていきましょう。基本的に不動産会社が受領できる仲介手数料には以下の上限が定められています。
| 不動産売却費用に対する仲介手数料の上限 | 売却費用の計算式 |
| 200万円以下の売却価格の上限 | 売却価格 × 5% + 消費税 |
| 200万円を超え400万円以下の売却価格の上限 | 売却価格 × 4% + 消費税 |
| 400万円を超える売却価格の上限 | 売却価格 × 4% + 消費税 |
このように仲介手数料は売却金額ごとに計算式が決まっており、不動産会社が貰える仲介手数料は正確に算出することができるのです。これは国土交通省が「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」として定めています。目安として例にすると、例えば、売却価格が3,000万円だった場合には、10%の消費税を含めた仲介手数料は105万6,000円です。
また、上限があったとしてもそれぞれの不動産会社が同じ仲介手数料とは限りません。なぜなら、不動産会社の仲介手数料の半額キャンペーンや、親類への不動産売却などで安く済む場合もあるからです。そのようなキャンペーンを実施している場合は仲介手数料を安くしてくれる可能性もあります。そのため、さまざまな不動産会社の仲介手数料とキャンペーンについて見比べておくと良いでしょう。
また、仲介手数料は業者によって異なります。しかし、1件1件不動産会社に出向いて複数社の仲介手数料を調べるには店舗へ出向くなど手間がかかります。不動産一括査定サービスを利用することで手間がかからず知ることができるので、利用をおすすめします。
おすすめの一括査定サイトは「すまいステップ」

- 初めてで不安だから実績のあるエース級の担当者に出会いたい
- 厳選された優良不動産会社のみに査定を依頼したい
- 悪徳業者が徹底的に排除された査定サイトを使いたい
\ 厳選した優良会社に査定依頼 /
すまいステップで一括査定する

400万円以下の場合には現地調査費がかかる場合もある
もし不動産の売却価格が400万円以下の場合なら注意が必要です。なぜなら、2018年より地方の空き家の売却が進まないことを受け、要件に追加があったためです。それは400万円以下の物件に関しては不動産会社が現地調査費等の費用相当額が請求できるというものです。
この場合の上限は18万円になります。万が一、400万円以下だから見当しないだろうと考えていると思わぬ出費に驚いてしまうかもしれないので注意してください。
不動産売却にかかる費用「登記関連費用」

次に不動産売却にかかる費用は登記関連です。登記関連費用ではいわゆる住宅の抵当権の抹消費用やその申請をお願いする司法書士手数料になります。主に住宅ローンが残ってる物件を売却する際に発生する費用のため、ローンが残っているか否かで費用が変わることが特徴です。
抵当権の抹消費用
そもそも抵当権というものはローンの返済が滞った際に銀行が差し押さえる権利があるというものです。そのため、差し押さえられる可能性がある不動産は買い手に好まれません。そのため、基本的には不動産売却の際に住宅ローンを全額返済した上で、この抵当権を抹消することが必要になります。
また、その場合には「抵当権抹消登記」が必要となり、そのために登録免許税も支払う必要があるでしょう。具体的には登記簿謄本から登記を抹消する費用として不動産1つにつき1,000円を法務局に支払うことになります。さらに、土地や建物にも抵当権がある場合は、そちらもそれぞれに1,000円を支払うことになるでしょう。
司法書士手数料
抵当権の抹消は基本的に司法書士が代理で行います。抵当権抹消登記は自身ですることも可能ではありますが、書類作成や法務局へ出向く必要があったりなど複雑で手間がかかる作業です。そのため、司法書士に頼むのがおすすめではあります。
もし司法書士に代理を頼む場合は希望に応じて、不動産会社が司法書士に依頼することになるでしょう。その際の司法書士手数料の相場は不動産1つに対して5千円~3万円程度といわれています。地区によって若干相場に違いがあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
また、個人で抵当権抹消登記をする場合では1,000円程度と安上がりではありますが、かかる手間や時間を考えると司法書士に代理を頼むのが無難と言えます。
不動産売却にかかる費用「印紙税」
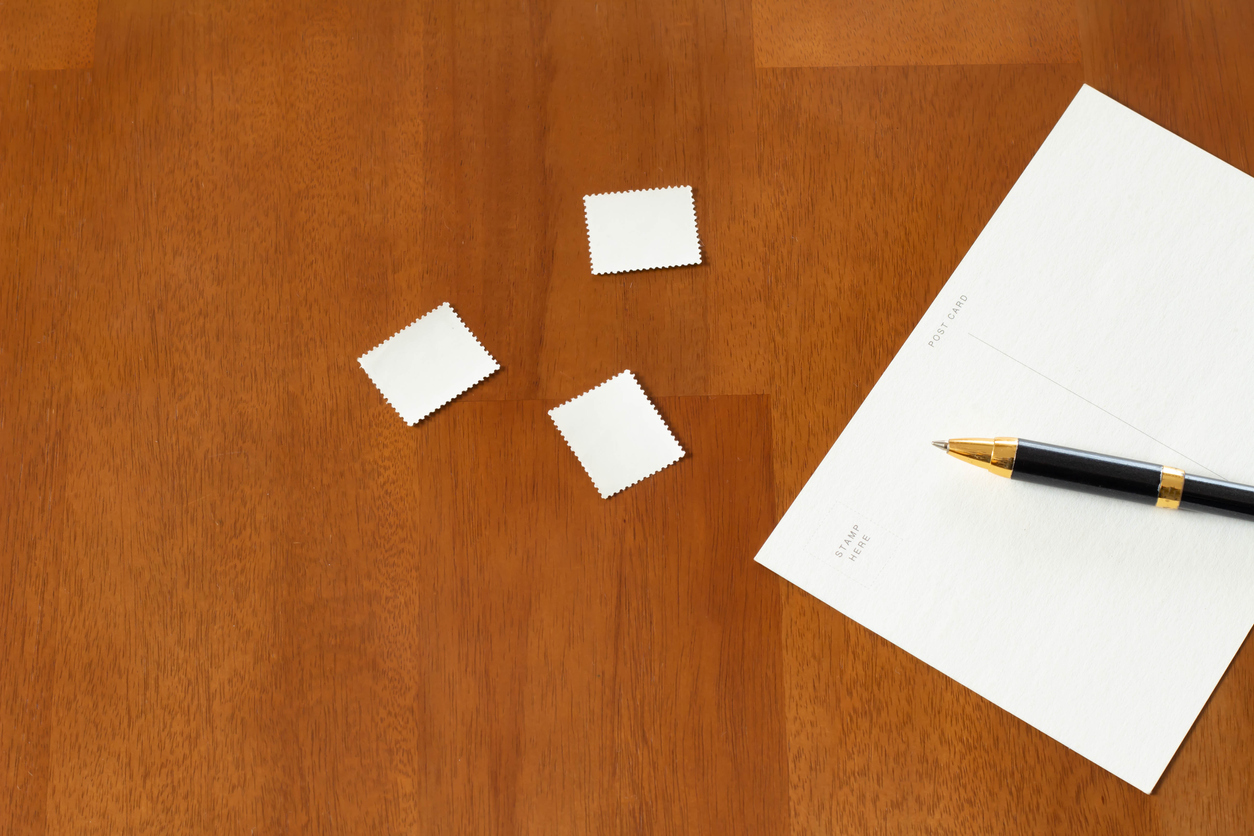
印紙税も忘れてはいけない費用の一つです。印紙税は不動産売買で契約を結ぶ「売買契約書」に必要な税を指します。売買契約書に貼るために必要になるもので、必ず決まった金額の印紙を貼ります。定められた金額の印紙を貼って消印することでようやく納税したことになるのです。印紙税の金額は不動産の売買金額にもよりますが、1万円~3万円程度が一般的とされます。
売買契約書の印紙税の金額は以下の通りです。
| 不動産の売却金額 | 印紙税 |
| 100万円以上500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円以上1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円以上5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円以上1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円以上5憶円以下 | 60,000円 |
また、この税額は国税庁によって不動産売買を促進するために軽減措置が講じられているものになります。これは平成26年4月1日~平成32年3月31日までの間の10万円を超える不動産売買が対象になっています。そのため、この期間中であれば本来の印紙税の税率より税が安く済むのです。
2通分の印紙税が必要となる
印紙税で注意が必要なのが、契約書の数だけ印紙税が必要になるということです。売買契約書は基本的に売主と買主のそれぞれの保管用の契約書に印紙を貼付する必要があります。つまりは売主と買主の契約書で2通分の印紙税がかかるということです。しかし、この2通分の印紙税は売主が全てを負担するわけではなく、売主と買主がそれぞれが負担することが一般的になります。
不動産売却にかかる費用「インスペクション費」

インスペクション費は建物状況調査費とも呼ばれる不動産を調査する費用のことです。このインスペクション費の相場は5万円~20万円といわれており、金額に幅があることが特徴です。これは延床面積によって金額が変動したり、給排水管検査などのオプション検査によって変わるためです。
具体的にどのような調査があるかと言うと、建築士が目視で住宅基礎や外壁などの調査をすることに加え、計測機器を使用した計測なども行います。さらに床下の調査も行い、シロアリなどの害虫被害なども確認します。
なぜこのような調査が必要であるかと言うと、不動産がどんなものでどんな状態かは不動産を売却する上で売主にアピールすることに関わってくるからです。不動産売却は基本的に中古物件であるため、日常生活に起きうる劣化や性能低下がないかはかなり重要です。そのため、建築士に依頼し、しっかりとお墨付きを貰うことで買主に不動産に興味を持ってもらいやすくなる情報が集まるでしょう。
また、インスペクション費ではインターフォンや浴室乾燥機などの住宅設備については除外されるので注意してください。住宅の生活の根幹に関わる部分が中心で、住宅設備に関しては売主自らが作動確認をすることが必要です。その際は付帯設備表と呼ばれる調査シートを使って、自ら調査を行うことになります。
瑕疵担保保険への加入が必要
インスペクションを行うことのメリットの1つとして、瑕疵担保保険に加入できるということがあります。瑕疵担保保険はインスペクションを行うことで加入できる保険です。内容は住宅に瑕疵(=予期し得ない欠陥)が発生した際に保険で修繕することができるというものになります。例えば万が一予期しない欠損があった場合、売主に資力が無くてもこの保険に入っていれば修繕が可能になるのです。買主と売主の双方にメリットがある保険なので、不動産売却においてメリットとしてアピールできるでしょう。
また、住宅ローン控除も適応できるため、税金対策においても加入がおすすめです。
不動産売却にかかる費用「測量費」

測量費とは手持ちの不動産(土地)と隣地との境界を測量するための費用です。具体的には土地家屋調査士へ依頼することになります。売主には不動産を売却する際に境界をはっきり明示する義務があるため、この測量は必須です。費用は市や国の立ち会いの有無で変わりますが、50万円~100万円が相場といわれています。この測量は定型業務であるため、調査士次第では金額が変わらないことも特徴です。
測量がなぜ必要かについてさらに具体的に見てみましょう。
売主には土地の境界を明示する義務がある
もしすでに「確定測量図」という測量図がある場合は隣地との境界が確定していることになるため、測量は必要ありません。しかし、古くからある土地の場合は隣地との境界が明瞭ではないケースがあります。その場合買主は、隣人との境界トラブルを避ける為、測量を行う必要があるでしょう。
トラブルを避けるためにも現代では境界がはっきりとしていることを買主は望むケースが多くなりました。そのため、測量を行って境界を明確に示すことが必要不可欠になったのです。具体的には隣地との境界を指す「民々境界」、道路との境界を指す「官民境界」の2種類があります。この2つの境界は売主も明示する義務があるのです。
また、隣地所有者と境界を確認しあったら「筆界確認書」と呼ばれる覚書で締結することになるでしょう。もし、筆界確認書が存在しなくても逆に「確定測量図」があった場合は境界が間違いなく確定している証明になります。
半年以上かかることもあるため早めの準備が必要
境界が確定してない場合には測量が必要となりますが、その場合は時間がかかると認識しておく必要があるでしょう。なぜなら、境界確定には隣地所有者の同意を得る必要があるからです。さらに官民の境界を確定するには、道路の反対側の土地所有者の同意も得る必要があることもあります。
このように土地所有者が多い場合には、測量に半年以上時間を要することもあるのです。そのため、確定測量を行う場合には、早めに依頼することが重要になります。具体的には測量会社に「確定測量図」の作成を依頼するという形になるでしょう。不動産売却の作業の中でも測量は比較的時間が必要になる作業といわれているので、早めの依頼がおすすめです。
不動産売却にかかる費用「その他税金」

不動産売却においてかかる費用の中には雑多な税金もあります。例えば不動産売却で譲渡所得が発生した場合は所得税や住民税、復興特別所得税が生じる場合があるでしょう。譲渡所得は不動産売却で得たお金の金額によって税金がかかります。
具体的には
で算出することができます。
つまりは仲介手数料、印紙税、測量費用などを差し引いた額が純粋な利益である譲渡所得となるのです。そのため、もし譲渡所得で利益が出ていない場合には申告する必要はないでしょう。
3,000万円特別控除が適用されるケースもある
譲渡所得では3,000万円を控除してくれる特例もあります。例えば3,000万円特別控除を適用して譲渡所得が0以下となれば、所得税および住民税、復興特別所得税は発生せず税負担が重くならないのです。ただし、これは居住用財産のみの適用となります。そのため、基本的にマイホームが対象となり、アパートや投資用のワンルームマンション、ただの更地は適用となりません。
不動産売却にかかる費用「固定資産税精算金」

最後に覚えておきたいのが「固定資産税精算金」についてです。固定資産税、つまりは不動産などの固定資産に対して納める税金のお話になります。この固定資産税は1月1日時点で資産を所有するものが納税義務者となります。
しかし、そうした場合は不動産売却などで不動産を手放したにもかかわらず、固定資産税払わなければいけないことになります。すでに手放した売主が固定資産税を払うのは不合理でしょう。その場合には売主が買主からその年の残りの固定資産税を貰い、精算するという方法があるのです。これが固定資産税精算金といいます。ただし、これは買主が自ら行う義務はないため、売主が主張して初めて成立するため注意しましょう。
管理費や修繕積立金
もし不動産がマンションなどであった場合、管理費や修繕積立金がかかります。その場合はその費用を翌月分当月末払いで支払うことはよくあることです。もしこれが不動産を手放した以降の精算になる場合には、これも固定資産税と同じく、買主に負担を請求しても良いとされています。その場合は売主と買主で精算を行うことも可能ということも覚えておきましょう。
不動産売却をして戻ってくる費用もある

最後に不動産売却において戻ってくる費用についても見ていきましょう。出費が多い不動産売却でも保険や一部税金が戻ってくる場合があります。知らずにいた場合はそのお金がリターンしてこないこともあるため、なるべくお金を手元に残すためにも、どんな費用が戻ってくる可能性があるのか知っておきましょう。
火災保険料
火災保険は保険料を返還してもらえることがあります。これが見当するのは、例えば火災保険に長期一括契約で契約していた場合です。不動産売却時に契約を途中解約することで、残りの年数分の保険料を返還してもらえます。ただしこれは契約した保険会社で解約手続きが必要になるので、忘れないように注意しましょう。
銀行保証料
住宅ローンを組んでいて保証会社に保証料を支払っていた人は銀行保険料も返還してもらえることがあります。不動産を売却する際の抵当権の抹消に伴い、残りの期間分の保証料が戻ってくるのです。これには保証料を支払っている状態かどうか確認が必要になるため、見当する保証会社で確認してみましょう。
所得税及び住民税の還付
居住用財産の売却で譲渡損失が発生した場合は所得税の還付を受けられます。譲渡損失は「譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用」で算出し、マイナスとなった譲渡所得が譲渡損失にあたるかが焦点となるでしょう。その際には必ず3,000万円特別控除を適用する前にマイナスになるか、まずは判断する必要があります。
また、譲渡損失は損失が発生していても確定申告が必要なことも盲点です。たとえ損失があったとしても、不動産の費用や税金で損をしないためにはしっかりと確定申告をすることが必要ということを覚えておきましょう。
まとめ

不動産売却では多くの費用がかかります。仲介手数料や登記費用、印紙税など事務作業的な部分でかかる費用もあれば、インスペクション費や測量費といった不動産の査定に関わる費用もあります。さらにそこに税金もかかってくるのです。それぞれの費用を合わせると自らの負担は相当大きなものとなるでしょう。
そのため、せっかく不動産でお金を得ようとしていても、上手く費用を抑えるやりくりがなければ損をしてしまう可能性が高くなります。大切な資産であるからこそ、損をしてしまわないように各要件をしっかりと確認し、費用を抑えていくことが大切です。まずはご紹介した算出方法や各要件をチェックして、ぜひ不動産売却における費用の見直しをしてみてくださいね。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。


