「農業を引退して別の事業を始めたい」「農地を相続したけど自分は農業をする予定はない」などの理由で、農地の売却を検討される人は多いのではないでしょうか。
実は、戸建てなどの一般的な不動産と違い、農地の売買は農業委員会からの許可が必要となり、簡単には売却することはできません。また、売却手段は農地のまま売却する方法と転用して売却する方法とに分かれ、それぞれに確認事項が異なります。
この記事では、農地のまま売却or転用して売却のそれぞれに着目し、条件や手続きの流れ、売却にかかる費用や税金など詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産一括査定サイト利用者が選んだおすすめサービスTOP3
この記事を読まずに、先におすすめの査定サービスを知りたい人におすすめなのが、以下の3サービスです。 マイナビ編集部で実施した独自アンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声と編集部の知見が合わさってできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)
\\この記事は専門家監修のもと作成しています//
- 農地の売買は農業委員会からの許可が必要で、農地のまま売却する方法と転用して売却する方法の2種類あります。
- 農地のまま売却する場合は農業を専業とする人にしか売れません。農地を転用して売却する場合、立地基準と一般基準の両方で条件を満たしている必要があります。
- 農地は売却しづらい不動産ですが、放置してしまうと固定資産税の負担がかかったり農地の価値が下がったりなどといったリスクがあります。自分で農地を活用することが難しい場合、農地の買取を行う不動産会社を頼ることも検討してみましょう。
農地売買の条件

「農地の売買には許可が必要」と述べましたが、そもそも所有者は自分なのになぜ自己判断では売却できないのでしょうか。それは、農地が食料を生産できる国にとって貴重な土地と考えられているからです。簡単に別の用途に変えてしまうことは大変リスクが伴うため、以下のように厳しい条件が定められています。
農地のまま売却する条件
まず前提として、農地は現在農業を専業とする人にしか売ることができません。なお、これから新しく農業を始めるという人や、投資目的の場合も売却できない仕組みとなっています。
具体的には、以下の条件をクリアしている農家に対してのみ、売却することが可能となります。
- 専業の農業従事者である
- 取得後50ha以上(地域により異なる)の農地を保有している
- 所有農地のすべてを耕作している
- 農業のための人材・機械を所有している
このように農地売却は通常の不動産売却よりも買い手が限られ、査定価格が上がりづらいです。場所や広さなどによっては、売却に相当の時間を要することあります。
転用して売却する条件
農地転用とは、農地を農業以外の目的で利用することです。農地を相続した場合や、農業を引退したいといった理由で、地目を変えて駐車場にしたり店舗や家を建てたりするなどの例があります。
しかし、この場合も自己判断での決定はできず、許可が下りなければ転用はできません。転用可否は立地基準と一般基準という2つの条件をもとに審査されます。
立地基準をクリアする
農地は下記の5つの種類に分けられており、基本的に転用が可能となるのはそのうちの第2種農地と第3種農地のみです。この区分けを立地基準と呼びます。自分の農地の立地基準は、管轄エリアの農業委員会に問い合わせて確認しましょう。
| 農地区分 | 転用許可 | 内容 |
| 農用地区域内農地 | 不許可 |
|
| 甲種農地 | 不許可 |
|
| 第1種農地 | 不許可 |
|
| 第2種農地 | 一部許可 |
|
| 第3種農地 | 許可が下りやすい |
|
上記のように、市街地に近い農地ほど許可が得られやすい傾向があります。第2種農地や第3種農地のような市街地化の傾向が著しいエリアに関しては、「農地として残すよりも他用途に変更したほうが効率がよい」と判断され、許可が下りやすくなるのです。
一方、農用地区域内農地や甲種農地、第1種農地などは、農業に適したエリアと判断され、基本的に転用の許可が下りないと考えておきましょう。
一般基準をクリアする
立地基準を満たしても、次のような一般基準を満たさなければ転用はかないません。
- 転用する事業が申請通りに行われるか
- 転用後の事業を不備なく運営できる資金・計画性があるか
- 周辺農地への影響を与えないか
このように、転用したのちどういった目的で使用されるのか、それが地域にとって悪い影響を与えないかといったことを審査されます。たとえば、第三者に土地を貸している場合は、借主の同意を得なければ転用はできず、埋め立てて住宅を建てる場合は、雨水が隣接する畑に悪影響を及ぼすようでは許可は得られません。
確実に転用目的が達成されるとわかるよう申請しなければ、農地転用を認めてもらうことは難しいでしょう。
農地売却ならイエウールがおすすめ

- 月間ユーザー数No.1で安心(2020年7月時点)
- 提携している不動産会社の数も業界No.1(2020年7月時点)
- 全国エリアをカバーしているので地方の不動産も売却しやすい
- 田んぼや畑など農地の売却にも対応している
- 悪徳業者が排除される仕組みがあるので安心して利用できる
※2020年7月「不動産の一括査定サイトに関するランキング調査」より(株)東京商工リサーチ調べ
\全国カバー率No1のサービスで査定依頼/
イエウールで一括査定する
農地のまま売買する手順

農地を農地のまま売却する流れは、一般的に次の通りです。
- 買い手を探す
- 売買契約の締結
- 農地売却の許可申請を行う
- 買い手が仮登記を行う
- 売却許可後に本登記と精算
それぞれの詳細を見ていきましょう。
1.買い手を探す
農地のまま売買する場合は、最初に買い手を見つけます。買い手の見つけ方はそれぞれですが、以下の方法が一般的です。
- 近所の農家などに買い手がいないか自身で探す
- 農業委員会などの農業関連機関を利用して探す
- 農地を扱う不動産会社に相談する
農業委員会に相談すると、近隣で農地を求めている人を紹介してもらえます。紹介してもらうには、斡旋(あっせん)申込書を提出し、斡旋委員を介す必要があります。
また、なかなか買い手を見つけられない場合は、農地を扱っている不動産会社に相談することもおすすめです。ただし、農地の売買を取り扱う不動産会社は少なく、近隣の不動産会社では対応してもらえない可能性もあります。
2.売買契約の締結
農地の買い手が見つかったら、売買契約を締結しましょう。農地を売るには農業委員会の許可が必要ですが、許可までに時間がかかるので、許可を得る前に買い手と売買契約を締結します。
「許可を得る前に売買契約を結ぶのは不安…」と思われるかもしれませんが、買い手が不明だったり、売却の成立が不透明だったりすると許可が下りない可能性が高くなります。契約書に「売却許可が得られなかった場合は契約を白紙にする」などと明記して、農地を先に売買契約を締結しましょう。
また、通常の不動産売買のように価格交渉も行います。農地の価格を決定する主な要素は次の通りです。
- 日照や雨量、土壌・土層の状態
- 農道や灌漑(かんがい)排水の状態
- 集落・集荷地との接近程度
- 災害の危険性
同じ農地でも、田か畑かによって価格が変化します。一般的に田んぼのほうが高い傾向です。また、地方の純農業地域と市街地の都市的農業地域を比べても、価格は大きく異なります。
3.農地売却の許可申請を行う
売買契約を締結した後、所轄の農業委員会に売却許可を申請します。農地の状況や売り手の審査だけでなく、提出した書類をもとに、買い手が新しい所有者として適切かを含めて審議されます。許可申請の結果がわかるまでは1~2ヶ月程度かかります。
農地売却の許可申請に必要な書類は次の通りです。
- 登記事項証明書
- 賃借人等の同意書(農地を貸し出している場合)
- 相続関係図等(登記名義人が死亡している場合)
- 公図の写し
- 位置図
- 付近見取図
- 法人調書(買い手が法人の場合)
- 営農計画書
- 耕作証明書
- 売買契約書の写し
- 農地等権利移動許可申請書
以上は一般的に必要とされる書類で、各農業委員会ごとに異なる場合もあるため、事前に自治体のホームページ等で確認しておきましょう。
4.買い手が仮登記を行う
売却許可が下りるまでの間に、買い手は所有権移転請求権仮登記を行います。仮登記は通常の不動産売買ではほとんど行われないため、耳馴染みのない人も多いでしょう。仮登記は、あくまで仮に所有者を買い手に移転するもので、登記を確定しているものではありません。
ただし、仮登記は必ずやらなくてはならないものではないということは念頭に置いてきましょう。仮登記には固定資産税評価額の1%分の登録免許税や司法書士報酬がかかるため、行わないケースもあります。しかし、仮登記を行うことで、売却の意思を明確に示すことができ、その後の本登記も楽になるというメリットが得られます。
5.売却許可後に本登記と精算
売却の許可が下りたら、農地の引き渡しと本登記が行えます。
引き渡しは売買契約書に則って決定しましょう。売買代金を精算し、農地を引き渡したら売買が完了します。仮登記から本登記への切り替えも引き渡し日に並行して行うことが多いです。本登記に売買許可証の提示を求められることがあるため、引き渡しに持参するとスムーズです。
農地売買自体はこれで完了ですが、売却で利益を得た場合には確定申告をする必要があるため忘れないようにしましょう。
転用して売買する手順

農地を転用して売却する際のフローは次の通りです。
- 不動産会社に売却の依頼をする
- 農地転用の許可申請を行う
- 売買契約の締結
- 買い手が仮登記を行う
- 転用許可後に本登記と精算
それぞれのステップの詳細を見ていきましょう。
1.不動産会社に売却の依頼をする
農地を転用して売買する場合、農地売買に強い不動産会社に売却の依頼しましょう。農地売買の経験豊富な不動産会社なら、転用のややこしい手続きも相談しながら行うことができます。
また、経験豊富な会社であれば、農業委員会の転用許可を下りやすくするノウハウを知っている可能性があります。そうした会社や担当者なら、信頼して売買を任せられるでしょう。不動産会社を探す際は、農地売買の実績をチェックしてみてください。
2.農地転用の許可申請を行う
続いて、農業委員会で転用の許可申請を行います。自分で申請することも可能ですが、複雑な書類も多いため、行政書士に委託することもできます。転用許可申請に必要な主な書類は次の通りです。
- 登記簿証明書
- 賃借人等の同意書(農地を貸し出している場合)
- 相続関係図等(登記名義人が死亡している場合)
- 位置図
- 公図の写し
- 周辺土地利用状況図
- 現況写真
- 事業計画書、土地利用計画図等
- 建物等の平面図、排水計画図等
- 資金計画書
- 預貯金残高証明書、融資見込み証明書
- 土地改良区の意見書
- 地区除外申請書
このほかにも転用目的によって追加の書類が必要な場合もあります。自治体ホームページや農業委員会の窓口などで事前にチェックしておきましょう。
また、農地が4ha以上の場合は農林水産大臣、4ha以下の場合は都道府県知事の許可が必要です。それぞれに宛てた農地転用申請書を農業委員会に提出することになります。
3.売買契約の締結
買い手が見つかったら、農業委員会からの許可を得る前提で売買契約を結びます。どのタイミングで買い手が見つかるかによって、この手順が前後することもあるでしょう。
売買契約は、曖昧な利用目的で交わすことはできません。転用申請に出した目的に準じた利用が見込まれる買い手と売買契約を結びましょう。
農業委員会からの転用許可が下りるまで約1~2ヶ月かかるといわれています。万一、許可されなかった場合は事前に交わした売買契約は無効となるよう、契約書に明記しておくとトラブルを防げます。
4.買い手が仮登記を行う
転用して農地を売る際も、許可が下りる前に買い手が所有権移転請求権仮登記を行います。仮登記をすることは、次のような目的で行われます。
- 許可が下りるまで別の人に売買しないことの約束
- 許可が下りた場合、確実に買い手に所有権を移転する
こうした意味を持つ仮登記ですが、転用の場合も絶対に必要な手続きではありません。しかし、トラブルを防ぐためには必要な手続きです。例えば、仮登記をしないと、転用許可が下りなかったことにして契約を破棄し、ほかの人に売却するといったことが起り得ます。このように、仮登記は買い手の安心につながります。
5.転用許可後に本登記と精算
農業委員会より許可が下りたら、精算して引き渡しを行い、所有権移転の本登記を進めます。大筋の流れは農地をそのまま売却するときと同様です。
転用許可が取れるまで、買い手を数ヶ月待たせることになります。許可後、できるだけスムーズに手続きを進めて、双方が納得できる取引になるように心がけましょう。
また、農地のまま売却するときと同様に、売却で利益を得た場合は確定申告が必要です。
農地売却の方法についてより詳しく解説したこちらの記事もおすすめです。

農地を売却しない場合のリスク

前述したように、農地を売却するには許可申請など、複雑な手順を踏む必要があります。「めんどうだからそのままじゃいけないの?」「遠方にあるから売却するほうが大変…」と考える人も多いでしょう。
しかし、農地は売却しないで放置しているとデメリットの大きい資産です。デメリットを受けないために、使わない農地は売却することをおすすめします。具体的に次のようなリスクが考えられます。
- 固定資産税の負担が大きい
- 農地が劣化する
- 周囲の農家に迷惑がかかる
本章では、以上のリスクを詳しく見ていきましょう。
固定資産税の負担が大きい
まず、農地は使用しないで持っているだけでも固定資産税がかかります。税額は農地の評価額によって異なり、毎年1月1日時点の持ち主に課せられる決まりです。放置していても毎年税額の負担があることはデメリットです。
さらに、放置を続けることでその負担が増える恐れがあります。これは、近年増加する遊休農地や耕作放棄地を減らすための対策で、本来農地に対して適用される減税措置が適用されなくなるのです。
課税対象の評価額が1.8倍にも膨れ上がるため、売却しないで放置することで負担が大きくなってしまいます。
耕作放棄地について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

農地の価値が落ちる
通常の更地に比べ、農地は放置によるダメージが激しいといわれています。適切な管理が行われなければ、農地はみるみる劣化していくでしょう。放置された土地は、資産としても農地としても価値が下落してしまいます。
価値が下落した農地は、いざ売却しようと思ったときに買い手が見つからない場合が多いです。伸びた雑草を取り除き、生産力のある農地に戻すためには、手間や時間、費用がかかります。売却活動が大変だからといって後回しにするよりも、すぐに売却したほうが時間や費用の節約になるでしょう。
周囲の農家に迷惑がかかる
農地を放置することで、周囲の農地にも悪影響が出る場合があります。
管理しないでいると、農地には雑草が生い茂り、農薬の散布もないため虫が増えます。それに伴って動物が出現するようになったり、ゴミを不法投棄されたり、さまざまなトラブルにつながることも珍しくありません。
こうしたトラブルは、周辺の田畑にも影響します。現れた動物や虫によって農作物が襲われることや、ゴミが土に悪影響を及ぼすこともあるでしょう。自分の畑が受けた被害が、隣の放置された農地を原因としているとわかれば、損害賠償を請求される恐れもあります。
近隣農家とのいざこざに発展すると、その後の売却や転用にも影響します。こういった事象を防ぐためにも、農地が荒れる前に売却しましょう。
農地売買の注意点
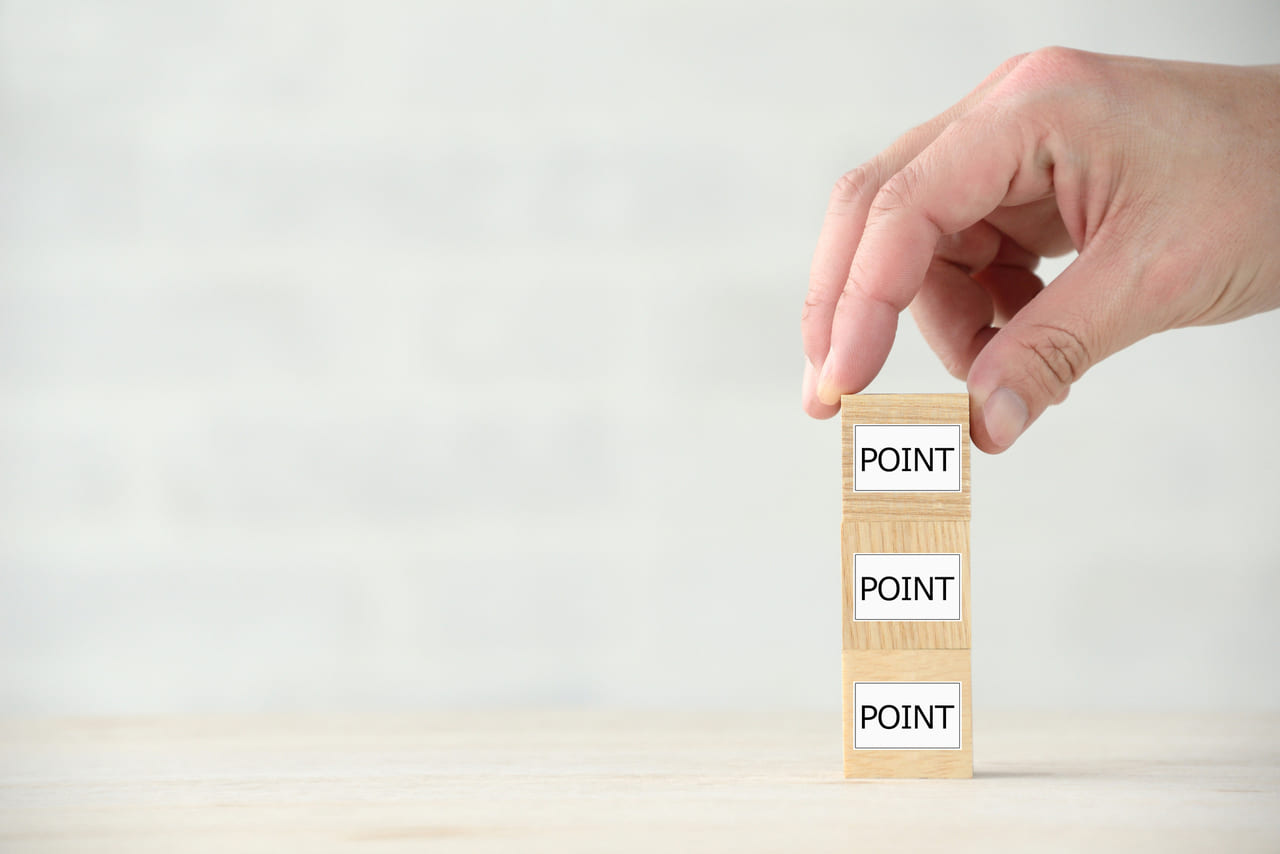
農地の売買で失敗したくない人は、以下の点もおさえておきましょう。
- 周辺環境の整備が必要なケースもある
- 農地売却に強い不動産会社を選ぶ
- 農地が荒れていると売買できない
- 転用後は速やかに売却する
- 不許可の場合は違約金が発生しない
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
周辺環境の整備が必要なケースもある
農地を転用し宅地として売買する場合、周辺環境の整備が必要になることもあります。具体的には、接道義務を満たすように道路整備を行うケースが多いです。
宅地として売却するなら、当然建築基準法を満たさなくてはいけません。建物を建てるには、建築基準法で認められた道路に面する土地である必要があります。周辺が農地に囲まれて道路がない場合、そのままでは宅地に転用することはできません。道路と接するように宅地を設定する、または道路整備をすることで宅地として認められます。
道路整備には費用がかかり、制限によって自由に整備できないことが多いので、専門家の意見を聞きながら慎重に進めましょう。
農地売却に強い不動産会社を選ぶ
農地を売却するなら、実績のある不動産会社を選ぶようにしましょう。農地の売買には許可や届出が必要で、宅地の取引よりも難しいといわれています。
農地売買の実績だけではなく、担当者が信頼できるかをチェックするとよいです。売り手の要望や不明点をきちんとくみ取り、対応する力量や誠実さがあるかどうかの見極めが重要になります。
よい不動産会社を効率よく見つけるためには、一括査定サイトの利用がおすすめです。一括査定サイトなら、複数の不動産会社にまとめて査定依頼ができ、手間や時間が省けます。
また、査定額だけで不動産会社を選ばないようにしましょう。あえて高い査定額を提示し、契約を結ぶことだけを目的とした悪徳業者も存在します。金額だけでなく、実績や担当者の力量で選びましょう。
一括査定サイトに関してより詳しく知りたい人はこちらの記事をお読みください。

一括査定サービス利用者が選んだおすすめサービスTOP3
※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)
こちらは、サービス利用者のアンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声と編集部の知見が合わさったできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。
なお、不動産一括査定サービスは、それぞれ対応するエリアや提携する不動産会社が異なるため、1つだけでなく複数のサービスを利用することをおすすめします。
次の記事ではより多くのサービスを含めたランキングや「査定結果の満足度TOP3」や「親族・友達におすすめしたいTOP3」などカテゴリ別にもランキングを紹介しています。さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。

農地が荒れていると売買できない
放置されている遊休農地や耕作放棄地は、買い手が現れにくいです。荒れた農地を売却したいのであれば、事前に手入れをしておきましょう。手入れは業者に依頼したり、近隣の農家に耕作してもらったりする方法があります。
耕作放棄地を手入れせずに手放したいなら、農地バンクに登録しましょう。農地バンクでは、再生できる耕作放棄地を借り受け、大規模農家に貸し出す取り組みが行われています。借り手が見つかれば賃料を得られ、農地が荒れることもありません。
また、自治体で補助金が設けられ、耕作放棄地の再生に必要な費用を一部補助してくれる場合もあります。条件や補助金についての詳細は、各自治体に確認してみてください。
転用後はすみやかに売却する
農地を転用した後はすみやかに売却しましょう。農地の転用は、農地以外の用途で所有者が使用する場合と、第三者に売却する場合にのみ許可されます。転用後に土地を少しだけ利用して売却するといったことは認められません。
また、2022年以降、売却価格が下降する可能性もあります。農地の税制面などを優遇されていた生産緑地が、2022年に解除されるため、多くの農地が売りに出されると予想されているからです。これを2022年問題と呼ぶこともあります。こうした事情で価格が下落することも考慮して、農地はなるべく早めに売却しましょう。
2022年問題について詳しく解説した次の記事もおすすめです。

不許可の場合は違約金が発生しない
農地売買の許可が下りなかった場合、売買契約は無効化されます。許可が下りなかったときの契約解消では、違約金は発生しないため安心してください。
通常の不動産売買であれば、売買契約締結後に契約解除しようとすると、ペナルティを受ける場合がほとんどです。農地売買の場合は、売買契約書に「不許可になった場合に契約を白紙にする」という条項を明記するため、違約金なく取引することができます。
ただし、売買契約時に買い手から支払われた手付金は、契約解除時に返還しなければならないため注意しましょう。
農地売買にかかる費用や税金

農地を売る際も、通常の不動産売買のように費用や税金がかかります。費用を想定しておかないと、思わぬ出費で転用後の事業がうまくいかない恐れもあります。きちんと把握しておきましょう。
農地売買にかかる費用
農地売買に必要な費用は、主に次の2つです。
- 仲介手数料
- 行政書士報酬
売却の仲介業務を不動産会社に依頼すると、仲介手数料がかかります。その金額は農地の売買金額に応じて計算されます。不動産会社によっても異なるため、依頼する前に確認しておくと安心です。
不動産売買における仲介手数料について詳しく解説したこちらの記事もおすすめです。

農地売買にかかる税金
農地売買に必要な税金は、主に次の3つです。
- 譲渡所得税と住民税
- 売買契約の印紙税
- 抵当権抹消登記の登録免許税
それぞれを深掘りしていきましょう。
譲渡所得税と住民税
不動産を売却して得た利益を譲渡所得といい、それに対して所得税と住民税が発生します。譲渡所得の計算式は以下の通りです。
このように、売買金額がそのまま譲渡所得になるのではなく、農地の取得や売却にかかった費用を差し引いて計算します。
税率は以下の通りです。
| 所有期間 | 所得税(復興特別所得税を含む) | 住民税 |
| 5年以下の短期譲渡所得 | 30.63% | 9% |
| 5年を超える長期譲渡所得 | 15.315% | 5% |
譲渡所得についてより詳しく知りたい人はこちらの記事もご覧ください。

印紙税
印紙税とは売買契約書に貼り付ける収入印紙代のことです。税額は契約する金額によって以下のように変動します。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万円超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超え1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超え5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超え10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超え50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超え | 60万円 | 48万円 |
軽減税率が適用されるのは、2022年3月31日までに作成される契約書とされています。印紙税を節約するという面でも、早期の売却がおすすめです。
登録免許税
売却する農地に抵当権が設定されていた場合、売却時に抹消する登記手続きを行う必要があります。
抵当権とは、ローンを組んで購入する際、その資産を金融機関の担保として設定する権利のことです。抵当権が行使されると、金融機関が農地を競売にかけるなどして売却することができます。ローンを完済すると、抵当権を抹消することが可能です。抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1つあたり1,000円かかります。
また、所有権移転登記の登録免許税は、原則買い手の負担です。
農地売買で適用できる減税制度
控除制度を利用することで、農地売買にかかる税金を節税できる可能性があります。主な特別控除制度は以下の通りです。
| 控除制度 | 条件 |
| 800万円の特別控除 |
|
| 1,500万円の特別控除 |
|
| 5,000万円の特別控除 |
|
以上のような条件を満たす農地売買なら、税金の負担を軽減できるでしょう。
不動産売却にかかる税金についてはこちらの記事もおすすめです。

農地売却にかかる税金を一覧化したこちらの記事も参考にしてください。

農地売買でよくある疑問

最後に、農地売買でよくある疑問をQ&A方式でまとめました。農地売買についての疑問解消にお役立てください。
農地は売却しづらい?
通常の居住用マンションやアパートなどと比べてしまえば、農地は売却しづらい不動産だといえます。農地のまま売却する場合、買い手が農業を営んでいる人に限定されるため、特に売却は難しくなるでしょう。
農地売却は、近隣農家に農地を手放したい旨を相談し、買い取ってくれる人がいないか探すことから始めましょう。周りに購入希望者がいなければ、転用を視野に入れて活動を始める必要があります。
早期の売却を希望しているなら、農地の買取を行う不動産会社を頼るのも手です。買取は、通常の売却と異なり、不動産会社が直接買い手となるため手間がかからず、早期売却が目指せます。ただし、金額は仲介売却の7~8割ほどになるため、高額売却を目的としている人にはおすすめしません。
転用しないで別用途に使うとどうなる?
農地を許可なく農業以外の用途に使用すると、農地法違反の罪になります。
そもそも農地とは、田や畑、牧場にあたる土地のことです。農地として地目登録されている土地は、勝手に処分する、勝手に建物を建てるといったことができません。また、農地として使用していたとしても、その土地の一部に建物を建てたり、太陽光パネルを置いて発電したりすることも禁止されています。
無許可で農業以外の用途に使用していたことが判明すると、工事の中止や原状回復、場合によっては懲役や罰金がかせられます。必ず転用許可を得てから使用しましょう。
農地の活用方法は?
農地は次のような活用方法に向いている土地といわれています。
- 太陽光発電用地
- 賃貸住宅経営
- 借地経営
- 駐車場経営
- 倉庫、トランクルーム経営
- 高齢者向け施設経営
農地は面積が広大なことが多く、さまざまな目的に利用できます。規模によっては、複数の賃貸住宅を建てて経営することも可能です。高齢者向け施設は経営に面積の制限があるため、広い土地は重宝されます。
また、農地は日当たりがよいことがほとんどなので、太陽光発電システムを設置する用地としても活用できます。
広く、利便性のよい農地なら、売却するだけでなく転用して活用することも視野に入れましょう。
農地の活用法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

土地活用の方法に迷っているなら「HOME4U土地活用」がおすすめ

まとめ

戸建てやマンションなどの不動産に比べ、許可がないと売却できない農地の売却は難しく、時間を要することも多いです。農地のまま売却する場合と転用する場合とで手順や注意点が異なることも、より農地売買を複雑化しています。
しかし、使わない農地をそのまま放っておけば、土地が荒れて害虫などが発生し近隣に迷惑がかかる、不法投棄や犯罪に利用されるというリスクも生まれます。農地の価値が下落する前に行動することが大切です。情報を収集し、売却に踏み出しましょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。


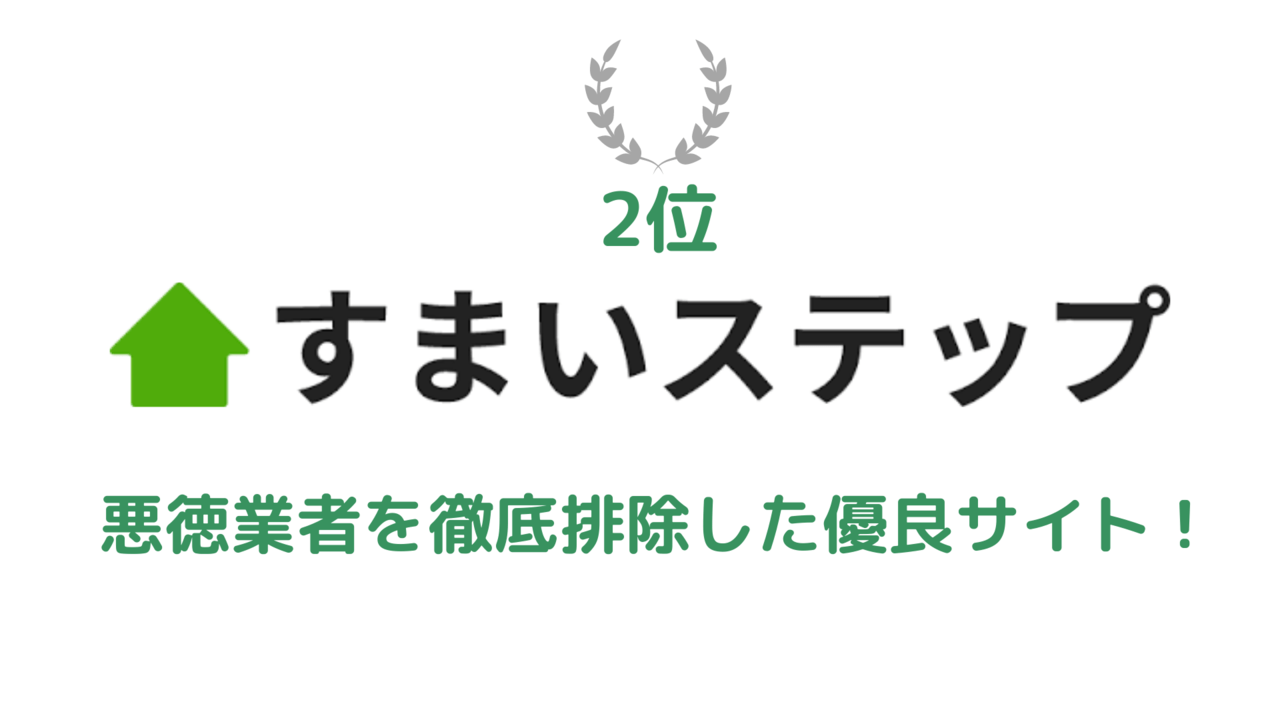

西崎さん.jpg)

