「マンション購入を検討しているが、どのくらいの価格帯で探せばよいのかわからない」「自分の年収でいくらのマンションが買えるのか知りたい」とお悩みではありませんか?
年収によって借入できる住宅ローンの価格は大きく異なります。マンションを購入するなら、無理なく返済していけるように年収から借入額・返済期間・負担率といった要素を検討しましょう。
本記事では、年収ごとに購入できるマンション購入金額を紹介します。返済期間や返済負担率などの要素でも徹底比較しますので、マンション選びにぜひお役立てください。
※株式会社リンクアンドパートナーズによる調査。アンケートモニター提供元:GMOリサーチ株式会社
購入できるマンション価格の目安は?

住宅ローンの返済を無理なく行うには、自分に適したマンション価格を見極めることが必要です。まず、購入できるマンションの価格を見定めるための目安を解説します。
自己資金と借入可能額を見て選ぶ
購入できるマンションの価格は、購入に充てられる自己資金と借入可能額で判断しましょう。
マンションを購入する際、次のような費用を自己資金から支払う必要があります。
- 頭金
- 手付金
- 印紙税
- 登記費用
- 仲介手数料
- 固定資産税等の精算
- 火災保険料
- 引っ越し費用
これらの費用は、新築でマンション価格の3〜5%、中古で5〜8%程度かかるといわれています。
頭金や手付金に関しては現金で用意する必要があるため、自己資金を見ていくらまで支払えるか判断しましょう。頭金はマンション価格の2割程度用意するとよいとされていますが、頭金を入れなくても購入できることも多いです。手付金は売買契約を結ぶ際にマンション価格の5〜10%を支払い、購入代金の一部に充てられます。
また、登記費用や仲介手数料などの諸費用はローンに上乗せして借入することも一般的です。手持ちがなくても諸費用分も借り入れることができれば、マンションを購入することができます。自己資金と借入可能額のバランスを見ることが大切です。
借入可能額は、借り入れる人の年収や就業状況、マンションの資産価値といった要素によって異なります。
借入金額は年収の6倍から7倍が平均
借入可能額は年収の6〜7倍が目安になるといわれています。どのくらいの価格帯のマンションを購入するか判断するだけなら、単純に年収から概算するのも有用です。この時の年収とは、税金や社会保険料を差し引く前の額面年収で計算します。
ローン金利が3%前後だった以前は、年収の5倍程度が目安といわれていました。しかし、超低金利状態が続く現在は、ローンの審査が下りやすく年収から7倍程度であっても借入が可能とされています。
例えば年収が300万円の場合、借入可能額は1,500〜2,100万円程度です。この価格が借入できるとして、自己資金を含めていくらのマンションが購入できるか判断しましょう。
住宅ローンを決める際の年収の倍率について詳しく解説したこちらの記事もおすすめです。

適正な返済負担率で考える
購入可能なマンションの価格を判断する上で、適正な返済負担率で考えることも大切です。返済負担率とは、年収に対するローン返済額の割合のことで、次のように計算します。
返済負担率が25%までであれば無理なく返済できるといわれています。将来に備え貯蓄をすることなどを考えると、20%以内に抑えるのが理想的です。
また、返済負担率を仮定して、理想的な返済額を逆算することもできます。毎月の返済額がわかれば現在の家賃と比較でき、より具体的なイメージを持つことができるでしょう。
借入限度額を計算する
上記の目安から、借入限度額を計算することも可能です。次の手順で計算しましょう。
- 年収の20〜25%がどの程度かを計算する
- 現在の家賃を参考に月々の返済額を決める
- 借入限度額を計算して購入に充てられる金額を確認する
購入できるマンションの価格を見誤ってローンを組んでしまうと、返済が難しくなり、最終的に家を手放すことにもなりかねません。無理のない範囲で住宅ローンを借入できるよう慎重な判断が必要です。
【年収別】購入できるマンション価格と返済額

では、年収別に購入できるマンションの価格と返済額を解説します。今回は年収の7倍を借入可能額とし、返済期間35年の固定金利1.3%として計算します。以下の表を参考に自身の自己資金を考慮し、購入できるマンション価格を導いてください。
| 年収 | 借入可能額目安 | 年間返済額 | 月々の返済額 |
| 300万円 | 2,100万円 | 747,132円 | 62,261円 |
| 400万円 | 2,800万円 | 996,180円 | 83,015円 |
| 500万円 | 3,500万円 | 1,245,216円 | 103,768円 |
| 600万円 | 4,200万円 | 1,494,264円 | 124,522円 |
| 700万円 | 4,900万円 | 1,743,312円 | 145,276円 |
| 800万円 | 5,600万円 | 1,992,360円 | 166,030円 |
それぞれの年収のケースについては以下で詳しく解説します。
年収300万円
年収300万の場合、35年1.3%の固定金利ローンの借入金額などは次のようになります。
- 借入可能額:2,100万円
- 年間返済額:747,132円
- 月々の返済額:62,261円
例えば、自己資金が300万円用意できた場合、2.400万円までをマンション購入に充てられると考えられます。頭金の有無や諸費用をローンに含めるかどうかで、購入できるマンション価格を判断しましょう。
年収400万円
続いては、同様の条件で年収400万円の場合を見ていきましょう。
- 借入可能額:2,800万円
- 年間返済額:996,180円
- 月々の返済額:83,015円
年収が400万円あれば、2,800万円まで借り入れることが可能です。頭金によっては3,000万円のマンションの購入も視野に入ってくるので、物件選びの選択肢が広がります。
毎月の返済額も8万円台で、現在家賃でこの程度払っているという方も多いのではないでしょうか?
年収500万円
同じ条件で年収が500万円になると、借入できる価格は3,500万円にもなります。
- 借入可能額:3,500万円
- 年間返済額:1,245,216円
- 月々の返済額:103,768円
マンション選びの選択肢が広がり、より設備の整った物件や部屋数の多い物件など、グレードをあげた部屋探しができるでしょう。
しかし、年間の返済額は120万円を超え、月々の返済も10万円を超えてしまいます。場合によっては、現在の家賃よりも価格が上がってしまうという場合もあるでしょう。
年収600万円
年収600万円の場合はどうでしょうか?
- 借入可能額:4,200万円
- 年間返済額:1,494,264円
- 月々の返済額:124,522円
4,000万円以上のマンションを選ぶことができるようになります。費用を上乗せしてローンを組むとしても、ある程度のグレードのマンションを選ぶこともできるでしょう。
月々の返済額は12万円を超えますが、単純計算で35万円以上の手取りがあると考えると、無理のない範囲で返済ができると考えられます。
年収600万円の人が借りられる住宅ローンについて詳しく解説したこちらの記事もご覧ください。

年収700万円
続いては年収700万円のケースです。
- 借入可能額:4,900万円
- 年間返済額:1,743,312円
- 月々の返済額:145,276円
年収が700万円あれば、借入可能額は4,900万円にもなります。頭金によっては5,000万円のマンションを購入することもでき、都心部や交通の便がよいエリアの物件も選択肢に上がってきます。
毎月の返済額は14万円を超え、年間では174万円もの返済が行われます。毎月の返済額を減らすのであれば、ボーナス払いといった工夫も検討しましょう。
年収800万円
最後に年収800万円のケースを見てみましょう。
- 借入可能額:5,600万円
- 年間返済額:1,992,360円
- 月々の返済額:166,030円
年収が800万円あれば、5,600万円まで無理なく借り入れることが可能です。都心部の新築マンションなど、設備が整ったマンションも購入できるでしょう。
しかし、5,600万円を借り入れると年間の返済額は約200万円になります。手取り年収が600万円程度とすると、3分の1を住宅費用に当てることになるため、注意しましょう。
【返済負担率別】購入できるマンション価格

続いては、返済負担率で購入できるマンション価格を見ていきましょう。
前章と同様に返済期間35年の固定金利1.3%の場合の返済負担率ごとの借入可能額を以下にまとめました。
| 返済負担率 | 年収300万円 | 年収400万円 | 年収500万円 | 年収600万円 | 年収700万円 | 年収800万円 |
| 15% | 1,265万円 | 1,686万円 | 2,108万円 | 2,530万円 | 2,951万円 | 3,373万円 |
| 20% | 1,686万円 | 2,249万円 | 2,811万円 | 3,373万円 | 3,935万円 | 4,497万円 |
| 25% | 2,108万円 | 2,811万円 | 3,387万円 | 4,216万円 | 4,919万円 | 5,621万円 |
| 30% | 2,530万円 | 3,373万円 | 4,216万円 | 5,059万円 | 5,903万円 | 6,746万円 |
それぞれのケースについて詳しく見てみましょう。
返済負担率15%
返済負担率を15%とすると、あまり高額なマンションを購入することは難しいです。年収ごとの借入可能額は次のようになります。
| 年収 | 借入可能額 | 月々の返済額 |
| 300万円 | 1,264万円 | 37,500円 |
| 400万円 | 1,686万円 | 50,000円 |
| 500万円 | 2,108万円 | 62,500円 |
| 600万円 | 2,530万円 | 75,000円 |
| 700万円 | 2,951万円 | 87,500円 |
| 800万円 | 3,373万円 | 100,000円 |
特に年収300万円の場合は1,300万円弱の借入に限られます。返済負担率を15%程度に抑えたいなら、頭金を用意して中古の価格の安いマンションを購入するなどが選択肢でしょう。
住宅ローンの返済比率について解説したこちらの記事もご覧ください。

返済負担率20%
返済負担率20%では、15%の場合よりも少し借入可能額が上がります。月々の返済額も現在の家賃より下がるという方が多いのではないでしょうか?
| 年収 | 借入可能額 | 月々の返済額 |
| 300万円 | 1,686万円 | 50,000円 |
| 400万円 | 2,249万円 | 66,666円 |
| 500万円 | 2,811万円 | 83,333円 |
| 600万円 | 3,373万円 | 100,000円 |
| 700万円 | 3,935万円 | 116,666円 |
| 800万円 | 4,497万円 | 133,333円 |
このように、年収の5〜6倍程度であれば借入が可能です。購入できる物件は限られますが、月々の返済額が低く、ゆとりある暮らしが実現できるでしょう。
返済負担率25%
返済負担率25%であれば、金融機関の審査が通りやすいといわれています。借入可能額は年収の7倍程度で、前章で紹介した借入可能額にも近いことがわかるでしょう。
| 年収 | 借入可能額 | 月々の返済額 |
| 300万円 | 2,108万円 | 62,500円 |
| 400万円 | 2,811万円 | 83,333円 |
| 500万円 | 3,387万円 | 100,416円 |
| 600万円 | 4,216万円 | 125,000円 |
| 700万円 | 4,919万円 | 145,833円 |
| 800万円 | 5,621万円 | 166,666円 |
毎月の返済額で見ても、無理なく返済できる範囲であることがわかります。購入できるマンションの幅も豊富になるため、この程度の返済負担率で考えるのがおすすめです。
返済負担率30%
多くの金融機関では、ローン審査の基準として「返済負担率30%以下であること」を挙げています。返済負担率30%の借入可能額と返済額は次の通りです。
| 年収 | 借入可能額 | 月々の返済額 |
| 300万円 | 2,530万円 | 75,000円 |
| 400万円 | 3,373万円 | 100,000円 |
| 500万円 | 4,216万円 | 125,000円 |
| 600万円 | 5,059万円 | 150,000円 |
| 700万円 | 5,903万円 | 175,000円 |
| 800万円 | 6,746万円 | 200,000円 |
借入可能額が上がり、グレードの高いマンションでも選択肢に含めることができます。しかし、月々の返済が困難になることもあるため、目先のことだけを考えてローンを組むのは危険です。
ローンを組む人以外にも収入のある人が同居している場合など、生活にある程度余裕があるか慎重に判断しましょう。
データから見たマンション購入の平均年齢や借入金額

マンションを購入するのはどういった人でしょうか?続いては、データから見たマンションを購入する年齢、借入金額、世帯年収の平均をそれぞれ見てみましょう。
平均年齢
新築マンションの購入者の平均年齢は、国土交通省「令和元年度住宅市場動向調査報告書」によると43.3歳でした。ただし、調査の中で最も多かったのは30歳代の世帯主で、戸建て物件に比べて50代、60代の購入者が多いことが平均年齢を上げているのでしょう。
また、住宅金融支援機構の「2019年度フラット35利用者調査」によると、フラット35利用者のうち、新築マンションの購入者の平均年齢は42歳でした。この平均年齢は年々上昇しています。
平均借入金額
住宅金融支援機構の「フラット35利用者調査 2019年度集計表」によると、マンションの借入金額の平均は2,743.2万円でした。
ただし、フラット35は審査が比較的おりやすいものの、変動金利よりも金利が高いため、変動金利の利用者はもう少し高い金額を借りていることが予想されます。
また、住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査【住宅ローン利用者調査(2021年4月調査)】」によると、融資率は90%超100%以下が最も多く、返済負担率は15%超20%以内の利用割合が最も多いです。
平均世帯年収
国土交通省「令和元年度住宅市場同行調査報告書」によると、世帯年収平均は新築マンションで798万円、中古マンションで694万円でした。内訳としては、新築・中古ともに600〜800万円の層が最も多く、次いで400〜600万円が続きました。
他の不動産種別と比べ、新築マンションの購入者の平均世帯年収が高い傾向にあります。年収400万円未満で購入している人はかなり少なく、ある程度収入が安定した層がマンション購入を検討しているようです。
マンション購入する際に注意したいこと

最後に、マンションを購入する際の注意点を紹介します。今回紹介するのは以下の4点です。
- ライフスタイルに適したマンションを購入する
- 維持費も含めて計算する
- 将来の出費を考慮して借入する
- 売却を考えて物件を選ぶ
ライフスタイルに適したマンションを購入する
マンション選びは、年収や借入金額だけで考えず、自分のライフスタイルを考慮して行いましょう。
購入時には広いと思っても、子どもが生まれたり親と同居することになったりと、将来部屋数が足りなくなる可能性もあります。コロナ禍で家で仕事をするようになったという人もいるでしょう。
このように、住む人数や目的は変化していくものです。現在のライフスタイルだけでなく、将来を想定した物件選びをおすすめします。
マンション探しを効率よく進めるなら、「タウンライフ不動産売買」がおすすめ
※株式会社リンクアンドパートナーズによる調査。アンケートモニター提供元:GMOリサーチ株式会社 希望に合う住宅を効率よく探すなら物件情報の一括取り寄せサイトが便利です。住みたい街の情報を入れるだけで、複数の不動産会社から希望の条件にマッチした物件情報が届きます。
とくに、編集部がおすすめしたいサービスがタウンライフ不動産売買です。タウンライフ不動産売買がおすすめな理由を以下にまとめています。
希望に合う住宅を効率よく探すなら物件情報の一括取り寄せサイトが便利です。住みたい街の情報を入れるだけで、複数の不動産会社から希望の条件にマッチした物件情報が届きます。
とくに、編集部がおすすめしたいサービスがタウンライフ不動産売買です。タウンライフ不動産売買がおすすめな理由を以下にまとめています。
維持費も含めて計算する
マンションを購入することだけに気を取られ、購入後の生活が苦しくなってしまっては元も子もありません。物件選びは購入後の維持費も含めて考えましょう。特にマンションは、戸建て物件に比べて管理費や修繕積立金といった維持費がかかるため注意が必要です。
マンションにかかる維持費は次の通りです。
- 管理費
- 共益費
- 修繕積立金
- 駐車場・駐輪場代
- 固定資産税・都市計画税
物件によっては他の費用がかかる場合もあるので、購入前に確認しておくとよいでしょう。
マンション管理の現状や管理組合の仕組みについて解説したこちらの記事もおすすめです。
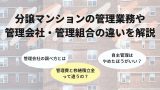
将来の出費を考慮して借入する
マンションの購入は、将来の出費についても考慮しましょう。
購入時には返済の負担が軽くても、将来のライフスタイルの変化で返済が滞ることがあってはなりません。お子さんの教育費、介護費、老後資金など、将来かかるであろうお金を考慮しましょう。
それぞれの家庭によって必要なお金は異なります。ローンを借り入れる前にファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することもおすすめです。
売却を考えて物件を選ぶ
購入した家に老後も住み続けると考えている方も多いと思いますが、「将来売却できるか」という観点でマンションを選ぶことも大切です。
資産価値が落ちづらいマンションの特徴は次の通りです。
- 人気エリア、生活に便利な場所にある
- 将来人口増加や開発が見込まれる
- エリアにある共有設備が充実している
- 間取りや広さがニーズに適している
ライフスタイルの変化が予想できないように、将来そのマンションに住み続けることができなくなることもあります。「子どもの独り立ちで少し狭い家に引っ越したい」「まとまった資金が必要になったので売却したい」など、将来売却したいと思ったときに売れるようなマンションを選びましょう。
まとめ

マンションを購入するなら、自分の年収や生活費を考慮しましょう。特に年収は、住宅ローンの借入可能額にも影響するため、無理のない返済額を調べる必要があります。
また、借入できたとしても返済が滞ってしまっては意味がありません。現在の生活費や将来のライフプランを考えて、自分に無理のない返済負担率で借入額を判断することも大切です。
本記事を参考に、適した価格のマンションを理解し、物件を選びましょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。



