国内の単身世帯は年々増加傾向にあり、一人暮らし用マンションを購入する人が増えています。厚生労働省の「令和2年版 厚生労働白書」によると、2019年の未婚率は女性23.9%・男性35%であるのが、2040年には女性24.9%・男性39.4%になると予測され、今後も増加しそうです。
最近では、賃貸マンションの家賃額と変わらない返済額で購入できる場合もあり「賃貸よりも購入したほうがよいのでは」と考える人も増えています。この記事では、一人暮らし用のマンションを購入するメリット・デメリットや購入時のポイント、注意点などをまとめました。一人暮らしでこれからの住まいをどうしようか考えている方は、ぜひ参考にしてください。
※株式会社リンクアンドパートナーズによる調査。アンケートモニター提供元:GMOリサーチ株式会社
一人暮らしマンションを購入するメリット

一人暮らしで賃貸マンションに問題がない場合は、マンションを購入することにあまり魅力を感じないと思う人も多いのではないでしょうか。一人暮らしマンションを購入すると次のようなメリットがあります。
- 自分好みのマンションにできる
- マンションが資産になる
- ローン完済後は居住費がほとんどかからない
- 設備が充実しているマンションに住める
現在はもちろん将来のことを考えると、マンションを購入したほうがメリットが大きいようです。以降で詳しく解説していきます。
自分好みのマンションにできる
購入したマンションであれば、自分の好みやライフスタイルに合わせて変更できます。自分にあった室内を実現すれば、今より生活を充実させることが可能です。ただし、大がかりなリフォームやリノベーションをする場合は、管理規約に則って管理組合の許可をとる必要があります。
これに対して賃貸マンションでは、壁紙を張ったり収納棚を増やしたり、壁を取り払って間取りを変更したりするなど、内装や設備を好きなようにアレンジすることは難しいでしょう。
マンション管理や管理組合の仕組みについて解説したこちらの記事もおすすめです。
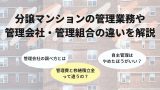
マンションが資産になる
マンションを購入すると所有権は自分のものになります。そのため将来的に住み続ける以外にも、売却したり賃貸として家賃収入を得たりして運用もできます。
将来の資産としての運用を考えている場合は、物件の周辺地域の賃貸住宅の需要や経年劣化による価値の値下がりも考慮して、購入するマンションを選ぶとよいでしょう。
ローン完済後は居住費がほとんどかからない
賃貸マンションは、いくら支払いを続けても家賃の支払いがなくなることはありません。しかしマンションを購入した場合は、住宅ローンの支払いが終われば管理費や修繕費の支払いだけになり、毎月の住居費の負担が少なくなります。
また、老後は収入が減ったり賃貸物件への入居が難しくなったりする可能性もあるため、少ない住居費用で済み続けられることは大きなメリットといえるでしょう。
設備が充実しているマンションに住める
分譲マンションは長期間住み続けることを前提にしているため、設備のグレードが賃貸マンションよりも高いケースが多いです。そのような設備には次のようなものがあります。
- 宅配ボックス
- 24時間利用可能なゴミ置き場
- 浴室換気乾燥機
- オートロック
- ホームセキュリティ
不在時でも荷物が受け取れる宅配ボックスや24時間利用可能なゴミ置き場は、一人暮らしの人にとって特に便利な設備です。また安心して暮らすなら、オートロックやホームセキュリティなどの設備も見逃せません。
一人暮らしマンション購入のデメリット

マンションを購入すると、自分のライフスタイルに合わせてアレンジできたり資産にできたりするなど、数多くのメリットがありますが、デメリットがあることも理解しておく必要があります。一人暮らしマンションの購入には次のようなデメリットがあります。
- 引越しが簡単にできない
- ローン以外にもかかる費用がある
- 売却してもローン残債が残る可能性
- 災害などのリスク
デメリットについてもひとつずつ詳しく見ていきましょう。
引越しが簡単にできない
賃貸マンションの場合は、オーナーに退去することを伝えるだけで比較的容易に引越しすることができますが、購入したマンションは簡単に引越しができません。購入したマンションを引越す場合は、売却したり賃貸に出したりして、自分で扱いを決定しながら業者を探す必要があります。
マンションを売却する場合は、仲介を依頼する不動産会社探しから成約までに平均で4ヶ月かかります。なかなか買い手が見つからない場合は、それ以上の期間がかかる場合もあるので注意しましょう。
ローン以外にもかかる費用がある
マンションを購入すると、住宅ローン以外にもさまざまな費用が発生します。事前に把握しておかなければ、毎月の支払いが思ったよりも多く、生活を圧迫する可能性もあるので注意が必要です。マンションを購入する際は次のような諸費用がかかります。
- 住宅ローンの手数料
- 登記費用
- 修繕積立基金
- 不動産取得税
新築のマンションを購入した場合は修繕積立基金が必要で、その額は20万~40万円と立地や居室の広さなどで幅があります。
不動産取得税は不動産を購入した際にかかる税金で、次の計算式で算出可能です。
税率は2024年(令和6年)3月31日までに取得した不動産は3%です。
また、購入後は次のような修繕積立金や管理費、固定資産税などがかかります。
- 修繕積立金
- 管理費
- 固定資産税
修繕積立金はマンションの大幅修繕に向けて積み立てておく費用ですが、築年数が経つほど修繕規模や箇所が増えるため金額が上がり、新築の場合の相場は10,000円程度です。
管理費はマンションの設備の保守点検や清掃委託、共用部分の水道光熱などに充てられる費用で、マンションを専有する面積により変動しますが相場は10,000円程度です。
固定資産税は毎年4~5月頃に納税通知書が送られてきて期日までに納めます。算出方法は次の通りです。
税率は市町村(東京23区は都)により異なりますが、標準税率は1.4%です。税額は建物の経年とともに評価額が低くなり下がっていきます。
売却してもローン残債が残る可能性
通常、住宅ローンを完済しないと売却できません。売却価格で完済するか、足りない場合は貯金などの自己資金で補って完済します。
新居を購入して引越す場合は、所有するマンションの住宅ローン残債と、新居の購入資金をまとめて借り入れできる「住み替えローン」というサービスを利用するのも一つです。ただし通常の借り入れよりも審査が厳しく、売却や購入のタイミングが難しいなどのデメリットがあるほか、実質的には二重ローン(タブルローン)になるので注意しましょう。
災害などのリスク
災害が起きた場合に、マンションでは修繕積立金などから修繕費が支払われます。しかし、修繕積立金は経年劣化によるメンテナンスに備えて蓄えられているため、災害の修繕までは想定していないケースが多く、追加で費用がかかる可能性があります。
マンションを購入する際は、建物の耐震性や災害の起こる可能性のあるエリアが分かるハザードマップなどを確認しましょう。また、火災保険や地震保険に加入しておくことも重要です。
おすすめの火災保険を紹介したこちらの記事も参考にしてください。

一人暮らし用マンション購入の6つのポイント

一人暮らし用マンションを実際に購入しようと思っても、マンションは購入する機会があまりないため、何をポイントに探せばよいのか分からないという人も少なくありません。一人暮らし用マンションを購入する際のポイントを次の6つにまとめました。
- POINT1:新築か中古か
- POINT2:広さと間取り
- POINT3:交通の便
- POINT4:周辺の施設
- POINT5:治安の良さ
- POINT6:売却のしやすさ
ひとつずつ詳しく確認していきましょう。
POINT1:新築か中古か
一人暮らし用のマンションを買う際にまず迷うのが、新築か中古かではないでしょうか。それぞれのメリット・デメリットを知り、自分にベストなほうを選びましょう。
| メリット | デメリット | |
| 新築 |
|
|
| 中古 |
|
|
新築マンションのメリットは、最新の設備がそろっていることです。断熱ガラスや床暖房、LED照明などを標準装備でそろえているところもあります。また修繕積立金も比較的安く済みます。反面、中古に比べて価格が高くなることや、建設前の場合は実際に物件を見て購入を決められないことはデメリットです。
中古マンションは、新築よりも安く購入できることがメリットです。また新築に比べて選択肢が多く、希望に合った場所などを探しやすい点もメリットとして挙げられます。他にも、実際に見て日当たりや設備を確認できることも魅力です。一方、月々の修繕積立金が高いところはデメリットといえます。
マンション探しを効率よく進めるなら、「タウンライフ不動産売買」がおすすめ
※株式会社リンクアンドパートナーズによる調査。アンケートモニター提供元:GMOリサーチ株式会社 希望に合う住宅を効率よく探すなら物件情報の一括取り寄せサイトが便利です。住みたい街の情報を入れるだけで、複数の不動産会社から希望の条件にマッチした物件情報が届きます。
とくに、編集部がおすすめしたいサービスがタウンライフ不動産売買です。タウンライフ不動産売買がおすすめな理由を以下にまとめています。
希望に合う住宅を効率よく探すなら物件情報の一括取り寄せサイトが便利です。住みたい街の情報を入れるだけで、複数の不動産会社から希望の条件にマッチした物件情報が届きます。
とくに、編集部がおすすめしたいサービスがタウンライフ不動産売買です。タウンライフ不動産売買がおすすめな理由を以下にまとめています。
POINT2:広さと間取り
一人暮らし用マンションは、1LDK~2LDKで広さが40~50平方メートル前後のコンパクトマンションと呼ばれるタイプがおすすめです。
1LDKを選ぶ場合
1LDKは一人暮らしの人におすすめのサイズです。寝室とリビングを分けることができ、ライフスタイルに合わせてレイアウトが可能です。友人や家族が来たときにもスペースを確保できるため便利でしょう。
また1LDKのマンションは、働き盛りの単身者をターゲットにしていることが多く、利便性の高い場所にある場合も多いです。
2LDKを選ぶ場合
寝室とリビングとは別に、趣味や仕事用の部屋を作りたい場合は2LDKの間取りがおすすめです。収納スペースも1LDKよりも増えるため、荷物の多い人に向いています。
2LDKの家は、単身世帯だけでなく夫婦2人やシニア夫婦世帯にも需要があるため、将来売却を検討している人にもおすすめです。ただし、1LDKより価格が高くなるため収入がある程度必要になります。
POINT3:交通の便
いくらマンションの設備が充実していて広くても、交通機関までの距離が遠いと通勤や休日のお出かけの際に不便です。そのため、マンションを購入する際は利用する交通の便の良さを忘れずに確認しましょう。
交通機関までの距離を確認する際は、地図に表記されている時間だけでなく実際に歩いてみることも大切です。交通機関までの距離など物件情報の表示は、不動産の表示に関する公正競争規約で「80m=徒歩1分」と決められています。この表示は信号や踏切、坂などは考慮されていないため、実際に歩くと思ったよりも時間がかかる可能性があるのです。
加えて、駅までバスを利用する場合は始発・最終バスの時間や料金、自転車の場合は駐輪場の位置と料金も確認しておくとよいでしょう。
POINT4:周辺の施設
マンション周辺の施設の充実度も確認しましょう。次のような施設が徒歩圏内にあると、生活するうえで便利です。
- スーパーマーケット
- コンビニ
- ドラッグストア
- 病院
- 飲食店やお惣菜屋
- 郵便局
- よく利用する金融機関
周辺の施設を確認する際は、距離だけでなく営業日時もチェックしましょう。一人暮らしの場合は、遅い時間まで営業しているスーパーやドラッグストアが近くにあると便利です。また病院やクリニックが近くにあり、具合が悪くなったときに歩いて受診できれば安心です。
POINT5:治安の良さ
安心して暮らすなら治安の良さも重要です。駅からマンションまでの道を歩いて、街頭の数や人通りの多さなどを実際に確認しましょう。繁華街など明るく人が多い場所は、トラブルが多く治安が悪い場合もあるので注意が必要です。
地域の詳しい治安状況は、警視庁や道府県警察本部のホームページで公開している防犯マップで確認できます。
POINT6:売却のしやすさ
マンションを購入する際は、将来売却する可能性を想定することが大切です。需要が低く売れにくいマンションを購入すると、売却益だけで住宅ローンの残債を完済できなかったり、まとまったお金にならなかったりします。
マンションの需要はその時々により変化するため、将来売却しやすいものを選ぶことは難しく感じるかもしれません。しかし1KDKや2LDKの一人暮らし用のマンションの場合は、交通機関やスーパーなど生活に必要な施設が近くにあり、利便性が高いマンションは需要が下がりにくい傾向にあります。
また、マンションの管理会社が物件をしっかり管理しているか、管理人が常駐しているかといった点も売却のしやすさにつながるようです。
一人暮らし用マンション購入の注意点

マンションは大きな買い物です。購入時の注意点を事前に把握しておくことで、失敗を防ぎましょう。
- 無理のない返済にする
- ライフスタイルが変わったときにどうするか考慮する
- 働けなくなったときの保障内容を確認しておく
上記の3点について詳しく解説します。
無理のない返済にする
借入可能額と返済可能額は違います。借りられるからといって借入可能額いっぱいに借りると、毎月の返済が大変です。生活を豊かにするためにマンションを購入したのに、返済で苦しめられては意味がありません。
そこで理想の返済負担率について解説していきます。
理想の負担率
一般的に返済負担率は、年収の25%以下を目安にするとよいといわれています。できれば20%以下に抑えられると余裕のある返済が可能です。
住宅ローンの返済比率についてより詳しくし知りたい人はこちらの記事もおすすめです。

年収から適正な借入額のシミュレーション
次の条件で借入額のシミュレーションをしてみます。金利はフラット35の最頻金利(2021年7月現在)、毎月の返済額は全国の平均に近い額で設定しました。
- 金利:固定金利1.33%
- 毎月の返済額:90,000円(ボーナス返済なし)
- 年間返済額:108万円
この設定で、借入期間25年と35年で借入可能額をシミュレーションしてみました。
| 年収 | 返済負担率(年間返済額/年収) | 借入期間25年の場合の借入可能額 | 借入期間35年の場合の借入可能額 |
| 400万円 | 27.0% | 680万円 | 895万円 |
| 500万円 | 21.6% | 1,424万円 | 1,874万円 |
| 600万円 | 18.0% | 2,168万円 | 2,853万円 |
“参考:住宅金融支援機構「フラット35 ローンシミュレーション 年収から借入可能額を計算」で試算”
この条件設定の場合は返済負担率が20%で、借入可能額が中古マンション購入の場合の平均借入額の約1,600万円に近い、年収500万円がマンションの購入できる年収ラインといえます。
返済額などの計算は難しいため、各金融機関のホームページにあるシミュレーターを活用するのがおすすめです。また毎月の返済額に加え、管理費・修繕積立金が合計2万円程かかる点に留意しておくとよいでしょう。
住宅ローンの返済について詳しく知りたい人は、こちらの記事もあわせて読んでみてください。

ライフスタイルが変わったときにどうするか考慮する
一人暮らし用マンションを購入後に、結婚・転勤・転職・介護などでライフスタイルが代わり、住み続けることが難しくなる可能性があります。そのような場合に備え、事前にマンションをどうするか考えておくことが大切です。
購入したマンションなら、売却以外に賃貸に出すこともできます。一人で考えることは難しいので、住まいに詳しいファイナンシャルプランナー(FP)などのプロに相談してもよいでしょう。
働けなくなったときの保障内容を確認しておく
一人暮らし用のマンションを購入する際は、病気やけがで働けなくなった場合についても考えておく必要があります。
多くの住宅ローン商品は、団体信用生命保険(団信)への加入を必須としています。団体信用生命保険は、契約者が死亡するか高度障害状態になった場合に、ローン残高を肩代わりしてくれる保険です。
高度障害状態とは次のような状態を指します。
- 両目の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く失ったもの
- 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも足間接以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
”引用:住宅金融支援機構「債務弁財される場合、債務弁財されない場合」”
高度障害以外の病気やけがをカバーしたい場合は、団体信用生命保険に疾病保証特約を付けることを検討しましょう。ただし、就業不能状態が1年を過ぎなければ全額返済できないなど、厳しい条件の場合もあるため事前に確認することが大切です。
加えて、生命保険会社の就業不能保険や所得補償保険なども検討するとよいでしょう。
まとめ

国内の単身者は年々増加傾向にあり、それに伴い一人暮らし用のマンションを購入する人も増えています。また、賃貸物件の家賃と同等の返済額で購入できる場合もあるため、そのことも購入を選択する人が多くなっている理由のようです。
マンションを購入すると、自分の好きな内装や設備を選べて資産にもなります。また、老後の住まいも確保できるため安心です。ただし、転勤や結婚などライフスタイルが変化して住めなくなった場合は、売却したり賃貸に出したりするなどの手間がかかります。
マンションは人生の中でも大きな買い物です。現状だけでなく将来のことも考えて、慎重に検討することが大切です。メリット・デメリットを把握して、自分の理想にピッタリのマンションを見つけてください。
自宅購入については次の記事でも取り扱っているので、ぜひご覧ください。


※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。


