マイホームの購入を検討する際に、ほとんどの方は住宅ローンで購入資金を確保しますが、住宅ローンはどの段階で契約すると良いのか、いまいち分からないという方もいるのではないでしょうか。また、住宅ローンを契約するためには、どのような準備が必要なのかが気になっている方もいるでしょう。
そこで本記事では、住宅ローンを契約する際の流れや必要になる書類、住宅ローンを契約する際にかかる諸費用についてなど、住宅ローンの契約に関する情報を徹底解説していきます。これから住宅ローンを利用して物件の購入を検討している人は、しっかりと情報を押さえておきましょう。
\住宅ローンを探している人におすすめのサービス2選/
【新規】住宅ローンのプロに相談するなら「HOME'S 住まいの窓口」
不動産の大手ポータルサイトを運営する株式会社LIFULLの「HOME'S 住まいの窓口」では、住宅ローンを含め注文住宅に関するあらゆる相談が無料でできます。専門アドバイザーが中立的な立場でサポートしてくれるため、不動産会社やハウスメーカーなどから営業を受ける心配はありません。
【借り換え】住宅ローンを見直すなら「モゲチェック」
ローンの借り換えなら、低金利のローンへの借り換えサービスが便利です。モゲチェックでは、人気の住宅ローンを比較し、自身が借りられる最も低金利のローン(※)を案内します。毎月の返済額を平均約2万円軽減することも可能です。 ※付帯する団体信用生命保険を加味して運営会社 株式会社MFSが最も低いと判断する金利
住宅ローン契約の流れ
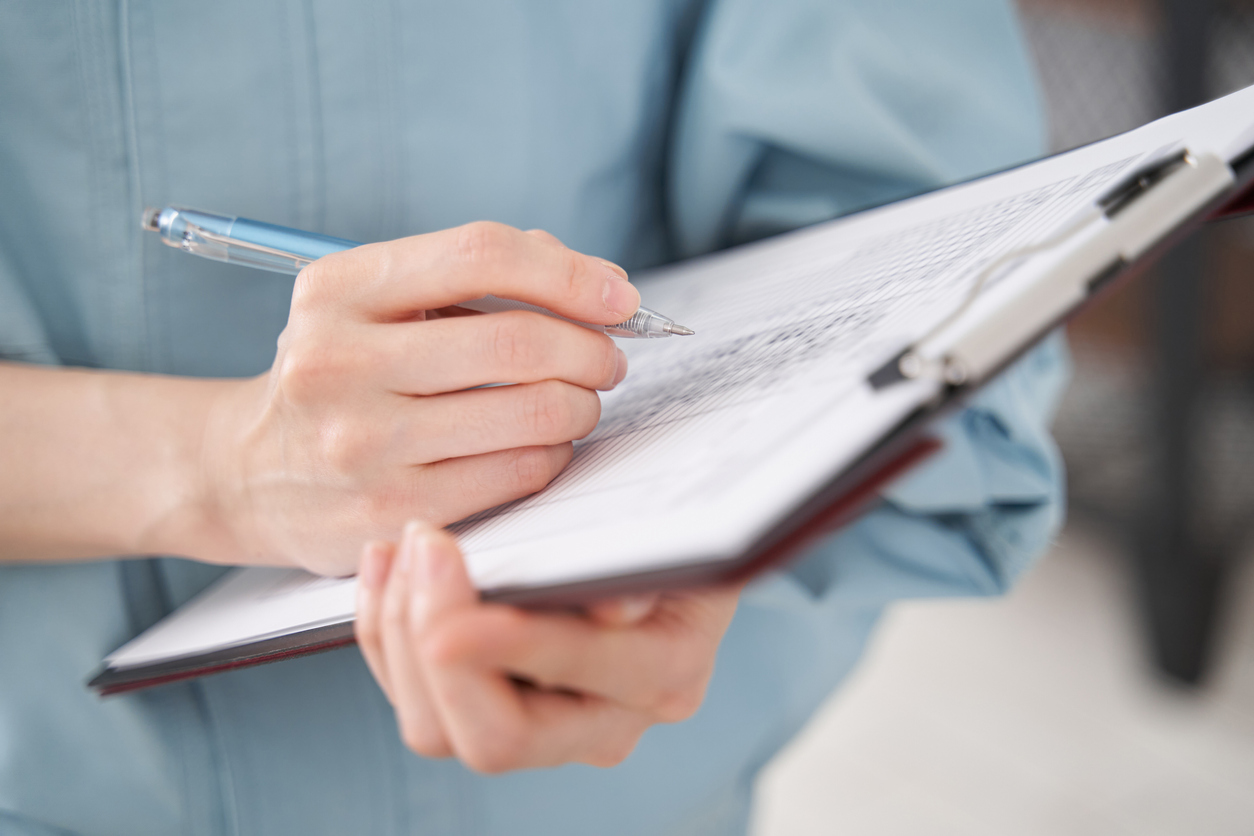
マイホームを購入する中で、住宅ローンは契約するタイミングがあります。また、すぐに契約できるものでもありません。ここではどの段階で契約を申し込むのか、契約時の審査から融資の実行まで流れを紹介していきます。
- 購入物件を探す
- 住宅ローンを借りる金融機関を決める
- 必要な書類を揃える
- 仮審査を申し込む
- 住宅売買契約の締結
- 本審査申し込み
- 住宅ローンを契約する
- 物件の引き渡しと融資の実行
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
購入物件を探す
そもそも住宅ローンとは、物件を購入する際に契約するものなので、まずは購入する物件探しから始まります。マイホームの購入は金額が大きいことから、人生の中で何度も経験することではありません。購入金額の上限はおおよそ年収の5倍が目安で、この上限内で物件を探すことが大切です。
住宅ローンは、新築や中古に限らず契約することができます。しかし中古住宅の場合は、金融機関で築年数や耐久性が審査されて、借入期間が新築住宅より短くなることを考慮して探すようにしましょう。
住宅ローンの仕組みなど基本的な情報について知りたい人は、以下の記事もおすすめです。

住宅ローンを借りる金融機関を決める
物件の目星がついたら、次は住宅ローンを契約する金融機関を決めますが、探し方は2通りあります。
まずは、住宅メーカーや不動産会社を介して購入を検討している場合には、提携している金融機関を紹介してもらう方法です。提携している金融機関では、手続きの手間が省けたり金利を優遇してくれたりなどのメリットがあります。
もう1つは自身で利用したい金融機関を探すことです。住宅ローンを取り扱う銀行は、都市銀行以外に信用金庫やネット銀行などがありますが、以下を目安にして各金融機関を比較し、自身の視点に合った金融機関を探しましょう。
- 金利タイプ(変動金利型、固定期間選択型、全期間固定金利型)
- 手数料が適切な金額で設定されているか
- 信頼できる担当者がいるか
自身で探す際は、インターネットや説明会などを利用してしっかりと下調べをしましょう。金融機関を決めたものの、審査に通らずに振出しに戻るということがないように、あらかじめ審査が甘い金融機関を選択するなどの対策も大変有効です。
以下の記事では、住宅ローンの審査が甘い金融機関について詳細を紹介しているので、あわせてお読みください。

必要な書類を揃える
利用したい金融機関が決まったら、次は申込に必要な書類を用意します。審査は1回だけではなく、仮審査と本審査の2段階になっています。各審査で用意する書類が異なるため、以下の表を参考に準備しておきましょう。
| 審査段階 | 必要書類 | 入手場所 |
| 事前審査 | 本人確認書類
(※運転免許証や健康保険証) |
本人 |
| 源泉徴収票の控え | 会社 | |
| 物件の見積書など関連書類 | 物件購入先 | |
| 本審査 |
|
役所 |
|
会社 | |
|
不動産会社もしくは売主側 | |
|
不動産会社もしくはハウスメーカー | |
|
本人 | |
|
金融機関 |
また、金融機関によっては上記以外の書類が必要になるケースもあるため、利用する金融機関に確認しましょう。
住宅ローンを契約する際の書類については、以下の記事でより詳しく紹介しているので、あわせて押さえておきましょう。

仮審査を申し込む
必要書類を揃えたら、次は仮審査に申し込みましょう。事前審査とも呼ばれる仮審査では、利用者の年収や他社からの借り入れ状況などから希望金額の融資が可能かどうか、滞納などはないかといった信用調査が行われます。また、実際にローンの融資を開始した際に、返済していく能力があるのかもチェックされます。
この審査はおおよそ3日から1週間程度で結果が出ますが、通過した場合は次のステップへ進みましょう。万が一、通過しない場合は借入金額などの条件を下げるなどの計画を変更するか、他の金融機関への借入を再度検討する必要があります。
住宅売買契約の締結
事前審査が通過したら、次は購入する物件の売買契約を売主・買主の間で締結します。契約を結ぶと、原則として内容変更はできません。よって疑問に思ったことや質問したいことがあれば必ず契約前に確認して、重要なことは契約書に追加で記載してもらいましょう。双方が契約内容に納得したうえで署名・捺印をします。
本審査申し込み
一般的には、売買契約を結んだあとに本審査の申し込みを行います。売買契約締結から物件引渡しまで、ケースによってはタイトなスケジュール調整が必要になる場合もあるかもしれません。ただし多くの場合は、引き渡しまでに1ヶ月程はかかるため、売買契約後の本審査申込でも十分に間に合います。
事前審査のときとは違い、本審査には10日から長くて2週間程度かかるでしょう。事前審査が通っても、本審査では落ちてしまうケースも全くないわけではありません。そのようなことに備えて別の資金調達方法も検討しておきましょう。
住宅ローンの審査基準や通過する際のポイントについて、以下の記事も参考にしながら対策しておきましょう。

住宅ローンを契約する
本審査を通過できたら、いよいよ住宅ローンを契約します。この住宅ローンの契約の正式名称は、金銭消費貸借契約兼抵当権設定契約といいます。これは金融機関と物件購入者同士でのやり取りになるため、不動産会社などは一切関与しません。そのため契約時に不備がないように、事前に金融機関に確認しておきましょう。特に確認しておくべき内容は以下の3点です。
- 金利の設定に間違いがないか
- 借入年数に誤りはないか
- 借入総額に間違いはないか
また住宅ローンの契約の際には、土地と建物を担保として設定するための抵当権の契約も行います。
物件の引き渡しと融資の実行
住宅ローンの契約が締結されたら、物件引渡しの日を待ちます。最後の手続きとして、物件引渡し日に購入代金のすべてを支払って登記を行います。そのため、金融機関の応接室などで買主はもちろん、不動産会社の担当や司法書士、中古物件の場合は売主が同席したうえで、決済の手続きをする流れが一般的です。当日の流れは以下の通りです。
- 各種契約内容の確認後、サイン
- 残金や手数料を各支払先へ振り込み、確認
- 登記に必要な書類を売主から買主へ
- 司法書士が所有権移転登記のために法務局へ
- 物件所有者が買主へ
- 不動産会社より買主へ物件の引渡しが完了
当日は、以上の流れで金銭的なやり取りと手続きが完了します。スムーズに事が運べば1時間程度で引渡しは完了です。
住宅ローンの仕組みをさらに詳しく知りたい人や、融資実行日について知りたい人は以下の記事もおすすめです。


住宅ローン契約に必要な書類

ここでは、契約時に必要になる書類について解説します。一部、審査のときと重複する書類もありますが、契約時にあらためて必要になる認識を深めるためにも、再度紹介します。
本人確認書類
住宅ローンの事前審査や本審査でも本人確認のための書類を提出しますが、住所や名前に虚偽がないかの確認になるため、契約時にも再度確認が行われます。必要になる本人確認書類は以下の通りです。
- 健康保険証
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 住民票の写し:発行後1ヶ月以内のもの
金融機関側は大金を融資するため、厳重な確認が何度も行われます。運転免許証やパスポートなどは有効期限内のものでなければならないため、更新が必要な場合は余裕をもって更新手続きを済ませておきましょう。
通帳
住宅ローンを借り入れる金融機関の預金口座がない場合は、預金口座を開設して通帳を作っておきましょう。住宅ローンの引き落としや融資実行の際に必要になります。なお、残高確認のために預金通帳の提示を求められるので、通帳は持参しましょう。
住宅ローンを組む物件の資料
住宅ローンを組む物件の情報を、不動産会社やハウスメーカーから入手しておきましょう。その際に必要になる主な書類は以下の通りです。
- 売買契約書
- 重要事項説明書
- 建築工事請負契約書
- 建築確認済書
- 検査済書
すでに契約済の場合は、収入印紙が貼付され消印済のものを提出するように求められます。未契約の場合は、見積書などで金額や引渡しの時期が確認できるものが必要です。これ以外にも、金融機関から書類や資料の提出が求められる場合もあるので、その際は不動産会社やハウスメーカーへ相談して取り寄せましょう。
収入を証明できる資料
会社員として勤務する給与所得者は、以下の書類で収入を証明します。
- 前年度の源泉徴収票:会社より入手
- 住民税決定通知書:1年に1回市区町村より送付される
- 課税証明書:市区町村で入手可能
個人事業主や所得税の確定申告者は、以下の書類で収入を証明します。
- 所得税の確定申告書(付属明細を含む)
給与所得者と個人事業主で証明する書類に相違はありますが、前年度の年収が分かる公的な書類の提出が求められます。
実印と印鑑証明
住宅ローンの契約時に必要になる書類関連の中で、実印は大変重要です。実印を持っていない人は、まずは身分証明書を持参して自分の居住する市区町村の役所へ行き、印鑑登録の手続きをしましょう。印鑑登録した印鑑が実印になります。
印鑑登録は、契約する本人が直接行けば即日で登録手続きが完了しますが、代理が登録申請する場合や身分証を持っていない場合は、手続きに数日かかることもあります。契約書には契約書に署名する全員の実印が必要です。そのため、実印登録はあらかじめ済ませておくようにしましょう。
また、実印の証明として印鑑証明書が必要になります。この印鑑証明書は役所で申請して、契約書に署名する人数分の発行1ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書の発行には身分証明書と実印、印鑑証明証が必要なので、忘れず持参して手続きしましょう。
住宅ローンの契約書

ここでは、住宅ローンの契約内容について詳しく解説していきます。マイホームの購入は一生に何度もある買い物ではないため、この機会に住宅ローン契約の意味やローン契約の際に金融機関が行う手続きについて、理解を深めていきましょう。
金銭消費貸借契約書
金銭消費貸借契約書は「金消」と略されることもあります。「金消」の確認は金融機関の担当者が同席し、説明しながら手続きを進めて借主の同意を得たうえで、署名・捺印して契約が成立します。契約時の確認内容は、借入金額、金利とそのタイプ(固定か変動か)、返済期日や返済期間、滞納が発生した場合の対応などについてです。
「金消」契約時と同時に、火災保険の加入を求められるケースもあるので、あわせて契約するようにしましょう。火災保険への加入を求められる主な理由としては、購入した物件が万一火事にあった場合に、優先して金融機関が保険金を受け取る仕組みを取れるためです。
抵当権設定契約書
抵当権はあまりなじみがないかもしれませんが、住宅ローンを組む際には切っても切れない関係にあります。金消契約で取り決めた返済が行われなかったり、金融機関が返済は難しいと判断したりした場合に、金融機関が所定の手続きを行い、担保にしたマイホームを競売にかけて債権を回収できるという民法に定められた権利です。
しかし、返済が滞ることがなければそのような心配もないため、滞ることがないようにしっかりと資金計画を立てたうえで住宅ローンを組むようにしましょう。
保証委託契約書
住宅ローン返済中に、借主が死亡したり重度の障害などになったりして、返済ができなくなった場合の保険として団体信用生命保険があります。よく「団信」と略されて呼ばれるものです。「金消」契約と同時に、自動的に加入を求められるケースがほとんどで、住宅ローン商品にはこの「団信」がセットになっているもの少なくありません。ただし、もともと持病がある人は加入できないケースもあります。
この「団信」に入っておくことで万一のことがあった場合に、住宅ローンの残債が金融機関へ一括で支払われ、残った家族が不安に暮らすことはなくなります。そのため、できることなら入っておいたほうがよいでしょう。
「団信」とは別に代位弁済の保証会社を利用する場合は、なんらかの事情で返済できなくなった借主の代わりに、保証会社が金融機関へ債権者として支払いますが、保証会社はその債務を借主へ請求することができます。住宅ローンの滞納によって競売にかけられる心配はなくなりますが、債務がなくなるわけではありません。
住宅ローン契約でかかる諸費用

住宅ローンを組むためには、諸費用の多くが数万円かかることが一般的です。ここでは、そのかかる費用の代表的な項目を紹介します。不動産会社や利用する司法書士の事務所によっては、設定している費用が異なるため、あくまで目安として情報を押さえておきましょう。
印紙税
住宅ローンを組む際に契約書を作成しますが、その際の借入額に応じて契約書に貼る印紙の金額が変動します。借入金額が高くなるほど、印紙税も高くなります。
- 1,000万円超え~5,000万円以下:2万円の収入印紙
- 5,000万円超え~1億円:6万円の収入印紙
この印紙税は、不動産の売買契約書にも貼り付ける必要があるので、自分の借り入れる金額がわかっている場合は、収入印紙代がいくら必要になるのか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
登記のための費用
不動産の所有権を、売主から買主へ変更する際に必要になる費用で、変更する登記のことを「不動産所有権移転登記」といい、登録免許税を支払う必要があります。この際の費用は、融資額に対して以下の式で求めます。
この不動産所有権移転登記をする際に司法書士へ依頼する場合は、さらに依頼料として費用がかかります。司法書士への報酬金はおおよそ3~7万円が相場です。
不動産所有権移転登記の費用についてさらに詳しく知りたい人は、以下の記事で一緒に押さえておきましょう。

火災や地震保険料
住宅ローンを契約する際に、火災保険や地震保険への加入を求められるケースもありますが、この保険会社への加入にも費用がかかります。しかし火災保険は、はっきりとした相場がなく、保証の充実度や契約年数によって2~10万円と金額に大きな差があります。
また地震保険も同じく、住む地域や建物の構造、築年数、契約期間などにより割引率などの条件で金額が大きく異なるでしょう。
万が一保険への加入が必要な場合は、保険会社と金額の確認しておくことをおすすめします。
保証料
この保証料とは、住宅ローン契約時に同時に入る団体信用生命保険の保証会社へ支払う費用です。この費用に関しては借入金額や返済期間、または金融機関によって対応が大きく異なりますが、下記のようなケースが多いようです。
- 35年返済の場合は、融資額1,000万円あたり20万円の保証料とするケース
- 保証料を金利に上乗せ
- 融資額に含む形で保証料の請求なし
保証料の費用を少しでも抑えたい場合は、団体信用生命保険について利用を検討している金融機関に確認しておくとよいでしょう。
事務手数料
事務手数料は融資を受ける際に支払う手数料で、金融機関によって異なります。通常3万~5万円で設定しているところがほとんどですが、中には融資額に対して金額が変動する金融機関もあります。
事務手数料も決して安くはないため、可能であればインターネットなどで情報収集したり、問い合わせたりするなどして、手数料がいくらになるのかを必ずチェックしておきましょう。
まとめ

利用する金融機関を決めたり審査のために万全な準備をしたりなど、各段階で重要なポイントは多いですが、住宅ローンの契約は物件の売買契約を結んでからの取り組みが大変重要です。
住宅ローン契約締結から引渡しまで、滞ることなくスムーズに進めていくためには、事前に流れを把握して契約時に必要になる保険の加入の有無や、それぞれにかかる費用について把握しておくとよいでしょう。住宅ローンについての理解を深め、夢のマイホームを購入してみませんか。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。


