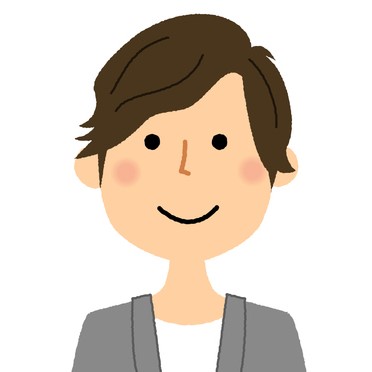不動産売却時に利益が出た場合には、税金がかかります。
せっかく不動産売却が上手くいき、高額な利益が出たとしても、税金の対策を知らなかったために受け取る利益が減ってしまった、などということは避けたいものです。
この記事では、不動産売却で利益が出た場合に、どのような税金がかかるのか、詳しく説明していきます。
不動産売却で損をしないためにも、売却する前に税金の知識を身につけましょう。
- 不動産売却で得た利益に対してどのように税金が課せられるかを知っておくことは重要です。知らないままでは、所得税や住民税の負担が増えることに気づかない、特別控除のことを知らず利用できないなどのように思わぬ出費や損に繋がるケースが発生します。
- 不動産売却で考慮する必要がある税金は、所得税、住民税、印紙税、登録免許税、固定資産税などです。不動産によっては特別控除によって大幅に売却時の税額が軽減されるので、適用できるものがないか確認しておきましょう。
- 不動産売却で税負担を軽減しようとすると、複雑な要件が絡むことも多いため専門家への相談がおすすめです。その際に話の理解を早めてスムーズに行動するためにも、あらかじめ税金の知識を身につけておきましょう。
不動産売却時に発生する税金を知っておく重要性とは
不動産を売却した場合、以下の3つの税金が発生します。
- 譲渡所得に対する所得税と住民税
- 売買契約時に貼付する印紙税
- 登記にかかる登録免許税
不動産売却によって得た利益に対してどのように税金が課せられるかを知っていなければ、思わぬペナルティを受けてしまいかねません。また、不動産の売却が完了するまでの間に発生する、印紙税や登記の際に必要な登録免許税といった税金についての情報も、正しく納税するために知っておかなければなりません。。
そこで本記事では、不動産を売却する際に発生する譲渡所得にかかる税金や、売買契約時に必要な税金、不動産売却による税負担を軽減する方法などについて、詳しく説明します。

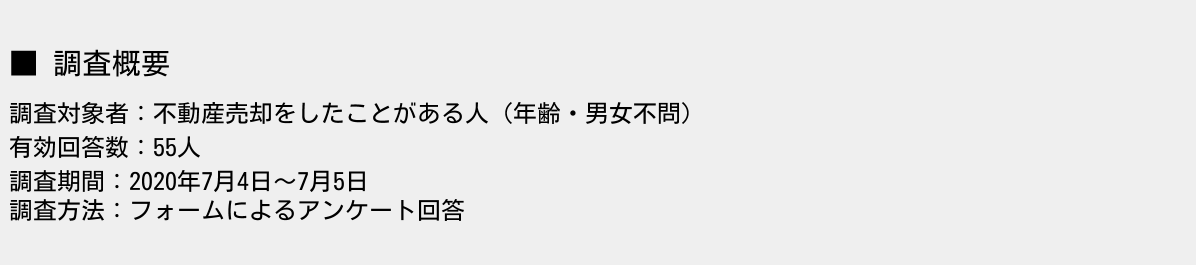
実際に不動産売却をした経験がある人55名に対してアンケート調査を実施したところ、半数以上が「税金のことについてもっと勉強をしておけば良かった」と後悔していることが分かりました。
売却益が出た場合は、所得税や住民税がかかることや、特別控除の存在を知らずに損をしたなど、不勉強による損や思わぬ出費になった人が多いようです。「不動産会社に任せれば安心」と考えるのではなく、不動産売却時には、税金について自分自身が勉強しておく必要があると認識しておきましょう。
譲渡所得に対する所得税と住民税
- 所得税には復興特別所得税が含まれている
- 譲渡所得とは譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いたもの
- 所有期間が5年以下か5年を超えるかで税率が変わる
- 譲渡所得税と住民税は分離課税になる
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その分に対して所得税と住民税が発生します。不動産売却の経験がない人は、譲渡して得た金額に対して税金が課せられると思いがちです。しかし、譲渡所得がどのように計算されるのか、不動産を持っていた期間によってどのように税率が変わるのか、などを知ってれば、正しい税額を算出することができます。
ここからは、譲渡所得に対する所得税と住民税が適切に計算できるよう、譲渡所得税額がどのような仕組みで算出されているかについて、詳しく説明します。
所得税には復興特別所得税が含まれている
2011年に発生した東日本大震災からの復興を目指すために、政府は同年12月2日に「復興特別所得税」を創設して、復旧に必要な財源を確保することとしました。復興特別所得税は所得税に含まれており、所得税を納める義務のある人は、所得税を納付すると同時に復興特別所得税も収めることが義務付けられています。
復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
復興特別所得税額は、 所得税額に2.1%を乗じた金額となっています。納付が必要な期間は2013年から2037年で、この期間内に所得税が発生した人は、同時に復興特別所得税も納付することになります。つまり、給与所得者の人は、2013年1月1日以降の給与等から、自動的に復興特別所得税が源泉徴収されるようになっているのです。
給与等の所得税に課せられるのと同じように、譲渡所得に対する所得税にも復興特別所得税が加えられることを覚えておきましょう。
譲渡所得とは譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いたもの
不動産の譲渡所得にかかる所得税は、不動産の売却価格そのものに対して計算されるものだと思われがちです。しかし、実際には不動産を売却するまでに、土地や建物を購入する際の費用(取得費」や、売却する際の費用(譲渡費用)がかかっています。そのため、譲渡所得は譲渡価額から取得費と譲渡費用を控除した金額になるのです。
この方法で譲渡所得を計算すると、取得費や譲渡費用によっては、譲渡所得が大幅に少なくなる可能性もあります。不動産の売却では、譲渡所得が発生した場合にのみ、譲渡所得税が生じるのです。
つまり、譲渡所得が発生しない不動産売却の場合、譲渡所得税が課せられないことになります。不動産の売却を考えているのであれば、譲渡所得がどれくらいになるかを事前に計算しておくと、売却後にかかる税額を考えながら売却準備を進められるようになるでしょう。
譲渡価額は売却価格に固定資産税と都市計画税の精算金を足したもの
不動産の譲渡価額と売却価格はどちらも同じものだと認識されがちですが、実はこれらは異なる意味を持っているのです。不動産を売却した値段が売却価額であることに対して、不動産の譲渡価額は、不動産を売った時の価格に固定資産税と都市計画税の精算金を加えたものになります。
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日の段階で不動産を所有している人に対して、その年分の税金が課せられるようになっています。よって、売却した日付以降の固定資産税の精算金を買主が代金とあわせて売主に支払いますが、その分も譲渡所得に含まれることになるのです。
建物の取得費は購入価格から減価償却費を差し引く
建物を手に入れた時にかかった費用は、購入価格全てが取得費となるわけではありません。建物は、使用していたり期間が経過したりすることによって、徐々に資産価値が下がっていきます。そのため、建物の取得費は、購入価格から減価償却費を差し引いた金額になるのです。
減価償却費は経年劣化によって下がる価値分の費用になるため、土地には適用されず建物のみに適用されるようになっています。
減価償却費の計算方法は、「建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数」で求められます。償却率は、木造なのか鉄筋コンクリートなのかといった、構造物の種類によって異なるため、建物の構造に合わせた償却率で計算しましょう。また、事業用として使われていた建物を売却する場合は、取得費が変わってくるため注意が必要です。
所有期間が5年以下か5年を超えるかで税率が変わる
不動産を売却する場合、不動産の所有期間が売却した年の1月1日の時点で5年を超えるかどうかによって、適用される税率が変わってきます。土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」に分類されるのです。不動産を売却するタイミングによって、どちらの方法で税額を計算することになるのかを知っておきましょう。
不動産の所有期間による税率の違い
不動産の所有期間によって、税額の計算方法は、以下のように分けられています。
| 短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合) |
| 39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%) |
| 長期譲渡所得(所有期間が5年超の場合) |
| 20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%) |
この表のように、不動産を所有している期間が5年以下よりも、5年を超えて所有していた方が、税率が安くなるため納税額を抑えやすくなります。
ただし、売却する金額や、買い手がつくかどうかによっては、必ずしも長期所有になるまで待った方が得になるとは言い切れないため、状況に応じて意識するようにしましょう。
譲渡所得税と住民税は分離課税になる
譲渡所得税や住民税は、退職所得(退職金)などと同様に、他の所得と区分して課税されます(分離課税)。そのため、分離課税となる不動産の譲渡による損益は、他の所得と通算(相殺)することはできず、譲渡所得から計算した税額を全て納付する必要があるのです。
給与所得等にかかる所得税は、会社の年末調整によってまとめて計算することができます。しかし、不動産の譲渡により売却益が出て税金が発生した場合、会社の年末調整とは別に確定申告をする必要があるため、注意しておきましょう。
売買契約時に貼付する印紙税

不動産の売買契約を結ぶ場合、売買金額に応じて収入印紙を契約書に貼付することで、印紙税を納付したことを証明する必要があります。印紙税額は売買金額にもよりますが、不動産売却の場合、1万円〜3万円程度になることが多いです。
不動産売買における収入印紙税額をあらかじめ調べておけば、、税額を考えながら不動産売買の手続きを進めやすくなるでしょう。
2通分の印紙税が必要となる
不動産取引の売買契約書を作成する場合、2通分の印紙税を納付する必要があります。これは、売買契約書を売主と買主がそれぞれ契約書を1通ずつ保管する必要があるからです。
印紙税額は売主と買主双方が負担することが多いですが、トラブルを避けるために、「印紙代は、各自が平等に負担する」といった文言を契約書に記しておくと安心できます。
また、収入印紙は不動産売買契約が成立した時点で貼付するようになっています。そのため、不動産売買契約を行う際は、各自が収入印紙を用意しておくと、よりスムーズに契約手続きが進むでしょう。
登記にかかる登録免許税
- 不動産1つあたり1,000円がかかる
- 抵当権の抹消は司法書士に依頼をするため1万円〜2万円かかる
不動産の売却によって登記変更をする際には、登録免許税の納付義務が発生します。ここからは、登記にかかる登録免許税について、詳しく説明します。
抵当権抹消登記の登録免許税は不動産1つあたり1,000円がかかる
抵当権抹消登記の際には、不動産1つあたり1,000円の登録免許税がかかります。これは、土地・建物それぞれに1,000円かかるようになっているため、物件の登記数に応じて登録免許税の費用が変わってくるのです。
抵当権の抹消手続きを司法書士に依頼をすると1万円〜2万円かかる
土地や住宅を購入するときに金融機関から借入を行っている場合、購入する不動産に対して担保(抵当権)を設定するケースがほとんどです。抵当権がついている不動産を売却する場合、不動産についている抵当権を抹消しなければなりません。
多くの場合、不動産会社が司法書士に依頼するようになっており、司法書士に抵当権の抹消を依頼すると、取引額に応じて、10,000円〜30,000円程度の相場で報酬が発生します。これは地区によっても若干相場に違いがあるため、事前に相場を確認しておくと安心して手続きを依頼できるようになるでしょう。
固定資産税の精算

毎年1月1日時点での不動産の所有者に対して、その年分の固定資産税が課せられます。そのため、年の途中で不動産を売却した場合、売却してから年末までの固定資産税は、すでに売主が支払っていることになるのです。そのため、不動産を売却する際は、固定資産税の精算が重要になってきます。
不動産を手放してから先の固定資産税は買主が清算する
不動産売買における固定資産税は、売却後の期間に相当する金額を買主から売り主に支払うのが一般的となっています。これは、不動産を所有していない売主が固定資産税を支払うのは、不合理であるというのが大きな理由です。
不動産売買における固定資産税の清算については、法律で定められているものではなく不動産取引における慣例となっているので、不動産を売却する前にこれらの税金の精算金について事前に取り決めておくようにしましょう。それによって、固定資産税の清算に関するトラブルを予防し、お互いが気持ちよく取引を進められるようになるのです。
不動産売却時に税額が軽減されるケース
- ケース1|居住用財産の3,000万円特別控除
- ケース2|居住用財産売却による軽減税率の特例
- ケース3|居住用財産の買換え特例
ここまでの説明から、不動産を売却すると、さまざまな納税義務が発生することが理解できたと思います。しかし、不動産売却時に適用される特例によって、大幅に税額負担が軽減できる可能性があるのです。
特に居住財産となる「実際に居住している物件」もしくは「実際に居住していた事実があり、住まなくなってから3年が経過する日の属する年の12月31日までの物件」には大幅な軽減が期待できます。
売却する不動産をこれまでどのように利用してきたかによって、負担する税額が大きく変わるため、不動産売却による税額が軽減される条件をよく理解しておきましょう。
ケース1|居住用財産の3,000万円特別控除
居住用財産を売却した場合、一定の要件を満たすことで、所有期間の長短に関わらず譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる特例があります。この特例が適用されるには要件が定められており、要件を満たすことで大幅に譲渡所得税が軽減される可能性があるのです。
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます引用:国税庁
ケース2|居住用財産売却による軽減税率の特例
居住用財産の所有期間が、譲渡した年の1月1日において10年を超えている場合、課税譲渡所得のうち6,000万円までは税率が下がるようになっています。実際の税額の計算方法は、以下の通りです。
- 課税譲渡所得の6,000万円までの部分について、所得税10%×2.1%=10.21%+住民税4%=14.21%
- 6,000万円を超える部分について、所得税15%×2.1%=15.315%+住民税5%=20.315%
この税額の計算方法は、先ほど説明した居住用財産の3,000万円特別控除と併用することが可能です。そのため、不動産を売却するにあたって、最終的に課税譲渡所得がどれくらいになるかをあらかじめ計算しておくことで、税負担を抑えながら不動産を手放せるようになります。
ケース3|居住用財産の買換え特例
例えば不動産を売却した後、新たにマンションや一戸建てを購入するなど、売却するだけでなく買い替える場合は、「居住用財産の買換え特例」が適用できる場合があります。
売ったマイホームの譲渡価額より買い替えたマイホームの取得価額の方が高い場合、不動産を売却した年分の譲渡益には課税されないというものです。その代わり、買い換えたマイホームを将来売却するときに、繰延べられた譲渡益を含めて税額が計算されます。
居住用財産の買換え特例が適用されたとしても税率は一律となっており、「所得税15.315%+住民税5%=20.315%」の税率が、譲渡益に対してかかってくるのです。この特例は、「居住用財産の3,000万円特別控除」や「住用財産売却による軽減税率の特例」との併用はできませんが、課税譲渡所得が3,000万円を超えた場合でも税負担を軽減できるというメリットがあります。
不動産売却は専門家に相談しながら税負担を抑えると良い

本記事では、不動産を売却する際に知っておくべき税金の種類や税額の計算方法、税負担を抑えるための方法について説明しました。不動産を売却するときに、売り主としてどれくらい納税しなければならないのかをイメージしておくことで、手元に残るお金を計算しやすくなります。
また、不動産の売買契約を締結する際に、税負担について売り主と買主とであらかじめ取り決めをしておくことで、トラブルを予防しながら手続きを進めていくことにもつながつのです。
税負担を軽減するためには、複雑な要件が絡むことが多いため、一度専門家に相談してみるのがおすすめです。ここで説明した内容を参考にして、不動産売却における正しい税金の知識を身につけ、納得いく不動産売却ができるように準備を進めていきましょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。