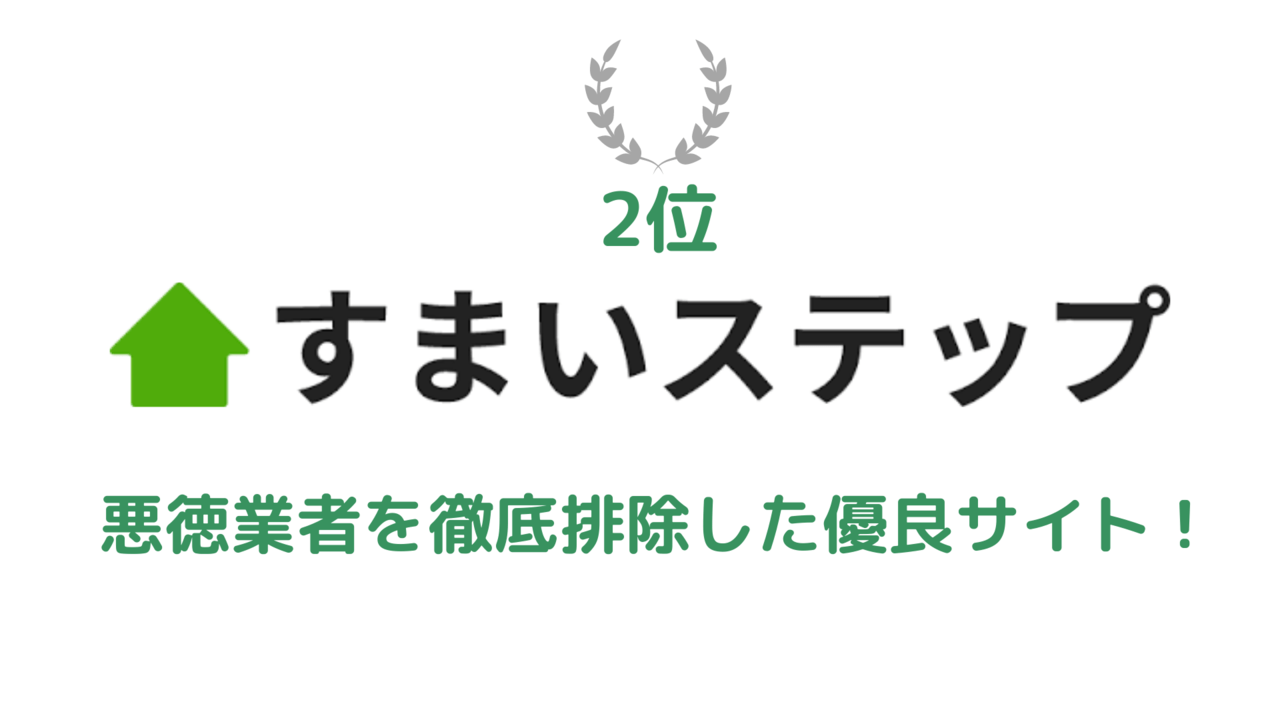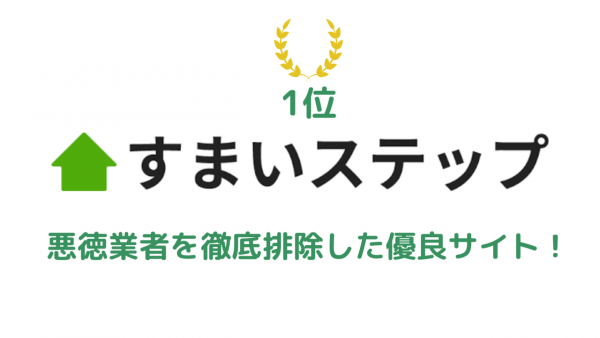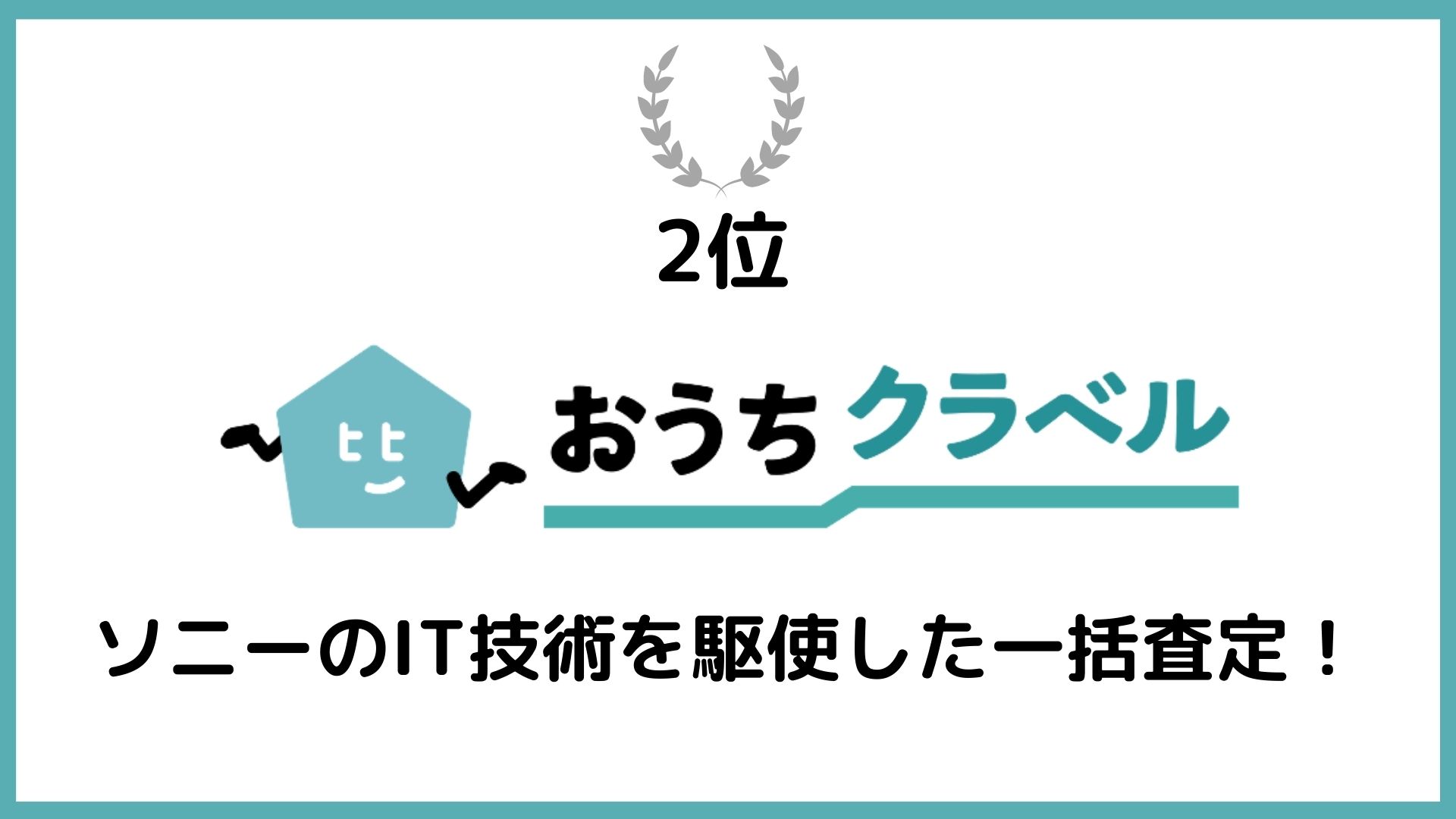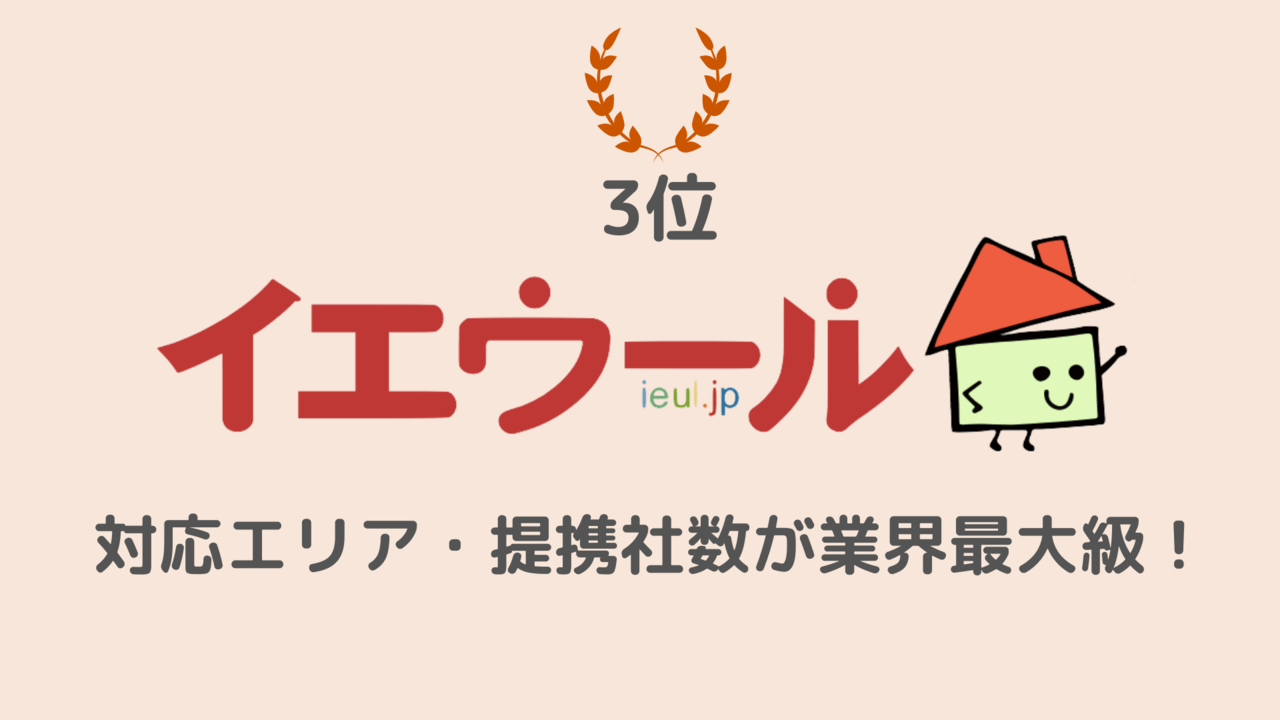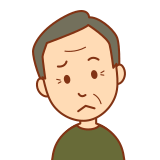
マンションの転売に興味があるが、本当に利益は出るのだろうか?
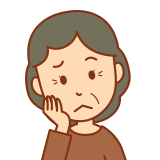
どのようなリスクがあるかが気になる…
マンション転売をしようと考えている人の中には、売却で最大限の利益を得るために、まずどこから対策したらいいのだろうと悩んでいる人もいるかもしれません。
マンションの転売で利益を生むためには、購入・転売時に欠かせないポイントを知っておく必要があります。その知識があれば、リスクを避けて利益を生むことができるだけでなく、一石二鳥、三鳥もの益があります。
この記事では、マンション購入時から転売のために準備できるポイントや、転売時に利益を多くするための対策をご紹介します。今回の内容を参考に、マンション転売時のリスクを回避しつつマンション転売で成功する確率をアップさせましょう。
※1:東京商工リサーチによる中古マンション投資の売上実績(2022年3月調べ) \初回面談実施でamazonギフト券5万円分もらえる/
公式サイトはこちら
マンション転売の基礎知識

そもそもマンション転売は、不動産投資の中で利益を出しやすい方法なのでしょうか。また個人が転売をしても、法に触れないか気になる所です。
そこでマンション転売の基礎知識として、投資の難易度や違法性、マンション価格の推移についてから紹介します。大金を動かす投資のため、慎重に行動していきましょう。
マンション転売は難易度の高い投資
マンションに限らず一度購入したものを売却するときは、中古の商品となり新品のときより値下がりするのが一般的です。マンションの購入を検討している人も同じ価格なら、中古より新築を選びます。また物件は経年劣化で年々価値は下がるため、転売で利益を出すのは簡単ではありません。
1980年代後半から1990年代前半に起きたバブル景気の頃であれば、特別なことをしなくても、簡単に転売で利益がでていました。しかしバブルが弾けて以降は、転売に関する規制も増えて利益が出にくくなっています。
マンション転売の違法性
個人のマンション転売が、違法になる可能性があることを知っていますか。宅地建物取引業の資格を持っていない人が転売を頻繁に行っていると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金を課せられます。
どの程度の頻度なら違法になるのかという明確な基準はありません。しかし不特定多数の人に利益目的で資格なく転売をしていると、罰せられる可能性は高いです。
マンション価格の推移
マンション価格の過去のデータは、国土交通省が運営する不動産取引価格情報検索で、2005年7月から検索することができます。データによると、リーマンショック後の2010年から一時的に下落が見られました。その後はアベノミクスやマイナス金利政策などで、2020年まで緩やかな上昇を続けています。
2021年以降はコロナの影響で生活様式に大きな変化が起こり、マンション価格の推移は不透明な状態です。しかしバブル期のように価格が数ヶ月で急変する可能性は低いため、転売は慎重に検討した方がよいです。
マンション価格の推移について詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめです。

マンション転売で儲けるための4つの購入ポイント

ネット上にあふれているマンション転売成功者の体験談では、よく「いくらの儲けが出た」という情報が載せられています。彼らはただ単に適当なマンションを購入し、転売することで儲けを出しているわけではありません。マンション転売で儲かるかどうかは、そのマンションを購入する時点でほぼ決まっているといっても過言ではないのです。
では、マンション転売に成功している人達は、どのようなポイントをおさえて購入物件を決めているのでしょうか。そのポイントを一つずつ見ていきましょう。
立地のよいマンションを選ぶ
立地のよいマンションは、年数を重ねてもその資産価値が暴落する可能性は低いという特徴があります。この立地のよさに絡む人気の理由として、次のような条件が挙げられます。
- 駅から徒歩400m圏内
- スーパー、学校、病院が近くにある
- 公園や河川などの眺望の良さ
- 大通りに面していない静かな区域
これらの点は好立地条件としてよく聞きますが、この中で最重要視したいのは駅からの距離です。駅は通勤通学でもよく利用する施設で、その利用頻度は毎日といっていいほど高いといえます。また、駅周辺にはコンビニや大型・小型商業施設が隣接していることが多く、買い物が便利というメリットもあります。
しかし、これらの条件を知っていても、住みよいと感じる場所は個々によっても多少の差があるでしょう。そこで参考にしたいのが、実際に住んでいる人たちの感想です。
毎年さまざまな不動産メディアで、取引事例をもとに調査して「住みたい街ランキング」を紹介しています。すでに移り住んでいる人たちは、どのような点に魅力を感じているのかといった情報がまとめられているので、マンションを購入する際は参考にしてみましょう。
投資用不動産を探すなら、「シーラの不動産投資」がおすすめ
[シーラ_文中_見出しなし]中古マンションを選ぶ
「価値が下がりにくいのは新築マンションでは」と思っている方は意外に感じるかもしれませんが、実をいうと価値が下がりにくいのは中古マンションのほうです。これには不動産会社が新築されたマンションの価値を年数の経過によって、どうとらえていくかという点が関係しています。
価値の下がり方を考える
一般的にマンション価値が下がる率は1年につき2%といわれています。しかし、この下がる率には一つ落とし穴があります。それは、この効果率を新築マンションに当てはめることはできないことです。
新築マンションは、まだ誰も住んでいないのが最大の魅力ですが、新築マンションを購入する人はある意味、新品というオプション料を購入時に支払っていることになります。そのオプション料といえる上乗せ費用は実に10%です。
しかし一度誰かが住んでしまうと、次に転売する際には新品という付加価値をつけることができないため、マンション価値は上記の10%分がそっくりそのまま下がってしまいます。
マンション転売を考えて購入するなら、できるだけ価値の下がる率を低く抑えたいものです。そのため、購入したマンションを一時住んだあとに転売することを考えるなら、価値が下がりにくい中古マンションを選ぶほうがお得といえます。
ヴィンテージブームを考える
昨今ではヴィンテージに価値を見出して、経年変化を楽しみつつ自分好みにアレンジする人たちが増えています。不動産業界にもそのブームの波は押し寄せていて、新築マンションより中古マンションのニーズが高まっている傾向にあります。
中古マンションをリノベーション(改装工事)して古いもののよさを味わいたい購入する人にとっては、中古だからといって価値が下がることはなく、逆に高値での売却が期待できます。
また、ヴィンテージニーズが高まっていることによって、不動産会社も「ヴィンテージマンション」という新たなカテゴリを作り売却に力を入れています。そういった市場価値の観点からも中古マンションを購入するほうが転売するのに有利といえるでしょう。
管理の優れたマンションを選ぶ
戸建てとは違い、マンションには必ず管理してくれる会社や管理規約が設けられています。購入の際に考えるべきことが「管理方法はよいものか」という点です。管理が行き届いていないと、次のようなことが起こりえます。
- ゴミ処理がきちんとされず不衛生になる
- 植栽が荒れて死角ができ、治安に悪影響がでる
- マンションの劣化が早まる
こういった問題のあるマンションは、管理の仕方に原因があります。マンションの管理が悪いと市場価値は下がり、いざ転売したいとなったときに安値でしか売却できず赤字になる可能性が高いです。管理の悪いマンションに引っかからないため、次の2つのポイントを知っておきましょう。
自主管理マンションは避ける
自主管理マンションでは、マンションの住人が管理規約に従ってそれぞれで管理を行います。自分で管理できる便利さはあっても住人それぞれの管理意識が違うことで、管理がきちんとされていない部分が出てくるのは必至です。将来的な不動産価値を守ることを優先して、自主管理マンションの購入は避けましょう。
管理費が安いマンションは避ける
管理費が何のために徴収されるのかや、その内訳について知っておくことも大切です。
管理費は大まかにいって、常日頃の管理のためや将来的な大規模修繕のために徴収されています。しかし管理費が安いマンションは、優先的に支払われる日常管理の費用を支出すると残る積立金が少ないため、大規模修繕の費用が十分に集まらないというデメリットがあります。
費用が集まっていないために満足な大規模な修繕ができず、時期を見送っているうちにマンションの価値がどんどん下がっていきます。そういった点から、管理費が安いマンションは避けたほうがよいといえるでしょう。
マンションの管理状態を見極めるためにできる対策として効果的なものは、「マンションの管理状況を事前に不動産会社へ問い合わせる」ことです。その際に次のポイントをおさえておくと、不動産会社の回答もあわせて見極めやすくなります。
- 管理戸数はどれほどか
- 入居率は高いか
- 担当のレスポンスは早いか
- 管理戸数に対しての担当の人数はどれほどか
こういった点を不動産会社に問い合わせることで、購入したいマンションの管理会社がマンション価値を上げてくれる会社なのかを見極められます。
物件探しはネットだけに頼らない
転売で利益が期待できるマンションは、誰しもが購入したいと考えるのが当然でしょう。そのため、簡単に物件の検索ができる不動産のポータルサイトなどのネットだけに頼っていては、ライバルに勝つことは困難です。
ネットに掲載される前の情報の収集で有効な方法は、人脈を頼りに知人の知人までつながることです。もし早くマンションを手放したいと考えている人に出会うことができると、相場よりも安い価格で譲ってもらえる可能性があります。
マンション転売で儲けるための4つの売却ポイント

マンションの転売を考慮した購入時のポイントを見てきましたが、次に見ておきたいのは売却時に参考にしたいポイントです。ここで4つの利益につながるポイントをご紹介します。
築10年以内にマンションを売却する
マンションの築年数はヴィンテージマンションなどの例外を除いて、年数が経つほど不動産価値に影響するものです。それにしてもどうして築10年以内なのでしょうか。それは、築10年を過ぎたマンションは大規模修繕が必要になるケースが多いからです。
もし大規模修繕をする必要があるとなると、どれほどの費用が掛かってしまうのかですが、大規模修繕の相場は100万円前後といわれています。修繕する内容は、主に屋上の防水塗装やタイルの剥がれなどの修繕です。
さらに築年数が10年を超えた頃にマンションを売却するとなれば、購入する人は大規模修繕の負担ものしかかります。100万円前後の負担増は軽くなく、築10年以上のマンションは特別な付加価値を加えない限り、売却は不利になります。
マンションが築10年を超えると売れにくくなる理由や、築年数別にマンションの売却相場を解説したこちらの記事もご参考ください。

リノベーションをした場合はどうなるか
2月から3月の間に売却する
日本では4月に新生活が始まるため、その前の2月から3月の間で子どもの通学を理由に、マンションの購入を考える人が増加します。国土交通省から指定を受け、不動産売買成約情報を収集・公開している不動産流通機構レインズでは、過去1年間の成約例を検索して見ることができます。
一例として、東京千代田区のデータから最も成約されている時期がいつなのかを下の表で見てみましょう。

2019年から2020年にかけての取引事例10件のうち、実に8件が年末から4月にかけて成約されています。
特にマンションの購入希望者の割合は、戸建てと比べて通学中の子どもがいるケースが多いです。そのため、売却計画を立てるときには2月か3月に成約することを目標にすることができるでしょう。また2月、3月以外では社会人が転勤で引っ越しを考えることが多い9月も狙い目といえます。
売却準備期間の余裕を持つ
マンションを転売する際は、売却準備期間を適切に設定することも大切です。不適切な売却準備期間で起こる売却したい人に不利な状況を、不動産業界では「売り急ぎ」と表現しています。この売り急ぎとは、売却したい人が目標売却時期が迫っていることで焦り、安く叩き売ってしまうことのような状況を指します。
もし余裕を持った売却準備期間を設定していないと、仲介期間の延長で費用がかさむことや購入希望者を探す労力に耐え切れずに、捨て値同然で売却してしまうことになりかねません。
この売り急ぎが起きてしまう背景には、売却時期設定で多くの人が勘違いしている点があるからです。したがって売却時期と売却開始時期は違うものとして心得るとよいでしょう。
売り出し期間の目安
サービスや対応がよい不動産会社を選ぶ
優良な不動産会社を選ぶことは、どのようなマンションを売却するときにも大切な点です。特に最終目標となる売却にまでこぎつける力があるかを見極めることで、マンション転売を成功させることができます。そのためには、保証や提案内容を確認することを重点に選びましょう。
多くの不動産会社は、売るために売り方を他会社と差別化しています。どんな特徴をアピールしているのかをチェックすると、自分が必要としている売り方なのか、売れなかったときの保証はどうなっているかといったことが読み取れます。自分に合った満足できる売却活動をするため、厳選してください。
大手不動産会社と中小不動産会社の基礎的売却力はほとんど差がありません。そのため、他の会社と差をつけるためにどのようなサービスを提供しているのかという点を、比較検討すると転売をしやすくなります。
囲い込みを避けて売却専門の不動産会社を利用
不動産会社は、不動産売却を専門にしているかや囲い込みをしていないかを確認しておきましょう。
囲い込みをされると売却のチャンスを逃すだけでなく、買主の要求に合わせた売却金額に変更するように迫られるリスクもあります。あらかじめ囲い込みをしないか、担当者に直接問い合わせるとリスクを回避できます。
売却を専門にしている不動産会社はノウハウを心得ているので、マンション転売時の強い味方です。どの会社が不動産売却を得意としているかを知るためには、公式ホームページで見ることが近道です。またマンション売却実績が多いところであれば、売却の中でもマンションを上手に売り切る方法を知っているでしょう。
担当者の信頼を確認するポイント
- 宅建士の資格があるか
- 売却仲介経験年数と成約件数
- 親身にこちらの話に耳を傾ける
このようなチェックポイントを確認しておくだけで、不動産会社選びでのトラブルを避けられるだけでなく、いち早く成約できるのでぜひ確認しましょう。またよい不動産を見つけるうえで試す価値があるのが一括査定サイトです。次の章では、その一括査定サービスの内容やメリットについて触れていきます。
マンション売却は一括査定サービスでまずは無料査定を

不動産査定には、無料で受けられる一括査定サイトというツールがあります。とても便利な査定方法なのですが、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、一括査定サービスの特徴や、初めて査定サービスを利用する人におすすめのすまいステップについてご紹介します。
一度に複数の不動産会社に査定依頼ができる
一括査定サイトを使うと複数の会社から無料で査定結果を受け取ることができるので、マンション売却の仲介契約をしていない段階で大まかな売却金額を予想したいときに役立ちます。
もし一括査定サイトを使用しないと、どのような手間がかかるのでしょうか。査定サイトを利用しない場合の手間は以下の通りです。
- 一軒一軒の不動産会社に足を運ぶ必要がある
- 不動産会社の営業時間に合わせなければならない
- 不動産条件の記入が面倒
- 結果を取りに行く必要がある
なにより1回で複数の不動産会社に査定を依頼することで、適正価格を知ることができます。
質の高い不動産会社を見つけやすい
マンション転売のため、最寄りの不動産会社をピックアップし1軒1軒担当者まで比較をするのは、膨大な手間と時間がかかってしまいます。初めてマンションの売却をする人にとっては、慣れない作業で負担になるでしょう。
一括査定サイトなら、独自の基準で登録会社が厳選されていて、査定依頼を出すときに自動で最適な不動産会社をリストアップしてくれます。自身では把握していなかった質の高いところも見つかりやすくなります。
一括査定サービス利用者が選んだおすすめサービスTOP3
※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)
こちらは、サービス利用者のアンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声と編集部の知見が合わさったできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。
なお、不動産一括査定サービスは、それぞれ対応するエリアや提携する不動産会社が異なるため、1つだけでなく複数のサービスを利用することをおすすめします。
次の記事ではより多くのサービスを含めたランキングや「査定結果の満足度TOP3」や「親族・友達におすすめしたいTOP3」などカテゴリ別にもランキングを紹介しています。さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。

また、マンション売却に適したおすすめの一括査定サービスをランキング形式で紹介しているこちらの記事も併せてチェックしてみてください。

マンション転売に必要な諸費用

マンション転売について注意すべきポイントを解説してきましたが、かかる費用も気になるのではないでしょうか。購入時と売却時でそれぞれ次の費用がかかります。
マンション購入時
- 仲介手数料
- 印紙代金
- 不動産取得税
- ローンの抵当権設定費用
これらの出費はマンション購入に限らず、不動産を取得するときに必ずかかってくる費用です。購入代金内訳のおよそ6%にあたる部分がこれらの費用だということを覚えておきましょう。
マンション売却時
- 仲介手数料
- 印紙代金
- ローン抵当権の抹消費用
- 転売で得た利益に譲渡所得税
マンション売却時は購入時に比べて、かかる費用はあまり大きくありません。これらの費用は売却代金内訳の約4%にあたります。
また、仲介手数料の相場は、購入・売却ともに物件価格の3%に6万円を足した額が上限です。3,000万円で購入したマンションであれば、96万円程もかかります。しかし仲介手数料には下限額は決まっていないため、不動産会社によっては値引き交渉を行うことも可能でしょう。
不動産の仲介手数料の値引きについてはこちらの記事でも取り上げていますので、併せてチェックしてみてください。

マンション転売でかかる税金

上記で紹介した経費で触れている税金について、マンション転売の利益を減らしてしまう売却時にかかるものを詳しく紹介します。
譲渡所得にかかる税金
もし転売したマンションが購入金額よりも高く売れて利益が出たときには、この譲渡所得に対する税を支払う必要があります。
譲渡所得税は以下の式で計算されます。
- 所得税
- 復興特別所得税
- 住民税
この税金は、譲渡所得金額に税率を掛けて割り出されます。さらに、売却の際には譲渡所得にかかる税金だけではなく、手続きにかかる税金もあります。
売却の手続きの際にかかる税金
売却の手続きにかかる費用は3つあります。
印紙税
印紙税は、マンションの転売で作成する売買契約書に貼らなければならない印紙の金額です。
国税庁では取引金額別に以下の金額を設定しています。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え 1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え 5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
引用元:国税庁 「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
補足ですが、上記の金額は平成9年4月1日~平成26年3月31日に作成された譲渡契約書とは税額が違います。また、軽減税率の適用される期間は平成26年4月1日~令和4年3月31日までです。
抵当権抹消時の登録免許税
マンション購入時にローンを組むと、貸し付けをしている銀行は支払いが滞ったときに、マンションを担保にできる権利(抵当権)が発生します。マンションを転売するときには、ローン残高を売却した利益やその他預貯金などで完済しなければならないです。
ローンを完済すると銀行側はマンションを担保に取る理由がなくなるため、抵当権を抹消する手続きが必要になります。この抵当権抹消手続きで必要になるのが登録免許税です。
登録免許税は、1不動産につき1,000円と決められています。マンションの転売では、土地と建物部分をそれぞれ1つと数え、登録免許税として2,000円を法務局に支払います。
仲介依頼時の消費税
仲介手数料を支払う際や、司法書士に上記の登記手続きを依頼して手数料を払うときなどには消費税が発生します。ちなみに、消費税率はサービスに対して払われるので10%です。個人が売却する場合は、マンション自体には譲渡に関わる税がすでにかかっているので消費税は要りません。
マンション転売の税金対策

マンション転売時にはさまざまな税金がかかりますが、できるなら支払う税金額をおさえて少しでも売却益を自分の手元に残したいものです。そこで節税対策について見ていきましょう。
5年超えてから転売する
先ほど挙げたマンション所得金額にかかる所得税、住民税、復興特別所得税は、所有期間が5年越えであれば税率が軽減されます。軽減税率はそれぞれ以下の通りです。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 |
復興特別所得税 |
| 5年超え | 15% | 5% | 0.315% |
| 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% |
5年越えの合計税率が20.315%なのに対し、5年以下は39.63%と実に19.315%分の節税になります。なお、所有期間とは購入から売却した年の1月1日までの期間です。
特別控除を適用する
政府は空き家をなくすための対策として、マイホームを売却したときの税金をさらに軽減するための措置を提供しています。その中でも多くの人が利用しやすいのが「3,000万円特別控除」と呼ばれる特例です。
この制度は売却した譲渡所得から3,000万円分は非課税とするありがたいものです。この適用を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 所有者が実際に住んでいたか
- 売却した前年、前前年にこの特例を受けたことがないか
- 売却した前年、前前年にマイホーム買い換え特例を受けていないか
- 売主と買主は生計を同じくする親子、親戚関係でないか
多くのマンション売却では適用条件を満たしているため、利益が3,000万円を超えるまでは譲渡所得税は0円です。ただし注意すべき点は、転売目的で自身が住む予定のないマンションの売却だと使えないということです。
マイホームならば10年超えてから転売する
この特例は3,000万円特別控除を受けても、譲渡所得額がプラスになる場合に併用できる軽減税率です。受けられる主な条件は所有期間が10年を超えている居住用マンションで、さらに所有権のある者が住んでいた物件であること、以前にこの特例を受けていないこと、売り手と買い手が親子や生計を共にする親族関係にないことなどが挙げられます。
軽減されたあとの税率はそれぞれ以下のとおりです。
| 譲渡所得金額 | 所得税 | 住民税 |
| 6,000万円以下 | 10% | 4% |
| 6,000万円超え | 15% | 5% |
ちなみに、この譲渡所得金額は特別控除の3,000万円を引いて残った金額に当てはめられます。また、所有期間は購入時から売却した年の1月1日までです。
3,000万円の特別控除を受ける際は、この特例措置も併用できることを知っていれば納税額を大幅にカットできます。自分の転売予定マンションが、所有期間が10年超えているかをぜひ確認してみましょう。
利益がないマンション転売で損益通算
マンション転売に慣れた人でも、毎回利益が出せるとはかぎりません。想定より安い売却になってしまい、譲渡所得金額がマイナスになることもあります。譲渡所得税は0円のため対策をする必要はないと考えてしまいますが、損益通算という制度で節税が可能です。
副業でマンション転売を行う人は、毎年本業の収入に対して所得税や住民税を支払っています。損益通算では、マンション転売のマイナス分を本業の収入と合算して、次年度の税金を計算することになります。通常より収入を少なく見積もれるため、節税になってくれます。
マイナス分が本業の年収より大きな場合は、さらに繰越控除という制度を使います。1年分ではカバーできなかったマイナス分の残りを、次年度の収入から差し引くことができます。確定申告は必要ですが、最長で3年間は節税が可能です。
マンション転売の注意点

ここまでマンション転売で利益を出すポイントや節税対策を紹介してきました。しかし損をしないために、購入資金の確保や売却方法で注意点が2つあります。どのような注意点か詳しく見ていきましょう。
投資用マンションでは住宅ローンが使えない
転売用のマンションを自己資金だけで購入するのは非常に困難で、ローンの利用が一般的です。しかし自身が住む予定のないマンションの購入では、住宅ローンは使えません。住宅ローンの条件に自宅としての利用が明記されているため、不動産投資ローンを使うことになります。
不動産投資ローンの金利は、住宅ローンの0.5~2.0%程度より高く、1.5~4.5%程度となっています。転売まで数年間所有する場合、毎月の返済額は住宅ローンより高額になります。
金利が高い代わり、融資を受けられる限度額は年収ベースで10~20倍程度となります。住宅ローンは5~8倍程度のため、不動産投資ローンなら購入する物件の選択肢が増えるでしょう。
買取の利用は慎重に検討
マンションの売却先がいつまでも見つからないと維持費の出費が続きます。購入価格より高く売却できたとしても、維持費分で損失がでるかもしれないです。しかし早く手放すためとはいえ、買取の利用は慎重に検討をしてください。
買取は仲介と違い、不動産会社が物件を購入します。購入希望者を探さなくてよく仲介手数料も必要ないですが、買取額は仲介の売却価格の7割程度になります。買取った物件を不動産会社が別の人に売却して利益を得るため、仲介の売却より安くなります。
マンション転売での買取は利益が出ない可能性が高いため、損切りの最終手段として活用しましょう。
まとめ

マンションの転売で利益を出せるかどうかは、購入する物件選びから決まってきます。失敗を避けるには、売却するタイミングや仲介を依頼する不動産会社選びも重要です。
また、購入時や売却時にかかる税金を知って節税できる部分は積極的に国の特例措置を利用しましょう。手続きをしないと適用されないものが多く、初回は迷うかも知れませんが忘れないでください。
この記事で取り上げた「マンション転売で儲けるためのポイント」を参考に、最大限の利益を得ましょう。
不動産一括査定サイト利用者が選んだおすすめサービスTOP3

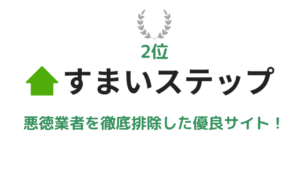

不動産一括査定サイト利用者が選んだカテゴリ別TOP3
≪査定結果の満足度TOP3≫
≪サイトの使いやすさTOP3≫
≪親族・友達におすすめしたいTOP3≫
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。