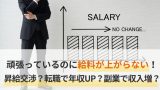都会にそびえたつタワーマンション。最新の設備や周辺環境が充実していて、住んでいる人たちのステータスが高そうで、何より見晴らしが素晴らしそうで、一生に一度はこんなところに住んでみたいと憧れる方も多いと思います。
しかし、タワーマンションに住んで後悔したという声も少なくはありません。タワーマンションの購入費や家賃は高額ですし、住んでから理想と違う事に気づき後悔する前に、メリットだけではなくデメリットについてもしっかり把握しておくことが大切です。
そこで、この記事では実際に住んだ方々の声を分析し、タワーマンションのメリット・デメリットと失敗しない選び方を紹介します。
※株式会社リンクアンドパートナーズによる調査。アンケートモニター提供元:GMOリサーチ株式会社
タワーマンションに住んで後悔した人っているの?

タワーマンションとは、高さ60メートル以上、およそ20階建て以上の住居用建築物をいいます。一般的なマンションとは異なる超高層建築物ならではの特徴、メリット・デメリットがあります。
まずタワーマンションに住んでどのくらいの人が後悔したと感じているのか、さまざまな調査の結果を見ていきましょう。
およそ4人に1人が後悔している
憧れの住まいというイメージがあるタワーマンションですが、一定数の住民の方々が「住んで後悔している」「住んでみて良かったと思わない」「住み続けたくない」などと感じているようです。
ある民間会社の調査では、27%の人たちがタワーマンションを買って「後悔している」あるいは「どちらかと言えば後悔している」と答えています。およそ4人に1人がタワーマンションを購入して後悔していることになります。
また、新宿区の調査では5%前後の住民がタワーマンションに不満を感じていると回答しています。「タワーマンションに住んでみて良かったと思いますか」という質問に対し、3.5%の住民が「良かったと思わない」と、また「タワーマンションに住み続けたいと思いますか」という質問に対し、6.3%の住民が「タワーマンションには住み続けたくない」と回答しています。
“参考:新宿区「新宿区タワーマンション実態調査報告書(令和元年度)」”
人気であることに変わりはない
一方、大多数の住民がタワーマンションに満足しています。その割合は7~9割と高いものです。
先に紹介した民間の調査では、73%の人たちがタワーマンションを買って「想像以上に良かった」「後悔していない」と答えています。また、新宿区の調査でも、90.5%の人たちが「タワーマンションに住んでみて良かった」と、別の質問で77.2%の人たちが「このタワーマンションに住み続けたい」「このマンションではない他のタワーマンションに住みたい」と回答しています。
別の民間の調査でも、理想とするマンションのタイプとして「高層マンション、タワーマンション」をあげる人が22.4%(複数回答可)もいます。これらのことからも、タワーマンションに人気があることに変わりないと言えます。
タワーマンションの真実!後悔した人の体験談
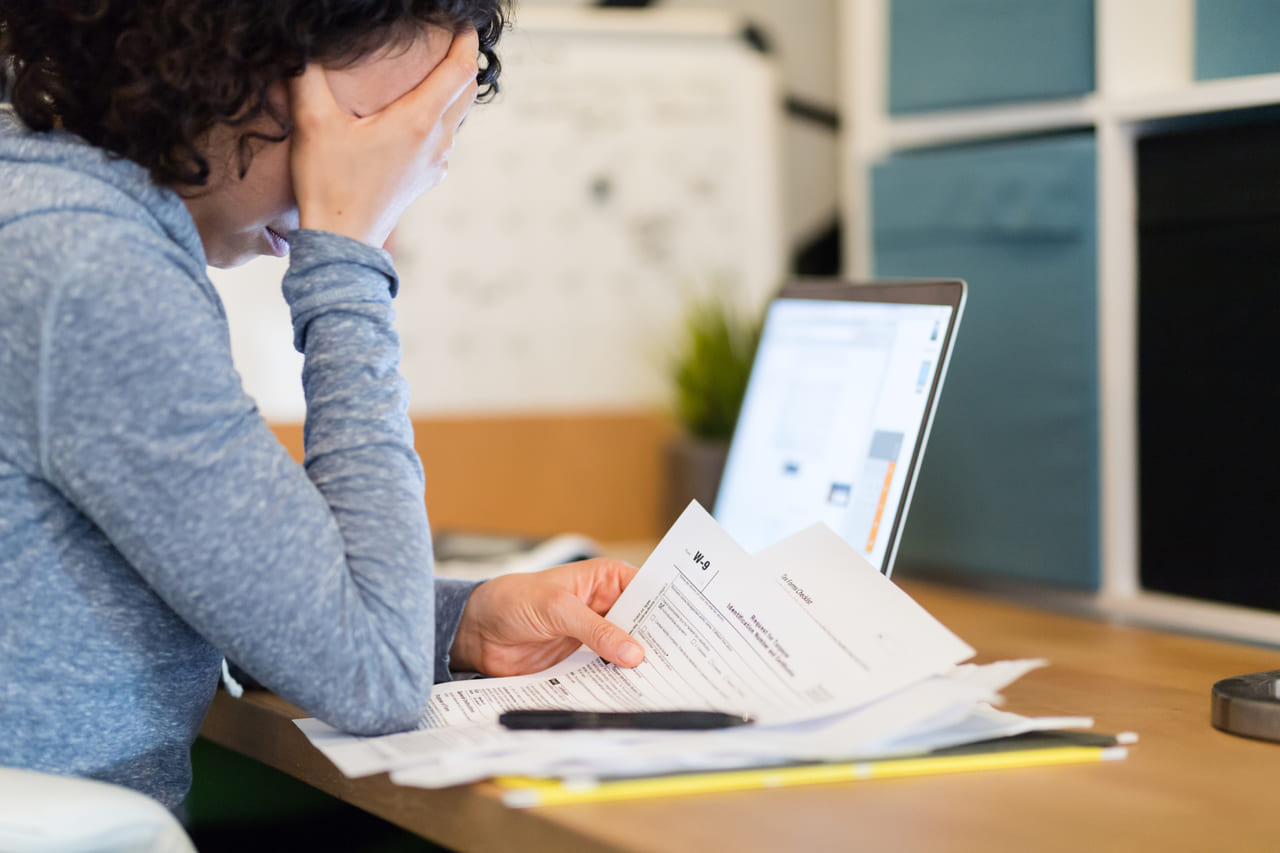
およそ4人に1人が購入して後悔している人たちは、タワーマンションのどのようなところに不満を感じているのでしょうか。実際に住んでいる人たちの体験談をまとめてみると、次のような8つの理由が見えてきました。
- ベランダがほぼ使えない
- 資金面の維持が大変
- 自宅への行き来に時間がかかりすぎる
- 災害時の不安
- 住民間の人間関係
- 騒音問題などのご近所トラブル
- インターネット回線が遅くなりがち
- 資産価値が下がりやすい
ベランダがほぼ使えない
後悔の理由の1つ目は、ベランダが使えないことです。多くのタワーマンションでは、景観を損ねる、あるいは高層階になるにつれて強風が吹くため危険であるなどの理由で、ベランダを設けていなかったり、布団・洗濯物の外干しや物を置くことを禁止しています。
その代わりに浴室乾燥機や乾燥機付きの洗濯機が用意されていますが、毎日毎日部屋干ししなければならないということは、かなりのストレスに感じてしまうようです。終の棲家としてマンションを購入したのであればなおさらです。
資金面の維持が大変
2つ目は、資金面での維持が大変であることです。
まず、月々支払わなければならない住宅ローンの返済額や家賃が負担だという声があります。タワーマンションは一般的なマンションと比較して立地条件が良く、超高層建築物のため建築費が高くなります。そのためタワーマンションの坪単価は一般的なマンションよりももともと高いのが通常ですが、さらに高層階ほど坪単価が上がる傾向があり、それに伴って住宅ローンの借入額や家賃も上がってしまうのです。ある民間会社の調査によると、25~29階にある部屋の坪単価を1とした場合、50~54階の部屋は1.115と高くなり、逆に4階までの部屋は0.942と安くなります。
また、住宅ローンの返済額や家賃とは別に支払わなければならない管理費、共益費、修繕積立金などが負担だという声があります。タワーマンションは一般的なマンションよりも共用施設や付属設備が充実しているので、それらの維持管理する経費が高くなってしまうからです。
そして、固定資産税が高いという声があります。タワーマンションは固定資産の評価が高い傾向があるので、固定資産税も高くなります。なお、賃貸の場合は修繕積立金と固定資産税の支払いは不要です。
自宅への行き来に時間がかかりすぎる
3つ目は、エントランスから自分の部屋まで行き来するのに時間がかかることです。タワーマンションには1000世帯程度が居住しており、エレベーターがないと上下に移動できないので、特に朝の通勤・通学の時間帯は渋滞が起こることがあります。
また、自分や家族の行き来だけでなく、用事があって訪れた人にも負担がかかります。例えば、宅配便の配達員が重い荷物を上の階まで運ぶのは大変ですし、セキュリティも厳重であればあるほど入退出のチェックが大変です。そのようなことからデリバリーを頼むのが申し訳ない、気疲れを感じてしまうという声もあります。
災害時の不安
4つ目は、災害時の不安です。5割以上の住民が災害時の不安や課題を感じています。新宿区の調査では53.2%の人たちが地震・台風等の災害時においてタワーマンションならではの「不安がある」と回答しています。また、別の神戸市の調査でも52.1%の人たちがタワーマンションには「防災⾯の不安や課題がある」と回答しています。
“参考:神戸市「中央区内タワーマンション実態調査報告(平成27年度)」”
まず、地震に対する心配があります。タワーマンションの多くは制震構造や免震構造を採用し、揺れには非常に強い構造物になっています。しかし、近年増加している長周期振動を伴う地震が発生すると、建物をあえて長時間大きく揺らすように設計しているため、特に高層階では室内の家具が移動・転倒したり、地震酔いにより体調不安を訴える住民が多くいますし、高層階だと階段を使って避難すると時間がかかってしまいます。
停電時の心配もあります。地震・風水害や電気設備の故障で停電すると、エレベーターや機械式駐車場が使用できなくなり、各部屋でもオール電化になっているため照明などの電化製品、レンジ、給湯・給水設備なども使えなくなるため、特に子どもや高齢者、要介護者がいる世帯で不安を感じている住民が多いようです。
防災対策や避難生活に不安や課題を感じている住民も2~3割以上います。神戸市の調査では⾼齢者に対する現在及び今後の⼼配の内容として「災害時の避難対策」をあげた人が37.1%、⾏政からほしい情報で「防災」をあげた人が21.3%と、それぞれ回答項目のなかでトップになっています。
住民間の人間関係
5つ目は、タワーマンションの住民の間での人間関係、特にマンション内格差と呼ばれる問題があります。タワーマンションは先述のように住んでいる階が高いほど部屋の資産価値が上がるため、住んでいる階によってどのくらいの所得層なのかがある程度分かってしまいます。そこからヒエラルキーが生まれ、近所付き合いにはお金がかかることや見栄の張り合いなどでストレスを感じる人もいるようです。
騒音問題などのご近所トラブル
6つ目は、騒音問題などのご近所トラブルです。タワーマンションは建物を軽量化するため、やむを得ず壁を薄めにしていることがあります。そのため生活音が響いたり、騒音・悪臭などのトラブルがまったくないわけではありません。また、隣人がクレーマーであるなど、居住者間のトラブルに悩まされている人も少ないようです。
新宿区の調査の管理組合に対する質問で、日頃のマンション管理運営で困っていることについて、18.2%(複数回答可)の管理組合が「居住者間のトラブル」をあげています。
マンション管理の現状や管理組合の仕組みについて解説したこちらの記事もおすすめです。
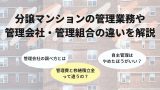
インターネット回線が遅くなりがち
7つ目は、インターネット回線の速度が遅くなりがちなことです。タワーマンションではインターネット回線を共用設備として備え、それを各部屋に分配して使用するため、回線が混雑し速度が落ちてしまう傾向があります。各部屋でそれぞれ回線を敷けばこの問題は改善されますが、施設的に個別契約に対応できないところも少なくありません。
資産価値が下がりやすい
最後の8つ目は、資産価値が下がりやすいことです。タワーマンションの部屋を売却したり賃貸に出したら、想定外に安値になってしまいタワーマンションを購入したことを後悔したという声は決して少なくありません。
マンションの資産価値の大部分は建物分で占められており、その割合は新築の場合、建物8に対して土地2とも言われています。そのため建物の老朽化で建物分の価値が下がると、その影響をもろに受けて資産価値全体も大きく落ち込んでしまうのです。
売れやすいタワーマンションについて詳しく知りたい人はこちらの記事もおすすめです。

メリットはないの?タワーマンションのいいところ

ここまでタワーマンションのデメリットについて見てきましたが、タワーマンションならではの魅力やメリットもあります。タワーマンションに住んでここが良かったというところも見ていきましょう。たくさんありますが次の5点に絞って紹介します。
- セキュリティ面で安心
- いつでも美しい眺望が楽しめる
- 害虫への遭遇率が少ない
- 周囲の生活環境が整っている
- 毎日ゴミ出し可能
セキュリティ面の安心
多くのタワーマンションにはオートロック、テレビ付きインターホン、防犯カメラなど、最新の防犯設備が備わっており、昼間は管理人が常駐、夜間は警備員が巡回するなど、24時間有人管理をしているので、安心して生活できます。また、高層階であれば窓からの侵入が難しいこともタワーマンションのメリットです。
新宿区の調査でタワーマンションを選んだ動機として「防犯面で安心」をあげた人が57.4%(2位)、神戸市の調査でも同様の質問に対して「セキュリティ」をあげた人が16%(3位)となっています(いずれも複数回答可)。
いつでも美しい眺望が楽しめる
いつでも美しい眺望が楽しめることは最大のメリットといってもいいでしょう。高層階であれば、山や海、夜景、花火などが見え、開放感も抜群、外からの目線を気にする必要もないので、1日中カーテンを開けて楽しんでいるという人もいます。
新宿区の調査でタワーマンションを選んだ動機として「眺望が良い」をあげた人が47.5%(3位)、神戸市の調査でも同様の質問に対して「眺望」をあげた人が17%(2位)となっています(いずれも複数回答可)。
害虫への遭遇率が少ない
害虫への遭遇率が少ないこともメリットのひとつです。エレベーターに乗ってきたり、衣服に着いてくることもありますが、虫は高く飛べないため、高層階であるほど害虫に会う確率は低くなります。虫が入ってこないので気軽に窓を開けて換気することができます。
新宿区の調査では、タワーマンションを選んだ動機として「虫が少ない」をあげた人が19.7%(複数回答可)います。
周囲の生活環境が整っている
周囲の生活環境が整っていることも大きなポイントです。再開発エリアに建設されることが多いので、敷地内や近接地にスーパー、行政機関、郵便局、銀行、図書館などが入った商業施設や文化施設がつくられることもあります。敷地内にもゲストルーム、パーティールーム、フィットネスジム、キッズルームなど充実した共用施設や、コンシェルジュサービスがあるマンションもあります。また、交通アクセスが良く、駅に直結しているマンションもあります。
新宿区の調査では、タワーマンションを選んだ動機として「交通の利便性」をあげた人が64.5%(1位)、「コンシェルジュ等サービスの充実度」をあげた人が34.7%、「パブリックスペースの充実度」をあげた人が25.0%います。神戸市の調査でも同様の質問に対して「交通の利便性」をあげた人が23%(1位)います(いずれも複数回答可)。
毎日ゴミ出し可能
多くのタワーマンションではゴミ収集・処理設備が整っており毎日ゴミ出しができるので、部屋にゴミが溜まったり、悪臭や害虫が出ず、非常に衛生的です。各階にゴミステーションが設置されていたり、各部屋のキッチンのシンクにディスポーザーが備え付けられているマンションもあります。
やっぱりタワーマンションに住みたい!失敗しない選び方とは

ここまでタワーマンションのメリット・デメリットを見てきましたが、やはりデメリットを上回る魅力がタワーマンションにあると思った方も多いのではないでしょうか。そこで、住民の方々が後悔したと感じた点から学び、失敗しないタワーマンションの選び方を探ってみましょう。ポイントを5点紹介します。
- エレベーターの設置基数が十分な物件か
- 修繕積立金がいくらかかるか
- 共用施設が充実している物件か
- 資産価値が落ちにくい物件か
- 十分な災害対策ができている物件か
エレベーターの設置基数が十分な物件か
1点目は、エレベーターの設置基数が十分な物件であるかという点です。マンションに設置する適正基数は総戸数100戸に1基と言われています。他にもチェックしておきたい点は次の通りです。不動産会社の営業担当者に確認し、できれば朝の通勤・通学の時間帯のエレベーターホール等の様子を実際に見ておきましょう。
- 定員は十分か(9~13人乗りが良い)
- 高階層用と低階層用に分かれているか
- 階段を利用できるか
- 防犯カメラで外部からエレベーター内部を確認できるか
- 駅に近い場所に設置されているか
修繕積立金がいくらかかるか
2点目は、修繕積立金がいくらかかるかという点です。新宿区の調査によると、修繕積立金の平均は1平方メートルあたり174円です。しかし、修繕積立金の金額設定は、はじめは安めに設定し徐々に値上げしていきます。したがって、将来の値上げを見越して1平方メートルあたり250〜300円、ハイグレードなマンションであれば400円ほどを見込んでおいたほうがよいでしょう。将来の値上がりは長期修繕計画を確認すればある程度把握できます。
共用施設が充実している物件か
3点目は、共用施設が充実している物件であるかという点です。共用施設にかかる経費が物件の購入費や管理費などにも上乗せされていますので、自分の資産の一部であることを意識して吟味しましょう。豪華さに目を奪われるのではなく、現在や将来の自分・家族にとって必要なのかをよく検討しましょう。あると便利な共用施設は次の通りです。
- スカイラウンジ
- フィットネスジム
- ゴミステーション(365日24時間利用できる)
- ディスポーザー
- ゲストルーム
- 宅配ボックス
なお、新宿区の調査によると、区内のタワーマンションの69.6%が「ゲストルーム」、47.8%が「パーティールーム」、39.1%が「フィットネスジム」、21.7%が「キッズルーム」を設置しています。
資産価値が落ちにくい物件か
4点目は、資産価値が落ちにくい物件であるかという点です。前にも述べたように、タワーマンションの資産価値は築年数が古くなるにつれて落ち込んでいくことはどうしても避けられません。しかし、できるだけ資産価値が落ちにくい物件を選ぶことができれば、将来物件を売却・賃貸に出した後の資金計画に余裕ができます。
資産価値が落ちにくいタワーマンションには、次のような特徴があります。
| 項目 | 内容 |
| 立地 |
|
| 希少性 |
|
| 生活利便性 |
|
| ブランド力 |
|
| 眺望・間取り |
|
| 管理・メンテナンス |
|
資産価値のあるマンションについて詳しく知りたい人はこちらの記事もおすすめです。

十分な災害対策ができている物件か
5点目は、十分な災害対策ができている物件であるかという点です。地震、台風や長時間の停電など災害時の対策についてチェックしたい項目は次の通りです。
- 耐震構造は何か(免震、耐震、制振/制震)
- スプリンクラー、防火壁、非常口、避難路、非常用電源等の状況
- 避難場所は安全なところにあるか、キャパシティは十分か
- 防災用倉庫はあるか、医薬品や食料品等の備蓄は十分か
- 自主防災組織は組織されているか
- 非常時の災害行動マニュアルは整備されているか
- 日頃から住民同士のコミュニケーションの場はあるか
マンション購入なら、不動産情報の一括取り寄せができる「タウンライフ不動産売買」がおすすめ
※株式会社リンクアンドパートナーズによる調査。アンケートモニター提供元:GMOリサーチ株式会社 希望に合う住宅を効率よく探すなら物件情報の一括取り寄せサイトが便利です。住みたい街の情報を入れるだけで、複数の不動産会社から希望の条件にマッチした物件情報が届きます。
とくに、編集部がおすすめしたいサービスがタウンライフ不動産売買です。タウンライフ不動産売買がおすすめな理由を以下にまとめています。
希望に合う住宅を効率よく探すなら物件情報の一括取り寄せサイトが便利です。住みたい街の情報を入れるだけで、複数の不動産会社から希望の条件にマッチした物件情報が届きます。
とくに、編集部がおすすめしたいサービスがタウンライフ不動産売買です。タウンライフ不動産売買がおすすめな理由を以下にまとめています。
まとめ

今回はタワーマンションに住んで後悔したという声から、タワーマンションのメリット・デメリット、失敗しないタワーマンションの選び方を探ってきました。
タワーマンションに住んで後悔したという声には、資金面、利便性、安全性などさまざまな背景があります。しかし、たとえデメリットがあったとしてもタワーマンションが魅力的な物件であることは変わりありません。入居前に確認しておくべき点のチェック漏れがないように気をつけるとともに、長期的な計画をしっかりと立てて、後悔のない住まい選びをしましょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。