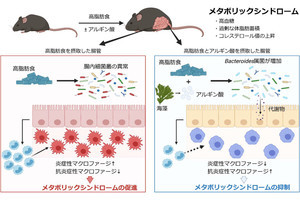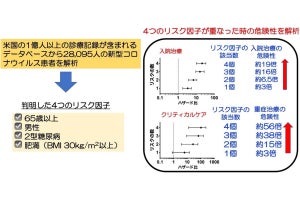沖縄科学技術大学院大学(OIST)は10月15日、タンパク質「XRN1」が、脳が食欲や代謝を制御するのに重要な役割を果たすことを特定し、マウスを用いた実験で前脳にて同タンパク質を欠損させると、マウスの食欲が旺盛になり、肥満となることを明らかにしたと発表した。
同成果は、OIST 細胞シグナルユニットの髙岡翔平大学院生(研究当時)、同・栁谷朗子博士、同・モハメッド・ハイサム博士、同・山本雅教授らの研究チームによるもの。詳細は、国際生物学総合誌「iScience」に掲載された。
肥満は、基本的に食物の摂取量(カロリーの摂取量)に対してエネルギーの消費量が少ないという不均衡が原因となって起こるが、脳がどのようにして膵臓や肝臓、脂肪組織などの末梢組織と協調して食欲や代謝を制御しているかについては、よくわかっていないという。
そこで今回の研究ではメッセンジャーRNA(mRNA)分解の最終段階を制御し、遺伝子活性に重要な役割を果たしているタンパク質「XRN1」に着目。前脳の一部のニューロンにおいて、XRN1をなくしたマウスを作成して実験が行われた。
その結果、脳内にXRN1がないマウスは生後6週間で急速に体重が増え始め、生後12週までには肥満になっていることが確認されたほか、マウス体内の脂肪組織や肝臓などで、脂肪の蓄積も見られたという。
また摂食行動の観察から、XRN1欠損マウスは対照マウスに比べて1日あたりの摂食量が約2倍に増加していることも確認されたという。
さらに、XRN1欠損マウスの過食の原因解明に向け、食欲を抑えるホルモン「レプチン」の血中濃度を測定したところ、対照群に比べて異常に高い値となっていることが確認されたという。正常であれば、マウスは食欲を感じなくなるはずだが、XRN1欠損マウスは対照マウスとは異なり、高濃度のレプチンでも効果がなく、食欲が抑制されていないことが判明(レプチン抵抗性)したという。
加えて、5週齢のマウスから、インスリンに対して抵抗性があり、マウスの血糖値と血中インスリン値が、加齢に伴ってレプチン値の上昇とともに著しく上昇していることも確認されたとする。
マウスの血糖値と血中インスリン値が上昇したのは、レプチンに反応しなかったためであると考えられると研究チームでは説明しており、レプチン抵抗性があったために、マウスは摂食行動を続け、血糖値が上昇し、結果として血中のインスリン値が増加したと考えられるとしている。
このほか、エネルギー消費量の調査も実施。6週齢のマウスでは、エネルギー消費量に全体的な差は見られなかったが、対照マウスは最も活動的な夜間に炭水化物を燃焼し、活動の少ない日中に脂肪を燃焼するという切り替えができるのに対し、XRN1欠損マウスは、昼夜問わず脂肪を効率的に消費せず、炭水化物を主なエネルギー源としていることが確認されたとのことで、XRN1欠損マウスでは、脂肪を効果的にエネルギー源として利用できないということが明らかとなった。しかし、なぜこのようなことが起こるのかは、まだ謎のままだとするが、総括して、XRN1欠損マウスが肥満になった原因は、レプチン抵抗性による過食だったと考えられるとしている。
なお、XRN1欠損によってどのようにレプチン抵抗性と食欲増進がもたらされるのかについては、肥満マウスの視床下部では、強力な食欲増進物質の1つである「アグーチ関連ペプチド」(AgRP)というタンパク質を作るmRNAが増加していることが確認されていることから、研究チームでは推測の域を出ないとするが、このタンパク質の増加とそれを産生するニューロンの異常な活性化が、マウスのレプチン抵抗性の原因になっているのではないかと考えられるという。そのため今後は、神経科学の研究ユニットと協力して、XRN1がどのように視床下部のニューロンの活動に影響を与えて食欲を調節するかを正確に解明していくとしており、最終的には肥満に対する標的療法の開発につなげられればとしている。