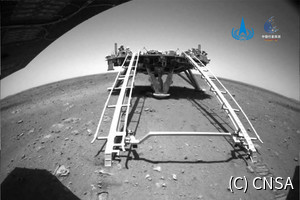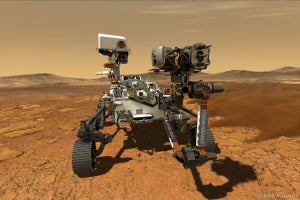宇宙航空研究開発機構(JAXA)は8月17日、米国航空宇宙局(NASA)と欧州宇宙機関(ESA)の合計3機の火星観測衛星によるデータから、砂嵐によって引き起こされる水散逸のタイミングと大きさを定量化することに成功したと発表した。
同成果は、JAXA 宇宙科学研究所 太陽系科学研究系の青木翔平プロジェクト研究員が参加する国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の天文学を扱う学術誌「Nature Astronomy」に掲載された。
長年、太陽系内では、ハビタブルゾーンにある地球にのみ液体の水があると考えられてきた。しかし数多くの探査により、火星や木星・土星の衛星、冥王星などの地下や分厚い氷の下に液体の水がある可能性が示唆されるようになってきた。
こうした液体の水が存在する可能性のある天体のうち、地球から最も近いのが火星だ。火星は約35億年前、海と呼べるレベルで大量の液体の水があったことが、さまざまな証拠からわかっている。しかし現在は、液体の水を維持するのは不可能なほど希薄な大気と、酸化鉄の赤い砂漠と荒れ地が支配する乾燥しきった世界となってしまっている。
大量の水が失われた理由は現時点で明確な答えは出ていないが、これまでの説では、水は水素と酸素に分かれて宇宙に散逸していったと考えられてきた。それは、火星の核が早い段階で冷えてしまい、固有磁場が失われたことで、太陽風によって大気が剥ぎ取られてしまうのを防げなくなり、その結果、水は水素と酸素に分かれ、宇宙へと散逸していってしまったためとされてきた。
そして、地表から宇宙へと水蒸気を運んだのが砂嵐だとされている。地表面付近で発生する砂嵐によって水蒸気が高高度にまで輸送され、あとは太陽風に吹き飛ばされるという考えだが、これまで砂嵐によって水蒸気が宇宙に運ばれていく様子が網羅的に捉えられたことはなく、詳細は不明であったという。
そこで今回の研究では、NASAの観測衛星「Mars Reconnaissance Orbiter」(MRO)と、同・観測衛星「Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN」(メイブン)、欧州宇宙機関(ESA)の観測衛星「ExoMars Trace Gas Orbiter」(TGO)の3機の計4つのセンサーが同時に捉えた、2019年1月から2月にかけて発生した小規模な砂嵐の観測データを活用して調査が行われた。
砂嵐が発生した際の地表面から宇宙空間までのダスト、温度、氷雲、水蒸気、水素が詳細に分析された結果、小規模の砂嵐が発生して大気が加熱され、氷雲が消失させられ、水蒸気が大気上層に輸送されていく様子が判明したほか、砂嵐によって、水素の散逸が通常の5~10倍にまで増大していることも示されたという。また、中層大気における水蒸気量の増加から、散逸水素が増大するまでの期間が約1週間であることも確認された。
このような小規模の砂嵐は火星でほぼ毎年発生していることから、砂嵐が火星水環境の進化に与える影響は大きいことが明らかとなったと研究チームでは説明している。
-
2019年1月に発生した小規模な砂嵐の前後における大気場の変動(Chaffin et al., 2021, Nature Astronomy改変)。上から、「水素原子発光強度の鉛直高度分布[kR]」(メイブン)、「水蒸気組成比の鉛直高度分布[ppm]」(TGO)、「タルシス山地域の画像」(メイブン)、「氷雲の光学的厚さ」(MRO)、「高度50kmにおける大気温度[K]」(MRO)、「ダストの光学的厚さ」(MRO)。2019年1月7日前後の砂嵐発生に伴って、ダストの光学的厚さが増加するとともに、大気温度の上昇および氷雲の消失が観測され、また水蒸気が上層へと輸送され、約1週間後には散逸水素が通常の5~10倍へ増大するという一連の様子が、複数の探査機によって捉えられた (出所:JAXA 宇宙科学研究所Webサイト)