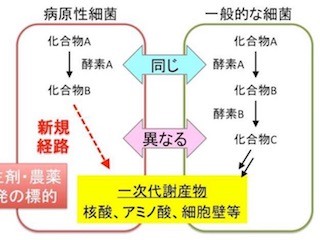神奈川県立産業技術総合研究所は、揮発した残留農薬を迅速・特異的に空気中から直接検知可能なセンサを開発したと発表した。
|
|
同センサの農薬検知機構。(i)寒天ゲル中には、始めにDNAアプタマーが含まれている。(ii)空気中の揮発農薬分子に触れると、農薬分子は寒天ゲルの中に吸着され、DNAアプタマーと複合体を形成する。(iii)複合体がナノポア(小孔)を通過しようとすると閉塞するため、小孔の閉塞を微小電流値の変動にもとづいて識別し、 農薬の有無を検知する。(出所:神奈川県立産業技術総合研究所記者発表資料) |
同研究は、神奈川県立産業技術総合研究所の藤井聡志研究員と、東京大学生産技術研究所の竹内昌治教授らの共同研究グループによるもので、同研究成果は、6月16日に英国王立化学会Lab on a Chip誌電子版に掲載された。
食品の残留農薬試験は、対象食品の一部をサンプルとして収集し、その抽出物から残存農薬成分を質量分析機等により分析する手法が厚生労働省により定められている。残留基準値を超える食品の販売・輸入は食品衛生法により禁止されているが、現在の手法は、食品を分析に使用する破壊検査であることから、全品を検査することができない。
同研究グループは、こうした残留農薬を、食品を傷つけることなく調べる技術の研究開発を進めており、空気中に揮発した農薬成分(オメトエート)100ppbをおよそ10分で検知するセンサの開発に成功した。同センサのセンサ素子は、人工的に作成した細胞膜、細胞膜に1ナノメートルの小孔を作るタンパク質(アルファ-ヘモリシン)、合成DNAからなる。まず、空気中に揮発している農薬成分を寒天ゲルによりセンサに吸着させると、寒天ゲルに取り込まれた農薬成分は、DNAアプタマーと呼ばれる特殊な合成DNAと結合し複合体を形成する。次に、このDNAアプタマーと農薬成分の複合体を電気泳動力によってナノポア(小孔)に移動させると、複合体はナノポアを閉塞させ、ナノポアを通るイオン電流の変動が観測される。これにより、農薬成分の有無が識別可能となるということだ。
|
|
(i)同センサ全体図。(1)センサ素子(2cm四方) (2)電流値を取得・信号増幅する装置 (3)測定時に使用するタブレット型端末<BR>(ii)同センサに農薬を処理しない場合、構造が類似する農薬4種を処理した場合、オメトエートを処理した場合。オメトエートを特異的に検知していることが示されている。(出所:神奈川県立産業技術総合研究所記者発表資料) |
また、同研究チームは、揮発した農薬成分(気中オメトエート濃度 100ppb)に10分間曝露したセンサにおいて、農薬成分の検知信号を得ることに成功した。検知までの時間は、農薬成分への曝露時間も含めて約12分で、同結果は、開発センサが空気中に揮発した残留農薬を検知できる性能を有することを示している。さらに、食品抽出物による残留農薬検査に見立てた実験も行われた。塩水に溶解した農薬成分の場合、厚生労働省の定めるコメの残留農薬の基準濃度(5μM)は約4秒で、その1000倍薄い5nMの溶液でも約50秒で検知することができた。そのほか、同センサは選択性にも優れ、オメトエート以外の類似構造の分子には反応しないことが確認されている。
同センサを用いると、食品を傷つけない非破壊検査によって残留農薬を調べることできるようになると考えられるため、現在の残留農薬試験では困難な全品検査が可能になり、食品の安全性が高められると期待される。また、同センサは現在の試験で用いられている質量分析機などに比べて小型化が可能であるため、IoT技術と組み合わせることで、将来的には生産現場や小売店など、あらゆる場面で残留農薬基準の管理ができるようになると考えられるという。今後は、開発センサの農薬検知に要する時間を短縮し、残留農薬試験技術としての実用性を向上させていくということだ。