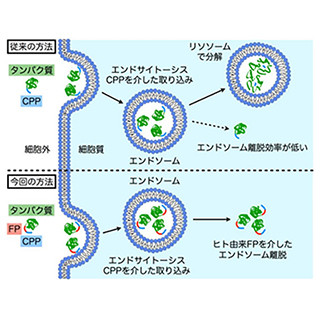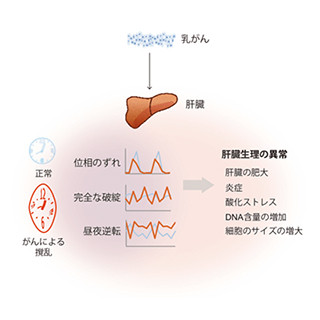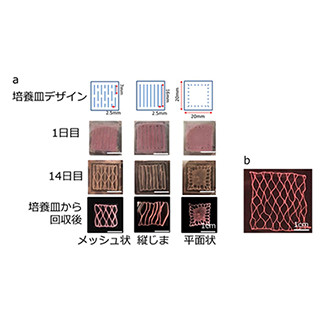京都大学は、同大工学研究科・清中茂樹准教授、同・浜地格教授、慶應義塾大学・柚崎通介教授らの研究グループが、脳内にあり、記憶の強化や減弱に深く関わる神経伝達物質受容体であるAMPA受容体に蛍光の目印をつけ(蛍光標識)、イメージングで動きを調べることのできる新たな手法を開発したことを発表した。この研究成果は4月7日、英国の科学雑誌「Nature Communications」に掲載された。
グルタミン酸受容体の一種であるAMPA受容体は、記憶の強化や減弱に伴い細胞膜上での発現量が変わることが知られている。記憶の分子メカニズムを究明するには、細胞膜上のAMPA受容体に目印をつけ、その動きをイメージングによって観察できる技術の開発が不可欠となる。これまでに、蛍光たんぱく質や抗体を使ってAMPA受容体を蛍光標識する技術が開発されているが、細胞膜上だけでなく細胞内の受容体も標識されてしまうため脳組織への適用ができないという問題があり、現在、記憶の分子メカニズム解明が滞っている一因となっている。
このたび同研究グループは、AMPA受容体を蛍光標識できる新たな有機化合物(ラベル化剤)を開発し、生きた神経細胞や脳組織にも適用できることを見出した。AMPA 受容体を発現させたがん細胞株にこのラベル化剤を振りかけたところ、細胞膜を透過せず、細胞膜上に提示された受容体だけに目印をつけられることが判明したという。また、受容体は蛍光標識後も正常な活性を持つことが確認され、本来の機能を備えた受容体の動きを調べられることもわかったという。
次に、AMPA受容体を天然に発言している培養神経細胞に、開発したラベル化剤を適用したところ、ラベル化剤を添加した神経細胞からはAMPA受容体がシナプス(神経細胞の接合点)に集積して存在する様子を傾向観察で明確に捉えることができたという。また、蛍光標識したAMPA受動態の運動性をFRAP法と呼ばれる蛍光色素の褪色を利用した手法で解析した結果、シナプス膜上で運動が抑制されたAMPA受容体の比率が、従来考えられていたものよりもずっと多いことが明らかとなった。これまでの手法(AMPA受容体の動態解析には蛍光たんぱく質を利用した標識)では、膜上だけでなく細胞内の受容体も標識されていたが、同研究グループが新たに開発したこの手法は細胞膜上の受容体だけを標識するため、AMPA受容体本来の運動性を正確に解析できたと考えられるという。
また、脳内におけるAMPA受容体本来の役割を正しく理解するためには、脳組織から神経細胞を取り出して人工的に調製した培養神経細胞だけでなく、脳組織内の受容体を調べる必要があるが、脳組織は神経細胞や多くの非神経細胞(グリア細胞)が密集することで形成され、脳組織中は密集度が非常に高い環境にある。従来の抗体を用いた蛍光標識法では、サイズの大きな抗体(約10ナノメートル)が深くまで浸透せず、組織の深部にある受容体を調べることができなかった。一方、今回開発されたラベル化剤は、サイズの小さい有機化合物(1ナノメートル未満)であり、実際にラベル化剤を脳組織に添加するとよく浸透し、深部の受容体にも蛍光の目印をつけることができたという。以上のことから、同研究で開発した手法は、これまで蛍光標識が難しかった脳組織の深部にある受容体にも適用できることを実証したということだ。
同研究グループは今後、従来の問題点を克服したこの分子技術を用いて受容体の異常を調べることで、神経疾患や精神疾患の原因解明や新たな診断方法の開発が期待されるとしている。