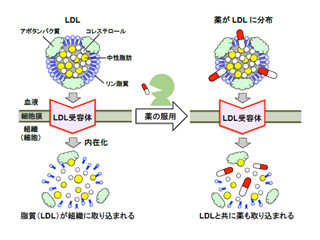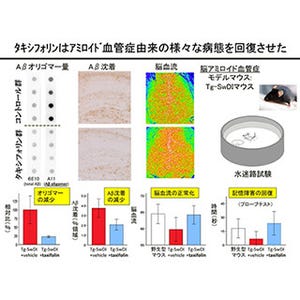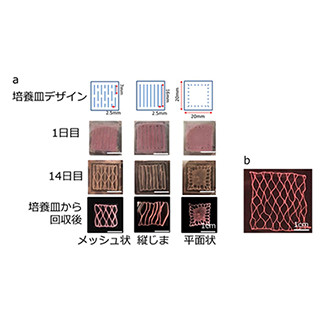北海道大学(北大)は、同大学院薬学研究院 助教の黒木喜美子氏、同 日本学術振興会特別研究員の高橋愛実氏、同 教授の前仲勝実氏、産総研-東大 先端オペランド計測技術オープンイノベーション ラボラトリ ラボチーム長の三尾和弘氏らの研究グループが、異なるクラスのMHC分子の特徴的構造をあわせ持つ免疫抑制タンパク質HLA-Gの新規構造解明したことを発表した。
「HLA-G」は、ヒトの体内において免疫反応を抑制するために働くタンパク質で、ひとつの遺伝子から多様な形を持つタンパク質として存在することで、広範な免疫細胞の活性化を抑制している。最も存在量が多いHLA-G1タンパク質は、さらにシステイン残基を介した対のタンパク質を形成し、単独として存在する時に比べてより強い免疫抑制シグナルを伝達する。その理由として、対のタンパク質(ダイマー)として存在するHLA-G1に対し、抑制シグナルを伝達する受容体が2つ結合することで受容体と解離しにくくなるとともに、細胞内シグナル伝達因子群が集積して細胞内へのシグナル伝達がより効果的になることが、研究グループの構造解析によって明らかになっている。
一方で、他のHLA-G タンパク質が実際にどのような形で存在し、どういう機能を果たしているのかについての知見はなかった。今回、研究グループが注目したHLA-G2タンパク質は、HLA-G1タンパク質に比べてひとつの構造単位を欠損しているため、これまでは対のHLA-G1タンパク質と同様に、システイン残基を介した対のタンパク質として生体内で安定に存在するよ予想されていたが、その実体は不明であった。また、HLA-G1タンパク質を産生できないヒトが、HLA-G2タンパク質を中心とする他の形のHLA-Gを生成することで、HLA-G2はHLA-G1と同等の機能を持っている重要なタンパク質であると考えられる。そのため、HLA-G2タンパク質のかたちを明らかにし、免疫抑制能をHLA-G1と比較し理解することは、今後のバイオ医薬品としての応用における重要な知見となると期待されていた。
同研究グループは、HLA-G2タンパク質の立体構造を明らかにするために、HLA-G2タンパク質を大腸菌封入体の巻き戻し法によって大量調製し、高純度に精製できていることを電気泳動にて確認したうえで、ネガティブ染色法による電子顕微鏡解析で、HLA-G1タンパク質との全体構造比較およびHLA-G2タンパ ク質の構造解析を行った。また、ヒト受容体 LILRB1、LILRB2との結合特異性および結合様式を表面プラスモン共鳴法による相互作用解析によって明らかにした。同時に、対のタンパク質形成様式を確認するために、対のタンパク質形成に必須であると予想されていたシステイン残基をセリン残基に置換した変異体 HLA-G2 タンパク質を調製し、その分子量や性質を野生型 HLA-G2と比較したという。
その結果、これまでに予想されたシステイン残基を介する対のタンパク質として存在するのではなく、システイン残基に依存しない対のタンパク質として存在することが判明し、これはHLA-G1タンパク質とは異なるダイマー形成様式であったという。システイン残基をセリン残基に置換した変異体HLA-G2タンパク質が野生型と変わらない挙動を示すことからも、システイン残基がダイマー形成に必須ではないことが明かとなった。
また、電子顕微鏡解析で得た三次元電子マップにHLA-G1結晶構造を当てはめると、システイン残基(Cys)はダイマー接触面ではなく外側に露出していること、同様に糖鎖修飾部位であるアスパラギン残基(Asn)も外側に露出し、糖鎖結合がダイマー形成に影響しないことが示唆されたという。興味深いことに、HLA-G2構造はHLA-Gが属するMHCクラスIよりもMHCクラスIIに類似した立体構造を取っていることも判明したという。このことは、進化上、遺伝子重複によって形成されたと考えられるMHCクラスIおよびクラスIIの遺伝子進化においても新たな知見となるということだ。また、HLA-G2は HLA-G1と異なる形をとることで、結合する受容体がLILRB2に限られること、ダイマー形成により結合解離しにくい強固な結合を示すことが、表面プラスモン共鳴法により明らかになった。
これらの結果から、HLA-G2はダイマー形成により受容体に強固に結合することがわかった。結合する受容体はミエロイド系抗原提示細胞に限られているため、HLA-G2は直接B細胞やT細胞機能に影響しない、標的細胞が限局的である副作用の少ない新規免疫抑制バイオ医薬品としての発展が期待されるという。同研究グループは、HLA-G2タンパク質がコラーゲン誘導型関節炎モデルマウスにおいて長期間の炎症抑制効果を持つことを明らかにしており、今後の研究によってヒトへの応用が期待できるとしている。