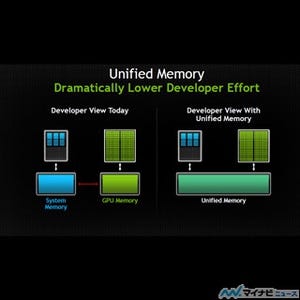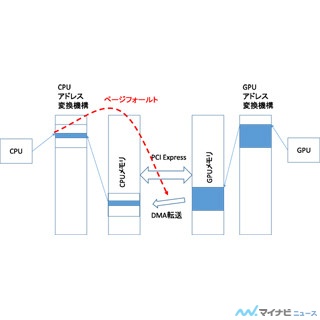NVIDIAのHPCソリューション
NVIDIAのHPCソリューションについて、エンタープライズソリューションプロダクト事業部の杉本事業部長が、GPUによるCAEアプリケーションの高速化とGPUコンピューティングの活用について説明を行った。
なお、この写真のアジェンダのTesla K40やCUDA6については森野氏、Just The Factsと題して米国NVIDIAの成瀬氏が登壇して説明を行った。
GPUを産業ユーザに受け入れてもらうためには、それらのユーザが使うCAEソフトがGPUを使って高速で動作するようになることが必要である。そのため、NVIDIAはCPUとGPUのハイブリッドコンピューティング環境を提供するだけでなく、CAEアプリを作るISV、産業ユーザ、国立研究所などとのコラボレーションで開発を促進している。また、NVIDIAは、線形ソルバツールキットやCUDAライブラリ、GPUコンパイラなど、CAEアプリの開発を助けるソフトやツールを開発、提供を行っている。
次の図はCAEを販売するISVの主要製品と、そのGPU対応状況を示すもので、グリーンの字の製品はGPU対応が済んでいる。単純に数えると、ほぼ半分のアプリでGPUが使える。ただし、1つのユーザにとってみると、自分が使うアプリがGPU対応になっていれば良く、比率は問題ではない。
右下の棒グラフは、各社の2010年と2011年の売り上げを示すもので、この上位9社でCAEマーケットのほぼ75%のシェアを占めている。
次の図は分野別のアプリのGPU対応の状況を示すもので、まだ、リリースには到っていないが、GPU製品を開発中、あるいは研究評価中というものを含めると主要CAEアプリの殆どでGPU対応が進められていることがわかる。
興味深いのは、GPUを使う場合のライセンス料のカウント法で、多くの製品で、CPU1コアの追加と、GPU1チップの追加が、実質的に同じカウントとなっている。また、AutodeskのMoldflowに到っては追加コスト無しという太っ腹なライセンスとなっている。
そもそも、GPUをつける方が性能向上が大きいから、各ISVはGPUサポートを行っているのであるから、CPU1チップ(4コアとか8コアとか)と比べてGPU1チップの方が性能が高くなっているケースが多いと思われるが、従来のライセンス法のCPUコアカウントのライセンスは、すでに多くのユーザに対して行っているので、これをソケット単位に変えると大幅な減収になってしまう。一方、GPUのライセンス料は下げて普及を促進してGPUサポートの投資を速く回収しようと言う作戦かと思われるが、何にしろ、GPUに有利なライセンスとなっていて、GPUの普及を強力に後押しする効果があると思われる。
NVIDIAはNVIDIA GRIDと呼ぶリモート表示技術と、K1、K2というGRID用のGPU製品を持っている。GRIDの主要な用途は、リモートのPCなどの端末で仮想デスクトップを実現したり、サーバで走っている3Dゲームをプレイしたりすることであるが、CAEの解析結果をリモートのPCやタブレットなどに表示するためにも使える。
表示画面だけを転送して表示するので、一般的には膨大な量となる解析データを移動する必要がない。また、ノートPCやタブレットでも表示できるので、会議室や自宅、出張先などどこでも結果を見ることができる。また、顧客やサプライヤなどとの打ち合わせにも使える。そして、企業秘密の解析データをサーバから持ち出す必要が無いのでセキュリティの点でも安心である。
デモンストレーションを見ると、インタラクティブに3Dデータを見る視点を変えたりしても違和感のない表示が得られており、十分なレスポンスであった。
もちろん、業界や事業規模によってCAEの普及度は異なるのであるが、日本自動車工業会の調査結果のように、GPUが性能、コスト、電力などの面でCPUに比べてメリットがあるケースは多くあり、また、CAEベンダのGPU対応を加速しており、製造業でのGPUコンピューティングは立ち上がりつつあるという印象である。