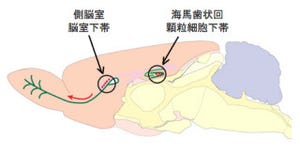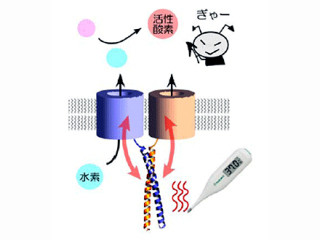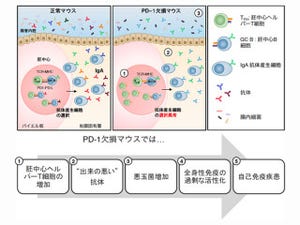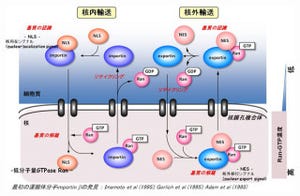理化学研究所(理研)は5月25日、動物細胞同士の接着に必要な細胞膜タンパク質「カドヘリン」分子群に属する「Celsr1(セルサー1)」が、脳・脊髄の基となる「神経管」形成のために必要な「神経板」湾曲において中心的な役割を担うことを突き止め、神経板を一定方向に収縮させる仕組みを明らかにしたと発表した。
成果は、理研発生・再生科学総合研究センター高次構造形成研究グループの竹市雅俊グループディレクター、西村珠子研究員(現・神戸大学バイオシグナル研究センター助教)、本多久夫客員主幹研究員(兵庫大学健康科学部教授)らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米科学雑誌「CELL」(5月25日号)に掲載された。
胚の発生過程では、1つの受精卵が分裂・増殖を繰り返しダイナミックに形や位置を変えて、神経や内臓などの組織、器官へと分化していく。この過程の1つに、「神経管」形成と呼ばれる重要なイベントがある。
神経管形成とは、初期胚の表面を取り巻く外胚葉が背側で肥厚し、将来的に神経管になる細胞層のことである。胚の背側にできた神経板が左右に盛り上がって内側に湾曲して溝を作り、やがて背側で融合して神経管を形成するのだ。
この過程で、神経板の細胞は「神経上皮細胞」に分化し、最終的に脳や脊髄などの中枢神経系を形成する(画像1)。神経管形成が正常に進行せずに神経管が閉鎖しないと、脳・脊髄が体の外に露出する「神経管閉鎖障害」を引き起こしてしまう。
ヒトの場合、神経管が形成される妊娠4~5週ごろに起こりやすく、日本では1万人に対して約6人の割合で見られる(出典:厚生労働省調査より)。
画像1は、神経管の形成過程。主に脊椎動物の発生では、受精卵の細胞分裂(卵割)がある程度進むと、組織や器官の基本となる三胚葉(外胚葉、中胚葉、内胚葉)に分かれる。
その内、神経系を形成する基となるのは外胚葉だ。胚の背側部分の外胚葉から神経板が分化し、左右に盛り上がって内側に湾曲して溝(神経溝)を作り、やがて背側で融合して神経管を形成するのである。
この過程で神経板の細胞は神経上皮細胞に分化し、最終的に中枢神経系を形成するという流れだ。青部分は、「神経冠細胞」を示す。神経冠細胞は、神経管が形成される過程で離脱し、末梢神経系を形成する。
今までに神経管形成に関与する遺伝子やタンパク質は複数が報告済みだ。神経管形成の仕組みは、(1)神経上皮細胞の表層にある「頂端側収縮」が必要であること、(2)「収斂(れん)伸長」が関与すること、(3)「平面内極性」制御が関与すること、などが部分的にわかっている。
なお収斂伸長とは、二次元に広がって分布している細胞群が、一方向に整列、再配置されることにより細胞層が伸長する現象。胚発生の過程でダイナミックな形態形成を起こすために重要な現象の1つである。
また平面内極性とは、上皮細胞層など二次元的な平面上に形成される細胞膜や細胞内の成分のある一定の偏りのことだ。通常、細胞膜や細胞内の成分は均一に分布しておらず、細胞の空間的制御や機能を維持するために特定箇所に特定分子が局在している。
しかし、神経管形成の仕組みはどれがどのように関連するかは不明で、神経管形成過程の全容解明が待たれていた状況だ。
研究グループは、神経管形成過程をより詳細に理解するため、生きたニワトリ初期胚を用いて、湾曲しつつある神経板の細胞、すなわち表層にある神経上皮細胞の頂端部における細胞同士の接着面を観察した。
すると、個々の細胞の接着面が体の中心線(左右対称形の生物において、前面・背面の中央を頭から縦にまっすぐ通る線)に向かって一定方向に収縮し、この収縮が神経板の湾曲と「収斂伸長」の原動力となることが発見されたのである(画像2・3)。
接着面の収縮が起きることは以前からわかっていたが、「収縮に方向性があること」と「収縮によって収斂伸長が引き起こされること」がこの研究によって初めて明らかになった。
画像2は、神経板が湾曲する様子の模式図だ。一層の上皮細胞シートが中心線に向かって陥入する。上皮シートの陥入は、細胞の頂端側で局所的な収縮が発生することによって起きる仕組みだ。
この局所的な収縮には、頂端側に存在するカドヘリンなど「細胞接着因子」()が関与していることが知られていたが、今回、この収縮には一定の方向性(赤矢印)が存在することが明らかとなった。
なお、カドヘリンなどの細胞接着因子は、細胞境界面において同じ分子同士が結合して細胞を接着させる機能を持つ。カドヘリンと類似の構造を持つ多くのタンパク質があり、分子群を構成する。Celsr1はその1つで、細胞間接着のためではなく平面内極性を作るために働くのが特徴だ。
画像3は、神経板の湾曲と収斂伸長の時の細胞の様子を観察したものとその模式図。最初(0:00)は全体的に横に広がっていた細胞群が、時間の経過とともに縦方向に伸長していく様子がわかる。このように二次元に広がって分布している細胞群が、一方向に整列、再配置されることにより細胞層が伸長する現象を収斂伸長と呼ぶ。
体の前後軸(頭-尾)に対して直角方向に分布する境界部(赤線)は収縮し、前後軸方向に平行な境界部(青線)は伸びる。この一定方向の収縮が神経板の湾曲と収斂伸長の原動力となることが発見された。
接着面の収縮は、細胞骨格タンパク質の1種「アクトミオシン」(アクチン繊維にミオシンタンパク質が結合した複合体で、筋肉や細胞骨格の収縮に必須)が収縮することによって起きる。
そこで、「方向性がある」アクトミオシンの収縮がどのようにして起きるのかを明らかにするため、過去に知られている関連因子群から引き金となる因子が探索された。すると、カドヘリン分子群に属するCelsr1が、アクトミオシンの収縮に関連すると突き止められたのである。
ニワトリ初期胚でCelsr1の働きを阻害する実験が行われたところ、神経管が正常に閉鎖しないことが確認された(画像4)。Celsr1は、平面内極性制御因子として知られており、カドヘリンと同様に細胞同士が接着する部分でCelsr1同士が結合することで、細胞の平面上(2次元)において特定分子を局在させる働きをしている。
神経上皮細胞の頂端側では、Celsr1は、胚の前後軸に直行する接着面だけに集まることがわかった。そして、これがアクトミオシンの収縮を引き起こす一連の生化学的シグナル経路を活性化して、神経板を一定方向に湾曲させることが明らかになったのである。
また、数理モデルを導入して神経管形成過程の神経上皮細胞の動きをシミュレートしたところ、細胞接着面の形態変化がアクトミオシンの一方向的な収縮によるものであることを確認した。
つまり、神経管形成過程で、Celsr1が神経上皮細胞の頂端側において、体の前後軸と直交する細胞間接着面に局在し、ここでアクトミオシンの収縮を引き起こす。その結果、これらの接着面だけが収縮し、神経板は、収斂伸長を引き起こしながら、体の中心線に向かって一定方向に湾曲するのである。
今回の研究により、個々の細胞の動きがダイナミックな「形態形成」の原動力となることが見出され、神経管形成の全体像を総合的に把握することに成功している。
ちなみに形態形成とは、発生において生物の形態が形成される過程のことをいう。生物の形は、単に細胞の増殖・分化だけで作られるのではなく、細胞の空間的配置を組織的に調節し、生物種に応じた特徴的な組織、器官の形態が作られるのである。
また、これまで収斂伸長は細胞の移動による再配置によって起きると考えられていたが、神経管形成においては細胞の移動ではなく、細胞接着部位の収縮によって再配置が引き起こされることが明らかとなった。
これは、発生研究のモデル生物であるショウジョウバエの形態形成研究において「細胞接着部位の局所的な収縮が組織全体の大きな形態変形を引き起こす」という概念を脊椎動物でも実証したことになり、動物における発生メカニズムの普遍性を示唆するものといえる。
研究グループは今後、ニワトリ初期胚で明らかになった仕組みがほかの動物種、特に哺乳類にも存在するかどうかを明らかにし、形態形成機構の原理についての理解を深めることを目指すという。それにより、神経管閉鎖障害の発症メカニズムの解明や医学的対処法の開発につなげることが期待できるとも述べている。