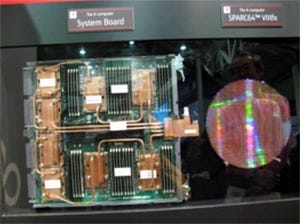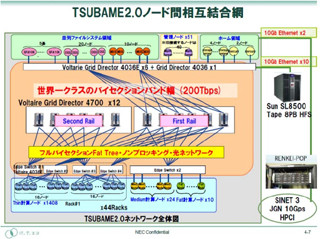高効率な空冷テクロノジ「Sandia Cooler」
米国Sandia国立研究所(Sandia National Laboratories:SNL)は画期的な空冷テクノロジである「Sandia Cooler」をライセンスすると発表した。このテクノロジは、同研究所のJeffrey Koplow氏が発明したもので、従来の放熱フィンと冷却ファンを用いる方法より圧倒的に効率が良いという。
図1に示すように、通常のヒートシンクは銅やアルミなどの熱伝導率の高い金属で作られ、チップで発生した熱をCPUパッケージのヒートスプレッダを経由してヒートシンクのベースプレートに伝える。そして、ベースプレートから熱伝導でフィンの表面まで熱を運ぶ。フィンの表面には冷却ファンからの風が当たっており、フィンの表面から熱を奪って運び去る。高電力のチップの場合は多くの熱を運び去る必要があるので、多くのフィンを立てて熱を奪う面積を増やすという構造となる。しかし、1枚のフィンを薄く長くしてしまうとベースプレートに近い部分は良いが、先の方までは熱が伝わらず有効に働かなくなってしまうので、ヒートパイプを使ってフィンに熱を伝えるなどということになる。
フィンの表面には空気が流れているのであるが、実は、詳細にみるとフィンの表面にくっついて動かない薄い空気の層ができ、フィンの表面の空気は流れていない。この動かない空気の層を「境界層」という。この境界層は空気であり、熱伝導率が低いので熱が通りにくい。このため、多くの熱を運ぼうとすると、よりフィン面積の大きい大型のヒートシンクを使うか、あるいは冷却ファンの回転数を上げて風速、風量を増すということになる。風速を上げると境界層が薄くなり熱伝導が良くなるが、冷却ファンを回す電力が多く必要になる。
また、古いパソコンを開けてみると、CPUのヒートシンクのフィンにはほこりがこびりついている。こうなるとフィンの表面からほこりの層と境界層を通って熱を伝えることになって熱伝導が悪くなるので、さらに冷却ファンの回転数を上げることが必要になってしまう。
Koplow氏の考案したSandia Coolerは図2の写真のようになっており、渦巻き状のフィンの部分を回転させるという構造になっている。この写真のフィン部分の直径は10cmである。
この構造を真横から見ると図3のようになる。回転するフィンはインペラー(Impeller:渦巻きポンプ)と呼ばれ、渦巻き状の部分はインペラーフィン、下側の板の部分はインペラープラテン(platen)と呼ばれている。通常の冷却ではフィンを固定して冷却ファンを回して空気を動かすが、Sandia Coolerでは下側のベースプレートは固定で、上側のインペラーが回転する。なお、この写真ではフィンが見えるように取り外されているが、本当はフィンの上にはカバーがある。
そして、この両者の間は、30μm程度のエアギャップで隔てられている。このため、Koplow氏は、この構造を」Air Bearing Heat Exchanger」と呼んでいる。このエアギャップは、磁気ディスクの円盤からのヘッドの浮上と同じ原理で、回転でできる空気流で浮上しており圧力と回転数(数1000rpm)で決まる距離に保たれる。このため、それほど精度の高い加工は必要ない。また、向きを変えるとインペラーの重みで圧力が変わるが、問題になる程度ではなく、横向きや逆にしても使えるという。
図2の写真で渦巻きの中央に白く見える部分がブラシレスモーターであり、固定子はベースプレートに付けられており、インペラーが回転子になっている。フィンが回転すると、図4のように、中央部分の上側から空気を吸い込み、その空気は渦巻き状のフィンの間を通って外周へ排気される。このようなモーター一体型の構造であるので、冷却ファンのモーターを回して風を送る方法よりも電力効率が高い。
熱はチップからベースプレートまで伝導で伝わり、エアギャップを通ってインペラープラテンに伝わる。そしてインペラーフプラテンから渦巻きフィンの表面に伝導で伝わる。
このフィンは回転しているので表面の空気の流速が速くなり、通常のフィンと比較すると境界層の厚みが数分の1になって空気への熱の伝達が良くなるという。また、固定のベースプレートと回転するインペラーのプラテンの間のエアギャップは静止した空気の層ではなく、回転するプラテン表面に近い空気はそれに引っ張られて横に動きミクロな対流が発生するので、静止したエアギャップに比べると何倍も多くの熱を伝えることができるという。
さらなる効率改善の余地や、室外機などのアプリへの適用も可能
熱の伝わりやすさの逆数を「熱抵抗」と言い、℃/Wという単位で表す。CPUチップと周囲の空気の間の熱抵抗が1℃/Wということは、50Wの発熱があると、チップの温度は空気の温度より1℃/W×50W=50℃上昇するということである。つまり、効率の良いヒートシンクは熱抵抗の値が小さい。なお、同じヒートシンクでも風速が速くなれば境界層が薄くなり、熱抵抗の値は下がっていく。次の図5は、Koplow氏の論文に示されたモーターの消費電力と熱抵抗の関係を示す図である。
図5でRinternalと書かれた緑の破線は、ベースプレートとインペラーの金属部の熱伝導による熱抵抗であり、0.025℃/W(この図の縦軸はKW-1となっているが、これは絶対温度のK/Wの意味であり、℃/Wと同じ)でモーター電力にかかわらず一定である。そして、Rairgapと書かれた赤い破線がエアギャップの熱抵抗で、モーター電力が2.5Wの時は0.04℃/W程度で、モーターの電力を増して回転数を上げると0.01℃/W以下に低下していく。
そして、上側の青の破線が渦巻きフィンから空気への熱抵抗である。これもエアギャップの熱抵抗と同様にモーターの電力(回転数)に依存して境界層の厚みが変わるため、2.5Wの時は0.27℃/Wであるが、15Wにすると0.14℃/Wに低下している。このSandia Cooler全体の熱抵抗は一番上の黒の実線で、その内訳は大部分がフィンと空気の間の熱抵抗で、エアギャップや金属部分の伝導の熱抵抗は全体の2割程度にとどまっている。
論文では、従来方式の高性能ヒートシンクで0.2℃/Wの熱抵抗を実現するには、冷却ファンに100Wの電力が必要であり、大きさも1050立法cmを必要とするが、試作品のSandia Coolerは同じ熱抵抗を実現するモーター電力は20W(図5によると7.5W)で済み、大きさも240立法cmになると書かれている。また、この試作品は効率を最適化した設計にはなっておらず、さらに性能を改善できる余地があるという。
さらに、回転するフィンの方が、通常のヒートシンクのフィンよりほこりがつきにくい。このSandia Coolerの技術はチップの冷却だけでなく、エアコンの熱を逃がす室外機などにも使える。CPUのヒートシンクもそうであるが、エアコンの室外機などもほとんど清掃されないので、ほこりがつきにくいというのは長く使用しても冷却効率の低下が少ないという大きなメリットがある。
ということで、Sandia研究所の発表では、エアコンや冷蔵庫などが全部Sandia Coolerを使うと米国の総電力消費を7%以上下げられると見込んでいる。