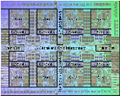2010年8月22日(米国時間)に第22回Hot Chipsが開幕した。といっても日曜日の22日はチュートリアルで、23日、24日が本会議という日程である。場所は恒例の米国スタンフォード大学のメモリアルオーディトリアムである。当地は、昼間は暑いものの湿度は低く、朝晩はちょっと肌寒く感じるという気候で、猛暑にうだる日本とは比べものにならない快適な気候である。
今回のHot Chipsでは、Intelの10コア20スレッドサポートの「Westmere EX」、そして、AMDの次世代プロセサコアである「Bulldozer」と「Bobcat」の発表が行われる。また、中国のInstitute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences(ICT)から256ビット幅のベクタユニットを2個搭載するプロセサ「GS464V」が発表される。このプロセサはTop500で台頭著しい中国がプロセサも含めて純国産スパコンの開発を目指して開発してきているものである。また、IBMの新メインフレームプロセサの「zEnterprise 196」の発表が行われる。一般の読者にはなじみが薄いかと思われるが、5.2GHzクロックと商用プロセサでは最高のクロックを誇る高性能、高信頼プロセサである。
そして、日米の10PFlopsスパコン「京」のプロセサである「SPARC64 VIIIfx」と「POWER7」は昨年のHot Chips 21で発表されているので、今年はそれに続いて、プロセサ間を接続して通信を行うインタコネクトチップの発表が行われる。富士通からはICCと呼ぶインタコネクトコントローラが発表され、IBMからはBluewatersのインタコネクトに使用されるPOWER7 HUBモジュールの発表が行われる。数万のオーダのプロセサを使うスパコンでは、プロセサ間の接続をどうするかが大きな問題で、注目される発表である。
また、NVIDIAのFermi GPGPU、Microsoftの新Xbox 360のプロセサ、Intelの5600シリーズのWestmereについても発表が行われる。
8月22日のチュートリアルは午前が不揮発性メモリで、Samsung ElectronicsのTony Kim氏がFlash、Micron TechnologyのEd Doller氏が相変化メモリ(Phase Change Memory:PCM)、Everspin TechnologiesのSaied Tehrani氏がMRAM、SEMATECHのPual Kirsh氏がRRAMについて講演し、最後にシステム的な観点からこれらのメモリの使い方に関する2件の講演が行われた。
製品化の観点ではFlashが圧倒的に先行しているのであるが、相変化メモリも1GbitのチップがISSCCで発表されており、かなり実用化に近づいた感がある。Doller氏はFlashに比べてPCMは書き換え寿命が大幅に長く、1ビットだけの書き換えが可能で、読み出しも速いことからFlashを使うSSDとDRAMの中間のメモリとして使えることを強調していた。また、EverspinのTehrani氏は微細化によりスピントルク注入の効率があがり、65nmテクノロジでは密度もR/Wの性能もDRAMに迫り、加えて不揮発性が実現できるとアピールしていた。これを実証するような製品が出てくれば大きく評価が変わると思われるが、まだ、大容量チップの製品化という観点では距離がある感じが否めない。
使い方の観点では、Objective AnalysisのJim Handy氏は、DRAMとHDDのアクセス速度とビット単価のギャップを埋めるものとしてFlashによるSSDの存在意義があるという。単純にビット単価を比べると20倍程度の違いがあるのであるが、エンタープライズ用の15000rpmなどの高速ディスクは大容量を主眼とするディスクよりかなり高く、さらに高速のアクセスを要求する場合にはヘッドの移動時間を減らすため、一部のトラックだけを使うというShort-Strokeという使い方がなされ、この場合のビット単価はSSDと大差ないコストになる。このようなエンタープライズ用の高性能ディスクを置き換える用途で大きなマーケットが見込めるという。また、IBMのRich Freitas氏は、不揮発性で、DRAMのようにアクセス速度が速く、2020年時点ではビット単価はHDD並みという目標のStorage Class Memory(SCM)の実現の観点から各種の不揮発性メモリテクノロジの比較について述べていた。
午後のチュートリアルは光インタコネクトに関するものである。オーガナイザがOracle(のSun部門)のRon Ho氏なので、講演者はOracleの人が2人、その他は、Hewlett-Packard(HP)、Massachusetts Institute of Technology(MIT)、Columbia University(コロンビア大学)が各1人という顔ぶれで、Intel、IBMなどの光テクノロジを開発している会社の人は含まれていなかった。
最初の講演者は、SunのJack Cunningham氏で、Sunは最終フェーズには残れなかったがDARPAのUHPCプロジェクトで光インタコネクトの開発を行っており、その成果を中心に高性能光インタコネクトテクノロジ全般について説明を行った。光による伝送は、電気による伝送と比較して、広帯域でエネルギー消費が少ないことが大きなメリットであり、Luxteraからはすでにコネクタの中に光-電気の変換回路を内蔵したアクティブケーブルが商品化されている。また、従来から使われているMach-Zehnder型の変調器はサイズが大きいが、共振リングを使った変調器やフィルタは小型でうまく動作することが説明された。ただし、製造バラつきや温度の影響を補正するためにヒータを組み込んで共振周波数を調整している。
HPのAl Davis氏は、大規模データセンタでは通信やストレージとのデータ伝送のネットワークの需要が増えており、電気伝送ではまかない切れなくなりつつある。ということで光に目が向いているが、まだ、技術的成熟度に不安があるという。やはりユーザから見ると、光の技術的メリットを保持して、値段は従来の電気伝送より高くならないものが欲しいと述べていた。
MITのVladimir Stojanovic氏とコロンビア大のGilbert Hendry氏はオンチップのコア間の光接続に関する講演で、Hendry氏は3D実装を使って、プロセサコアチップの上に光インタコネクトを制御する電気のチップを積み、その上に光の通信路のチップを積層するという構造を提案していた。
最後に登壇したSunのFrankie Liu氏は変調器と光デテクタの回路設計のトレードオフを中心に講演し、送信回路と受信回路が光通信に必要な電力のそれぞれ1/3を占め、両方を合わせると2/3の電力がこれらの回路で消費されると説明していた。