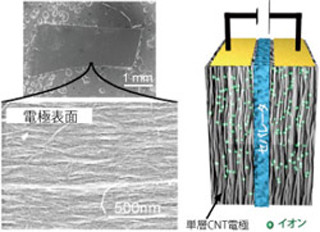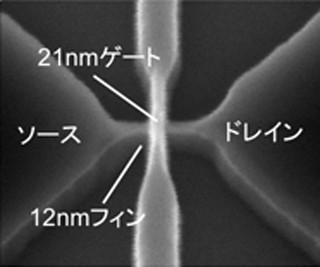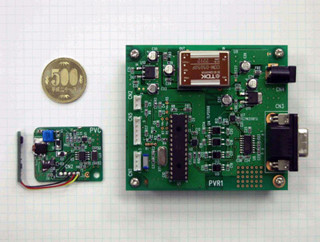産業技術総合研究所(産総研)は、複数のCdSe/ZnSコアシェル型量子ドット(半導体ナノ粒子)を蛍光特性を保ったまま粒径20~100nmの微小なガラスカプセルに封じ込めたガラスカプセル蛍光体を開発したことを発表した。
バイオ分野では、細胞や生体関連物質に結合させて、体内や体外でその形態、量、分布、動きを調べるために、蛍光試薬を用いており、従来は有機蛍光試薬が用いられてきた。直径が2~10nm程度の量子ドットは、吸収と発光の波長域が離れているので発光検出が容易であるほか、粒径を変えて、発光波長を調整することができ、高効率で発光し、耐光性が格段に高いため、高性能蛍光試薬として期待されてきた。
しかし、量子ドットは比表面積が大きいため凝集・沈殿しやすく、これを防ぐため、透明な材料で被覆して安定化し、溶媒への分散性を向上させる技術が開発されてきた。これまでに、ポリマーで被覆した量子ドットが市販されているが、発光輝度を高めることは難しく、またバイオ用途では、高濃度の塩などを含む溶液中に希釈分散し、励起光として強い紫外線を照射するが、このような条件では、成分の溶出や紫外線による劣化のため発光輝度が低下したり、溶出したカドミウムなどの有毒成分により細胞死が起きたりするといった問題があった。
従来より、ポリマーよりも丈夫なガラス中に量子ドットを高濃度に分散させて、高輝度発光と高耐久性(化学的耐久性および耐光性)を両立させる研究が進められてきたが、量子ドット分散濃度が低いので高輝度化は難しいなどの課題があった。
蛍光試薬に求められる要件として、発光が高輝度であること、バイオ用の緩衝液などに希釈分散した場合に劣化や成分の溶出を起こしにくく、強い紫外線(励起光)を照射した際にも光劣化しにくいこと、細胞へ導入しやすいサイズ(100nm以下)であることなどが挙げられるが、この高輝度を確保するには、カプセルに10個以上の量子ドットを入れる必要があるため、カプセルの粒径は約20nm以上となってしまう。
研究チームは、目的とする粒径20~100nmのガラスカプセルを得るには、ゾル-ゲル法の1つであるストーバー法が適していることを発見、量子ドットの発光効率を高く保持したままガラスカプセルに閉じ込め、耐久性を向上させるために、まず、量子ドットの表面を適切に被覆保護し、その後、表面を被覆した量子ドットの集合体を形成、その上にシリカを堆積させてガラスカプセル蛍光体を作製するという3段階作製法を開発した。
3段階作成法の詳細は、まず、ステップ1としてCdSe/ZnS量子ドットを含む有機溶媒にケイ素アルコキシド(1)を添加。ケイ素アルコキシド(1)を部分的に加水分解させ、量子ドットの表面を加水分解物で被覆する(有機溶液A)。一般に量子ドットの発光効率は表面の状態に大きく影響されるが、この被覆によりCdSe/ZnS量子ドットの発光効率の低下を抑えることができるようになる。
次のステップ2では、部分的に加水分解したケイ素アルコキシド(2)を含む水溶液を調製。これをステップ1で調製した有機溶液Aと混合し、アルコキシド(1)で覆われた量子ドットの表面にアルコキシド(2)の層を形成する。量子ドット表面のケイ素アルコキシドは水に触れて加水分解が進み、親水性となって水相に移動し、同時に集合体を作る。適切な種類や濃度のケイ素アルコキシドを選択して、アルコキシド(2)の加水分解速度がケイ素アルコキシド(1)よりも遅くなるようにすることで、量子ドットが凝集して大きな塊となることを防ぐことができ、結果として、量子ドット間の不完全な化学結合の生成などによる発光効率低下が避けられるようになる。
そしてステップ3として、量子ドットの集合体にさらにシリカ(ガラス)層を堆積させて量子ドット分散ガラスカプセル蛍光体を作製する。これは、ストーバー法により、アルカリ性の溶媒中でケイ素アルコキシド(3)を加水分解させ、量子ドット集合体を核として堆積させることで行う。このステップでは緻密なシリカ層が堆積されて量子ドット集合体を被覆するので、作製したガラスカプセル蛍光体は高い耐久性を備えていることとなる。
同3段階作製法により、CdSe/ZnSコアシェル型量子ドットの密な集合体を核とし、その上に発達した網目構造をもつシリカが堆積した粒径20~100nmのCdSe/ZnS量子ドットを10個以上含んだガラスカプセル蛍光体を得ることが可能となった。ステップ1、2で用いるケイ素アルコキシド(1)、(2)の濃度などを制御することで、例えば粒径40nmのカプセルと粒径95nmのカプセルを作り分けることもできる。
量子ドットの発光効率は、カプセルに分散させた後も、もとの量子ドットと同程度(20~35%)で、透過電子顕微鏡観察およびICP-AES分析により見積もったところ、例えば粒径47nmのガラスカプセルは25個程度のCdSe/ZnS量子ドットを含むことが判明した。ガラスカプセル蛍光体の発光輝度は量子ドットの発光効率と分散濃度の積に比例するが、今回作製したガラスカプセル蛍光体は発光効率の高い量子ドットを高濃度で含んでいるおり、ガラスカプセルは高輝度の蛍光体であることが判明した。
こうして作製されたガラスカプセル蛍光体はバイオ用の緩衝液中で10nM(nmol/L)程度(量子ドットの濃度)まで薄めても成分の溶出が少なく劣化しにくい。また、高濃度の塩を含むHEPES緩衝液中でのガラスカプセルからのカドミウムの溶出量は、市販のポリマーコートCdSe/ZnS量子ドットに比べて10分の1以下と少なく、高耐久性であることが確認された。加えて紫外線照射に対する耐光性も、市販のポリマーコートCdSe/ZnS量子ドットに比べて100倍程度高かったという。
また、同ガラスカプセル蛍光体は表面を化学修飾してカルボキシル基などを導入することも可能で、これを応用するとガラスカプセル蛍光体表面に抗体を付けることができるため、生体内に存在する特定の分子を観察できる蛍光プローブにもなるという。
量子ドット1個1個からの発光は点滅することが知られており、蛍光試薬として用いる場合、各輝点が点滅すると、蛍光試薬で標識した物質の移動と混同する恐れがあるので、点滅が少ないことが望まれるた、CdSe/ZnS量子ドット1個からの発光と、ガラスカプセル(平均15個のCdSe/ZnS量子ドットを含む)からの発光の時間変化を、蛍光顕微鏡を用いて測定比較した結果、量子ドット1個では点滅が明確なのに対して、ガラスカプセルでは、多数の量子ドットが含まれるため、それぞれの量子ドットからの発光が平均化されて点滅が観測されず、発光強度が安定化したことが確認された。また、ガラスカプセル1個の発光強度は、量子ドット分散数から予想されるように、量子ドット1個の発光強度の約15倍であり、発光強度の安定性の面からも、ガラスカプセル蛍光体が蛍光試薬として有利であることが確認できたという。
なお、研究チームでは、今後、細胞や生体関連物質を対象とする基礎研究用蛍光試薬から、感染症の迅速診断など臨床応用まで視野に入れたバイオ分野での広い応用を目指して量産性の検討を行い、ベンチャー化に向けた準備を進めつつ、関連メーカーとの連携を図る計画であるとするほか、また、高輝度・高耐久性という特長を活かして、電子材料用の蛍光体としての用途も開拓していくとしている。