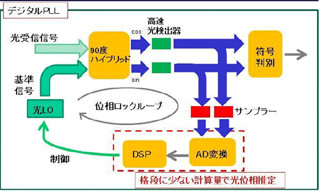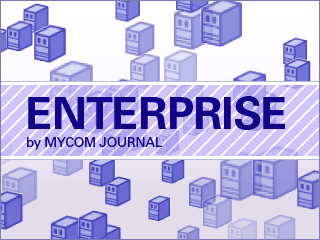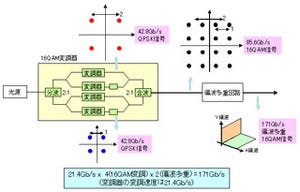九州大学は、情報通信研究機構(NICT)の委託を受け、光ラムメモリ素子の開発に成功したことを明らかにした。
インターネットの発達により、国内の情報通信量は年率約40%の割合で増え続けており、それらの通信経路の切り替えを行うルータに起因する消費電力は2015年ころには国内総発電量の9%を占めるとの予測がなされている。こうした機器の消費電力低減に向け、光信号を電気信号に変換することなく、光のまま処理する全光ルータの実用化が実現が期待されているが、そのためには光ランダムアクセスメモリ用の光ラムメモリ素子が必要で、その候補として双安定半導体レーザなどの双安定デバイスが提案されてきた。
しかし、双安定半導体レーザを光ラムメモリ素子として機能させるためには、一定動作範囲内の設定電流駆動が必要となるが、その動作電流範囲は設定値の数%程度と狭く、個々の素子性能などのバラつきから集積化時に全素子を同一電流で駆動できず、また素子ごとで独立した電流設定は事実上困難であり、実用化の妨げとなっていた。
今回、同大では半導体レーザなどの能動光導波路中で生じる多モード光干渉現象に着目、同応用により異なるモードを同一の双安定半導体レーザで発振させることに成功した。これにより、これまでの課題であった、相互利得抑制効果を大きく得ることができる、多モード光干渉導波型光ラムメモリ素子を実現した。今回の成果で、従来の10倍以上の動作電流範囲(対設定電流比100%以上)を実現したことによって、素子の性能バラつきや経年劣化が生じても、全集積デバイスを同一電流駆動することが可能となり、光ラムメモリ素子の実用化へ前進する成果が得られたこととなった。
同大とNICTでは、今後、今回の成果による動作電流範囲を維持しつつ、さらに小型化・低消費電力化を進めることで素子の高集積化を進め、数年後の実用化を目指すとしている。