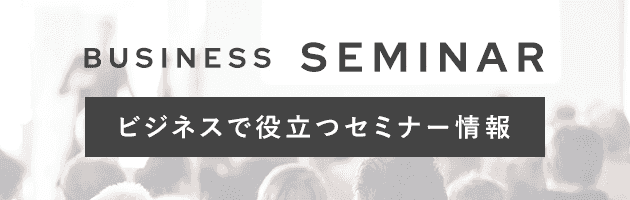5G向けに割り当てられたものの、利活用が全く進まないミリ波。その状況を打開するためか総務省の有識者会議「競争ルールの検証に関するWG(ワーキンググループ)」で、ミリ波対応端末への端末購入補助に関する議論が進められているようですが、前向きな姿勢を見せる政府に対し、端末購入補助をする側の携帯電話会社は消極的な様子です。一体なぜでしょうか。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。
円安と端末値引き規制がミリ波の議論に影響か
主として30GHz以上とされる「ミリ波」は、国内でも5G向けとして28GHz帯が携帯4社に割り当てられているのですが、周波数が非常に高いので障害物にとても弱いので面でのエリアカバーに向かないなど携帯電話向けとしては非常に扱いにくく、ほとんど活用が進んでいません。
それは海外でも同様のようで、韓国では一度携帯3社に割り当てられたミリ波の免許が、3社ともに整備計画を達成できなかったことからすべて取り消され、新たに別の会社へと割り当てられるに至っています。
最初の5G向け周波数帯としてミリ波だけが割り与えられていた米国でも、その後は6GHz以下の「サブ6」など、低い周波数帯が割り当てられるとともに、注力度合いがそちらへシフトしているようで、世界的にも携帯各社が扱いにくいミリ波を避ける傾向が強まっている様子がうかがえます。
しかし、そのことを強く問題視しているのが、電波を割り当てる側の政府です。日本政府も折角割り当てられたミリ波をいかに活用するか、総務省で議論が進められているのですが、最近そのミリ波を巡って動きを見せているのが、前述の競争ルールの検証に関するWGです。
このWGは元々、携帯電話市場の公正競争と競争促進に実現に向けた評価・検証をするために設けられたもの。