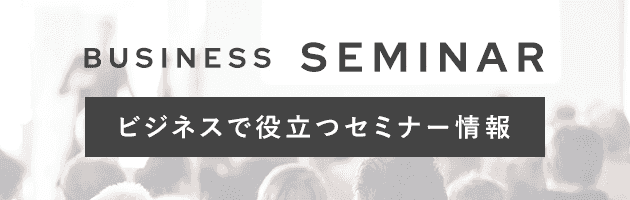琉球大学は5月14日、ミドリイシ属サンゴの精子に存在するタンパク質の中から、酵素「プロテイン キナーゼ A」(PKA)によりリン酸化される基質の候補を選別し、それらのタンパク質をコードする遺伝子の動物間における共通性と遺伝子進化を検証した結果、サンゴの精子に存在する基質の多くが動物に共通しており、リン酸化を受けるアミノ酸配列は保持されつつ機能変化を遂げていたことが推定できたと発表した。
同成果は、琉球大 熱帯生物圏研究センターの守田昌哉准教授、同・花原望氏、同・寺本(守田)真梨子氏、同・アリヨ イマニュエ ルタリガン大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、分子進化に関する全般を扱う学術誌「Journal of Molecular Evolution」に掲載された。
精子のべん毛運動は、べん毛内に存在する「べん毛軸糸」にあるモータータンパク質「ダイニン」と、軸系の骨組みとなる「微小管」の滑り運動により実現されている。精子は、卵由来精子活性化物質などによって活性化され、べん毛運動を行うという仕組みだ。
活性化の引き金となる刺激を受けると、ダイニンの滑り運動が起きるような情報が伝達される。PKAの場合は、まず精子内でPKAの活性化物質(cAMP)が、酵素「アデニル酸シクラーゼ」(sAC)により、生物のエネルギーの通貨こと「アデノシン三リン酸」(ATP)を材料に作られる。cAMPの濃度が上昇するとPKAは活性化し、さまざまな基質をリン酸化し、べん毛運動の活性化につながるのである。
多くの生物で、sAC-PKA経路が精子べん毛運動の活性化に関係することが報告されており、その共通性が示されている。しかし、情報伝達の上流にあたる同経路の活性化から始まってべん毛運動が活性化する下流の情報伝達系の多くが不明のままだったという。そこで研究チームは今回、その課題の解決に取り組んだとする。
同研究ではまず、PKAのべん毛運動への関与を薬理学的かつ間接的に調べるため、精子の細胞膜の過分極を引き起こしてsACを活性化する薬剤をサンゴの精子に加え、実際に活性化するのかどうかが検討された。その結果、精子が活性化し、sACの関与が推定された。また、膜透過型のcAMPアナログが与えられた場合も、同様に活性化したとのこと。これにより、PKAがミドリイシ属サンゴの精子のべん毛運動の活性化に関与することが推定された。
-
(a)サンゴの精子にsAC活性化薬剤valinomycinを加え、実際に活性化が起きるかが検討された。(b)膜透過型のcAMPアナログの8-bromo cAMPを与えても、同様に精子の活性化が確認された(出所:琉球大プレスリリースPDF)
次に、活性化PKAによりリン酸化される基質が探索された。精子の構成タンパク質の遺伝情報から推定される分子量から網羅的な探索が行われ、約2500個のタンパク質が同定された。それらの遺伝子から推定されるアミノ酸配列から、PKAの基質となるモチーフ(PKAの標的となる特定のアミノ酸配列)を検索した結果、ダイニンなどを含め、その配列を持つタンパク質の遺伝子が約140個選別された。
その約140個の遺伝子について、他の分類群の動物での探索を行ったところ、一部の遺伝子は刺胞動物やサンゴ固有だったが、多くの遺伝子が動物に共通していることがわかったという。その一方で、他の生物の精子で報告されているPKAの基質とは一致しないものも多かったとのこと。これは、べん毛の基本構造は維持されつつも、構成要素であるタンパク質には違いがある可能性があるという。つまり、多くのPKAの基質となる遺伝子は動物で共通だが、サンゴにしかない遺伝子があったように、他の動物にしかないタンパク質の遺伝子もある可能性があるということである。
続いて、PKAの基質となるタンパク質がどのような進化を経たのか、アミノ酸置換を指標に検証が行われた。すると、約60個のタンパク質の遺伝子が機能変異をしつつ、PKAの基質として機能していることが突き止められた。さらに、ミドリイシ属サンゴ種の公開遺伝子情報を用いて、アミノ酸の同義置換と非同義置換の比較が行われ、その置換率が特定のアミノ酸をコードする「コドン」(アミノ酸は3個の隣り合った塩基配列で記されており、その3塩基の連なりのこと)で、非同義置換が正の選択を受けたのかどうかが検証された。その結果、単離された遺伝子の60個ほどが、正の選択を受けていたという。
加えて、PKAにリン酸化される「スレオニン残基」では、モチーフ配列の保存性と置換率に違いは見られなかったが、「セリン残基」のモチーフ配列の保存率は、正の選択を受けたタンパク質の方が高いこともわかった。また、他の組織で利用されているPKAの基質と一致するものは、強い純化選択を受けていたという。正の選択は、特定の条件に適応進化する際に起こることが先行研究で示されており、これはサンゴの精子べん毛運動を活性化する過程が、放卵放精型や多種同調産卵など、ミドリイシ属サンゴの特徴的な繁殖生態に適応することにつながった可能性があるとする。
-
(a・b)PKAにリン酸化されるスレオニン残基では、モチーフ配列の保存性と置換率に違いは見られなかった。(c・d)セリン残基のモチーフ配列の保存率は、正の選択を受けたタンパク質の方が高いことがわかった(出所:琉球大プレスリリースPDF)
研究チームは今回の研究成果により、ミドリイシ属サンゴの繁殖、サンゴ礁の維持の理解につながることが期待されるとしている。