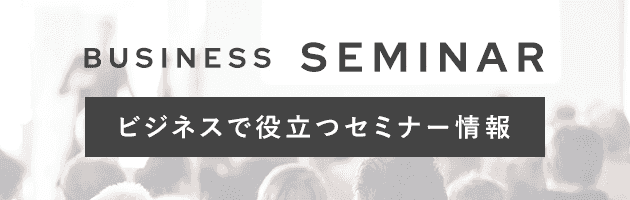東芝は4月22日、量子インスパイアード計算機「シミュレーテッド分岐マシン(SBM)」を用いた5G基地局におけるリソース制御技術を開発したと発表した。
5G通信の最適な時間と周波数の割り当てを行うリソース制御アルゴリズムを開発することで、5Gの規格で期待される最小伝送遅延である1.0ミリ秒を達成するために必要な0.5ミリ秒以下で、20端末のリソース割り当てを行うことに成功したという。
東芝 研究開発センター情報通信プラットフォーム研究所ワイヤレスシステムラボラトリースペシャリストの小畑晴香氏は、「5Gは、高速、低遅延、高信頼な伝送を実現するため、柔軟なリソース割り当てが可能となっている。だが、新しい技術の発展とともにパラメータは増大しており、超低遅延の実現には、超高速のシステム応答時間が必要になる。いわば、5Gならではの能力を最大限に活かすには、超高速に膨大なパラメータを最適化する必要がある」とし、「高速に最適化問題を解くことが可能なSBMを、5Gのリソース制御に応用することで、各端末の通信品質を考慮した割り当てを、0.5ミリ秒以下で行えることを確認できた。複数端末の超低遅延通信が可能となり、工場や倉庫といった産業や物流の現場の産業機器のリモート制御や、自動化の加速に貢献できる。工場のDX化には重要な技術となる。SBMにより、超低遅延に制御が可能になることで、社会のDX化を促進することができる」と、今回の技術の狙いを説明した。
この技術を用いることで、複数端末が超低遅延で通信できるようになることから、工場での複数のロボットの自動制御を実現。自動化したロボットを、数ミリ秒の高速で動作させることができ、労働力不足の解消や生産性向上につなげることができると期待している。
東芝では、約2年前から研究開発を開始。基地局における5Gの無線リソース制御に着目し、これを最適化する技術の実現を目指したという。
5Gの無線リソース制御とは、有限な時間と周波数の組み合わせである「無線リソース」に対して、5Gの規格上の各種制約のなかで、どの端末データを、どの無線リソースに割り当てるか、という組み合わせ最適化問題と捉えることができる。
だが、端末ごとに品質の良い周波数は異なっており、各端末に対して、なるべく品質が良い周波数を使用できるように割り当てたいという要求がある。また、仮に20端末の割り当てを行う際にも、割り当て順序だけでも10の18乗の組み合わせが存在するという課題があった。さらに、最小の伝送遅延を達成するには、0.5ミリ秒以下での最適化が必要になっていた。
こうした課題を解決するために、東芝では、同社が持つSBMを活用することにしたという。
「最初は、すべてをSBMによって解こうとしたが、時間がかかってしまうことがわかった。そこで、一度緩和した条件で最適化問題を解き、その解と統計情報を用いて、さらに最適化を行う2段階最適化手法を採用した。これによって、大きく性能があがり、高速化を実現できた。目標としていた0.5ミリ秒以下でのリソース割り当ての最適化を実現できた」という。
SBMは、膨大な数の選択肢から最適なものを見つけ出す「大規模組み合わせ最適化問題」を解くために用いられる技術で、製造や材料開発、交通、物流、金融、創薬、遺伝子工学、AIなどの様々な分野での課題解決に貢献することが期待されている。
2016年に東芝が提案した量子分岐マシンが原点となっており、2019年には東芝がシミュレーテッド分岐アルゴリズムを提案。FPGAを実装したSBMや、CPUやGPUを搭載したSBM、クラウドサービスとして提供する環境も用意している。利用シーンにあわせた実装形態を選択することができ、複雑化する社会課題の解決にも活用できるとしている。
「今回のリソース制御技術の実現に向けて、SBMの中身をかなりモディファイしている。東芝で自社開発していることから、様々な問題に対して的確な方法で求解できるようにアルゴリズムを変更した。ここには多くのノウハウが含まれている。他社が簡単に追随できるものではない」と自信をみせた。
実証では、SBMによるシミュレータによって、20端末をランダムに配置し、そのチャネルを計算。結果をSBMに渡して解くことを1000回繰り返した。1000個のサンプル問題に対して、SBMを応用したリソース制御アルゴリズムの検証では、従来のGreedyアルゴリズムを10万回繰り返えして探索した割り当てよりも、質の良い割り当てが可能になることが確認できたという。従来手法では局所的な最適を行うのに対して、SBMでは全体最適を行うことができ、Greedyアルゴリズムでは辿り着けないような最適割り当てが、SBMでは可能になることがわかったという。また、計算結果にかかる時間から、すべてのサンプル問題を、実時間処理として最大0.3ミリ秒で求解できることが確認でき、最小伝送遅延を達成するのに必要な0.5ms以下で超高速に組み合わせ最適化問題を解くことが可能になると判断した。
「SBMを用いることで、超高速に、膨大な数のパラメータを最適化できるため、リソース割り当てに限らず、無線通信分野のさまざまなアプリケーションへの適用が期待できる。SBMを広く活用することで、超高速、超低遅延、超高信頼の5Gの実現を目指すことができる」と述べた。
同技術は、2024年4月21日~24日に、アラブ首長国連邦ドバイで開催される国際会議「IEEE WCNC 2024」で発表する。今後は、実装に向けて、5G基地局に関連するパートナー企業に対する提案を行っていくほか、基地局だけに留まらず、5G無線領域に幅広く展開していく考えも示した。
-
各端末の通信品質を考慮したリソース割り当てを0.5ミリ秒以下で実現できるようになれば、複数端末との低遅延通信が可能となるため、複数のロボットなどをリアルタイムで制御することが可能となり、工場の省人化・無人化などの促進が可能となる (出所:東芝)
「今後の実用化に向けては、実際のシステムに実装して検証する必要がある。通信機器ベンダーやキャリアと連携しながら検証していきたい。また、無線領域以外にもSBMの応用先を広げて、社会に役立てたいと考えている」(東芝 研究開発センター情報通信プラットフォーム研究所ワイヤレスシステムラボラトリーエキスパートの谷口健太郎氏)としている。