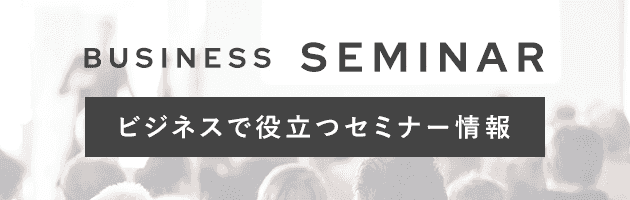本連載の第232回では「会議が白熱しても成果を出せないのはなぜか」という話をお伝えしました。今回は、前回の議論を元に対応策としての議論の可視化についてお話します。
参加者が活発に意見を交わして会議が大いに盛り上がっても、必要な成果を上げられないことはありませんか。前回のコラムでは、その理由を「情報量」と「論理構造」という2つをキーワードに紐解きました。
簡単におさらいすると、特に白熱した会議では多くの発言が飛び交うことで、情報量が膨大になってしまいます。読者の方の中には「自分はすべて記憶しているから大丈夫」という方もいらっしゃるかもしれませんが、他の参加者全員についても当てはまると自信を持って言える方は少ないのではないでしょうか。つまり、会議が白熱すればするほど、それと比例して情報量が増大し、参加者全員が共通認識として得られる情報の比率が下がってしまうことが想定されます。
また、「論理構造」については会議が白熱して様々な議論が出てくると、議論の論理構造の理解が追い付かなくなる、または人によって異なる理解をしてしまうということが起きます。同じ話を聞いたとしても、参加者の立場や経験、専門知識などによって異なる理解をしてしまうのは不自然なことではないでしょう。
そのため、会議が白熱した割に意思決定に至らなかったり、後から認識の相違が発覚して問題になってしまったりということが起きるのです。
ではどうしたらよいのでしょうか。リアルタイムで議論を可視化・共有すればよいのです。お勧めなのはプロジェクターやオンライン会議ツールの画面共有機能を使って、参加者全員で同じ資料を見ながら、議論を可視化していくことです。それによって先ほど挙げた「情報量」と「論理構造」の2つの問題をクリアできます。それでは、1つずつ見ていきましょう。
1. 「情報量」は「要約」で絞る
会議参加者の発言内容を一言一句、漏らさずに記述するのはそもそも高度なタイピングスキルが必要な上、記述する情報量が膨大になってしまいます。議事録として後から見直すのであればそれでも差し支えないかもしれませんが、リアルタイムに参加者間で共通認識を得るのにはあまり向いていません。
そのため、参加者の発言内容について「一言で表現するとどういうことなのか」という要約を記述するのがよいでしょう。PowerPointやGoogle Slideなどのプレゼンテーションツールに四角形のオブジェクトを置き、そこに書き込んでいくのがおすすめです。その際、各々のオブジェクトのサイズを小さめにすると、自ずと書き込める量が限られて要約しやすくなります。1つのオブジェクト内に表現するのにはどうしても文字数が足りないという場合には、オブジェクトを追加してそこに追記しましょう。
2. 「論理構造」は「図解」で示す
各々のオブジェクトは小さい箱なので情報量が限られます。そのため、議論を構成する論理的なつながりが長い場合にはオブジェクト内で表現することが困難です。そこで、各議論の要約を書き込んだオブジェクト同士を矢印でつなぎ、どのように論理がつながっているのかを表現しましょう。
つまり、議論が「AならばB、BならばC」のような論理構造であれば、A、B、Cそれぞれのオブジェクトを「A→B→C」というように表現します。これを会議の間、記述し続けることで議論がどのような論理構造になっているのか、その共通認識を参加者全員がリアルタイムで持つことができます。
なお、そのメリットは「自分の発言の意図はちょっと違う」とか「〇〇さんの話していることは論理が飛躍しているのではないか」という参加者からの指摘が入ることによって、議論の真意についての理解の誤りをその場で正したり、論理的な抜け漏れや間違いに気が付くことにつながります。さらに、論理構造が図解されることで「さらにこういうことも考えられるのではないか」といったアイディアを参加者が思いつくきっかけにもなることもあります。
ここまでで、会議での議論をリアルタイムに可視化し、共有することのメリットをお伝えしました。慣れないうちは操作に手間取ってうまくいかないこともあるかもしれませんが、何度もやっているうちにスムーズにできるようになるはずです。ぜひ、トライしてみてください。