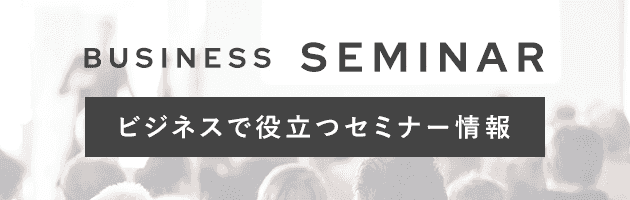パナソニックが、「新・商売の基準」の取り組みをさらに進化させる。2023年4月に発表した「新・商売の基準」は、「くらしを守る。地球・社会を想う」を基本方針に掲げ、商品を販売したあとも、顧客とIoTでつながり続け、長く安心して利用できる環境を提案。商品を使い続けながら、満足度を向上することを目指してきた。
それから1年を経過して、今回、新たに発表した取り組みでは、メーカーによる検査済み再生品「Panasonic Factory Refresh」の販売を開始。サーキュラーエコノミーの実現に貢献するほか、IoT接続を通じて収集したデータを活用した商品やサービスのさらなる充実を図る。
パナソニック 執行役員 コンシューマーマーケティングジャパン本部長の宮地晋治氏は、「IoTを活用し、お客様とつながり、アフターサービスの充実を図ることで、購入した商品を安心して使い続けてもらう仕組みを強化する。『くらしを守る、地球・社会を想う』という『新・商売の基準』を引き続き推進し、ウェルビーイングとサステナビリティの両立を図る。そして、パナソニックファンを増やしていきたい」と語る。
同氏は、パナソニックくらしアプライアンス社副社長およびパナソニックマーケティングジャパン 代表取締役社長も兼務する。
前編では、宮地氏に、「新・商売の基準」の進化について聞いた。
―― パナソニックは、2023年4月に「新・商売の基準」を打ち出しました。1年を経過して、その手応えはどうですか。
宮地:市況そのものが厳しい1年でしたから、販売面では苦戦した部分もありました。しかし、指定価格制度による新販売スキームや、SCM改革、CXの強化といった仕組みづくりについては、うまく進めることができたと考えています。また、新販売スキームの実現のベースとなる「強い商品」づくりという点でも手応えを感じます。たとえば、一人暮らし世帯を対象にしたパーソナル食洗機「SOLOTA」による新たな需要層の開拓や、持ち運びに適したパームインシェーバーでは累計販売台数が10万台に到達するといった実績が出ています。これらの商品は、新販売スキームの導入によって、技術者が持つ力を、感動を与える商品の開発に集中させたことによって生まれたものです。従来の仕組みでは、新製品の発売から一定期間を経過すると、2割引きから4割引きの価格で販売され、この販売価格を見直すために、あまり機能が進化していないにも関わらず、マイナーチェンジと称して、毎年、新製品を投入していたわけです。しかし、新販売スキームにより、メーカーが指定した価格での販売が行われ、毎年投入していたマイナーチェンジ商品を開発することがなくなり、ひとつの商品を2年、3年、販売できるようになりました。技術者はよりお客様に愛される商品づくりに向けて、深く考える時間を創出し、パナソニックならではの感動を与える商品を作ることができ、それをお客様に購入してもらえる仕組みが回り始めました。
―― 新販売スキームでは、うまくいっている商品と、苦戦している商品があります。この原因については分析が進んでいますか。
宮地:負けている商品は、ひとことでいえば「商品力がない」ということになります。お客様から評価される商品にはなっていないということなんです。それは、機能だけでなく、価格設定やサービスを含めて、評価されていないということだと思っています。いま、成果があがっているのは、食洗機やシェーバー、ドライヤーなど、パナソニックが得意とする分野です。国内で圧倒的支持をいただけるブランドになれば、新販売スキームによる好循環を生み出すことができるという手応えはあります。
―― パナソニックでは、2023年4月から、IoT延長保証サービスを開始しています。2024年度末には1000万人の登録を目標にしていましたが、すでに、2024年3月末時点で約900万人が登録しています。利用者が順調に増えていますね。
宮地:IoT延長保証サービスは、7カテゴリー、約500品番のIoT対応商品の購入者を対象にしたもので、専用アプリで登録すると、保証期間を2年間無料で延長ができます。さらに、ネット接続により、困りごとや使いこなしに関するお役立ち情報や便利機能の紹介、電気代の目安の可視化、節電運転などによる省エネサポートなど、購入後も安心して家電を使用できる環境を実現しています。
具体的には、ドラム式洗濯乾燥機の場合、排水時間のデータなどを活用して、排水トラブルが起きる前に、排水フィルターのお手入れを提案するほか、冷蔵庫では稼働時間のデータにより、定期診断レポートを毎月配信して、エコな使い方や便利な機能などを紹介しています。さらに、稼働データをもとに、冷蔵庫内の温度上昇を検知した場合には、対処方法をわかりやすく伝えています。2024年5月からは、エアコンのメンテナンスが必要なユーザーに対して、アプリにダイレクトに通知するサービスを試験的に開始します。このように、購入していただいた商品を、安心してお使いいただくために、IoT接続によって蓄積された使用データをもとにして日ごろのお手入れを提案するといった活動も行っています。
ただ、大量のデータが集まっているものの、私たちがそれを使いこなせているのかというと、まだまだ課題があります。4月になって、朝の時間帯に電子レンジの利用が増加したというデータを見て、お弁当を作っている人たちが増加したという推測が成り立ちます。しかし、そこに対して私たちはどんな提案ができるのか――。この提案力にはまだまだ課題があると思っています。いただいたデータをもとに、お客様に貢献できる形で活用し、お返しができているのか、という点では、やらなくてはならないことはまだ多いといえます。また、もっと積極的にトライを繰り返しながら、よりよい提案につなげていく努力もしなくてはなりません。社員のアイデア出しも重要ですし、ここにAIを活用していくという手法もあるでしょう。様々な可能性をもとに、なにができるのかということを考えていく必要があります。
―― IoT延長保証サービスの利用者数の目標は、上方修正してもいいように見えますが。
宮地:つながるお客様の規模は大切ですが、いま、私たちに求められているのは、なにができるかということです。お客様からいただいたデータを活用して、価値をお客様に還元する循環を作っていくことが大切だと考えています。そして、お客様の満足度を高めることで、パナソニックファンを増やしたいと思っています。
―― 今後、データを活用したサービスでは、どんなことに取り組みますか。また、「新・商売の基準」において目指している、長期間に渡って、安心して使ってもらうための仕掛けではどんなことに取り組んでいますか。
宮地:これまでの家電は、購入した後は、経年とともに満足度が減少していました。しかし、お客様とIoTでつながり続けることで、パナソニックならではの購入後の体験価値の提供や、満足度向上を実現することができます。パナソニックは、幅広いカテゴリーの家電商品を提供しています。その強みを生かして、毎日蓄積されるくらしのデータをもとに、購入後の新たな価値を提供していくことに力を注ぎます。たとえば、地域ごとに家電の使用データを収集し、分析することで、それぞれの地域でのエアコンの稼働時期などを把握し、それにあわせて、エアコンクリーニングの提案を、地域の販売店と連携しながら行うといったことも想定しています。
2023年12月からは、公式ショッピングサイトである「Panasonic Store Plus」において、冷蔵庫やドラム式洗濯乾燥機といった大型家電の取り扱いを開始しましたが、これらの配送設置時には、IoT接続を行うサービスを無料で提供しています。まだ地域を限定したサービスですが、今後は、対象エリアを順次拡大していくことになります。
「新・商売の基準」では、長く安心して利用してもらえる提案が必要です。ここでは、これまでのエアコンクリーニングサービスに加えて、新たにドラム式洗濯乾燥機のヒートポンプユニットのクリーニングサービスを、2024年5月から関西地区で開始します。2021年度から発売したNA-LX・Aシリーズを対象に、熱交換器や乾燥風路をクリーニングするもので、サービス料金は1万6500円とし、クリーニング後2年間のアフターサービスも提供します。ヒートポンプは、パソナニックが先行して取り組んできたものですが、これを安心して、より良いコンディションで使い続けてもらうためのお手入れを、データを活用しながら啓発するとともに、アフターサービスの充実を図ります。パナソニックのドラム式洗濯乾燥機は、ヒートポンプユニットが本体上部にあるため、大掛かりな分解作業や製品の移動が不要でクリーニングすることができます。サービス開始にあわせて、専用治具を独自開発し、認定技術員が丁寧なクリーニングを行います。パナソニックには、全国約100拠点があり、年間約3300万件の問い合わせに対応し、年間約180万件の修理を行っています。こうしたアフターサービスの接点があるからこそ、パナソニックの家電を安心して使い続けることができ、購入後の満足度を高めることができると考えています。
―― 「新・商売の基準」における今後の施策について教えてください。
宮地:2024年度は、4つの取り組みを推進します。ひとつめは、IoT接続を通じて収集したデータを活用した商品やサービスの充実です。たとえば、エアコンのエオリアでは「新・AI快適おまかせ」機能を搭載し、リモコンのボタンひとつでより、快適に運転できるようにしましたが、ここでは、3年間に渡る3万件以上の体感アンケートや利用者操作履歴のデータを活用してアルゴリズム化。温度を自動的に設定する新機能として提供しています。2つめは、電力会社や国、自治体などとの連携により、CO2排出量削減への貢献や、熱中症対策などの地域と密着した取り組みをスタートさせます。すでに、栃木県鹿沼市とは「省エネエアコン定額利用制度」を実施しており、市民の熱中症予防や、CO2排出量の削減といった効果を生んでいます。3つめが、他社との協業です。一例としては、ヤマト運輸のクロネコメンバーズを対象に、音声プッシュ通知サービスを2022年4月から開始しており、家電を通じて、荷物のお届け予定通知やご不在通知を音声でお知らせすることができています。このように、家電とくらし情報の連携によって、くらしの質の向上を図ることを目指します。そして4つめが、パナソニックグループが提供している次世代ファミリーコンシェルジュサービスのYohanaとの連携です。忙しい家族のくらしをサポートし、パナソニックならではの暮らしのウェルビーイングを追求することになります。
―― パナソニックマーケティングジャパンでは、2023年4月から、専門店や量販店ごとの商流軸の体制を刷新し、全国7社のエリア会社体制へと移行しました。それぞれに社長を配置して地域への密着度を高めていますが、どんな成果があがっていますか。
宮地:これまでパナソニックショップでは、午後6時までに注文を受付けつければ、翌日に届けるという仕組みを敷いていました。しかし、地域によっては、人材不足が理由となって、そのスキームが成り立たないといったケースが出てきています。また、地域ごとの人口の違い、年齢差なども顕著になり、全国一律での施策が、エリアによって合わなくなってきたのも事実です。それぞれの地域にあった施策が必要であり、地域の販売店やお客様への価値提供の方法もエリア特性にあわせることが大切だと判断しました。それが、エリア会社体制へと移行した基本的な考え方であり、それぞれの地域のお客様にお役立ちにつながる取り組みになると考えています。
これは、施策の柔軟性にもつながります。新たな商材を試験的に扱ってみたり、新たな施策に取り組んでみたりといった場合も、全国一律での施策を待つのではなく、これまでにはなかった「エリア単位」という手法で対応できます。また、収集したデータをもとに、エリア特性を捉えた訴求を行ったり、そのエリアで響く店頭POPを作ったりといったことも可能になります。地域によって「刺さり方」が違いますから、全国一律で、ひとつのツールで訴求するのではなく、それぞれ地域にあった提案をすることが、販売店の支援につながり、最終的にはパナソニックのファンづくりにつながると思っています。
いまは、家電全体の総出荷が減少するフェーズにあり、商品の機能訴求だけでなく、地域の販売店をどうサポートするか、お客様にパナソニックファンになってもらうために、販売店と一緒になってなにをするかが重要な要素です。販売店の従業員を増やすことが難しくなるなかで、パナソニックとして、効果的な販売事例を紹介し、エリアに最適なツールを提供するなど、いまの時代にあったサポートはなにかといったことを追求しているところです。対面販売の強化に加え、デジタルの良さを活用することも大切です。2024年度は、それらの取り組みを形にして、次期中期計画のなかで販売店の売上げ向上につなげたいと考えています。
(後編へ続く)