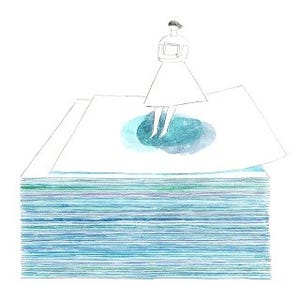チェストの片側を持ち上げ、半ば引きずるようにして動かしているとき、ふと、足の裏に鋭いものがチクリと刺さる感覚があった。「痛っ」と思わず声を上げながら、陸子は足の下に何があるのかのぞきこんだ。
それは、白く、小さな破片だった。陸子がこの部屋に持ち込んだものではない。それは、直己の足の親指の爪のかけらだった。
直己の足の爪は、厚かった。直己が陸子の家に来るのが日常の一部になった頃、直己は「爪切り貸して」と言い、陸子の小さな爪切りで足の爪を切ろうとしたのだが、うまく切れず、ぎざぎざになってしまった。陸子は、好きな男の足の爪をぎざぎざにしたその爪切りがなんだか気に入らなくなり、ドイツ製の切れ味の良い、少し変わった形の爪切りを探して手に入れた。
最初は使い慣れないせいか、難しい顔をして使っていた直己だったが、「これ、よく切れる」とだんだん喜んで使うようになり、自宅の爪切りはまったく使わなくなってしまった。「爪を切るために、うちに来てるんじゃないの?」と、陸子はよくからかったものだった。
切られて落ちた、白く、厚い爪のかけらを陸子はしげしげと眺め「貝殻みたいだね」と言ったことがある。二人で海に行ったとき、陸子は決してきれいではないその砂浜で、欠けた貝殻を拾った。白くて小さな貝殻で、ちょうど直己の親指の爪と同じくらいの大きさだった。
「切りすぎた直己の爪みたいじゃない?」と陸子が言うと、直己はいつものように、腹から響くような声で笑い出し、「じゃあこれは、切りすぎた俺の爪の標本として大事に保存してくれよ」と言い出した。陸子が手頃なガラスのケースを見つけてきて、それらしく飾ってやると、直己はまたそれに大笑いしていた。他人に話しても、何が面白いのかまるで理解されないようなことを笑いあう仲だった。
些細な意地の張り合いで、どちらかが笑い声をあげるのをやめたとき、終わりが始まるのだ。そして、二人の間でだけ通用していた笑いや、二人にしかわからない言葉は、どこにも記録されず、どこにも行かず、ただ消え去ってゆく。
とっくに消え去ったと思っていたその存在が、チェストの下に眠っていて、不意に陸子の足の裏をチクリと刺したのだった。
別れてから、直己のパジャマは簡単に捨てることができた。簡単に、というよりは、そこに彼の身体の大きさや、身体の匂いがしみついているような気がして、つらくて見ていられなかった。不意に視界に入ると、ビクッとした。感情を揺さぶるものが家の中にあるのが怖かったから、無理やり追い出すようにして捨てた。
ひげ剃り、歯ブラシ、靴下。それらのものも捨てた。見たくなかったし、終わったことを自分にわからせなくてはいけないと思った。彼の生活に関わるものがある限り、「また前のように、何事もなかったかのように、この家に来てくれるのではないか」という希望を捨てられなかったから、ものを捨てたのだ。
それは、自分から希望を捨てるようなことだった。捨てたくなんてなかったけれど、その希望にしがみついていたら、もっと大きな希望を失うかもしれない。陸子にとっては、自分を守るための必死の選択だった。それでも、もう自分の道具としてもすっかり手になじんでしまったあの爪切りだけは、捨てることができなかった。欠けた小さな白い貝殻も。
気分転換のために始めた模様替えの手を止め、陸子はチェストの引き出しの奥から、ガラスケースに入れた貝殻を取り出した。貝殻の欠けた部分に、拾った爪のかけらを合わせてみる。全然合わない。合うわけがないのに、合わせてみる。そんなつまらないことでも、直己がいれば、一緒に笑う起爆剤になった。
あんなに大きかった笑い声が、今はどこか遠くから聞こえるさざ波のように遠くにしか思い出せない。笑い声を止めてはいけないのだ。つまらないことで止めたら、うまく流れなくなってしまう。どうしても止まってしまうとき以外は、止めてはいけないのだ。
陸子は貝殻を見つめながら、自分のしてしまった失敗を振り返り、涙を流さずに_過去を振り返ることができるようになった自分に気がついた。時間は進んでいる。確実に。希望を捨てた分だけ、別の希望をつかんでいる。陸子は立ち上がり、力を入れて、チェストを新しい場所に向けて、ぐっと強く動かした。
<著者プロフィール>
雨宮まみ
ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)を昨年上梓。最新刊は『女の子よ銃を取れ』(平凡社)。
イラスト: 安福望