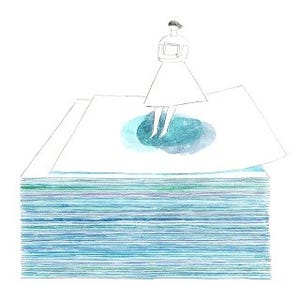美波にとって、男はいつも、「去っていくもの」だった。いつかは必ず、離れていく。別れがある。だから、過ぎ去っていくものなのだといつしか思い込むようになっていた。
「ずっと一緒にいよう」「いつまでもそばにいて欲しい」「愛してる」。それらの、継続的な愛情を誓うような言葉は、美波を喜ばせ、今度こそと思わせ、そのぶん、男が去っていったあとには、あまりにも大きな喪失感を残した。
美波は、そういう言葉がだんだん嫌いになっていった。どうせ守れない、その場だけの言葉なら、言わなければいい。その場では真実だった、と知ってはいても、男に去っていかれたあと、いつも思い出すのは「ずっと一緒にいよう」と言ったのに、ということで、あんなことを言うほど好きだったはずなのに、去っていかれるなんて、ということだった。
男に去っていかれたあと、美波に「愛された自信」なんかは残らず、ただ「自分はまた、何か失敗をしたのだ」「継続的に愛される魅力がないのだ」「一緒にいるのが嫌になるようなことをしてしまったのだ」としか思えなかった。
男たちが去っていく理由は、それぞれ違っていた。新しく好きな相手ができてしまったとか、「君とつきあうのに疲れた」とか、「今は恋愛じゃなく、仕事に集中したい」とか。
どんな言葉でも、美波にとっては同じ言葉だった。どんな言葉も、その意味は「もう、君と一緒にはいたくない」だったからだ。思い出のあるものはすべてその瞬間に、愛された証から、愛されなかった証に姿を変えた。
美波は、男が去るとそれらのものを捨てた。ベッドのシーツも買い換えた。ひどいときは、引っ越しもした。同じ場所にいると、思い出してしまうからだ。どんなに愛されたかを思い出し、それを失ったことを思い出し、夜中のベランダにふらふらと出て行ってしまいそうになるからだ。
もう、愛されることはないんじゃないか、とそのたびに思ったし、また愛されることができた、という喜びのあとに別れが訪れると、前のときよりもさらに深い絶望が待っていた。
死んだりしてはいけない、こんなことで、そんなことをしてはいけない。美波はそう思う一方で、死ぬに値する絶望を抱え込み、このままではいけないと思い、11階の部屋から2階の部屋へと引っ越すことにした。住む場所を変え、街を変え、暮らしを変えるという、目先に集中しなければいけない課題を作ることで、考える時間を減らして作業に没頭していった。
引っ越しのときに、困ったのが、ベランダにあった薔薇の鉢だった。最後に美波を愛した男が、誕生日に送ってきたものだった。美波の誕生日は5月で、薔薇の季節だった。
「ちょうど、車で通りかかった店にこれがあって、いちばん美波に似合うと思ったから」
男はそう行って、いきなり、儚いピンクの花をつけたその苗木の鉢植えを、美波の家のベランダに持ち込んできたのだった。
捨てるとしても、あまりにも大きなものだし、植物とはいえ生きているものを捨てるにはしのびない。植物に疎い美波でも、薔薇の栽培が難しいことぐらいは知っている。どうせ枯れさせてしまうだろうから、それまでは置いておこうかと思い、薔薇の鉢は美波の2階の部屋の、少し広くなったベランダにやってきた。
ひまがあれば、思い出して落ち込んでしまうから、何か集中できることが欲しかった。 美波は薔薇のことを調べ、園芸用の手袋や虫をつけないためのスプレーなどの一式を買い込み、毎朝、どうせ眠れないのだからと早起きしては、薔薇の手入れをした。
道具を揃えると、一つの鉢だけでは物足りなくなり、簡単なバジルやミントなどのハーブ類や、小学生の頃に育てた朝顔を買ってきて育ててみたりした。
意外なことに、どれもうまく育ち、美波は自分で育てたハーブを使って料理をしたり、どうせ料理に使うならと大葉を育ててみようか、なんて思ったりもした。自分で育てたハーブで料理をしているなんて、嘘みたいだなとぼんやり思うこともあった。
よく眠れず、食欲の落ちた美波の身体には、朝の水やりのときに嗅ぐハーブの香りが唯一食欲をかきたててくれるありがたい存在だった。薔薇は、枯れなかった。これでいいのかな? と思いながら手探りで世話をしていたが、一時的に調子が悪くなることもあれば、また持ち直したりもした。
そして、ベランダに打ち水を繰り返した夏が過ぎ、やっと涼しい風が吹くようになった頃、その薔薇は蕾をつけた。
たった、それだけのことだったが、美波はふいに「自分にもできることがあるのだ」ということを、心から感じることができた。ただ、人に去っていかれるだけの、なんの魅力も取り柄もない女なのではないと、その蕾が証明してくれているように思えた。
蕾が開き、花が咲いたとき、美波はその美しさに引き寄せられた。また、同じことを繰り返すかもしれない。けれど、私にも、もしかしたら、何かを続けることができるかもしれない。新しい希望の色は、淡いピンク色だった。美波はそれを、いつまでも見ていた。
<著者プロフィール>
雨宮まみ
ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)、マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)、『女の子よ銃を取れ』(平凡社)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。最新刊は、『東京を生きる』(大和書房)。
イラスト: 安福望