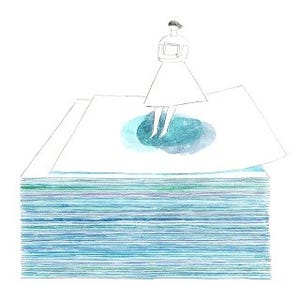そのマグネットを見つけたのは、美術館の地下のミュージアムショップだった。最初は何かわからなかった。小さな鉱石の形をしたものが三つ、箱に入っていた。手に取ってみると、鉱石にしては軽い。けれど、プラスチック素材にしては少し重い。
蓮実はポップに書かれている小さな文字を目で追い、それがマグネットだと知った。
「ねえ、これ見て」
離れたところで食器を見ていた亮二に声をかける。「マグネットなんだって」。亮二がほめるのを待つ。蓮実はあまり、こうした無駄なものは買わない。亮二がほめて、背中を押してくれるのを待っていた。
「なんか、飴みたいだね」
亮二の言葉に気勢を削がれ、蓮実は「でも、綺麗じゃない?」とだめ押しをする。亮二の返事を待たずに、むきになってこのマグネットを買おうと決めていた。
その日は、亮二の家に泊まった。亮二の家でシャワーを使わせてもらってから、キャミソールにショーツという姿で真っ白なバスタオルを肩にかけ、蓮実は冷蔵庫からミネラルウォーターを出した。亮二がシャワーを浴びている水の音が聞こえる。
ふといたずら心であのマグネットを取り出し、冷蔵庫にひとつ、貼り付けてみる。ペパーミントグリーンの、きれいな、模造品の石。
亮二の冷蔵庫には何も貼られていない。インテリアにも、持ち物にもこだわる亮二は、すぐに気づくだろう。蓮実が肩にかけているバスタオルだって、オーガニックコットンの良い品だ。
この部屋に合うような、亮二の目にかなうような良いパジャマを選べず、蓮実はそんな姿で亮二の家で時間を過ごしている。その亮二の家に、ちょっと邪魔なアクセントを加えてやりたくなった。この家に滞在している自分のように。
亮二と別れることになったのは、それから八ヶ月後のことだった。春が来ようとしていた。
亮二の「仕事が忙しい」「疲れている」という言葉を、聞き飽きるほど聞いていた。お互いに休みである土日に会えなくなると、会う回数は驚くほど減った。平日の夜は亮二の帰りが遅く、夕食だけ一緒にとることもできなかったし、疲れているのに泊まりに行ったり、出かけようと誘うのもためらわれた。亮二からは誘ってこなかった。
本当に疲れているのだろう、と思ったが、だんだん「いつまでこんな生活が続くのだろうか」と不安になった。ずっと、月に一度とか、多くても二度ぐらいしか会えないまま、恋人と呼んでいいかわからないような関係が続いていくのか、と。
「一緒に住まない?」
蓮実がそう言ったとき、亮二は顔を伏せた。髪の生え際の少し上のあたりに、以前はなかった白髪がたくさん生えているのが見えた。
ああ、この人にとって、私は「疲れる」ことなのだ。蓮実はそう悟った。その一言がきっかけで、二人は別れることになった。亮二はもう、蓮実と会う体力もないようだった。メールで「蓮実の期待には答えられない。誰とも、住むとかそういうことは考えられないし、いつかそれができるという約束もできない」と、短い文章が送られてきた。「わかった」とだけ返すと、「本当にごめん」と返ってきた。
その四日後のことだった。朝八時に家のインターホンが鳴った。出ると、「宅急便です」と言う。何も送ってこられる予定がなかったので、蓮実は戸惑った。コンランショップの紙袋が見えた。いやな予感がした。
ガムテープを剥がし、開けると、亮二の家に置いていた蓮実の日用品が丁寧に梱包されて入っていた。クレンジングを始めとする化粧品類、少しだけ置いていた下着、いつか着替えて置きっぱなしになっていたワンピース、貸していた写真集。「これもう読んだから、あげるよ」と言った雑誌も入っていた。亮二の好きな建築家の記事が出ていた雑誌だった。
拒絶の意志ではなく、善意で返してくれたのはわかっていた。ものを大切にする亮二だから、蓮実のものも、きっと大事なものだと思ったのだろう。ただでさえ自分が理由で別れるのだから、せめて返さないと申し訳ないと思ったのだろう。
空になったと思った紙袋を畳もうと持ち上げると、底に違和感があった。逆さにすると、小さな石がころん、と落ちてきた。あの淡い緑色のマグネットだった。
ここまでです、と線を引かれた気がした。あの家には、もう二度と入れない。あの家に自分のものを置いておくこともできない。亮二の領域に、踏み込むことはできない。
拒まれて初めて、当たり前のようにあの家にものを置けた、亮二の家での特権階級にいた時代が甘く、懐かしく思えた。それを思い出すのはまだひどくつらく、蓮実は紙袋にものを戻し始めた。全部捨ててしまおうと思った。
でも、あのマグネットだけは入れられなかった。勝手に踏み込んでも良かった、あの時代の勲章。蓮実はそれを、普段開けない引き出しの中に放り込んだ。いつか、美しい、ただの勲章として見られるようになる日が来るまで、にせものの石は引き出しの中で眠り続ける。
<著者プロフィール>
雨宮まみ
ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)を昨年上梓。最新刊は『女の子よ銃を取れ』(平凡社)。
イラスト: 安福望