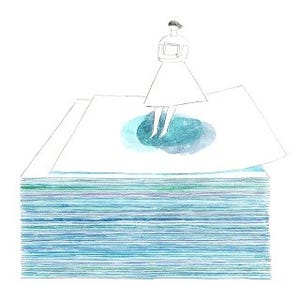優等生、と呼ばれて生きてきたような人間は、いったいどこでどうやって、恋愛というものをおぼえていくのだろう、と奈都子は思っていた。
奈都子自身、そう呼ばれてきたし、学校にいた頃は自分がだいたいのことはうまくやれるタイプの人間だと信じていた。女子同士のグループ付き合いもうまくやれた。時期が来ていないだけで、いずれ大人になれば自然に恋愛もするのだろう、と焦らずに考えていた。
しかし、大学生になって、周りが恋愛の話ばかりになっても、奈都子は「恋愛」というものがあまりピンと来なかった。
紹介するよ、と男性を紹介されたこともある。「お洒落な人だなぁ」とか、「こんな感じの人とつきあえたら、自慢に思えるんだろうなぁ」とか、ぼんやりと「良い評価」は浮かぶものの、自分がどう思うか、というと、目の前のこの人と二人で会話したり、肌を触れ合わせたりすることが、全然楽しそうには思えないのだった。
奈都子はそのまま卒業して広告会社に就職し、四年が過ぎた。そして、初めて恋をした。「あの人に会うと緊張する」という、「それ」が恋なのだと気づくまでに少し時間がかかった。最初は「嫌いなのかな?」と思ったほどだった。そして、気づくと余計に緊張するようになった。
相手は会社の取引先の課長の、戸張という男だった。彼は奈都子よりも十一歳年上で、結婚していた。だから、奈都子は「どうにもなる気はない」と、自分に言い聞かせていた。絶対に先へは進めない、ということが、逆に奈都子に安心感を与えていた。
会社の中にいると、人によって態度が変わる人をよく目にする。そういう姿を見るたびに「嫌だな」と思いつつ、自分自身だって態度を変えているかもしれない、と我が身を振り返るたび、奈都子は小さな苦い塊を呑み込んだような気持ちになった。大人になる、ということは、堂々と「わたしはいい子です」と胸を張れないうしろめたさを抱え込んでいくことなのか、と知った。
戸張は誰に対しても、態度を変えない珍しい人に見えた。たまに雑談をするようになり、奈都子は戸張がコーヒーが好きで、気に入った店で豆を買い、自宅で手動のミルで挽いてから自分でコーヒーを淹れるのだと知った。
近づくためにどうすればいいのか、奈都子は「勉強する」ということ以外の手段を知らなかった。いや、近づいてはいけないんだ、と思いつつ、こんなのは近づくうちには入らないだろう、と思い、仕事の帰りに普段は行かないデパートの食器売り場に足を踏み入れ、上等なコーヒーミルを買った。地下の食料品売り場で豆も買って、挽いてみた。
淹れてみると、なんだかぼんやりした味がした。薄いな、と思った。でも、こういうのが好みの味なのだろう、と考えると、するすると飲めてしまった。それからは自分の中で気持ちを確認するかのように、一日に一杯、夕食後にコーヒーを飲むのが習慣になっていった。
奈都子はその「勉強の成果」を、戸張に話すのをひそかに楽しみにしていた。会社に戸張が現われたときは、やっとこの時が来た!と少し緊張した。
「戸張さん、私、コーヒーミル買ったんですよ」
緊張が顔に出ないよう、なんとか微笑みを作りながらそう言った。
「お、いいね。うちは最近、コーヒー禁止なんだよ」
「えっ、どうしてですか?」
「妻が妊娠して、妻もコーヒー好きなもんで、飲めないのに匂いがするなんて拷問みたいだから、禁止されたっていうわけじゃないんだけど、僕もつきあってコーヒー断ちしてるんだよ」
奈都子はそこからどう言葉を絞り出したのかよく覚えていない。帰宅してから気づいたのは「おめでとうございます」とちゃんと言えなかったことだった。
「勉強」のために買ったコーヒーミルが、目にするのもつらいものに成り果ててしまい、奈都子はこれをどうしようかと考えた。値の貼るものを買ってしまったし、捨てるにしても、木の土台がついているものを「燃えないごみ」に入れるのは、なんだか間違えているようで不安である。かと言って、バラバラにもできない。
困り果てて考えているうちに、会社を辞めた仁名という友達の顔が思い浮かんだ。彼女は結婚後、すぐに妊娠がわかり「自分は仕事と両立はできないと思う」と、わりとあっさり会社を辞めてしまったのだが、もともと作る側の仕事に興味があったようで、子供が3歳になった今では、デザインの勉強をしつつ、小さな仕事を引き受けたりもしていると聞いていた。
自分とはタイプの違う仁名の自由な感じに惹かれ、不思議と仁名のほうでも奈都子は話していて気持ちが落ち着く相手だったらしく、たまに会うつきあいが続いていた。子供を仁名の夫が見ていてくれる日に食事に行くと、仁名は必ず、わざわざ店を変えて、最後においしいコーヒーが飲みたいと言って、同じ店に行った。
「家ではコーヒーメーカーで済ませてるけど、本当は一回ずつ手挽きで淹れるほうがおいしいのよね」
仁名がそう言ったことも覚えていた。
不要なものかもしれないな、と思いつつ、勇気を出して「コーヒーミルが余っているんだけど、いる?」と写真つきでメールをしてみると、即座に「欲しい! でも、どうして? それすごくいいやつじゃない」と返信が来た。
なにかもっともらしい言い訳を考えなくては、と焦っていると「おいしいコーヒーを家で飲めたらいいなと思って買ってみたんだけど、淹れてみたら自分はエスプレッソの濃い味のほうが好きだって気づいたの」と、思わぬ本音が出てきた。
仁名は「もったいない!」とか「なんで買ってから気づくの!?」と面白がっていたが、週末に奈都子が仁名の家にコーヒーミルを届けに行くことで話がついた。こういう後処理だけはどんどん器用になっていくな、と奈都子はぼんやり考えた。
仁名の家には、仁名一人しかいなかった。旦那さんが実家に孫の顔を見せに行っているのだという。仁名は行かなくて良かったのか訊くと、「全然! 近いからけっこう行ってるんだよ。今日ぐらい行かなくても別に誰も気にしないし」と平気そうだ。
持ってきたコーヒーミルを渡すと、仁名はとても喜んだ。そして、何かたくらみのあるような顔をして「ちょっと待っててね」とキッチンのほうに姿を消し、ラッピングされていない箱を持って出てきた。
「お礼にこれ、あげる」
奈都子が箱を開けると、そこにはカプセル式のコーヒーメーカーが入っていた。
「エスプレッソのほうが好きなんでしょ? これ、結婚祝いでもらったんだけど、私はエスプレッソは濃すぎて苦手で、一回も使ってないんだよね。奈都子がコーヒーミルくれるって言ったとき、交換できる! って思ったんだ」
仁名が奈都子の言葉を待っている気配がする。けれど、奈都子は顔を上げられないでいる。なぜか、今になって初めて、自分でも驚くほど突然、涙が出てきた。こらえても漏れる嗚咽に気づき、仁名は驚きながら素早くタオルを持ってきて、奈都子をソファに座らせ、背中を撫でてくれた。
初めて恋をしたの、誰にも言えない恋だったの、だめだったけど、私がんばったんだよ、好きだったんだよ。
呑み込み続けてきた苦い塊を全部吐き出すように、奈都子は仁名の前でしばらく泣いた。甘えられる相手の前で流す涙は、ほんの少しだけ、甘いのだということを、初めて知った。
<著者プロフィール>
雨宮まみ
ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)を昨年上梓。最新刊は『女の子よ銃を取れ』(平凡社)。
イラスト: 安福望