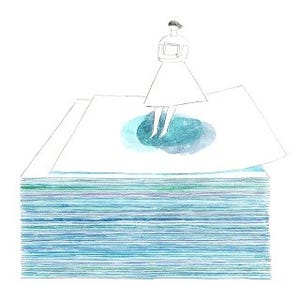「俺、背が高い女が好きなんだよね」
隣のテーブルから、真治のその言葉が聞こえてきたとき、輝水(てるみ)は少し身を固くした。
映画好き同士で友達を紹介し合っているうちに、なんとなく仲良くなったグループでの会だった。みんな、職種や会社はバラバラで、辛うじて年齢は30代~40代と、それなりに近いと言えないこともない範囲内におさまっていた。
輝水は背が高い。172cmある。学生時代から周りよりも背が高く、「そんなこと気にすることないよー」と無邪気に言われるたびに、「背が高い、ということは、何らかのハンデになることなのだ」と思わされた。
輝水は目立つことが嫌いだったが、どこにいても目立ってしまう。男性と比べればそれほど大きいわけではなかったが、「大きい女」というだけで、珍しそうに不躾な視線を投げてくる人もいたし、まるで見下されているようだ、と不快感を露にされることもあった。「背が高いと、似合う服が多くていいな~」と、背の低い女性に言われることもあったが、本気で羨んでいるとはどうしても思えなかった。
輝水は身長のせいで悪目立ちしないよう、いつも気を配っていた。派手な色のものは身につけない。できるだけ地味で、周りにとけこめるような、存在感のない服を選んだ。そして靴は、ヒールのないフラットシューズを履いた。
真治は決して、背の高い男ではない。その真治が「背が高い女が好き」と言ったことに、輝水は少し驚き、その先を聞こうと、隣の席の会話に集中した。
「そりゃ、ヒールはいたら俺の身長なんか抜かれちゃうかもしんないけど、でもいいじゃん、ヒールはいてその子がカッコ良かったら、その子と一緒にいるだけで嬉しいじゃん。自分と比べて、みたいなの、俺どうでもいいんだよね」
自分が初めて受け入れられたような気がした。そんなことを軽々と言ってのける真治のことが、急に器の大きい男に見えてきた。もちろん真治のほうも、近くに輝水がいる、ということを意識して言っていたに違いなかった。二人はその飲み会の帰り、なんとなく同じタクシーに乗り、真治の家に行き、なるようになった。
真治とつきあうようになって、最初に違和感を感じたのは、二度目のデートのときだった。
「ねぇ、いつもそんな靴だけど、ヒール履かないの?」
輝水が「履いたことないから」と答えると、真治は「じゃあ、俺にプレゼントさせてよ」と顔を輝かせて言った。「プレゼントさせてよ」の部分が嬉しくないわけではなかったが、輝水はその時点で後ずさりしたいほど腰が引けていた。あまり嬉しそうなリアクションを返せない輝水に、真治は「いいんだよ、俺の身長抜いたって。俺、気にしないし」と言った。
「今まで、男よりデカくならないように気遣って、ヒール履かなかったんだろ? 俺はそういうの平気だから、ヒール履いていいよ。普段気になるなら、俺と会うときだけでもいいし。絶対似合うから、行こう」
喜んでいいはずの言葉に、輝水は若干の違和感を持ち始めていた。それでも、つきあい始めのこんなときにケンカになるようなことは避けたい。真治がそんなに乗り気なら、そうしてみようか、と思い、輝水は真治についてゆくことにした。
真治は、女である輝水も入ったことのないような女性向けのお洒落なセレクトショップに躊躇なく入ると、「好きなの選んでいいよ」と言い、小さな声で秘密めかして「あんまり高いのじゃなければね」と笑いを含んだ声で言った。楽しいやりとりのはずなのに、輝水の心は、どこかこわばったままだった。
売り場の靴を見て、輝水の心は氷水につけられたようになった。どの靴も、9cmはあるピンヒールばかりなのだ。とても美しい、女らしい靴。人が履いているのを見るたびに「ああいう靴は、足が痛くならないのかな?」と不思議に思っていた、輝水の生活とは無縁な靴だった。
他の女の子ならきっと、ここで「好きなの選んでいいよ」と言われればすごく喜ぶんだろう、と思いながら、輝水は右も左もわからない森の中にぽつんと取り残されたように感じていた。どの靴が自分に似合うか、どの靴が好きかなんてわからなかった。どれを選ぶのが正解なのか、どれを履けば真治は喜ぶのか、まったくわからなくてパニックに陥りそうだった。
かろうじて、何の飾りもないシンプルなベージュのエナメルの靴を選ぶと、黒いパンツスーツの店員がすっと近づいてくる。「サイズをお出ししましょうか?」。聞かれるがままにサイズを言うと、店員は輝水の手から靴をもぎ取り、バックヤードへ続くドアの中へ消えていった。
「もっと派手なのでも似合うのに」
その真治の言葉を聞き、輝水は選択を間違ったことに気づいた。
「こういうお店初めてで、どういうのが似合うかわからないの」
勇気を振り絞ってそう言うと、真治は途端に嬉しそうな顔になった。
「輝水なら、こんなのも似合うはずだよ。こういうのも」
真治が指す靴は、ゴールドのオープントゥや、パイソンの型押しなど、輝水の想像を絶する靴ばかりだった。それらの靴を美しいと思わないわけではなかったが、いったいどういう服と合わせて、どんな顔をしてこれを履けばいいんだろう、と思うようなものばかりだった。
店員が箱を抱えて戻ってきて、輝水はベージュの靴を試着した。サイズは合った。立ち上がると、視界がぜんぜん違っていた。180cmを超える視界というのはこういうものか、と思った。鏡で見ると、ヒールを履いた自分の脚は長く見え、足首が細く見えた。
「似合うじゃん。シンプルだけど、最初のヒールならそういうのが合わせやすくていいのかもね」
真治のその言葉を、「許可」だと受け取り、輝水はその靴に決めた。
輝水は、休日に真治と会うときは律儀にその靴を履くようにした。それを履くと真治の身長を少し追い抜いてしまうので、並んで歩きながら話すときは視線の位置がずれて多少居心地が悪かったし、知らなかったが、エナメルの靴というのは硬くて、いつも少し歩いただけで小指がしびれるように痛くなった。靴擦れもできた。けれど、一日一緒にいるということは、それなりに歩く距離もあるわけで、輝水はトイレに立つたびにかかとのバンドエイドを張り替えながら痛みに耐えた。
ヒールのある靴に合うよう、服も買わなくてはならなかった。それまで馴染みのなかったワンピースや、膝丈のフレアスカートも買った。真治はそれらを見て、「いいね」と言ってくれたが、言葉を発する前に一瞬、不満そうな表情が目にあらわれることに、輝水は気づいていた。自分のセンスの悪さを責められているような気がした。
エナメルの靴のヒールは、どんどん傷んでいった。ささくれのようなものができていき、輝水はそれをどうしたらいいのかわからなかった。デート中に真治が退屈そうに携帯を見る時間が増えていった。土日の予定を「どうする?」と訊いても、「ちょっと疲れてるから、今週はごめん」と断られることが増え、三ヶ月経った頃、夜に真治の家に呼び出され、「別れたい」と言われた。
輝水の足の薬指にはまめができていたし、かかとにはかさぶたができていた。もういい、と思った。
「最後だから言うけど、輝水はスタイルもいいし、顔も綺麗なのになんで他の女の子みたいに努力しないのかずっと不思議に思ってた。そういう後ろ向きなところがどうしても好きになれない。俺は俺なりに、お前のコンプレックスを解きほぐそうとしたけど、それも無駄だったみたいだよな。宝の持ち腐れみたいでもったいないから、そういうとこ、もう少しなんとかしないと、お前の人生、何やっても楽しくないと思うよ」
輝水は、ああそうだったのか、と謎が解けたような気持ちになり、「わかった」とだけ言って部屋を出た。真治は送ってもこなかった。輝水は道路に出るとすぐにタクシーを拾い、その中で靴を脱いだ。
自宅の最寄りのコンビニの前で降ろしてもらうと、輝水は靴をゴミ箱に放り込み、裸足のままコンビニでビーチサンダルを買い、その場で履いて、ぺたり、ぺたりと軽い足音を響かせながら帰った。
真治が好きだったのは、「背が高い女」ではなく、「背が高い、いい女」で、輝水という素材を自分好みのいい女に仕立て上げて、それを連れている自分、という絵を描きたかっただけだったのだ、とわかってしまうと、これまでのすべてが「なあんだ!」と思えた。開放感のほうが悲しみよりもずっと大きかった。
それでも、その日から、自分が他の女の子みたいに努力しないのは、後ろ向きなことなのか? という問いが、心の奥にこびりついたようになった。
その日から、輝水は普段の生活に戻った。足に合った革のローファーを履いて、黒かベージュのパンツスーツで会社に行った。180cmの視界からも、足首が細く見える世界からも縁を切った。真治と同じで、自分には合わないものだったんだ、と思った。
しばらく経ってから、会社のトイレで後輩の女の子と一緒になった。彼女は髪をブラウンにカラーリングしていて、巻いていて、いわゆる真治の言うような「努力している女」だった。好きでも嫌いでもなかったが、それ以前に接点がない、と輝水は感じていたので、彼女が急に「先輩、ちょっと訊いてもいいですか?」と話しかけてきたときには、少し驚いた。
「先輩の靴、どこで買ってるんですか?」
「えっ、これ!?」
まさか彼女が、自分の地味なヒールのないローファーに興味を示すと思っていなかった輝水はうろたえた。
「そうです。先輩、その靴ずっと履いてますよね。あ、これ全然、悪い意味じゃなくて……。私、今までいろんな靴買ってるんですけど、足が痛くならないヒールってなかなかなくて……。会社だと特に長時間だから、合わない靴だとつらいんですよね。ほら、私、足汚いんですよ、傷だらけで、お座敷とか上がりたくないんです」
7cmぐらいのヒールの中から出てきた彼女の小さな足は、以前の輝水のように、薬指にまめができて、かかとが赤くなっていた。
「靴も、傷んだら捨てるみたいな感じで、無駄だなっていつも思うし、先輩みたいにちゃんとお手入れして長く履ける靴って、どういうところで買えばいいのかなって……。私にちゃんとお手入れできるかどうかわからないですけどね、ずぼらだし、ぼろくなったら捨てるみたいな生活してるから、ちゃんとした靴が欲しくて」
輝水は、「努力している前向きな女の子」にも、自分と同じような感覚があることに驚いた。こんなふうに、興味や本心を率直に打ち明けられることにも。自分もこんなふうにできれば、わけもわからないままエナメルの靴なんか選ばずに済んだのかもしれないと思った。
そして、自分が長年靴を買っている店のこと、そこで手入れの仕方も教えてもらえること、少し高くなるがセミオーダーにするとさらに足に合う靴になることを教えた。そして、ひとつ息を吸い込んで、勇気を出して訊いてみた。
「私はこういう靴しか持ってなくて、ヒールの選び方も買い方もわからないんだけど、足があまり痛くならないヒールって、どうやって選べばいいの?」
<著者プロフィール>
雨宮まみ
ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)を昨年上梓。最新刊は『女の子よ銃を取れ』(平凡社)。
イラスト: 安福望