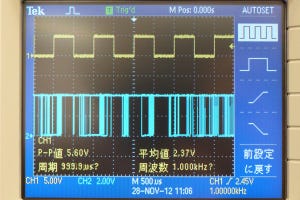今回は、高い電圧を測定できる「高電圧プローブ」について述べていきます。高電圧測定においては、操作や接続方法などを誤るとケガをしたり命に関わる恐れがあるので十分注意してください。
壊れるぞ!! - プローブは高周波・高電圧が苦手
本連載第2回で取り上げた受動プローブは、数百Vを超える高い電圧を加えると壊れてしまい、測定することができません。高い電圧を測定する際には、「高電圧プローブ」と呼ばれる専用プローブを用います。高電圧プローブには、数千~数万ボルトもの高い電圧が測れるものがあります。ここで"高電圧プローブさえ使えば安心"と思った読者もいらっしゃるかもしれません。しかし、ここに大きな落とし穴があります。実在の高電圧プローブ(写真1)を例にとってみましょう。
写真1:高電圧プローブの例 - Tektronix製P6015A型 |
写真1のプローブは、最大入力電圧2万Vをうたう大型のプローブで高電圧測定によく使われています。このプローブで周波数10MHzの電圧5千Vを測れるでしょうか。最大入力電圧2万Vのプローブなので、5千Vは問題なく測れると考える読者もいらっしゃるでしょうが、答えは「NO!」です。測れません。
なぜでしょう。それは10MHzという高い周波数が原因です。高い周波数になればなるほど、プローブに印加できる電圧は低下するのです(図1)。
図1:高い周波数になればなるほどプローブに印加できる電圧は低下する |
最大入力電圧とは、そのプローブに印加できる電圧のうち、最大の値を意味し、低い周波数においてのみ実現できる値なのです。注意を促すため、ほとんどの高電圧プローブには周波数と印加できる電圧の関係を表すグラフが添付されています(図2)。
図2:高電圧プローブに添付されている周波数と印加できる電圧の関係を表すグラフの例 |
図2はP6015A型(Tektronix製)の「デレーティング特性」と呼ばれるグラフで、周波数と印加できる電圧の関係を示しています。印加できる最大の入力電圧は2万Vですが、低い周波数に限定されています。400kHzを超えて周波数が高くなると、印加できる電圧はだんだん小さくなり始め、グラフから読み取ると10MHzにおいて約4千V、20MHzにおいて約3千Vしか印加できないことが読み取れます。
数100kHzより低い周波数ならほぼ安心ですが、MHz近くの周波数を測るときにはデレーティング特性グラフを見て印加できる電圧を確認しましょう。特に高電圧プローブにおいては、大きな事故につながりますので、十分に注意する必要があります。写真2は、高い電圧による絶縁破壊の例です。
写真2:高い電圧による絶縁破壊の例 |
プローブが溶ける!! 火傷する!!!
高電圧の測定においては、火傷にも注意が必要です。高い周波数の大きな電圧を測定すると、プローブは容易に発熱します。発熱による火傷に注意すべき領域をグラフ上に示しているプローブもあります(図3)。
図3:高電圧プローブに添付されている火傷に注意すべき領域を示したグラフの例 |
高電圧測定においては、測定時間を極力短くし、プローブが過熱するのを防がなくてはなりません。長時間測定を続けると、熱によりプローブの一部が熔解することすら起こりえます。
グランドの接続が外れると危険!! 命を落とすぞ!!!
受動プローブについても同じですが、特に高電圧プローブのグラウンド接続は確実にとらなければなりません。接続順番もまずグラウンドを接続し、続いてプローブ先端を接続するよう習慣づけてください。グラウンドワニ口が外れてしまったり、接続順番を守らなかったりすると、測定しようとしている1000Vもの高い電圧がオシロスコープの入力端子や筐体に発生します(図4)。
図4:筐体がグラウンド接続されていない場合、グラウンドリードがはずれれば1000Vもの高電圧がオシロスコープの入力端子や筐体に発生する |
高電圧に気付かず筐体や金属部に触れてしまえば命にかかわります。グランド付き電源ケーブルにより筐体を常にグラウンド(アース)に接続してください。こうすれば、人命に関わるような最悪の事態を防ぐことができます(図5)。
図5:筐体がグラウンド接続されていれば、グラウンドリードがはずれても安全で筐体電位はゼロである |
フローティング測定の落とし穴
図6のように、電位のある一点とさらに電位のある別の一点間の電圧を測定することを「フローティング測定」といいます。また信号源1を「差動電圧」、信号源2を「コモン電圧」と呼びます。
図6:フローティング測定 |
初心者が犯しやすいまちがいは、不用意にプローブのグラウンドリードをB点に接続しようとすることです。接続した瞬間に悲劇が起こります。信号源2は図7のように短絡されるので、信号源2自体が壊れるか、グラウンドリードを含む電流経路を焼き切ってしまいます。
図7:グラウンド付きのオシロスコープの場合 |
そうなればと、電流経路を取り去ってしまうという乱暴な方法を使う中級者もいます。電源ケーブルのグラウンドピンをあえて繋がないのです(写真3)。
写真3:正しくない方法 - "電源ケーブルのグラウンドピンをあえて繋がない"というような乱暴な方法はやってはいけない |
これはフローティング測定において全く正しくない方法です。1.感電、2.電源回路の故障、3.被測定回路への悪影響という3つの問題が生じます(図8)。
図8:グラウンドを浮かせたオシロスコープの弊害 |
オシロスコープの筐体や金属部が信号源2の電位をもつことになるので、金属部に触れると感電します。信号源2の電圧が高い場合は、人を死に至らしめます。人が触れないとしても、電源回路はAC100V電圧にさらに信号源2の電位が加わることになり、電源回路を故障させるなど、故障にいたるストレスを蓄積させることになります。信号源の出力インピーダンスが高い場合は、数百pFもある浮遊容量が回路の動作を狂わせます。筐体やグラウンドワニ口に数十Vの浮遊電圧が生じていることも多く、プローブのワニ口を測定点に接続するとその電圧により被測定回路が壊れることさえあります。
フローティング測定できるオシロスコープ
フローティング測定において電源ケーブルのグランドをきちんと接続しながら、既述のような数々の失敗をしないためには、どうすればよいのでしょう。1つ目の答えは、フローティング測定を念頭に設計された専用オシロスコープ(写真4、図9)を使うことです。
写真4:フローティング測定用オシロスコープの例 - Tektronix製TPS2000シリーズ |
図9:フローティング測定用オシロスコープ |
一般的なオシロスコープの入力BNC端子の外側金属部はオシロスコープの筐体に繋がれており、すべての外側金属部は互いに接続されています。ところが、この専用オシロスコープでは金属部分の露出を極力なくし、各入力BNC端子の外側金属部はオシロスコープの筐体からも、互いに外側金属部からも絶縁されています。したがって、各チャネルはグラウンドから独立しており、プローブのワニ口を測定点に接続しても、コモン電圧は短絡しません。金属露出部のない専用プローブを使って、差動電圧は1000Vまで、コモン電圧は600Vまでのフローティング測定ができます。
擬似差動プローブ
2つ目の答えは、プローブ2本で擬似的に差動プローブを作ることです。接続は2本のプローブの先端をA点B点に接続します。グラウンドワニ口は図10のようにアースに接続するか、図11のように互いを接続したまま中空にぶら下げておきます。
図10:グラウンドワニ口をグラウンド接続 |
図11:グラウンドワニ口を互いを接続したまま中空にぶら下げておく |
後は、オシロスコープの機能を使い、CH1とCH2の引き算をするだけです。こうすれば、A点B点間の差動信号だけがオシロスコープに表示されます。手持ちの2本のプローブがあれば、手軽にこの擬似差動プローブが作れます。しかし、擬似差動プローブを使うには2つの点に注意してください。第1に、特性と伝播遅延時間を合わせるため同じ型番のプローブを用いることです。第2に、オシロスコープで引き算する前に2つの波形を画面内からはみ出させない範囲で最大になるようオシロスコープの垂直軸感度を正しく設定することです。
2本のプローブどうしを軽くねじっておくと、グラウンドシールド線に飛び込むノイズをキャンセルできるのでノイズが軽減する、ということを知っておくと役立ちます(写真5)。
写真5:2本のプローブどうしを軽くねじっておくとグラウンドシールド線に飛び込むノイズをキャンセルできるのでノイズが軽減する |
そして3つ目の答えは「高電圧差動プローブ」を使うことです。これについては、次回に詳しく解説していきます。お楽しみに。
※ 本連載記事は、毎週火曜日と金曜日に掲載いたします。
| 著者 |
|---|
| 稲垣 正一郎(いながき・しょういちろう) 日本テクトロニクス テクニカルサポートセンター センター長 |