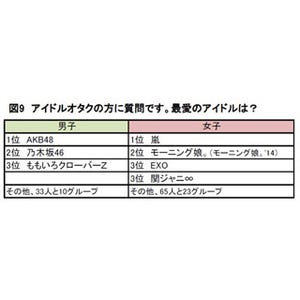ミュージカル『テニスの王子様』舞台『弱虫ペダル』『デスノート The Musical』『ライブ・スペクタクル NARUTO-ナルト-』など、日本が誇る多くの漫画・アニメ・ゲームを原作とし、舞台化した「2.5次元ミュージカル」。2014年3月に発足した一般社団法人 日本2.5次元ミュージカル協会は、世界を視野に一体どのような展開を考えているのだろうか。代表理事の松田誠氏にお話を伺った。
観客が求めていることを見極める
――2.5次元ミュージカルというとミュージカル『テニスの王子様』が今となっては代表的だと思いますが、ミュージカル『テニスの王子様』以前というのは、どういう状況だったんでしょうか
それまでにも2.5次元ミュージカルと呼べる作品はけっこうあって、古くは宝塚歌劇団の『ベルサイユのばら』(1974年)がそうですし、僕のほうでも『HUNTER×HUNTER』や『こちら葛飾区亀有公園前派出所』、『姫ちゃんのリボン』などの舞台化に携わり、2.5次元ミュージカルのはしりのようなことをしていました。
『テニスの王子様』は、漫画でもアニメでも人気があって、舞台化できたらいいなと思っているときに、演出家の上島雪夫さんのダンスを見て、この人とだったらいけるんじゃないかと思って、原作を持って会いにいったんです。そうしたら、「わかった、やりましょう」と言ってくださって。先生のセンスにかけていたので、そこで「うん」と言ってもらえなかったら、今のような2.5次元ミュージカルもなかったかもしれませんね。
――2.5次元ミュージカルに世の女性たちが惹かれる理由はなんだと思われますか?
そもそもミュージカル『テニスの王子様』の場合は、恋愛の話でもありませんよね。でも、その物語の中の関係性が美しくて汚れがない。女性は良い意味で夢やイメージや妄想の世界に投資が出来るのだと思うんです。男性の場合はもう少し俗的な意味合いが強い。だから握手会等に行くのではないかと。
もちろん、舞台によってはもっとフレンドリーに接したいというものもあるかもしれませんが、やはり即物的なところは少ないんじゃないかなって。『テニミュ』(ミュージカル『テニスの王子様』)を見ている人は、キャストと握手したいという思いよりも、ちょっと距離のあるところから、つまり舞台上にいる彼らを見ていたいと思っているような気がします。
――その違いをちゃんと見て対応するのは思ってるよりも難しいことではないでしょうか
僕の場合は姉がいるということもありますけど、「男くさい」気持ちのほうがわかりにくくて、女性の気持ちのほうが共感しやすいってことはあるんですよね(笑)。それに、2.5次元ミュージカルを見に来てくださる女性だって、お金に余裕がある人ばかりじゃないわけだから、演目を吟味したいですよね。そうなると、自分が欲しているものと合っているものにお金を使うと思うんです。人気のあるコンテンツだからとか、人気漫画が原作だからってなんでも見にいくかというとそうじゃない。なんなら好きだった作品だからこそ、その世界観が崩れるとアンチにもなることがあります。だから、いかにファンの欲求にフィットするかをちゃんと考えないといけないんですよね。
――あと、これは自分の場合もそうなんですが、ドラマや映画の中で原作があるなしに関わらず、キャラクターをその役に似合った人が演じていると 、ファンになるということは多いです
それもありますね。例えば『イタズラなKiss~Love in TOKYO』に主演の古川雄輝くんが中国で人気と聞きましたけど、それも、物語の中の入江直樹というキャラクターに古川くんがあっているということで注目されたわけですよね。そういう話を聞くと、キャラクターと俳優を結びつけて見るということに、女性は長けていると思いますね。
でも、物語に対して思い入れがあるからこそ、その思い入れを裏切ると見てくれなくなることもあります。やはり、舞台を作るときに、原作の世界と、全体の空間がフィットしていないといけないということは、いつも気にかけていますね。だから、『テニミュ』と、舞台『弱虫ペダル』のアプローチはやはり違うものなんです。例えば、『テニミュ』のアプローチを舞台『弱虫ペダル』にそのまま持っていくと、「なに歌ってるの?」って思われたりもするでしょうね。作品によって求められているものが違うんです。
プロデューサーの役割は
――その求められていることが違うことを見極めるのは誰になるんでしょうか
それはやはりプロデューサーだと思います。最初のビジョンを考えてからじゃないと、スタッフィングできないですからね。設計図を描いてから、誰に託すかを決めるのはプロデューサーの仕事なんです。その後は設計図をもとに話し合っていきます。
『ライブ・スペクタクル NARUTO-ナルト-』は、『テニミュ』のように、キャラクターにハマるタイプの人気というよりは、その物語や普遍的な世界が好きという人が多いと思うんですね。だから、僕は『ライブ・スペクタクル NARUTO-ナルト-』を手掛けるときに、ファンの納得するビジュアルにとことんこだわって、再現率をどこまであげるかに力を注いだんです。「ここまで本気でやってくれるんだったら見に行ってやろうじゃないか」って、そう思ってもらわないといけないなと思ったんです。
その上で、例えば『NARUTO-ナルト-』に出てくる大蛇丸(オロチまる)というキャラクターの怖さを舞台上でどう表現するかと考えた時、何か、漫画とは違うやり方を探さないといけない。そこで、歌を使うことにしたんですけど、原作の世界を表現するときに、どういうことをすれば一番効果的なのか、それは作品によってぜんぜん違いますね。
|
|
ライブ・スペクタクル「NARUTO-ナルト-」 |
――舞台を作る上で、やっぱり稽古や本番を経て変わっていくもんですよね。その辺はどうとらえられていますか?
もちろん客席でお客さまの反応は見てますね。これは良いところでもあるし、悪いところかもしれないのですが、演劇って最後の最後までねばれるんですよね。だからと言って、最後が一番良いってわけではなくて、初日には初日だからこその緊張感もあるし、日によって楽しみ方も違います。まったく同じものはないというのは、ライブならではの面白さですよね。
――そんな舞台でかなり重要なのがキャスティングじゃないかと思うんですが、こだわっていることって何ですか?
実は容姿を似せることはそんなに大変じゃないんですよ。髪型やメイク、衣装である程度なんとかなります。もちろん、体格とかは変えられないんですけどね。でも、もっと重要なのは、役者がそのキャラクターと同じ"種"を持っているかなんですよね。例えば、リーダー格のキャラや正義感のあるキャラを、そういう"種"のない人では演じられないんです。
――キャスティングのためのオーディションはどのようにやっているんでしょうか
書類審査が終わってからの面接が全部で3~4回くらいありますね。僕の場合は、絞り込まれてから面接をするのですが。一応は役ごとにオーディションはしてるんですけど、面接を重ねるうちに、「こっちのほうがいいんじゃないか」ってことは多いんです。それで、別の役のセリフを読んでもらって、オーディションを受けたのとは別の役になることも多いんです。それに、「この役のセリフ、一回も読んでないのに、この役に決まったんだけど……」なんて役者さんたちが言っているということもあります。見ているのはセリフを読んだときの感じではなく、その人の中にある"種"なんですね。
西森路代
ライター。地方のOLを経て上京。派遣社員、編集プロダクション勤務を経てフリーに。香港、台湾、韓国、日本などアジアのエンターテイメントと、女性の生き方について執筆中。現在、TBS RADIO「文化系トーラジオLIFE」にも出演中。著書に『K-POPがアジアを制覇する』(原書房)、共著に『女子会2.0』(NHK出版)などがある。