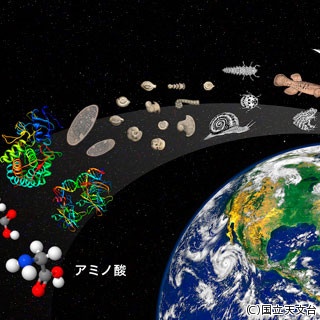東京大学(東大)と国立天文台は6月9日、アルマ望遠鏡と重量レンズのかけ合わせで、117億光年の距離にある銀河の内部構造を解明したと発表した。
同成果は東京大学理学系研究科の田村陽一 助教と大栗真宗 助教および国立天文台の研究グループによるもので、6月9日付けの「日本天文学会欧文研究報告」に掲載された。
重力レンズとは、質量が時空の歪みを介して光を曲げる減少で、非常に重い天体の周囲で生じ、その向こう側の天体の見かけの姿を拡大・増光する性質がある。
今回の研究では、今年2月にアルマ望遠鏡がとらえた117億光年の距離にあり、爆発的に星を生み出しているモンスター銀河「SDP.81」の画像を、同研究グループが提案した重量レンズ効果モデルを用いて解析した。
その結果、「SDP.81」では差し渡し200~500光年の塵の雲が、およそ長さ5000光年の楕円状の領域に複数分布していることがわかった。この塵の雲は、巨大分子雲と呼ばれる、恒星や惑星が生まれる母体だと考えられるという。また、重力レンズ効果を引き起こしている手前の銀河に質量が太陽の3億倍以上におよぶ超巨大ブラックホールが存在することも判明した。
今後、アルマ望遠鏡と重力レンズの組み合わせで、なぜモンスター銀河が形成されるのか、どのように超巨大ブラックホールが成長するかの解明につながることが期待される。