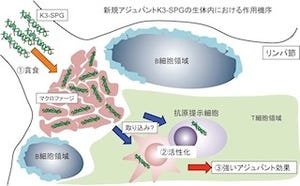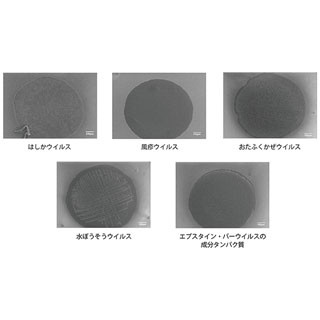順天堂大学は2月28日、理化学研究所(理研)との共同研究により、寄生原虫「クルーズトリパノソーマ」が原因となる熱帯病「シャーガス病」治療法の開発を目的とし、同原虫の「イノシトール3リン酸受容体(IP3R)」を標的とした「アンチセンス核酸」が、原虫のヒト細胞への感染を抑制することを発見したと発表した。
成果は、順天堂大大学院 医学研究科・生体防御寄生虫学の橋本宗明 准教授、同・奈良武司 准教授、理研 脳科学総合研究センター 発生神経生物研究チームの御子柴克彦 シニア・チームリーダーらの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、2月28日付けで英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。
シャーガス病は中南米に1000万人以上の患者がおり、主に心臓に寄生して心筋組織や心臓の刺激伝導系を破壊し、心不全による突然死を引き起こす恐ろしい感染症だ。流行地域は、原因のクルーズトリパノソーマを媒介する吸血性昆虫サシガメの生息域で、ほかのトリパノソーマ類が引き起こす「アフリカ睡眠病」や「リーシュマニア症」などと同様、患者の多くが貧困層であるため、製薬会社などによる治療薬の開発が遅れ、「顧みられない病」と称されている。宿主細胞を破壊して脱出しようとする多数のクルーズトリパノソーマの様子(画像1)は、同大Webサイトにて見ることも可能だ。
中南米から程遠い日本では関係ない感染症かというと、実はまったくそんなことはなく、日本には南米出身者が多く暮らしていることから、グローバリゼーションに伴う重要な輸入感染症として監視が必要な状況となっている。実際に日本では2013年、南米出身の抗体陽性者の血液が輸血に用いられていたことが判明している。また現在用いられているシャーガス病治療薬は末梢神経障害や吐き気などの強い副作用があり、治療効果も限られているため、新たな治療薬の開発が急務とされていた。
そうした背景の下、研究チームは治療薬の標的となる分子の探索を進めているが、その中で寄生原虫のクルーズトリパノソーマにおいて細胞内カルシウム濃度の上昇が宿主細胞への侵入に必須である点に注目。このカルシウム濃度の上昇を担う本体がIP3Rであることを究明した。
IP3Rは細胞小器官「小胞体」の膜に存在するチャネル(必要なイオンなどを細胞から出し入れする仕組み)の1種で、細胞内カルシウム(Ca2+)動態を制御する重要なタンパク質だ。細胞膜上の受容体刺激による「ホスホリパーゼC」の活性化によって生成されたIP3がIP3Rに結合すると、細胞質中にCa2+が放出され、それがセカンドメッセンジャーとなりシグナルが伝達されるという仕組みである。ヒトを含む動物では、特に脳神経系の高次機能の発現に必須の役割を担っており、「小脳失調症」などの脳疾患に深く関与することも確認済みだ。
このIP3Rの遺伝子を欠損させた原虫では細胞侵入能のみならず分裂・増殖、発育期転換、マウスに対する病原性のすべてが低下することが判明。これにより、IP3Rのに特異的に働く阻害剤は非常によいシャーガス病治療薬になると考えられるとされたのである。
そこでIP3Rの発現を特異的に阻害する手法として研究チームが着目したのが、次世代医薬品の候補として有望視されているアンチセンス核酸だ。アンチセンス核酸は次世代医薬品の候補であり、日本では現在「モルフォリノ化合物」で合成したアンチセンス核酸を用いた「デュシェンヌ型筋ジストロフィー」に対する臨床治験が始まっている。
今回の実験では、原虫をIP3R特異的なアンチセンス核酸で処理することによって、宿主細胞への侵入が抑えられるのかどうかが調べられた。なおアンチセンスとは、タンパク質を合成するメッセンジャーRNA(mRNA)の塩基配列に対して相補的な塩基配列をのことをいう。
アンチセンス核酸は、標的遺伝子のDNAやRNAに選択的に結合することによってタンパクの合成を抑制する仕組みを持つ。細胞内に20塩基程度のアンチセンスを有する核酸が導入され、標的mRNAに結合すると、その発現が抑制されるという具合だ。細胞内で分解されるのを防ぐために、一般的には修飾基が付加されたアンチセンスが用いられている。
このアンチセンス核酸の特徴により、標的タンパクの合成・分解の速度が速いほどその高い発現抑制効果が期待できるというわけだ。そこで最初に、クルーズトリパノソーマのIP3Rタンパク質の発現量および安定性が確認され、IP3Rがアンチセンス核酸の標的として適しているかどうかが調べられた。
しかし、IP3Rタンパクの発現量は微量で検出が困難であることが判明。そこで緑色蛍光タンパク質との融合タンパク(EGFP-IP3R)を強制的に発現させ、タンパク質合成阻害剤「シクロヘキシミド」で処理した状態でその分解速度が調べられた。すると、EGFP単体では処理後24時間で発現量にほとんど変化がない一方で、EGFP-IP3Rの発現量は速やかに低下すること(半減期は約3時間)が明らかにされた。これは、IP3Rが分解を受けやすく不安定なタンパク質であることを示しているという。
続いて、アンチセンス核酸の存在下で感染型原虫におけるEGFP-IP3Rの発現量が調べられた。すると、EGFP-IP3Rの発現量は速やかに低下。これはアンチセンス核酸によってタンパク合成が阻害され、EGFP-IP3Rが短時間で分解を受けたことを意味しているという。
次に、アンチセンス核酸が実際に原虫の宿主細胞への侵入を抑制するかどうかが調べられた。アンチセンス核酸で処理した感染型原虫をin vitro(人為的に制御された環境下での実験)で、マウスおよびヒト培養細胞への感染が行われ、すると宿主細胞への侵入が実際に抑制されることが確かめられたのである(画像2)。さらに、原虫とヒトではIP3Rの塩基配列およびアミノ酸配列が大きく異なるため、原虫に特異性の高いアンチセンス核酸をデザインできると考え、実際に原虫IP3Rに特異的な配列の複数アンチセンス核酸による侵入抑制効果も確認された。
細菌やウイルスとは異なり真核生物である原虫では、細胞の仕組みの多くがヒトと共通している。そのため高い抗原虫活性を維持しつつ、ヒトに対して副作用のない治療薬を開発することは難しい。そして前述したように、シャーガス病を含むトリパノソーマ感染症は主に貧困国で流行しているため、コストや普及の観点からも治療薬開発が遅れているのが現状だ。
そうした中での今回の成果は、これまで有効な治療薬がなかったシャーガス病に対してアンチセンス核酸を用いた治療薬開発に光を当てるものである。さらに、アフリカ睡眠病やリーシュマニア症など、ヒトや家畜に病原性を示すほかのトリパノソーマ症についても、アンチセンス核酸の高い特異性を生かし、IP3Rを標的とした治療法の開発が期待されるという。今後は感染動物モデルを用いて検証し、アンチセンス核酸の治療効果と安全性をさらに詳しく調べていく予定とした。