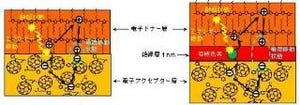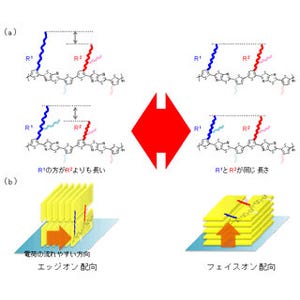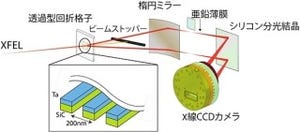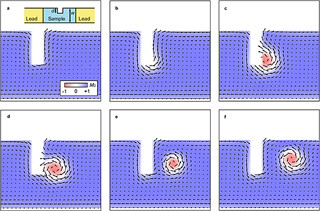理化学研究所(理研)は、アト秒(10-18秒)の時間幅をもつ極短パルスの極端紫外光(XUV)を高効率かつ高強度に発生できる手法を確立し、その手法を用いて卓上サイズでGWの瞬間出力を持つ孤立アト秒パルスレーザを開発したと発表した。
同成果は、同所 光量子工学研究領域 アト秒科学研究チームの高橋栄治専任研究員、緑川克美チームリーダーらによるもの。詳細は英国のオンライン科学雑誌「Nature Communications」に掲載された。
基礎科学の分野では、高速な物理現象を観測するため、これらの現象を止めて見るために一瞬だけ光るパルスレーザ光源の開発が進められている。パルスレーザをカメラのストロボにように使うことで、人間の目では絶対に追うことのできない原子や分子の動きを見ることができる。また、ストロボが光る時間幅、すなわちパルス幅が短くなればなるほど、より速い現象を止めて見ることが可能になる。このため、20年程前からフェムト秒レーザ(10-15秒)と呼ばれるレーザが実用化され、分子が振動する10兆分の1秒から100兆分の1秒程度の時間であれば、その動きを止めて見ることができるようになった。このような研究は、フェムト秒化学などの分野として発展している。
一方、2000年を過ぎると、さらに短い時間幅の光を発生させ、究極の高速運動である原子内で動き回る電子の動きを観測するという試みが始まった。ここで使われるのがアト秒パルスと呼ばれる短時間で光るストロボである。同分野はアト秒科学と呼ばれ、世界各国で盛んに研究されており、多くの研究者がアト秒パルスの時間幅を縮めることにしのぎを削ってきた。しかし、この10年間で開発された孤立アト秒パルスレーザの出力は、ナノジュール(10-9J)程度と低くかったため、非線形光学研究などの強い光の場を扱う研究にアト秒光源を利用することが難しく、応用や進展を妨げてきた。
アト秒パルスを作るためには、高次高調波発生と呼ばれる非線形な波長変換プロセスを使用する。時間的に孤立した(単一な)アト秒パルスを得るには、レーザ電場のキャリアエンベロープ位相を安定化させ、かつ電場周期が数サイクルの特殊なレーザを励起光として使う必要がある。しかし、このような要求を満たす励起レーザのパルスエネルギーには制約があり、その結果、高強度な孤立アト秒パルス発生の実現は困難だった。
|
|
|
図1 各研究機関が開発した孤立アト秒パルス光源の出力エネルギーと年代ごとの推移。カッコ内に発生したアト秒パルスの光子エネルギーと測定されたパルス幅を示した。今回開発された高出力化法によって、従来と比較して100倍以上の高出力化を実現した |
研究グループは、2010年に波長800nmと1300nmのレーザを時間・空間的に重ね合わせた2波長合成レーザを利用し、効率よく孤立アト秒パルス作り出す方法を開発した。2波長合成レーザを用いることで、簡易に連続的な高次高調波スペクトルを生成させることが可能になり、その結果、パルスエネルギーの大きな励起レーザを孤立アト秒パルス発生に使用できるようになった。
今回、2波長合成レーザを励起光として用い、これに最適位相整合技術と、独自の高調波エネルギースケーリング法を組み合わせたアト秒ビームラインを構築した。その結果、これまで実現されたアト秒パルス出力より100倍以上強い孤立アト秒パルスを作り出すことに成功した。また、レーザ光からアト秒パルスへの変換効率を10倍以上改善し、かつ高品質な極端紫外光(XUV)ビームを得ることにも成功した。
|
|
|
図2 高強度アト秒パルス発生ビームラインとパルス幅測定装置。波長の異なる2つのレーザを時間・空間的に重ね合わせた2波長合成レーザを利用し、効率よく孤立アト秒パルス作り出す方法を開発した。今回、その手法に、独自の高調波エネルギースケーリング法を組み合わせたアト秒ビームラインを構築した |
ガスセル内に充填されたキセノンガスから発生した高次高調波のスペクトルを見ると、単一波長(800nm)のレーザを励起光とした場合は離散的な構造を持つのに対し、2波長合成(800nm+1300nm)レーザを励起光とした場合は、連続的なスペクトル構造を持つことが分かる。特に、光子エネルギーが28~35eVの領域では、完全に連続な高調波スペクトルが得られており、このスペクトル構造から孤立アト秒パルスが発生していることを間接的に確認することができたという。
また、キセノンガスの圧力を調整して、位相整合条件を30eV近辺に最適化することで、従来法ではナノジュールと低かったパルスエネルギーを、最大で1.3μJ(28~35eV間の合計)にまで高出力化することができたほか、励起レーザからの変換効率は約1万分の1で、これまで実現された実験値と比べて10倍以上もの効率の改善を達成した。加えて、発生した高次高調波は、良好な空間分布と0.5ミリラジアンのビーム発散角を持ち、高品質なビーム特性も兼ね備えていることを確認。ビーム品質はイメージングなどへの応用の際に重要な役割を果たすため、今回の手法は、高い品質の高次高調波ビームを得ることができる、という点でも優れているとしている。
次に、得られた高次高調波が真にアト秒の時間幅を持った孤立パルスかを確認するため、自己相関法と呼ばれる手法を使ってパルス幅の評価を行った。実験では、反射鏡2枚からなる高調波空間分離器により、高調波ビームを空間的に2つに分割して窒素分子ビームに集光した。ここで、片方の反射鏡を前後させ、2つの高調波ビームの通る経路長を変えることで、窒素分子ビームにたどり着く時刻の差(遅延)を変化させている。この遅延時間(Δt)を関数として、窒素分子が高調波を2光子吸収して引き起こされるイオン化信号の強さがどのように変化するかを測定すれば、高調波自身の時間構造(自己相関波形)を知ることができる。
この結果、パルス幅が500アト秒の孤立アト秒パルスが発生していることが明確に確認された。これは、自己相関法で決定された孤立アト秒パルスの時間幅としては世界最短パルスになる。得られたパルスエネルギーと時間幅から、開発された孤立アト秒パルスレーザの瞬間出力は2.6GWと評価できる。この出力は、自由電子レーザ(FEL)技術で開発された光源と比較して、10倍以上高い値となる。また、発生装置の大きさも卓上サイズで、XUV-FELの光源を普通車に例えると、今回開発された光源の大きさはラジコンカー程度という非常にコンパクトなものとなっている。
今回開発した孤立アト秒パルスの高出力化法は、高い変換効率を保ったままアト秒パルスの出力エネルギーを拡大できる優れた特徴を持ち、軟X線からX線域において高強度の孤立アト秒レーザを開発する際の指針を与えてくれる。例えば、現在のレーザ技術と研究グループが開発したアト秒高出力化法を組み合わせることで、数100アト秒のパルス幅を保ちながら、XUV域で数10GW出力を持つ光源や、軟X線領域で数100MWの孤立アト秒パルスの発生が可能になる。
しかも、光源が卓上サイズとなったことで、大学の研究室や各企業で光源の所有を可能となり、短波長光源の利用の裾野を広げ、その応用研究を進展させると予想できる。特に、従来の孤立アト秒光源では難しかった、強い光と物質の相互作用研究にアト秒パルスを利用できるようになり、アト秒領域の超高速物理現象と非線形光学を組み合わせた未知の研究領域が拓かれるだけでなく、それらを利用して光学の分野に革新的な計測・解析技術や新しい粒子操作技術などがもたらされるものと期待できる。また、シード型FEL技術と孤立アト秒パルス発生法を融合させることで、アト秒パルスシード型FELといった新しい光源が誕生する可能性もあるとコメントしている。