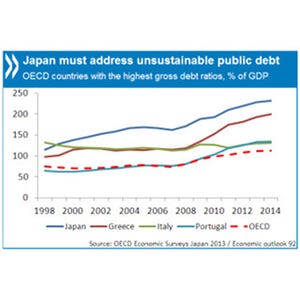経済協力開発機構(以下、OECD)は15日、所得格差に関するデータをまとめた報告書を発表した。それによると、税や給付による格差の軽減効果を除いた場合、2008年の経済危機の始まりから2010年末までの3年間で、所得格差はそれ以前の12年間を上回る勢いで拡大したことがわかった。
税と給付を講じた場合でも、2010年における富裕層10%の所得は、貧困層10%の9.5倍となり、格差は2007年の9倍から拡大。格差が大きかったのは、チリ、メキシコ、トルコ、米国、イスラエル。反対に、格差が小さかったのは、アイスランド、スロベニア、ノルウェー、デンマークだった。
OECD加盟国のジニ係数(不平等度を測る指標。0と1の間の数値を取り、数値が1に近いほど格差は大、数値が0に近いほど格差は小)を調べたところ、2007年~2010年の間に、平均市場所得の格差は1.3ポイント拡大。詳細を見ると、アイルランド、スペイン、日本、ギリシャなど、平均市場所得の下落幅が最も大きかった国々と、フランス、スロベニアにおける格差が大幅に拡大していた。一方、ポーランドとオランダでは格差は縮小していた。
家計の実質可処分所得について見た場合、2010年において上位10%に入る世帯の平均所得は、2007年とほぼ同水準にとどまった一方、2010年の下位10%に当たる世帯の所得は、2007年の水準を年率2%の割合で下回った。OECDによると、データを入手できた33カ国中、21カ国で上位10%が下位10%より良好な結果を示したという。
また、OECD加盟国の平均で、人口の約11%が相対的な所得貧困(可処分所得が、全国民の所得の中央値の半分に満たない国民の割合)状態にあることが判明(貧困率が最も高いのはイスラエルの21%)。さらに、2007年までの20年間に、ほとんどの国において貧困率が上昇したことが明らかになった。
相対的貧困率の増減率(2007年~2010年)を世代別に見ると、子どもは13%~14%に、若者は12%~14%に増加。一方、高齢者は15%~12%に減少した。
子どもの貧困率は、2007年以降、OECD加盟16カ国で拡大。中でも、トルコ、スペイン、ベルギー、スロベニア、ハンガリーでは、2ポイント以上増加しているという。OECDは 「高齢者に代わって若者と子どもが、所得の貧困の危機に最もさらされる年齢層になった」と分析している。
また、「経済危機、特に雇用危機が長引き、財政健全化に伴う財政緊縮策が定着する中、危機の代償が大きくなり社会的弱者がさらに深刻な打撃を受けるリスクが高まりつつある」と警告している。