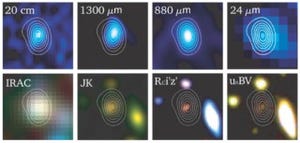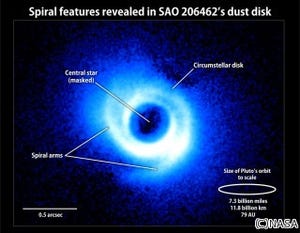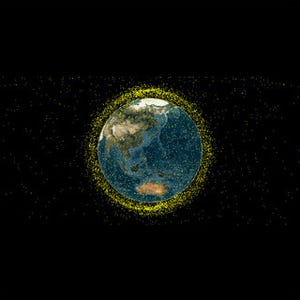京都大学などの研究者で構成される研究グループは、宇宙最初の星(ファーストスター、初代星)が生まれ、成長していく過程のコンピュータシミュレーションを実施し、その結果、太陽の約40倍の重さの星ができることを示した。これまで、初代星は太陽の数百倍という現在の宇宙にはほぼ見られないような巨大な星であると思われてきたが、観測的には太陽の数十倍程度であることが支持されており、今回の研究によりこのギャップが解決することとなった。同成果は、京都大学の細川隆史研究員(現 日本学術振興会海外特別研究員)、大向一行准教授、東京大学の吉田直紀准教授、米国航空宇宙局(NASA)ジェット推進研究所のハロルド・ヨーク博士などによるもので、2011年11月11日に「Science」オンライン速報版に掲載された。
宇宙は137億年前のビッグバンから始まったと考えられており、その後、少しずつ天の川のような銀河、太陽のような星々、地球のような惑星、そして人類のような生命が作られて来たと考えられている。こうした長い進化の最初の一歩が宇宙で最初の星 (初代星)であり、初代星はビッグバンから3億年後に誕生し、それは太陽の重さの100分の1の重さの星の赤ちゃん(原始星)であったことと考えられるようになってきている。
しかし、これは実は星形成の始まりにすぎず、この後、原始星は周囲に存在する太陽の1000倍に達する大量のガスを重力により集め成長していく。もし、原始星がガスの大半を集めることができれば、太陽の数百倍の重さの "モンスター星"になると考えられるが、その進化を実際にくわしく計算した例はこれまでなかった。今回研究グループは、この星の赤ちゃんが成長して、核融合反応によるエネルギーによって自ら光る一人前の星となるまでの約10万年にわたる進化をコンピュータ中に再現することに成功した。
この結果、原始星が太陽の20倍程度の重さになると、星の出す光、つまり明るさは実に太陽の10万倍に達し、この宇宙最初の星からの光は星周辺のガスを温め、ガスが星に降り積もるのを妨げようとし、最後にはガスは外側に流れるようになり、星の成長は完全に止まるため、最終的には太陽の約40倍の重さの星が残ることが示された。
これまで長い間、初代星は太陽の数百倍という現在の宇宙にはほとんど見られないような巨大な星と思われてきたが、今回の研究で発見された、 いわば成長の自己抑制機構によってそのようなモンスター星にはならないことが判明した。これは、はるか太古の宇宙での出来事であるが、研究グループでは、銀河に存在する最も古い星々をくわしく観測すると、初代星が死を迎え超新星爆発を起こしたときにまき散らされる様々な元素の存在量を知ることができることから、人類の手が届くところにも初代星の痕跡を見ることができると説明する。
これによる観測では、宇宙最初の星は太陽の数十倍であったことがを示唆しており、宇宙最初の星がモンスター星であったとのこれまでの理論的予想との食い違いが謎とされていた。今回のシミュレーションにより観測結果と一致する初代星形成の描像を初めて得ることができたことは、初代星形成の理論を前進させ、将来の宇宙望遠鏡や地上大型望遠鏡を用いた観測計画に重要な示唆を与える成果だという。