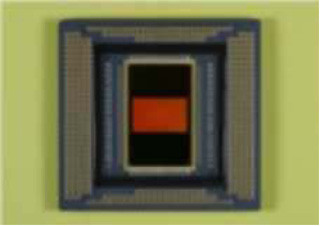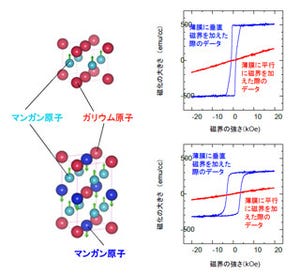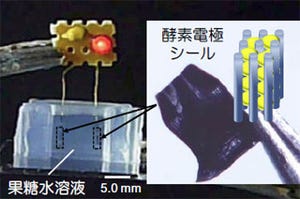東北大学大学院生命科学研究科の東谷篤志教授らの研究グループは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と英国ノッティンガム大学と共同で、線虫を用いて、宇宙環境においてもRNAi効果を確認するとともに、筋肉タンパク質の分解酵素の発現をRNAiにより抑えることで、1つの筋肉タンパク質の分解を宇宙空間で阻むことが可能であることを、実験的に証明した。
宇宙の無重力下では骨格筋に対する物理的負荷が低下して、筋肉や骨が萎縮することが知られているほか、人類による火星探査や宇宙ステーションでの長期滞在は、宇宙放射線の影響により白内障の発症やDNA損傷のリスクが想定されている。これらの宇宙環境リスクの克服は、人類が宇宙に長期滞在し活動する上で不可欠なほか、普段の地球上に住む人間の生活においても「寝たきり」や「ガンをはじめとする成人病疾患」に対処としても重要なものとなる。
RNAi(RNA interference:RNA干渉)は、二本鎖RNAと相補的な配列を持つmRNA(メッセンジャーRNA)が特異的に分解される現象で、特定の遺伝子発現のみを選択的に抑えることができる。同方法は、1998年にモデル生物の1つである線虫を用いて、米国研究者らにより発見され、その後、ヒトをはじめとする哺乳類の細胞においても同様の働きの存在が明らかにされた。現在、RNAi法は、ヒトの発ガンや眼の疾患などに対する遺伝子治療の1つとしての研究開発が進められている。
研究グループでは、98年より線虫のDNA損傷の修復に関わる遺伝子についてもRNAiを用いた機能解析ができることを報告してきたほか、2004年には、線虫国際共同実験(ICE-First)に参画し、宇宙フライトにより線虫の筋肉タンパク質が低下することも示してきた。
2005年に実施された宇宙実験に関する第5回ライフサイエンス国際公募において、「線虫C. elegansの宇宙環境におけるRNA干渉とタンパク質リン酸化:CERISE(C. elegans RNA interference Space Experiment)研究代表 東北大・東谷篤志」の実験提案を行い採択されたものの、スペースシャトルコロンビア号の事故調査などで延期され、実際の実験開始は、国際宇宙ステーション(ISS)の日本実験棟「きぼう」が完成した2009年になり、09年11月の「STS-129」にてスペースシャトルアトランティス号に実験材料を搭載し、11月19日から8日間「きぼう」にて宇宙実験を実施した。
その後、サンプルは宇宙で凍結し、2010年2月の「STS-130」のスペースシャトルエンデバー号で地上に帰還した。
これらサンプルを解析した結果、宇宙環境の無重力下においても、3つの異なる遺伝子(線虫に遺伝子組換えした緑色蛍光タンパク質GFP、細胞増殖に必須のタンパク質、筋肉を構成するα-アクチンを分解する分解酵素)をターゲットとして、それぞれ選択的なRNAi効果が確認された。
この成果は、将来的には、宇宙飛行士の無重力下における筋肉の委縮を抑える対策の1つとしての応用展開が期待されるという。また、研究グループでは、今回の宇宙フライトサンプルを用いて、無重力による生物影響について、線虫の全ての遺伝子発現やタンパク質発現をとおして解明する実験も引き続き行っていくとしている。