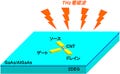理化学研究所(理研)と京都大学、首都大学東京らの研究チームは、約4,000年前に爆発した超新星残骸であるふたご座のクラゲ星雲(別名:IC443)が、爆発直後には太陽の1万倍以上も熱い巨大な火の玉であった証拠を観測することに成功したと発表した。
同星雲は地球からの距離が5,000光年程度と推定されており、双子の兄であるカストルの足元でフワフワと漂うクラゲのような姿をしている。
超新星残骸をX線で観測すると、爆風による衝撃波で加熱された高温ガスを見ることができる。同研究グループは、日本のX線天文衛星「すざく」を用いて、同星雲をX線画像で撮影、可視光写真に重ねることで、700万度の高温ガスが同星雲の中に包まれるように分布している状況を確認。さらに、同ガスのX線エネルギースペクトルの測定を行い、解析結果から、ほかの超新星残骸では見られない特異なシグナルを発見したという。
|
|
|
クラゲ星雲(IC443)の可視光画像(a)と可視光およびX線(RGBカラー)の合成写真(b)。クラゲ星雲は、約4,000年前に爆発した超新星の残骸であることが知られ、その直径はおよそ65光年に相当する。なお、右端で明るく輝くのはプロプス(ふたご座イータ星)と呼ばれる赤色の変光星である。可視光画像はDigitized Sky Survey(DSS)のデータを用いて作成(出所:理研Webサイト) |
具体的には、700万度のガスからの放射に加え、自由-束縛遷移と呼ばれる量子力学的プロセスに起因した2つのすべり台状のスペクトル構造を世界で初めて検出することに成功した。同構造は、原子を構成する電子が1つ残らず剥ぎ取られ、原子核がむき出しになった状態のSi14+やS16+が大量に存在していることを意味している。
電子が1つも残っていない原子を「完全電離イオン」と呼ぶが、SiやSを完全電離させるためにはガスの温度は700万度では不足で、少なくともその数倍は熱くなければならず、結論として、同星雲ではかつて現在の何倍もの高温であったことが想定されることとなる。
ただし、宇宙空間は1cm2あたりに原子1個以下という超高真空状態の環境であり、物質同士の衝突が非常に起こりにくいため、超新星残骸が高温になるプロセス - 爆発によってまき散らされた物質や衝撃波がはき集めた星間物質が衝突を繰り返す - が生じにくく、ガスが十分に加熱されるためには数百年から数千年規模の時間を必要とされる「ゆっくり熱くなるタイプ」が一般的であった。
一方、同星雲のように特に重い星は、寿命末期に自身の表層ガスを放出して星の周りに厚い雲を形成。その中心で星が爆発することで、爆風が雲と激しく衝突し合い、一気に加熱、爆発後数年で1億度を超す巨大火の玉に成長する「急激に熱くなるタイプ」の超新星残骸で、衝撃波が雲を突き破ると、中の火の玉は急速な断熱膨張により冷却され、現在の700万度まで下がったと見られている。完全電離イオンは、火の玉時代に作られたものであり、いわば「宇宙の化石」のように残り、爆発直後の様子を伝えているものと考えられる。
|
|
|
重い星が末期に作る厚い雲の例。りゅうこつ座イータ星(星は虫の繭にも似た雲の中心にあり、このような環境の下で超新星爆発を起こすと、まき散らされた物質は周囲の雲と激しく衝突して一気に超高温の火の玉が形成される。このとき高温にさらされたSiやSはすぐに完全電離することとなる)(出所:理研Webサイト) |
なお、今回同研究グループが明らかにした超新星残骸の特異性は、星の爆発が周囲を取り巻く厚い雲の中で起こった事実に起因する。この雲は、爆発前の星が少なくとも太陽の10倍以上は重く、なおかつ超新星を起こす直前まで自身の表層ガスを放出していたことを意味しており、この化石の発見は、爆発後の現象にとどまらず、爆発前の星の質量や活動性を解き明かす手がかりになると同研究チームではしている。
|
|
|
爆発直後のクラゲ星雲の想像図(厚い雲を灼熱の火の玉にした衝撃波が、まさに雲を突き破ろうとしている瞬間。そのとき内部からは強烈なX線やガンマ線が放射されたと推測される。この後、火の玉は急速な膨張によって冷えるが、完全電離イオンは「化石」のように残ることとなる)(出所:理研Webサイト) |
太陽の40~50倍以上重い星は、極超新星と呼ばれる通常の10倍のエネルギーを放つ爆発を起こすと考えられており、宇宙最大の爆発現象とされる「ガンマ線バースト」も、この極超新星に関連することが有力視されている。しかし、これらの天体現象は、宇宙の彼方で発生するため、観測が難しく、そのメカニズムも解明されていないのが現状である。
地球が属する天の川銀河にも300個程度の超新星残骸が存在しており、その内のいずれかが極超新星やガンマ線バーストを起こしていた可能性も考えられ、研究チームとしては、今回の成果はそのような大爆発の化石を探査する指針になるとしており、詳しい観測が可能な近傍の宇宙から化石を発見できれば、爆発メカニズムの解明などにつながると期待している。