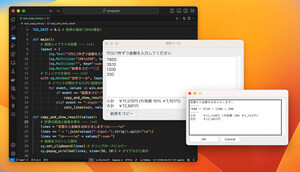O'Reilly(オライリー)のブログにちょっと気になる記事があった。タイトルは「電子書籍の注釈、リンク、メモ:絶対必要、それとも邪魔なもの?」。O'Reilly Radarの編集者の間で、電子書籍でページ上から直接利用できる辞書や注釈、メモ、Web検索などが必要な機能であるかが議論になった。その様子のレポートである。
筆者は最近、手に入れられるのならば電子版の本を購入している。本棚の問題に悩まされないのが大きな理由だが、辞書機能やメモ機能を使えるのも同じぐらいにありがたい。特に洋書を読むときには不可欠である。だから、これまで電子書籍の読書をサポートする機能が"余計な機能"だとはかけらも考えたことがなかった。必要なければ使わなければいいのだから、誰もが"あれば便利"と受け入れると思っていた。それだけに、この議論は気になる。
Wikipediaに移動したまま戻ってこない……
O'Reillyのシニア編集者Mike Loukides氏は「本を読んでいると様々な疑問が頭をよぎる。その答えが指先ひとつで分かるようなツールを欲しいとは思わない」と断言している。「チャールズ・ディケンズの『Little Dorrit (リトル・ドリット)』を読んでいる途中で『Marshalsea(マーシャルシー刑務所)』をWikipediaで調べたりしたら、債務者が収監される監獄の歴史が面白くなって、そのうち何を読んでいたか忘れてしまうだろう」と述べる。たしかにWebサイトで調べ物をしていても、いつの間にか関係のないページを読みこんでいることはよくあるので、この指摘はなんとなく分かる……。
さらに同氏は、読者がストーリーに集中できるように、例えば注釈は巻尾に載せるような形が望ましく、逆に全てを読者の目の前で解決するのは「押しつけがましい行為」としている。一つの例として「What Jane Austen Ate and Dickens Knew」という書籍を挙げた。これはディケンズの著作の世界について、当時の賃貸料やパンの値段などの現在の価値、500ポンドの月給取りの階級など細かいデータ・情報がまとめられた本だ。これらが全て小説に埋め込まれていたらストーリーが台無しだが、別の本として編纂されているからディケンズを読む際の参考書として「What Jane Austen Ate……」も楽しめるというわけだ。
面白いことに、技術畑の編集者であるLoukides氏が小説への愛情たっぷりの意見を主張しているのに対して、逆に文学を専攻していた編集者Adam Witwer氏がクールに電子書籍の諸機能を評価している。様々な補足情報も把握しながら困難な作品の読解に挑む文学研究者にとって、例えば「Ulysses (ユリシーズ)」など、作品によっては注釈へのアクセスが作品攻略の大きな手助けになる。だから、注釈機能などは研究者にアピールするはずだと指摘している。ただし同氏自身は辞書機能だけで十分であるとしており、シンプルに辞書機能だけが組み込まれたAppleのiBooksを気に入っているという。
Tim O'Reilly氏とMicrosoft PressのRussell Jones氏は、電子書籍の特徴を踏まえた編集の必要性を指摘している。O'Reilly氏が現場に携わっていたときには、本を通じて読者が抱くであろう疑問や読者からの反論を予想し、そうした欲求を満たすシナリオづくりを編集理念のひとつとしていたそうだ。大事なのは読者が必要な知識を求めること。本の中で解決に導くのもテクニックのひとつだし、読者がより多くの情報を求めて違う書籍を探したり、なにか行動するきっかけになるだけでも十分だとしている。
Jones氏は、より具体的に電子書籍コンテンツの可能性を示している。例えば電子書籍は、リンク情報と埋め込み情報のふたつを一緒に扱える。リンク情報はアップデート可能だが、リンク切れになる可能性がある。埋め込み情報はアップデートしづらいものの、必ずアクセスできる。この特徴を理解して適材適所で使い分ければ、ユーザーの関心を高め、ストーリーへの理解を深められる演出を加えられる。さらに、こうした補足情報はユーザーによってコントロールされるべきものだとしている。シンプルなジェスチャーや「Ctrl+クリック」のような簡単な方法で呼び出せ、同様に簡単に画面から消せるようにユーザーインターフェイスが設計されていれば、ユーザーの読書体験を損なうことなく、出版社は豊富な情報を電子書籍に望む限りの情報を詰め込めると指摘する。
紙の本の代替にとどまる米国の電子書籍
筆者の読書体験を振り返ってみると、電子書籍では簡単に注釈にアクセスできるから、注釈のマークに気づくとすぐにタップしてしまうし、ちょっと気になる文章があると後々のためと思ってハイライトしてしまう。仕事用の資料として読む本では大いに役立つが、小説にはむしろ必要のない作業である。これが紙の本なら注釈ページを開かないし、ハイライトも面倒に思うだろう。
こうした機能が必要であるかは、本を読む目的次第であり、それは人によって違うし、同じ人であっても読む本によって異なる。だから大は小を兼ねるで、Jones氏の言う「シンプルな読書モード」と「情報豊富なリサーチモード」を読者が簡単に切り替えられるのが実用的に思う。また紙の本をそのまま電子版にするのではなく、電子書籍の可能性を引き出す電子版の編集の実現も期待されるところだ。
この議論で浮き彫りになるのは、成長著しいものの、ソフトウエアもコンテンツもまだまだこれからという米電子書籍産業の未熟な一面だ。米国ではAmazon.comが紙の書籍よりも安く (かつ便利に)購入できるという価格破壊型のビジネスモデルで電子書籍市場を開拓してきたため、既存の紙の本の延長線上で、これまでの紙の本の役割を代替する存在として電子書籍が成長してきた。米国の電子書籍関連のニュースが毎日のように報じられているにも関わらず、何が新しいのか実体が見えてこないと思っている方も多いと思う。それは紙から電子への媒体の置き換えが進んでいるだけだからだ。コンテンツ面では、むしろケータイコミックやケータイ小説など、紙の本とは別のエコシステムで電子ブックが成長している日本のほうが先行している面が多々ある。
ところが"魔法のような利用体験"をうたうiPadが登場したことで、米国の状況が変わり始めている。紙の本のような役割だけでは、iPadや今後登場するであろうタブレットデバイスは明らかに役不足。タブレットに対する社会的な関心の高まりも相まって、ここに来て「電子書籍を読む」という行為そのものが問われるようになってきた。O'Reilly Radarでの議論は、米電子書籍産業の流れの変化を示すものだ。「読者が電子書籍にどのような読書体験を求めるのか?」……その実現が、今後の電子書籍市場の行方を左右する重要な要素になってくる。