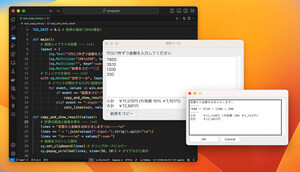このあたりでは時々、ローカルニュースで「マウンテン・ライオン」警報が発せられる。ベイエリアにやってくるまでMountain lionなんて聞いたことがなかった。海に近いし「Sea lion=アシカ」は知っていたので、ライオンよりもアシカ寄りの動物をイメージしたのだが、辞書で調べてみると「Mountain lion=クーガー」だった。そんな動物園でしかお目にかかれないような動物が普通に人里に迷いこんでくる。「いくらのどかな地域と言っても……」と思ったが、サンフランシスコではフィッシャーマンズワーフの外れに野生のアザラシの大群がいるし、モントレーの南ではラッコを目撃した。サーフィンをしていてサメにかじられたという話もめずらしくない。散歩中にウチの犬がスカンクの直撃弾を受けて大変な目に遭ったこともある。米国で暮らしていると、ごく普通の街中でも野生を身近に感じることが多い。野生動物ウォッチングの趣味はなくても、これだけ身近に動物がいると、ちょっと調べてみたくなる。
9月にサンフランシスコで行われたTechCrunch 50のプレゼンターに、「Birdpost」というバードウォッチャーのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を提供しているスタートアップが選ばれていた。ユーザーが目撃した鳥を登録し、そしてプロフィールで好きな鳥、嫌いな鳥について語り、同好の人々を見つけ出す。TechCrunch 50での評価は芳しくなかったのだが、自分を含めて同カンファレンスに参加した何人かがすでにメンバーになっていたことが最近発覚した。実は密かに面白いと思われていたようだ。
名前を知らなくてもバードウォッチャーに
バードウォッチングというと、鳥やアウトドアの専門知識が必要なニッチな世界というイメージだが、Birdpostは特に鳥に興味がない人でも気軽に参加できる。敷居の低さが魅力である。目撃登録した鳥は、サムネイル画像やマップ上で視覚的に一覧できるので図鑑を見ているようで楽しい。検索機能では「yellow legs, California (カリフォルニア州で、黄色い脚)」というように見た目の情報から探し出せる。鳥の名前や種類を知らなくてもバードウォッチャーになれるのだ。
画像はすでに登録されている写真や著作権フリーのものを使えるのだが、やはり自分で撮った写真をポストした方が獲物を捕らえたようで面白い。写真をメンバー同士でレーティングする機能もあるので、鳥に興味がなくても、カメラ好きが鳥を被写体とするためにBirdpostを始める可能性もありそうだ。もちろん鳥とカメラのどちらも好きという人には堪らないサービスだと思う。
自分のペースで楽しめるのもBirdpostの特徴だ。「Regional Checklists(地域チェックリスト)」という機能では、特定の地域に絞り込んで、メンバーが登録している鳥を一覧できる。自分が住んでいるカリフォルニア州サンタクララ郡だと375種類が登録されており、まずはこれらをコンプリートしたくなるし、このように地域ごとで切り取れると、庭先やビルの谷間で見かける鳥だけのバードウォッチングが成立する。山間部ではめずらしくない鳥でも、都市で目撃すれば珍鳥ということにある。日常生活の中で出会う鳥を記録し続けてもいいし、そこから知識をため込みながら公園や野山に行動範囲を広げて本格的なバードウオッチャーになる人もいるだろう。
ただ、アイディアは面白いのだが、残念なことにサービスが全般的にこなれていない。鳥の登録、他のメンバーとのコミュニケーションなど、個々の機能のステップがわかりにくい上に、それらが上手く連係していない。SNSとして使いにくいのだ。またデータや情報の量が乏しく、それらのつながりも充実していない。鳥を画像やイラストで楽しめるのはプラス評価だが、学術的な説明、他のメンバーが撮影した時の状況や目撃するためのテクニックなども同時に確認したいところだ。このようにサービスとして誉められたものではないから、TechCrunch 50では評価されなかった。
局地的なサービスから抜け出せないスタートアップ
とは言え、BirdpostのBen Crockett氏によると、米国のバードウォッチャーの潜在的な市場は4,500万人規模。これまで専門的な世界だったバードウォッチングに、誰でも参加できる仕組みを設けることで、その市場が開放されるという。実際、身近にこれだけ鳥がいるし、すでに自分を含めて何人もの門外漢の目を鳥に目を向けさせているのだから、その主張には肯けるものがある。
それを聞いて思い出したのは、Discovery ChannelがWebサイトで提供している「Sharkrunners」というオンラインゲームだ。プロジェクトチームと調査船を選び、GPSを装着したサメを追跡・調査するゲームなのだが、実際のサメの移動データと船の進み具合をベースにしているから動きがおそろしく遅い。ゲームとしては極めて退屈なのだ。船の残り燃料を考慮しながら方向とスピードを設定したら、「サメに近づきました」というメールが来るまで数日間放置するという具合だ。ところがプレイしてみると、止められなかったりする。ついにサメと遭遇し、調査方法を選ぶ際には、ダイブすればより詳細なデータが集まるものの危険度が非常に高い。かといって水面からのぞき込んでいるだけではデータが集まらない。ジレンマである。現実に忠実だから、ドキュメンタリーを読むように生物学者の調査ステップ、苦労や冒険を体験でき、これまで自分には縁の無かった生物調査の知識がいつの間にか蓄積される。
TechCrunch 50では、審査員が数多くのスタートアップに対して「そのサービスはニューヨークやシリコンバレー以外にも広がるのか?」と突っ込んでいた。例えば、ユーザーの評価や好みから自分に合ったレストランを効率的に見つけ出せる仕組みを作っても、"グルメ"ものは大都市でしか登録が増えない傾向が見られる。フランス人の審査員などアメリカ人ばかりの会場で「アメリカ人によるパリのレストランのリコメンデーションなんて、われわれにはジョークでしかない」という辛辣なコメントを残していた。
"食"は誰もが対象になる大きなトピックであり、それ故に多くのスタートアップが好んで取り組んでいるが、ユーザーの誰もが何かしらの"こだわり"を持っている。その全てを満たすサービスを提供するのは非常に難しい。逆にニッチの場合、こだわりを持っている人は小さな市場のごく一部。Birdpostのようにニッチを残りの大多数にもたらすためのサービスを構築すれば、ユーザーには新鮮な発見として受け止められる。
他にも今年のTechCrunch 50ではニッチをすくい取るサービスの健闘が目立っていたのだが、奇しくもサービス面でTechCrunch 50の評価がパッとしなかったBirdpostがニッチの可能性を最も浮き彫りにしている。