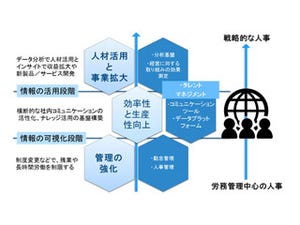組織の幸福度を高めることで、受注予算達成率も向上
同社が開発したサービスは、名札型ウェアラブルセンサーが目に見えない人の行動パターンを測定し、AIの「Hitachi AI Technology/H」が組織活性化につながるための個々人の行動についてアドバイスをするというもの。
「デバイスに搭載されたセンサーが無意識下で起きるノイズのようなちょっとした動きを測定し、組織単位のハピネスを可視化できるようになりました。赤外線センサーとビーコン(位置情報を取得するセンサー)によってコミュニケーションしている相手や現在地などを測定できるうえに、加速度センサーでどちらが話し手なのか、会話は双方向なのか一方通行なのかといった、より踏み込んだデータまでわかります」と、矢野氏。
人の動きだけでなく、その人がどこで誰と話していたかといったデータまで測定できるという。
さらに「データを取った後は、AIが行動を分析し『上司には午前中に合いに行ったほうがいい』『集中してある程度仕事を続けてから部下の質問に回答したほうがいい』など、組織のハピネスを向上させるために必要なアドバイスを自動で生成し、個人のスマートフォンに送ります」と、説明する。
実際に同社では、グループ内の営業職600人を対象に、名札型デバイスを装着する実証実験を行い、デバイスを装着した社員のスマホへ毎朝個別にアドバイスを送付。それを数カ月にわたり続けたところ、「アプリをより長く見て活用しているチームほど、ハピネスが向上していることがわかりました。さらにハピネスが上昇している職場では、下降している職場に比べて翌四半期の受注予算達成率が平均27%も高くなったのです」と矢野氏はその効果を示した。
ハピネスの高い社員は困難な課題にも積極的に
サービスが展開され始めてから約2年。すでに製造業やサービス業、金融業など幅広い業界において、20社以上に導入されている。さらに、働き方改革が注目されるようになり、時代もナレッジワーカーの生産性向上を求めるようになっているという。
「テレワークなどが普及すると組織で集まって仕事する機会は相対的に減るかもしれませんが、その分、対面で行われるコミュニケーションの重要性はますます高くなるはずです」と、矢野氏は働き方改革にも同サービスがフィットすることを指摘する。
従来は対面で行う必要のない問題に対しても会議室に集まって話し合うケースが多かったため、そのような無駄が減り、本当に必要な対面コミュニケーションの質を高めることができるのだという。
そのうえで矢野氏は「現在は部署単位が多いですが、これからは会社全体でハピネスを測定するような事例が多く出てくるといいですね」と、希望を述べた。
「そもそも社員は幸せに働くべきだと思います。幸福とは人間が究極的に行き着くべき関心ごとですよね。すべての活動はそのためにあるといっても過言ではないでしょう。アメリカの学術雑誌に掲載された論文では、ハピネスの高い人ほど難しい課題に取り組む傾向が強いという実験結果が発表されています。アンハッピーな人は本当にやらなければいけない困難な課題に挑戦する精神的な原資が欠乏している状態にあり、それほど大事でない楽な仕事を優先して作業しがちになってしまうのです」
先が見えない事業の推進や高い目標を達成して利益を出すなど、会社にとって大事なことは社員にとって難しいことが多い。しかし、ハピネスの高い組織で働いている人は、そのような業務にも積極的に取り組むのだと矢野氏は指摘する。
「苦しい状態でも大事なことから真っ先にやるような組織を作るには、社員がハッピーでないといけません。会社全体をそのような雰囲気にするためにも、このサービスを活用していきたいと考えています」
高い成果を出す人は日々目標を設定して仕事に没頭している
最後に、ハピネス向上を訴求する矢野氏に、幸福度を高めながら仕事をするために大切なことを伺った。
「常にチャレンジをすることですね。いい業績を残す人材は、自分の実力よりもちょっと高い目標を作り、日々挑戦し続けているといいます」
ハピネスの高い組織では積極的に難しい課題に取り組む傾向が強いという話があったが、それを自ら意識的に行うことが大事なのだという。
「簡単すぎるゴールであれば退屈を感じてしまい、難しすぎる目標を立てれば不安を抱くようになってしまいます。頑張らないと達成できない目標ですが、決して手の届かない距離ではないもの。1日や1週間、ないし数時間といった単位ごとにそのような目標を自ら設定することで、仕事に没頭することができるのです」と、矢野氏は語る。
楽しみながら仕事をすることの大切さを知っている矢野氏だからこそ、データとして測定することの難しい心理的なポイントに着目し、AIとIoTで幸福度を向上させるというアイデアを見出せたのかもしれない。