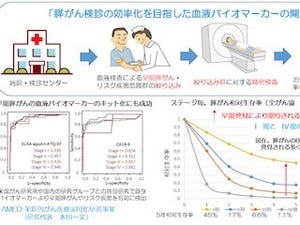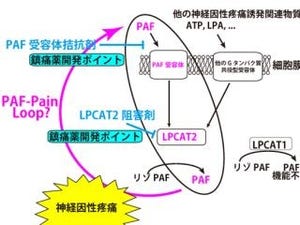国立がん研究センターとNECは7月10日、人工知能(AI)を活用し、大腸がん、および前がん病変(大腸腫瘍性ポリープ)を内視鏡検査時に発見する「リアルタイム内視鏡診断サポートシステム」の開発に成功したと発表した。
大腸がんは通常、前がん病変であるポリープから発生することが知られており、それを内視鏡的に摘除することで、大腸がんの罹患率を76%~90%抑制し、死亡率を53%抑制したという研究結果が明らかにされている。
そのため、ポリープを内視鏡検査時に見逃さないことが重要となるが、肉眼での認識が困難な病変や発生部位であること、また医師の技術格差などにより、24%が見逃されているという報告もある。同システムはこうした要因による見逃しを未然に防ぎ、医師の診断をサポートする目的で開発された。
AIによる画像診断、ポリープ発見率98%を達成
今回発表されたのは、画像解析に適した深層学習を活用したAI技術と独自の高速処理アルゴリズム、画像処理に適したGPUを用いたプロトタイプで、1台のPCで動作する。国立がん研究センターにて撮影された、大腸がんと前がん病変の約5,000例の内視鏡画像(静止画像および動画)を学習データとし、NECのAI技術群「NEC the WISE」を用いて解析を行った。
|
|
|
GPGPUクラスタの仕様。このプロトタイプではNVIDIAのTITAN X(Pascal世代)を利用しているが、システム販売時のコスト削減を考えると、CPUの利用も検討すべきと考えているとのこと |
国立がん研究センター研究所・新研究棟4階に設置されたAI解析エリア(GPGPUクラスタ)と中央病院内視鏡科の録画サーバーを、隔絶された閉鎖系VLANで接続することで、研究の速度を上げていく |
二者が協業したきっかけは、NECの顔認証技術における成果を知った国がん側から、今回のコンセプト実現に関する打診があったこと。大腸の病変は目鼻のような指標がなく、また周囲組織との差が少ないことから検出は困難だったものの、同研究センターの医師に学習データへのアノテーション追加の依頼をするなど、効率的な学習データの作成を行ったことで、このたびの成果が得られたという。
そうして作成したプロトタイプを使用して、新たに学習データとは異なる約5,000枚の内視鏡画像を評価したところ、前がん病変としてのポリープと早期がんの発見率が98%、偽陽性率は1%という高精度な結果が得られた。隆起した腫瘍のみならず、大腸のひだと見分けがつきづらい平坦な病変の検出にも対応する。検知を約33ミリ秒以内(30フレーム/秒)で行うことが可能となったことから、リアルタイム検知が可能なシステムとして公開した。
今後も開発を進め、2019年度以降に臨床試験、および保険診療への認可を含め、実用化を進めていく見込み。直近では、国立がん研究センターには全国より診断が困難な平坦・陥凹性病変の症例が集結しているため、これ以降、1,600例以上の同病変のデータをAIに学習させ、プロトタイプの精度を向上させる。また、画像強調内視鏡などの新型内視鏡と組み合わせることで、ポリープの質的診断なども目指す。
同プロジェクトを主導する国立がん研究センター・山田真善氏は、同システムを全国、さらには国外の医療現場で活用することで、内視鏡検査のクオリティ担保が可能になると意気込みを語った。加えて、診断コンセプトは似通っているため、胃がんなど他の消化器系のがんにも展開可能であろうと付け足した。
検査時間の短縮など、検出率以外の医療現場でのメリットは、今後の臨床試験で検証する。山田氏は、「今回のシステムは、自動車における緊急時の自動ブレーキと同じような立ち位置と考えている」として、医師による丁寧な内視鏡操作を基本とした、先述のような要因による結果のブレをなくす補助的な機能であることを強調した。また、国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 科長の斎藤豊氏は、高いポリープ検出率を安定して実現することで、検査結果が疾患の悪化防止に直結する大腸の内視鏡検査の受診率向上につなげたいと語った。