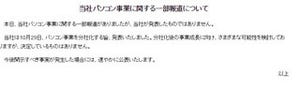東芝の経営状態が苦しく、再建が急務であることの是非は、今回の記事では置いておこう。単に厳しくなったのではなく、問題をごまかしたうえでよりひどい状態にもっていったことについて、経営陣には、経営施策上だけでなく、道義的にも責任を取る必要がある、と思うが、それはまた別の話だ。
今回考察したいのは、「東芝のテレビ事業がどうなるか」だ。
-
東芝、5500億円の赤字で無配 - PC関連では青梅事業所の閉鎖や人員削減
(12月22日掲載)
結論から言えば、開発拠点である青梅事業所は閉鎖になり、海外でのビジネスは事実上終息に向かい、国内向けに60万台程度のビジネスを目標とした、比較的小さなビジネスとして存続することになる。
こうなることは、2013年後半から明らかだった。東芝は、海外の大規模家電イベントにも積極的に出て行って、テレビの拡販と「REGZA (レグザ)」ブランドの定着に努めていたが、ドイツで開かれる「IFA」からも、アメリカ市場向けの「CES」からも手を引いた。海外では撤退戦の途上であり、その内容を改めて発表した、というのが正確なところだ。
そもそも東芝は、テレビをできるだけ「自社工場で生産しない」こと、液晶パネルを中心とした高コストだが差別化が難しいパーツについても「他社から供給を受ける」体制で成功したメーカーである。2012年頃、ソニーとパナソニックが「自社製造」ゆえの高コスト体制に苦しんでいる頃から、PCのノウハウを生かした「アセットライト戦略」で効率良くテレビ事業を展開している……とされていた。
だが、結果はみての通りだ。
「数を売る」テレビの終焉
その背景には、テレビビジネスの構造変化がある。ほんの4年前まで、テレビは家電の花形だった。家庭には「一家に一台」どころか、「一部屋に一台」の勢いでテレビが普及しており、単価が高いにも関わらず数が売れる家電であった。
だが、今はそれが変化した。世界中で「個室向け」のテレビ需要が落ち込み、小型低価格なものは売れにくくなった。また、少々大型でも、低価格な製品については、中国メーカーなどとの安売り競争が厳しくなっている。結局労働力や生産コストの低い国のメーカーに勝てず、かといって先進国では、スマートフォンやタブレットの普及により、個室ではテレビが求められなくなっていた。「数を売る」ことに最適化したやり方では、もはやテレビビジネスは立ち行かなくなったのだ。
だが、「テレビが売れなくなった」「テレビがいらなくなった」と考えるのは早計だ。日本においても、2013年後半以降、大画面・4Kテレビは好調に売れている。リビングで家族とテレビ番組を見たり、映画を楽しんだり、スポーツに一喜一憂したり、というニーズは失われていない。「一部屋に一台」から再び「一家に一台」に回帰した、と結論づけてもよい。