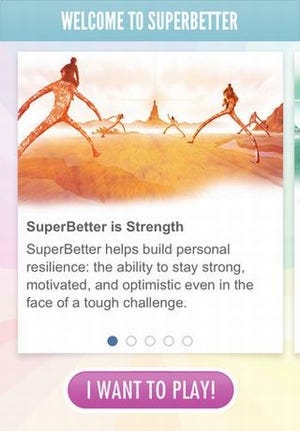社員が私物のスマートフォンやタブレットを業務に活用することを意味する「BYOD(Bring Your Own Deveice)」は今年のITトレンドの1つだが、ブロードバンドと使いやすい端末が実現する"いつでも・どこでも"により、新たな問題が浮上しつつある――デジタル残業だ。訴訟大国の米国では、このデジタル残業について、集団訴訟も起こり始めているという。
デジタル残業についてレポートしたOpenForumによると、一時期「セクハラ」ことセクシャルハラスメント関連の訴訟がドッと起こったように、電子残業関連の訴訟の波が押し寄せるかもしれないという。
というのも、最近のビジネスマンは会社の外にいる時間でもスマートフォンやタブレット端末から社内ネットワークにアクセスして業務をこなしており、特に時間給扱いのスタッフについては違反問題になりかねないからだ。
すでにAmerica Mortgageを相手に2011年、2012年に2件の集団訴訟が起きているという。原告の主張は「夜間や週末にも仕事をさせられたが、連邦法である公正労働基準法で定められた残業手当を支払っていない」というものだ。
「この集団訴訟の動向次第で、今後、同じような訴訟が次々と起こる可能性がある」と、弁護士事務所Gardere Wynneに勤務するCarrie Hoffman氏がコメントしている。
こうした事態を回避するアドバイスとしては、雇用主はまずスマートフォンの提供、遠隔から社内ネットワークへのアクセスの提供などが本当に必要かどうかを考えるべきだという。効率化の名の下に自宅から会社のメールを読めるようにすることが、どれぐらいメリットがあり、リスクになるのかを調べてみる必要があるというわけだ。
もちろん、緊急時に稼働しなければならないITスタッフなどはメリットのほうが大きいかもしれない(なお、米国では時間当たり27.63ドル以上の報酬を得ているIT担当者などは、労働省が規定する「例外」となるようだ)。だが、それ以外のスタッフであれば、次の就業時間まで待てるかもしれない。「ほとんどの場合、時間外に作業できるようにするデジタル手段を提供するメリットは少ない」とHoffman氏は述べている。
もしデジタル残業を認めるならば、「BlackBerryなどの端末を使って記録を残し、デジタルデバイスによる業務時間に関する記録をとるシステムを作って報酬を払うべき」とHoffman氏は助言している。
日常的に残業が多い日本において"デジタル残業"がどれぐらい問題になるのかはわからないが、まずは米国の動向に注目したい。