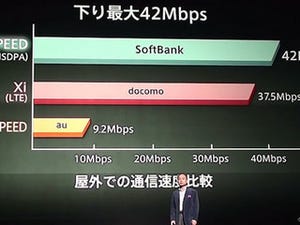近氏は、1980年のアナログ携帯、1990年の2G、2000年の3Gと、10年ごとにネットワークが進化していて、「今年こそが4Gの元年になる」と話す。4Gによるネットワークの改革が必要で、これは容量の増大とコストの低減が必要だという。これを実現するために、基地局1つずつのサイズを小さくしてマイクロセル化し、さらに基地局数を増やすとセルごとの干渉が増えるので、それを減少させることも必要になる。
国内のトラフィックは、スマートフォンの拡大も手伝って、特に都市部で増大している。東京でも23区内が、23区内でも渋谷区の1平方km範囲内が、といった具合に、局所的に高いトラフィックがあり、さらに屋内のトラフィックが全体の70%以上を占めているという。このため、AXGPでは都市部を中心に基地局を設置していく。近氏は、「どのくらいデータトラフィックをオフロードできるかがチャレンジ」として、3Gから4Gや無線LANへのトラフィックの移行を進めていく必要性を訴える。
「1,000倍のトラフィックは、マイクロセルだけではすべては解決できない」と近氏。基地局をこれまでの1,000倍設置するには、場所もないし周波数も足りない。特に数がたくさん必要なマイクロセルでは、干渉の問題も解決しなければならない。そこで重要なのがAXGPで採用しているTDD方式だという。
現在の3GやXiなどのLTEが採用しているFDDは、音声通話から発展したため、上下の周波数帯域が同じだけ必要で、データ通信時はダウンロードに比べてアップロードの帯域が余っている。また上下の間には干渉を避けるためにガードバンドと呼ばれる空白が必要で、これが全体の20~30%必要で、「大きな周波数を無駄にしている」状態だ。
それに対してTDDでは時間によってダウンロードとアップロードを分けており、上り下りの帯域を非対称にできる。ガードバンドはなく、時間による「ガードタイム」は全体の10%以下に収められるため、「インターネットに向いたシステム」だという。
このTDDを活用したTD-LTEシステムは、中国を中心に開発が進められており、世界32の携帯事業者が集まる「Global TD-LTE Initiative(GTI)」も設立され、チャイナモバイルやボーダフォン、ソフトバンクモバイルらの契約数は全世界で10億人以上に上る、と近氏。この中で、AXGPもTD-LTEと互換性のあるシステムとして参加している。「TDDの時代が来ると思っている。TDDは希望の光」と近氏は強調する。
さて、通常のTD-LTEと異なるのは、AXGPは既存のウィルコムの基地局と共用できる点だ。1995年から培ってきた、ウィルコムのマイクロセルによって、大容量を確保できる。近氏は世界的にマイクロセル化の流れはあるものの、干渉の問題や設置の問題などがあると指摘。それに対してウィルコムの基地局の場所をそのまま使え、干渉対策にもノウハウがあることが、「計り知れないメリット」だと説明する。ウィルコムの基地局は、全国に16万局あって、ソフトバンクはそのいくつかを廃止しているが、近氏によればPHS基地局は廃止しても、その場所にAXGPアンテナの設置は可能で、単純に減ったわけではないと指摘する。AXGPとPHSの共用アンテナは、8本のアンテナがあり、MIMOに対応できる点もメリットだという。