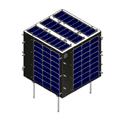1つ、興味深い問題がある。日本では「すばる」と呼ばれるプレアデス星団であるが、一般的な「主系列星あわせ」と呼ばれる方法で求められる距離(430光年)と、Hipparcosの観測結果から推測される距離(380光年)には10%以上の開きがある。星の進化モデルに影響を及ぼす可能性もあり、国立天文台・JASMINE検討室の郷田直輝氏は「我々がもう1回調べることで、どちらが正しいのか明らかにできるかもしれない」と期待する。
Nano-JASMINEに続いて、ESAもHipparcos後継機の「Gaia」を2012年に打ち上げる計画。こちらの精度は10マイクロ秒角と大幅に向上したものになるが、「Gaiaの成果が出てくれば価値は下がるかもしれないが、Gaiaのカタログが出てくるのは2017~18年になるだろう。それまでの数年間は、Nano-JASMINEで世界トップレベルの観測ができる」(郷田氏)という見通し。
以上は理学としての話題であるが、工学的に見てもNano-JASMINEはユニーク。何と言っても、特徴的なのはその小ささ。"超小型"とついているように、サイズは50cm立方、重量は35kg。主鏡の口径はわずか5cmだ。ちなみに、ESAの衛星は、Hipparcosが500kg、Gaiaが2tだ。
Nano-JASMINEでは、Hipparcosの1/10以下の重量で、同等の精度を実現する。これは、電子機器の小型化と性能向上によって可能になっており、例えばHipparcosは光電管だったが、Nano-JASMINEではCCDで観測を行う。超小型衛星ながら、姿勢制御にはリアクションホイールを搭載。これは4台搭載し、冗長性も確保している。
今回、記者会見で披露されたものは熱構造モデルであったが、エンジニアリングモデルは現在、東大にあるという。今後、フライトモデルは夏くらいから組み立てを開始し、年末までには完成させる予定だ。衛星の開発体制は、ミッション部(観測装置)を国立天文台が、バス部(電源系、通信系、姿勢制御系など)を東大の中須賀研究室がそれぞれ担当する。
衛星の開発費はおよそ1億円。打ち上げ費用はこれとは別にかかるが、今回はロケットが初号機(試験機)ということもあり、衛星インタフェースなどの実費のみ18万ドルで済んでいるという(打ち上げ自体は無料)。
天文台が"自前"の衛星を持つということは世界でもまだ珍しいことであるが、これを可能にしたのも、超小型衛星であるからだ。通常サイズの衛星に比べるとコストは2桁ほど安く、天文台の予算だけでほぼ賄うことができる。先般記事にしたアクセルスペースのウェザーニューズ衛星もそうだったが、"自前"の衛星がどんどん現実になる先駆けと言えるかもしれない。