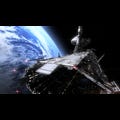大ヒットゲーム『龍が如く』シリーズの総合監督・名越稔洋氏は、デジタルハリウッド・東京本校にて、自身のゲーム制作に対する考えを語った。
同講義は、名越氏と映画『APPLESEED』や『ピンポン』、『ICHI』などの監督として知られる曽利文彦氏の特別イベント内で行われたもの。名越氏は、1989年セガ入社。AM2研のCGデザイナーとして『バーチャファイター』シリーズなどの制作に参加し、1994年、初のプロデュース作品『デイトナUSA』で大ヒットを記録。以降『スカッドレース』(1996)など数々の作品を手がけ、2005年に『龍が如く』を発表。『龍が如く』シリーズは合計320万本以上の出荷本数を記録している。2010年3月18日には最新作『龍が如く4 伝説を継ぐもの』が発売される予定。
『龍が如く』に込められたエゴイストな挑戦
斬新なアイデアでゲーム業界に新たなマーケットを築いた名越氏。その講義は、長きに渡るゲーム業界での経験をベースとした、CGクリエイターが持つべき精神性の話から始まった。「僕が『龍が如く』で総合監督と呼ばれているのは、ディレクター兼プロデューサーとして人や物、お金、機材などの管理も行っているから。今ではゲームも、シナリオとプロモーションと制作が同時進行で行われ、コンテンツとビジネスが直結した戦略的な作り方になりました。それだけに、CGクリエイターにも独特なビジョンが必要な時代と言えます」
ゲーム制作におけるコスト問題は欠かせないもの。従来ゲーム業界では、その問題をマーケットの拡大によって解消してきたが、その結果、市場には軸がぼやけた作品が増加した。本来、ものづくりはアグレッシブなものと捉える名越氏は、そのことについて常に違和感を感じていたという。そこで強まったのが"自分のやりたい形でマーケットも作れる作品を作りたい"という想いだった。「日本人なのだから日本人が楽しめるものが最も強いはず。アメリカ人の真似をしても勝てるはずがないなら、日本マーケットの独自性を取ろうと考えたわけです。その結果、『龍が如く』が生まれました。僕の思うヒットの条件は、認知度が高いのに未開拓なジャンルであること。そこで、ゲームではニッチだけど日本人なら誰もが知っているヤクザものにしました。ゲームには"体験できる"という強みもありますから、キャバクラや裏カジノなど、怖いけど行ってみたいという欲求を満たせる内容にしたのです」
過去の成功にあぐらをかくことなく、制作者としての原点を優先して取り組んだ名越氏。失敗したら会社をやめる覚悟だったが、結果的に『龍が如く』は、35万本のセールスをあげた。「でも、そこで終っては人の心を掴んだ証拠とは言えない。そこで1年後に続編を出そうと決め、前作に上回るセールスにするために動き、続編は60万本以上を売り上げ、一般的な認知を得ることができました。そこで初めて、こんなマーケットの作り方もあるんだと認識しましたね」
CG表現に大切なものと、これからのクリエイター
入力動作が加わるゲームは、他メディアと比較して表現の選択肢も多い。その多様な表現の中でCGを選ぶ場合はどう使うかが重要だ。「CGでは美しさなどが強調されがちですが、それよりも大切なのは"何を伝えたいのか"という想いや、見る人の心を揺さぶる新たな表現の追求だと思います。僕は映画だと曽利監督の『ピンポン』などにそれを感じました。"ピンポン玉の動きをCGで表現する"と聞くと何でもないことに思えますが、映像を見れば、それが製作者の気持ちを伝える上での必然的な技法であることがわかるのです」
さらに、3DCGをやるには物の裏側を知る必要があるだけに、3DCGを学ぶ人には探究心や好奇心が必要であると語った。「空間把握力を得るには、まずデッサンで形を追求する作業が必要です。同じように、探究心を持つことは物の見方を広げるなど、作品の制作へと必ず活きてきます。ですから、何でもいいので、ひとつは好きなことを追求してほしいですね」
またビジネス戦略とゲーム設計の関係にも触れ、自分の好きにできるほどのパフォーマンスを持つ、ニュータイプのクリエイターになってほしい、とエールを投げかけて講義は終了した。最後の質疑応答では「新しいジャンルでありながら、なぜそこまで自信を保てたのか」との質問に対し、「自信がないと思われないよう、宣伝や制作にお金をきちんとかけ、道のど真ん中を歩く精神で進んだ」と答えた名越氏。歌舞伎町を舞台にした作品で、業界に博打を仕掛けたオリジネイター。その大ヒットの裏側に隠された言葉に、聴講者は深い感銘を受けていた。
(C)SEGA